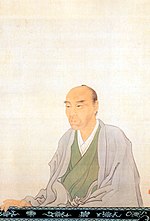検索結果
表示
このウィキでページ「紀行文洲」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 紀行や随筆、陸奥・出羽では『霞む駒形』『率土が浜つはひ』『秋田の仮寝』『小野のふるさと』といった紀行や素描本を綴り、蝦夷地ではアイヌの人々の生活を『えぞのてぶり』に写した。 蝦夷地から下北半島を漫遊、寛政7年(1795年)より7年間、弘前藩で採薬御用などを勤めたが行動不審を問われ日記や紀行…61キロバイト (10,861 語) - 2024年7月30日 (火) 05:05
- 『負籠の細道』中央公論社 1965(紀行文集、『旅』連載「日本の底辺紀行」改題) のち集英社文庫 『雁帰る』徳間書店 1967(エッセイ・紀行文集) 『恋愛と人生の45章』光風社書店 1967 『私の幸福論』大和書房 1968 のち女性論文庫 『失われゆくものの記』講談社 1969(紀行文、『太陽』1967年9月-1968年12月)…84キロバイト (14,047 語) - 2024年10月25日 (金) 10:42
- 東西遊記 (カテゴリ 日本の紀行)画像提供依頼:南谿の足跡の辿れる画像(板坂耀子著『江戸の紀行文』(中公新書)のpp151-153に載ってる感じ)の画像提供をお願いします。(2012年1月) 江戸時代後期の京の儒医である橘南谿が日本の諸地方を巡遊し、現地で見聞した奇事異聞を基に編纂して出板した紀行、『西遊記(せいゆうき)』と『東遊記(とうゆう…71キロバイト (5,507 語) - 2024年6月23日 (日) 14:34
- 古川古松軒 (カテゴリ 日本の紀行作家)こしょうけん)は江戸時代後期の旅行家、地理学者。 岡田藩に生まれ、中年期より日本各地を旅し、『西遊雑記』『東遊雑記』等の紀行を著し、また絵図を作製した。晩年、江戸幕府に命じられて江戸近郊の地誌『四神地名録』を編纂した。 その紀行文は、『奥の細道』など故人の足跡を辿り、名所を歌に詠むような従来の文学志向的な旅行から一線を画し…20キロバイト (3,060 語) - 2024年8月27日 (火) 06:16
- 阿川弘之 (カテゴリ 日本の紀行作家)を終了し、最終巻『天皇さんの涙』をもって文筆活動自体も終えることにすると表明した。 第三の新人と言われた作家グループの遠藤周作や、吉行淳之介、また紀行文等で知られる開高健らとは親友で、北杜夫、三浦朱門、安岡章太郎、講談社での編集担当であった大久保房男らとの長年の交友も知られており、随筆などでその交…45キロバイト (6,298 語) - 2024年11月15日 (金) 16:35
- し、テレビディレクターとして番組を制作。日本テレビ退社後は主婦、フリーライター、エッセイストとして活動。子育てをしながら世界を旅し、雑誌、週刊誌に紀行文、エッセーを発表し寄稿。1980年にニューヨーク大菩薩禅堂で坐禅し見性。1986年から「光の歌」を執筆。1990年から1992年頃にテーマパーク開…9キロバイト (1,143 語) - 2024年3月27日 (水) 15:41
- 中国国内では「新清史」の学術的成果は認められつつあるものの、「漢化」を否定する主張については反対が根強くある。2016年においても劉文鵬が「内陸亜洲視野下的“新清史”研究」で「『新清史』は内陸アジアという地理的、文化的概念を政治的概念に置き換えたことにより中国の多民族的国家の正統性を批判し…35キロバイト (5,147 語) - 2024年11月17日 (日) 08:41
- 清人の張秋穀や費晴湖から直接彩色などの画法を受ける。このとき紀行文『西遊日簿』は木村蒹葭堂の元を出立するところから始まり、備前の浦上玉堂を訪ね、同じく長崎を目指す司馬江漢と道連れとなったことなどが記載されている。壮年期になって4歳年下の谷文晁の門下となり、山水画や花鳥画を得意とした。また詩文にも巧み…3キロバイト (348 語) - 2021年5月16日 (日) 17:21
- 野や人脈は、崋山の発想を大きくするために得がたいものとなった。代表作に当時の風俗を写生した「一掃百態図」など。また、文人としては随筆紀行文である『全楽堂日録』『日光紀行』などを残し、文章とともに多く残されている挿絵が旅の情景を髣髴とさせるとともに、当時の文化・風俗を知る重要な資料となっている。…34キロバイト (4,329 語) - 2024年11月25日 (月) 02:19
- らと共に海峡を渡ってアムール川下流を調査した。その記録は『東韃地方紀行』として残されており、ロシア帝国が極東地域を必ずしも十分に支配しておらず、清国人が多くいる状況が報告されている。なお、現在ロシア領となっているアムール川流域の外満洲はネルチンスク条約により当時は清領であった。…18キロバイト (2,717 語) - 2024年8月21日 (水) 07:16
- 」の呼称がすでにあった。須賀(すか、「須」は音の仮借)は州処、須可(用例:万葉集/第十四巻第14巻3575)とも書かれ、砂丘で小高い所を意味する(「洲」及びその代用字「州」だけで水で囲まれた土砂の盛り上がった所を表す。)。現在の町名、中洲一丁目から五丁目までは1966年(昭和41年)からのもので、…36キロバイト (5,536 語) - 2024年11月4日 (月) 01:04
- 『中国・激動の世の生き方』(1979年、毎日新聞社)のち文春文庫 『午後八時の男たち トップが語る/強い企業の秘密』(1983年、光文社)のち文庫 『アメリカ生きがいの旅』(1984年、文藝春秋)のち文庫 『本田宗一郎との100時間 人間紀行』(1984年、講談社)「燃えるだけ燃えよ」文庫 『聞き書き 静かなタフネス10の人生』(1986年、文藝春秋)のち文庫…25キロバイト (3,235 語) - 2024年9月14日 (土) 05:48
- 受賞作『タイムスリップ・コンビナート』は「誰だかよくわからない人」からの電話で呼び出されて電車に乗って海芝浦駅へ向う様子を描写したものである。鉄道紀行文作家・宮脇俊三は、『時刻表2万キロ』の旅で初めてこの駅を訪れた後、「どこか旅へ行ってみたいが遠くへ行く時間のない人は、海芝浦駅へ行ってみると良い」…19キロバイト (2,208 語) - 2024年8月18日 (日) 08:28
- - 2010年3月 / 同年9月 - 2013年9月) - キャスター TBSニュース 日曜担当(不定期)-TBSラジオ 黒木奈々・汾陽麻衣の屋久島紀行(TBSチャンネル、2009年7月18日)- ナビゲーター SUNDAY FLICKERS(JFN、2014年10月5日 - 2015年6月28日、2017年10月1日…7キロバイト (758 語) - 2024年7月15日 (月) 14:52
- 』と呼ばれる日記をつけ始める。この日記は春水が江戸勤番となったため留守中の頼家の家事育児を知らせる目的でつけられたものがその後も続き、旅行の際には紀行文や和歌も添えられ、生涯59年間に渡って綴られている。春水による日記『春水日記』と共に後に山陽の研究のみならず当時の風俗や儒者の研究などに用いられる貴重な資料となっている。…8キロバイト (1,127 語) - 2023年12月4日 (月) 21:42
- 山丹交易 (カテゴリ 満洲の歴史)って筆録されて文化8年(1811年)に幕府に提出された『東韃地方紀行』中巻(「デレン在留中紀事」)には、黒竜江下流のデレンの集落に清朝によって設けられた「満州仮府」における山丹交易や北方諸民族が清朝の役人に進貢するようすが詳細な解説文やイラストレーションによって描写されている。…13キロバイト (1,858 語) - 2024年9月17日 (火) 02:36
- シンクレティズム紀行』人文書院 1992 『南洋・樺太の日本文学』(筑摩書房 1994年) 『海を渡った日本語―植民地の「国語」の時間』(青土社 1995年) 『戦後文学を問う―その体験と理念』(岩波新書 1995年) 『「大東亜民俗学」の虚実』(講談社選書メチエ 1996年) 『満洲崩壊―「大東亜文学」と作家たち』(文藝春秋…11キロバイト (1,438 語) - 2024年9月8日 (日) 15:38
- 間島省 (カテゴリ 満洲国の行政区分)に、1945年(康徳12年)には国務院の直轄とされた。 紀行文「滄茫たる北満洲」『三千里』(1936年2月号)に以下の記載がある。「延吉市の旧名は局子街。現在の間島省の首府である。従来に、龍井は間島の朝鮮人の中心で、延吉は中国人の中心だ。満洲事変以後、京図線が開通し、間島省の首府が延吉市となった。…14キロバイト (2,199 語) - 2024年9月23日 (月) 08:23
- 群書類從卷第三百二十七 紀行部一 作者:増基 編者:塙保己一 姉妹プロジェクト:Wikipediaの記事, データ項目 『増基法師集』(ぞうきほうししゅう)は平安時代の歌集。『いほぬし』『庵主日記』とも。平安期の私家集であるが、巻頭に30首の熊野紀行、巻末に50首の遠江日記を据えていることから、紀行文
- のレベルまで高めたと言われています。俳句を読みながら、江戸をたって東北地方をめぐり、北陸を経て美濃国大垣(岐阜県大垣市)にいたるまでの旅についての紀行文『おくのほそ道』などが有名です。 絵画も大衆化し、このころ菱川師宣(ひしかわもろのぶ)が浮世絵(うきよえ)を創始しました。浮世絵は、版画の一種で何