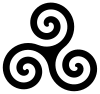ウアトネ
アイルランド神話においてウアトネ(古アイルランド語:Úaithne、現代発音:発音 [ˈuənʲə])は、ダグダの竪琴弾き。
かねてはダグダの竪琴の名(楽器の固有名)と解釈されていたが、近年の訳出では人物名ととられる向きが多い( § 出例を参照)[3]。
ただし辺見葉子は、"ウアトネという竪琴弾きは、「人物」というよりも、竪琴から旋律を引き出すダグダの能力を具現化したような存在ではないかと思われ"る、と解説する[4]。
出例
[編集]マグ・トゥレドの戦い
[編集]『マグ・トゥレドの第二の戦い』の記述によれば、ダグダの竪琴弾きウアトネ[注 1]が敵軍のフォウォレ族に連行されていた。終戦となり、ダグダは敵側の[宮廷の]饗宴館[注 2]に乗り込んで、ブレス(敵将、フォウォレだが神族の王座につき圧政により戦争に)やその父をみつけ、その壁にダグダの竪琴が置かれていた。ダグダの竪琴には二つの名前があり、すなわち「二つの野の樫」(仮訳和名[注 3]、原語名:Daur Dá Bláo)[7][10][注 4]と「四つ角の音楽」[11] あるいは「正規[調律]の四角形」(いずれも仮訳和名、原語名:Cóir Cetharchair)であった[13][14]。ダグダは(竪琴の)音楽を封じていたので、その名前で呼び寄せねば鳴らすことはできなかった。ダグダが(二つの)名前で呼ぶと(その詩歌が挿入される)、竪琴はみずからの意志で壁を離れてやって来たが、ついでに軌道上の九人の男を殺戮した[7][8]。
たとえばグレゴリー夫人による再話では、この場面に出てくる「ウアトネ」を人物でなくダグダの「竪琴」だとしているが、他にも例はある[注 1]。原文中の単語 cruitt の判断がきわどく、「ハープ」・「ハープ奏者」のどちらともとれる[3]。この点、辺見葉子も、上述したようにウアトネは人物ではなく、ダグダの能力の擬人化ではないかとみている[4]。その根拠だが、『マグ・トゥレドの第二の戦い』の展開状況から導いた結論である:すなわち、ダグダ、ルグ、オグマの三人でウアトネを救出するはずだが、その後、竪琴の言及はあれど竪琴弾きは現れない。そして竪琴弾きではなくダグダ自身が竪琴を弾く。その「三つの旋律」[注 5]で敵をかく乱、「眠りの旋律」が効いて敵は眠りにおち、三人は脱出した、とあるが、「三人」がダグダ、ルグ、オグマのことであれば、救助されているはずのウアトネの姿はどこにもいない、よってウアトネは人ではなく"シンボリカルな存在"であろう、と考察される[4][15]。
フロイヒの牛捕り
[編集]また『フロイヒの牛捕り』によれば、 ダグダの竪琴弾きウアトネは、妖精ボアンドすなわちボイン川の女神とのあいだに三人の息子をもうけ、彼らもいずれ竪琴弾きとなった。息子らの名は 「嘆きの旋律」Goltraige 、「笑いの旋律」Gentraige、「眠りの旋律」Súantraigeで、彼女の分娩中[17] にウアトネが奏でた「三つの旋律」から名付けられたという[23][4][注 6]。
語釈
[編集]電子版『アイルランド語辞典』(eDIL)では、úaithneには8つの項(8種の語義)がもうけられており、定義7としてウアトネ「ダグダの竪琴」としている[1][3]。ところが、同じ定義7によれば、アイルランド語彙集で「オルフェウス」と語釈されており[1]、とするならば人物のはずである。
ウアトネの竪琴は、『牛捕り』の旧訳者によれば、これは"出産 Childbirth"の意味である[21](eDIL定義2に合致する)。
ウアトネの竪琴は、辺見によれば「詩や音楽における調和」を意味するものであり[4]、これは eDIL定義5 "concord in music" に合致する[25]。フランスの学者フィリップ・ジュエ(Philippe Jouët)も、ダグダの竪琴の名として、ウアトネを「調和」の意味としており、竪琴の別名も「四角の調和」と解すれば、つじつまがあうとしている[26][14]。ジュエは、別の著作で、ウアトネには"木"、"労(出産・分娩)"、"柱"、"調和"などの意味があるが、連続の比喩によるものだと仮説している[27][要ページ番号]。
大衆文化
[編集]池上良太著『図解 ケルト神話』では「ダグザの竪琴」の名として「ウーズネ」[?]、「ダウル・ダ・バラオ」、「コイア・ケサルハル」をもちいる[28]。
アニメ作品『戦姫絶唱シンフォギア』においてキャロル・マールス・ディーンハイムが「ダウルダブラ」という器具をもつ[29]。
注釈
[編集]- ^ a b ウアトネを竪琴弾き("harper"、すなわち人名)とするのは、グレー英訳や辺見に準じた。グレゴリー夫人の再話では、楽器の固有名(ダグダの竪琴)と解している[5]。オカリー講義(1873年)では、本文で弾き手("harper")としているものの、欄外では竪琴("cruit", "harp")となっている(編者のサリヴァンとの見解の違いか?)[6]。
- ^ flettech>fletech、"a banqueting-house or hall"(eDIL)、Gray訳も"banqueting hall"
- ^ 辺見を典拠とできようが[4]、辺見はGrayの英訳名や英文解説のまま引用しており、和訳名を提示していない。ここは「二つの野の樫」とGrayから重訳し、「正規[調律]の四角形」については解釈にもとづき命名し、それぞれ仮訳和名を記している。
- ^ 異本:Daurdabla, Durdabla[9]
- ^ § フロイヒの牛捕りを参照。
- ^ Meid 編では "Goltraiges & Gentraiges & Súantraiges"だが[18]、辺見や Budgey の解説通り、"-s"は落とす[24]。Gantz 英訳では "Goltrade, Gentrade and Súantrade"。
出典
[編集]- 脚注
- ^ a b c eDIL s.v. "7 úaithne"
- ^ eDIL s.v. "1 cruitt". "harper".例は Fraech: "Úaithne c.¤ in Dagdai"
- ^ a b c eDIL 辞典も、"úaithne (7)" の項では楽器("The name of the Dagda's harp") として、『フロイヒの牛捕り』のTBFr.本(Dillon&Byrne 1933年 編本)を挙げているが[1]、cruitt の項では楽師("harper")として『フロイヒの牛捕』のFraech本(Meid 1967年編本)を挙げており[2]、矛盾している。
- ^ a b c d e f g 辺見葉子『中世アイルランド文学における竪琴というモノ』モノ学・感覚価値研究会〈2007年度第3回研究会発表〉、2007年11月4日。
- ^ a b Gregory, Lady (1910). Gods and Fighting Men: The Story of the Tuatha de Danaan and of the Fianna of Ireland. London: John Murray. p. 60
- ^ a b O'Curry, Eugene (1873). Sullivan, William Kirby. ed. On the Manners and Customs of the Ancient Irish. 3. London: Williams and Norgate. pp. 213–214
- ^ a b c Gray, Elizabeth A. ed. tr. (2003), Cath Maige Tuired: The Second Battle of Mag Tuired, Proof corrections by Benjamin Hazard, CELT: Corpus of Electronic Texts, §163–§164, p. 70; English translation: §163–§164, p. 71
- ^ a b c Brown, Arthur Charles Lewis (1966). Gods and Fighting Men: The Story of the Tuatha de Danaan and of the Fianna of Ireland. New York: Russell & Russell. pp. 233–234, 229, 368
- ^ a b c Stokes, Whitley ed. tr. (1891), “The Second Battle of Moytura”, Revue Celtique 12: §§163/164, pp. 108, 109
- ^ 似たような語釈に、A.C.L. Brown: "oak of two fields";[8] Stokes: "Oak of two greens[?]".[9]があるが、グレゴリー夫人の再話では"the Oak of Two Blossoms"とされる[5]。
- ^ A.C.L. Brown and Stokes: "four-angled music";[8][9] Lady Gregory:"the Four Angled Music"
- ^ Gray, Elizabeth A. ed. tr. (1982). Cath Maige Tuired: The Second Battle of Mag Tuired. Irish Texts Society. notes to §163, p. 113
- ^ Gray 訳では竪琴の名前は原文のままで"(Now that harp had two names, Daur Dá Bláo and Cóir Cetharchair)"[7]、その注釈では前者は "Oak of Two Meadows"と意訳されるが、後者は "coir" ‘proper, fitting, just, true’ +‘four-sided, square, rectangular’の複合語という解説であって訳名は提示していない[12]。これらを辺見もほぼそのまま(アイルランド語名、英語の語釈で)転用しており、ダグダの竪琴が"四角い形状"であったろう、と付記する[4]。
- ^ a b オカリー講義集によると、 coir は "調整 arrangement, adjustment"の意であるとしており、こと楽器に関するならば、 "竪琴の正しい調律あるいは調和 proper tuning or harmonizing of harp"という意味で伝わっている、とする[6]。
- ^ Gray英訳では"He [the Dagda] played sleep-strain to them, and the hosts fell asleep.. the three of them escaped unhurt from the Fomorians.."
- ^ eDIL s.v. "lámnad". With example from TBFr,: "in tan bóe in ben oc l.¤"
- ^ 原文中 lámnad、eDIL定義は "act of giving birth, parturition" で、この箇所の用例が挙げられる[16]。
- ^ a b c Meid, Wolfgang, ed. (2010), Táin Bó Fraích, Electronic edition compiled by Beatrix Färber, CELT: Corpus of Electronic Texts, §10, p. 4
- ^ Crowe, J. O'Beirne (1870). “Táin Bó Fraich [The Spoil of the Cows of Froech]”. Proceedings of the Royal Irish Academy: Irish MSS. series 1, pt. 1: Irish, pp. 140, 142; English tr. pp. 141, 143. JSTOR 20706388.
- ^ Leahy, A. H., tr. (1906). “Tain Bo Fraich”. Heroic Romances of Ireland. 2. London: David Nutt. p. 22
- ^ a b Crowe (1870), n13, p. 162.
- ^ Gantz, Jeffrey, tr. (1981). “Cattle Raid of Fróech”. Early Irish Myths and Sagas. Penguin UK. ISBN 9780141934815
- ^ 原典: Meid 編[18] および Crowe 編[19]。 Crowe (1870)の英訳[18]、 その改訳である Leahy (1906)[20] はいずれもウアトネを楽器 "harp" と訳すが、Crowe は注釈で人 "harper"とも訳せることを述べている[21]。 Gantz (1981) 英訳では "Úaithne, the Dagdae's harper".[22]。
- ^ Budgey, Andrea (2002). “8. Commeationis et affinitatis gratia: Medieval Musical Relations between Scotland and Ireland”. In McDonald, Russell Andrew. History, Literature, and Music in Scotland, 700-1560. University of Toronto Press. pp. 226. ISBN 9780802036018
- ^ eDIL s.v. "7 úaithne"
- ^ Jouët, Philippe (2007). L'aurore celtique dans la mythologie, l'épopée et les traditions. Yoran Embanner. p. 394. ISBN 9782914855334
- ^ Jouët, Philippe (2012). Dictionnaire de la mythologie et de la religion celtiques [Dictionary of Celtic mythology and religion]. Yoran Embanner. ISBN 9782914855921
- ^ 池上良太「No.091 ダウル・ダ・バラオ(コイア・ケサルハル);」『図解 ケルト神話』新紀元社〈F-Files No.044〉、2014年04月30日 。ISBN 978-4-7753-1178-3。
- ^ “ダウルダブラ” [Daur da Bláo]. シンフォギアGX. 2 February 2024閲覧。