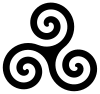ドルイド

ドルイド(Druid)は、古代社会における祭司のことだとされてきた。日本語ではドゥルイドとも表記する。女性形はドルイダス(Druidas)。

ドルイドは宗教的指導のほか、政治的指導、公私の争い事の調停と、古代の社会に重要な役割を果たしていたとされていたが、実際、彼らがどのようなことを行っていたのか、よくわかっていない。ドルイトに関するほとんどのことが近世に作られたものであり、19世紀にはウエールズにそれを実践する者たちもいたが、オカルト趣味とみなされている。
カエサルの『ガリア戦記』 (紀元前58年 - 51年) によれば、ドルイドの社会的影響力はかなり大きかったようである。争い事の調停あるいは裁決をし、必要があれば当事者に賠償や罰金を課した。ドルイドの裁決を不服とした者は、社会的地位や信用を失った。このほか、ドルイドは兵役や納税を免除される特権的地位にあった。
ドルイドの宗教上の特徴の一つは、森や木々との関係である。プリニウスの『博物誌』によると、ドルイドが珍重したのはヤドリギの中でもロブル(オーク)に寄生した物だけで、彼らはオークの森を聖なる地とした。彼らはヤドリギを飲み物にするとどんな動物も多産となり、あらゆる毒の解毒剤になると信じた[1][2]。
近代になって発掘された古代ガリアの奉納物には、オークで作られた物が多い。また、ドルイドが四葉のクローバーなどの希少な植物を崇拝していたということが伝えられている。なお、神木の概念自体はケルト人に留まらず世界中に存在する。
比較宗教学においてドルイドは、古代ローマのフラミネスや古代インドのブラーフマナ(婆羅門)と関連付けられている[3]。
古典文献の取扱い
[編集]先住の人々の社会は本来無文字文化であったが、他文明との交流によって文字を獲得した。ガリアではラテン文字[4]とギリシア文字[5][6]を使用していた。またブリタンニアにおいて、ローマ帝国の入植以前にパピルスを輸入した記録があり、当時の知識層が文字を書き記していたことが窺える。アイルランドでは、4世紀末に独自のオガム文字を使用していたと思われる。[7]。
しかし教義について、ドルイドは文字で記録せず口伝伝承を行った。そのため、ドルイドについての記録はギリシアやローマ帝国、修道士たちの「外からの目」によるものしか残されていない。歴史の一部としてドルイドを扱う場合、こうした文献の記述を無批判に受け入れることはできない。
語源
[編集]語源的には「ドルイド」はdru-vid-sと分解され、vidは「知る」「知恵」などを意味する[8][9]。druについてはオークの木を意味するという見解と強意の接頭辞とする見解とがある。前者は1世紀の博物誌にも記されている[10]ほど歴史のある見解であり、少なくとも1968年には主流派を成していた[11]。が、アイルランドにオーク崇拝が見られないこと[12][13]、ドルイドの職能はオークの木にまつわる祭祀に限らず広範に亘ったこと[14]などの指摘により、現在は後者が有力視されている[15]。
ガリアのドルイド
[編集]ガリアの社会構成
[編集]ガリアの社会は他のインド・ヨーロッパの民族にも見られるような知識層(祭司)・騎士・民衆の三層構成を成していた(三機能仮説)。こうした階層分化は前七世紀頃(ハルシュタット後期)の古代社会で既に発生していた[16]。この知識層がドルイドである。『ガリア戦記』において民衆の身分は奴隷に例えられ、それほど知識層と騎士の特権は強かった。だがこの頃ドルイドの権勢は最盛期を過ぎ下り坂であったと考えられている。
ガリアの知識層を指す単語としてはドルイドのほかにもウァテス・バード・サケルドス[17]・グトゥアテル[18]・セムノテオイ[19]など様々なものが文献に登場する。このうちウァテスとバードについては古典文献の記述[20]から異名ではなく実際にドルイドと共に知識層を構成していた階級であると考えられている。だがこの三階級の職能は完全には分化しておらず、一部で重なり合っているためその関係には諸説がある。
- ドルイド
ガリアの知識層の中で最高位を占めるとされる階層。職能としては祭司と政治的指導者を併せ持つ。このため、文献の中でサケルドス(祭司)ではなくドルイドという表現が使われた場合、書き手はその人物を政治的指導者だと強調している可能性がある。
- ウァテス
占い師。先述の通りドルイドも占いを行っていたと考えられるため、ウァテスをドルイドの中で下位の序列を指すとする者もいる[21]。その一方で、同じ理由で彼らがドルイドと同等の権利を有したとする者もいる[22]。またポセイドニオスがドルイドの中で生贄に直接手を下す特別な集団にウァテスという別の名称をあたえることで、ドルイドを生贄の儀式から切り離したのではないかという意見もある[23]。
- バード
吟遊詩人。ドルイドとウァテス程ではないがその職能はドルイドと重なりあう部分がある[24]。
ガリア人の神
[編集]人身御供の儀式
[編集]複数の古典文献において、ドルイドが人身御供の儀式に関わっていたことが記されている。しかしドルイドが自身の教義を残さなかった以上、人身御供の儀式を裏付ける考古学的な根拠を発見するのは困難となる。一見当時の生贄と思われる遺体が発見されてもそれが本当に生贄なのか罪人への処罰だったのか判断するのは難しい。さらにいえば罪人の処罰を生贄の儀式に利用した可能性や、戦死などの理由で死亡した遺体を宗教的儀式に利用した可能性もある。
イギリスで発見された湿地遺体であるリンドウ・マンは、人身御供の犠牲者であるとする見方がある。「彼」は健康状態がよく、爪が整っており高い身分の人間だったと推測されている。リンドウ・マンの腸にはヤドリギの花粉が残されており[25]、これはプリニウスが記したヤドリギを珍重し薬として用いるドルイド像を連想させる。しかし彼がドルイドによる人身御供の儀式の犠牲者、あるいは自ら望んで生贄となったドルイドそのものであったとしても、ガリアで同様の儀式が行われていたかどうかは断定できない。

グンデストルップの大釜の内側のプレート Eでは巨大な人型に捕まえられた人間が大釜に浸されようとしており[26]、 これが残酷な人身御供の儀式を示していると捉える見解がある。しかしこれについては三重の死の一部を指していると見る向きもあり、またそもそも大釜自体がトラキア起源であり、プレートに示されているのは儀式ではないとする説も有力である。
関連項目
[編集]- ディウィキアクス - カエサルによるガリア征服の協力者となったハエドゥイ族の指導者。キケロは『予言について』で彼のことをドルイドであると記しており、それが事実であるとすれば唯一の歴史に名を残したドルイドであるという事になるが異論も多い。
- ミーリウク・マク・ブアン(Míliucc maccu Buain) - アイルランドのドルイドであった可能性のある人物。ムルフーの『パトリック伝』では「異教徒」、ティーレハーンの『コレクタネア』では「魔術師」とされている(『オックスフォード ブリテン諸島の歴史 vol.2』p.巻末35)。
- サン島 - ポンポニウス・メラの"Sena"は、フランスブルターニュのこの島に、かつて予言などの超自然的力を具えた六人の女ドルイドがいたと記す[27]。
- ノルマ (オペラ)
- ヤドリギ
- 答えのない質問 - チャールズ・アイヴズの楽曲。
脚注
[編集]- ^ もっとも、こうしたドルイドの信仰をプリニウスは完全に迷信と見做していた。
- ^ プリニウス 2009, p. 290.
- ^ 中沢 1997, pp. 322–323.
- ^ 「ワットモウによれば『それまで書字は一般的な行為ではなかったが、ラテン語の流入とともに、自由に使える技術となった。それゆえに曲りなりにも文字が書きはじめられたとき、ほとんど例外なしに、ラテン語とラテン文字が使われることになった』のである。」(ピゴット 2000, pp. 53–54)
- ^ 「またガリア南部からは、ギリシア文字で書かれた多数の碑文が発見されている。」(ピゴット 2000, p. 54)
- ^ 「スイスで出土した前1世紀の鉄の剣には『コリシオス』という人名がギリシア文字で刻印されていたし、カエサルも曖昧な記述ながらガリアの知識層がギリシアのアルファベットにある程度通じていたことを伝えている。」(ピゴット 2000, p. 99)
- ^ 例えばコリニーの暦はドルイドの手によるものとされている。
- ^ サンスクリットのvedaと同源である(鶴岡 1999, p. 79)
- ^ ルドルフ・トゥールナイゼンによる(中沢 1997, p. 270)
- ^ 「そのために(ロブルを表すドリュスという)ギリシア語の言い換えから、ドルイドと称されたのではないか、と推測できるほどである。」(プリニウス 2009, p. 290)
- ^ 「現在(原著の発行された1968年)のところ、プリニウスなどの古典古代の識者が指摘したのと同様、ギリシア語の『樫』(drus)と関係があるとみなす傾向にある。」(ピゴット 2000, p. 182)
- ^ ヤン・デ・フリースによる(中沢 1997, p. 301)
- ^ アイルランドにおける樹木崇拝の対象はイチイ、ナナカマド、ハシバミなどであった(中沢 1997, p. 301)。
- ^ フランソワズ・ル・ルーとクリスチャン・J・ギョンバールによる(中沢 1997, p. 321)
- ^ 「現在では強意の接頭辞とする説のほうが有力である。」(中央大学人文科学研究所 1991, p. 19)
「現在では『多く』を意味する〈強意の接頭語〉と解釈する説が有力である。」(木村 2012, p. 132) - ^ 原 2007, p. 137.
- ^ グリーンは『ガリア戦記』においてガリアの知識層を指してサケルドスという単語が使われたとしている(グリーン 2001, p. 67)が、鶴岡は「古典古代のドルイドの記述のうちにドルイドを神官や僧侶-ギリシア語でἱερενςあるいはラテン語でsaerdos-と定義しているものはない。」(中沢 1997, p. 16)としている
- ^ 宗教にまつわる高官の称号でありガリアの四つの碑文に登場する。『ガリア戦記』8-38にカルヌテス族のグトゥアテルが登場するがこれを人名として解釈するのは誤りである(マイヤー 2001, p. 78)。
CIL XIII, 1577 adlector(?)] ferrariar(um) gutuater praefectus colon(iae) [3] / [3] qui antequam hic quiesco liberos meos [3] / [3] utrosq(ue) vidi Nonn(ium) Ferocem flam(inem) IIvirum bis [
CIL XIII, 2585 C(ai) Sulp(ici) M(arci) fil(ii) Galli omnibus / honoribus apud suos func(ti) / IIvir(i) q(uinquennalis) flaminis Aug(usalis) P[3]OGEN(?) / dei Moltini gutuatri(?) Mart(is) / sevir cui ordo quod esset civ(is) / optimus et innocentissimus / statuas publ(icas) ponendas decrev(it) // ]DO[3]VSVA[3]/diorata Mato Antullus / Mutilus Combuocovati f(ilius) / ex v(oto) s(olvit) // Iovi et Aug(usto) / sacrum
CIL XIII, 11225 Aug(usto) sacr(um) / deo Anvallo / Norbaneius Thallus gutuater / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL XIII, 11226 Aug(usto) sacr(um) / deo Anvallo / C(aius) Secund(ius) Vi/talis Appa / gutuater / d(e) s(uo) p(osuit) ex voto - ^ "semnotheoi" 月川はその意味を「尊き神々」と解説している。(中沢 1997, p. 329)
「そしてケルト人やガラタイ(ゴール)人たちのところにはドリュイデスないしはセノムテオスと呼ばれる人たちがいたのであり、」(ラエルティオス 1984, p. 13) - ^ 「あらゆるガリア人のうち格別に敬われている人々は、一般に三つの階級がある。バルドイと預言者とドリュイダイである」(ストラボン『地理誌』4.4)(中沢 1997, p. 342)
「この地域一帯では、人々は次第に文明化され、高度な学問の探求が盛んだが、それはバルディ〔バード〕とエウハゲス〔預言者〕とドリュシダエ〔ドルイド〕が創始したものである。」(アンミアヌス・マルケリヌス『ローマ史』15.9.8)(中沢 1997, p. 345) - ^ マッカーナ 1991, p. 14.
- ^ 「『ウァテス』は占いの担当者で,したがって非常な権力を持っていた.ドルイド僧と同様の宗教上の権限を有し,かつ『物理』に関する知識があるとみなす学者もいるくらいなので、その権勢の程がしのばれる.」(デュヴァル 2001, p. 627)
- ^ 中央大学人文科学研究所 1991, p. 30。これを述べた月川は「思いつき」であると冒頭で断りを入れてはいる(中央大学人文科学研究所 1991, p. 19)
- ^ 失われたポセイドニオスの著書に、ドルイドが行ったとされる戦の仲裁にバードが関わっていたとする記述があったと考えられる(中央大学人文科学研究所 1991, p. 30)
- ^ グリーン 2000, p. 129.
- ^ グリーンはストラボンの『地理学』を引用し、喉を切り裂いた人間の傷口から流れる血を大釜に集めようとしている場面であるという解釈も可能であることを示している(グリーン 2000, p. 118)。
- ^ 『ブルターニュのパルドン祭り --日本民俗学のフランス調査』新谷尚紀 関沢まゆみ 悠書館 2008 p.284
参考文献
[編集]- 木村正俊『ケルト人の歴史と文化』原書房、2012年。ISBN 4562048735。
- グリーン, ミランダ・J 著、井村君江・大出健 訳『図説 ドルイド』東京書籍、2000年。ISBN 4-487-79412-9。
- 中央大学人文科学研究所『ケルト 伝統と民族の想像力』中央大学出版部、1991年。ISBN 4-8057-5305-6。
- 鶴岡真弓; 松本一男『図説 ケルトの歴史 文化・美術・神話を読む』河出書房、1999年。ISBN 4-309-72614-3。
- デュヴァル, ポール=マリー [in ドイツ語] (2001). "大陸ケルト 宗教と神話 ガリア人". In イヴ・ボンヌフォワ (ed.). 世界神話大事典. 大修館書店. ISBN 4469012653。
- 中沢新一; 鶴岡真弓 月川和雄『ケルトの宗教 ドルイディズム』岩波書店、1997年。ISBN 4-00-000645-2。
- 原聖『興亡の世界史07 ケルトの水脈』講談社、2007年。ISBN 978-4-06-280707-4。
- ピゴット, スチュワート 著、鶴岡真弓 訳『ケルトの賢者 「ドルイド」』講談社、2000年。ISBN 4-06-209416-9。
- プリニウス 著、大槻真一郎 他 訳『プリニウス博物誌 植物編』(新装)八房書房、2009年。ISBN 978-4-89694-931-5。
- マイヤー, ベルンハルト 著、鶴岡真弓 平島直一郎 訳『ケルト辞典』創元社、2001年。ISBN 4-422-23004-2。
- マッカーナ, プロインシァス 著、松田幸雄 訳『ケルト神話』青土社、1991年。ISBN 4-7917-5137-X。
- ラエルティオス, ディオゲネス 著、加来彰俊 訳『ギリシア哲学者列伝』岩波書店、1984年。ISBN 400336631X。
関連書籍
[編集]- ジェームズ, サイモン 著、井村君江 吉岡晶子 渡辺充子 訳『図説ケルト』東京書籍、2000年。ISBN 4-487-79411-0。