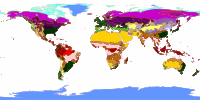ノート:サバナ気候
本記事の編集に関して
[編集]本記事は一時期分量が8,000~9,000バイト程度ありましたが、平成29年9月7日にIPユーザーによって殆どが除去され、白紙化に近い状態となりました。その後有足魚さんが修正され、概要部を整備してくださいました。先ほど私が分布地域についての説明を加筆したところです。
しかし、要約欄やノート欄での説明もなく突然大半が除去されたため、白紙化荒らしと解釈せざるを得ないようにも思います。確かに除去前のページでは出典が一切ありませんが、除去後のページでは気候ではなく米の生産に関する記述のみが残されているため(これも無出典ですが)、百科事典の品質改善のための編集とは解釈できないように私は考えます。
すぐ差し戻した方がよいのかもしれませんが、有足魚さんが出典つきの加筆をされていたこともあり、戸惑っています。出典のある記述を除去することは慎重に行う必要がありますし、有意な編集を活用することは記事の質の向上のために重要でしょう。このため、以下2つのうちどちらの方針をとるか、皆さんの意見を伺いたく思います。
- 差し戻したうえで出典追加を行っていくか、
- 新たに記事を作り直していくか
希望や、編集に関する意見などがあれば以下にご記入ください。ご意見をお待ちしています。よろしくお願いします。 --郊外生活(会話) 2017年10月7日 (土) 10:12 (UTC)
- 自分が編集する前に履歴をよく確認しておくべきでしたね。さて、出典があるからと言って記述を除去してはいけないわけではありません。記事がより優れたものになるなら構わないのです。もちろん記述に出典はあるべきですが、確かに事実らしいことで、将来的に出典を用意できそうなら一時的に{{要出典}}を付けて記述を残しておくという手もあります。--有足魚(会話) 2017年10月7日 (土) 10:48 (UTC)
 返信 (有足魚さん宛) 返信ありがとうございます。私が現実世界で忙しいこともあり、新たに加筆することで改善を行うのには時間がかかると考えています。そのため一旦差し戻して、有足魚さんの加筆をWikipedia:ウィキペディア内でのコピーに基づき加筆する形でいきたいと思っています。一時的には除去となりますが、除去後すぐに復元します。
返信 (有足魚さん宛) 返信ありがとうございます。私が現実世界で忙しいこともあり、新たに加筆することで改善を行うのには時間がかかると考えています。そのため一旦差し戻して、有足魚さんの加筆をWikipedia:ウィキペディア内でのコピーに基づき加筆する形でいきたいと思っています。一時的には除去となりますが、除去後すぐに復元します。- また出典追加と出典なき記述への対応は、温暖湿潤気候での編集と同様の方針で考えていることも申し添えておきます。 -郊外生活(会話) 2017年10月7日 (土) 12:47 (UTC)
![]() 報告 差し戻しのうえ、大量除去後の有意な加筆を復元しました。編集の要約でコピー元の版および当該記述を加筆された方のお名前を記してあります。何か不都合がありましたらこちらでお知らせください。 --郊外生活(会話) 2017年10月22日 (日) 16:09 (UTC)
報告 差し戻しのうえ、大量除去後の有意な加筆を復元しました。編集の要約でコピー元の版および当該記述を加筆された方のお名前を記してあります。何か不都合がありましたらこちらでお知らせください。 --郊外生活(会話) 2017年10月22日 (日) 16:09 (UTC)
Omotechoさんの編集について
[編集]2024-06-16T06:23:37(UTC)版(特別:差分/100743375)のOmotechoさんの編集についてです。
- {{要ページ番号}}の件、申し訳ありませんでした。ページ数を明記しました。問題なければ他のケッペン気候区分記事群でも同様の対応を行います。
- サバナ気候#参考文献に{{参照方法}}を貼られていますが、私はこのテンプレートは適切でないと考えます(記事冒頭の{{出典の明記}}が適切な対応と考えます)。Omotechoさんが追加された文献を除けば、参考文献で掲載されている文献は高校検定教科書地図帳2冊(帝国書院、二宮書店)と、『アメリカ』(朝倉書店)だけで、いずれも私が追加したものです(2017-10-22T15:35:36(UTC)版(特別:差分/66025433)および2021-01-10T18:11:24(UTC)版(特別:差分/81275312))が、地図帳に関しては、この記事の参考文献として使えるのは世界の気候区の地図のページにおける、どこの地域がどこの気候区にあたるかの記載で、『アメリカ』は、北米の都市がどの気候区にあたるかの解説で、それぞれこの記事の現在の内容で出典として明示できそうな箇所は既に全部提示しています。なので、現在の版で脚注が提示されていない記述は、これらの3冊に基づくものの脚注が用いられていないといった類ではなく、もともと無出典で加筆されていた内容です。私が編集を行う前の版(例えば2017-04-23T08:25:52(UTC)版)で既に記載されていた内容も少なからず確認できると思います。このため、{{参照方法}}ではなく{{出典の明記}}が適切なタグかと思います。ただ、この記事では主要な参考文献となるべき気候学の文献が全く提示されていないといった問題がありますので、後日別途対応を検討しています。(余談ですが、高校地理におけるケッペン気候区分のウェイトに対して、大学の気候学であまり取りあげられないので、文献探しは意外と苦労します)--郊外生活(会話) 2024年6月22日 (土) 15:03 (UTC)
- 迅速なご返答に感謝し、脚注に1件ずつ掲載ページを示してあるので、「参照方法」テンプレートの使い方は外れていると同意します。図書館に行くのもネット上のデータベースでも、これら資料を調べ尽くせていない点でためらうなら、記事冒頭に「出典の明記」をお願いするべきでした。
- 考えていたことは、本文と参考資料欄の連携というよりも、参考文献欄では、地図帳であっても脚注で示した参照ページを全件、羅列するかどうか。資料調べをする際に便利だけど必須ではないです。それは「参照方法」テンプレートでは示せません。
- 見るべきページが多すぎる。見出し「分布」によると14項目。
- Aw:海外12件、国内1件。
- As:1件(ハワイ諸島のごく一部)
- 仮の結論:示すべきページ数が大量で煩雑すぎるので、現状の記述で十分。
- [引用]
- 帝国書院編集部『新詳高等地図』帝国書院、2016年。ISBN 978-4-8071-6295-6
- 二宮書店編集部『詳解現代地図』二宮書店、2017年。ISBN 978-4-8176-0397-5
- [ここまで引用]
- 見るべきページが多すぎる。見出し「分布」によると14項目。
- 以上を考えたのに判断できずに止まり、提案もしくは質問に移れません。
 コメント「へー、ウィキペディアにはこう説明していあるんだ」という誇らしさ。そう感じるのは身内びいきで、出典はご趣旨のとおり記載の担保という第一の役割を担います。読み手には、信頼できる観測や知見に触れる扉という役目もますます大切かと感じます。
コメント「へー、ウィキペディアにはこう説明していあるんだ」という誇らしさ。そう感じるのは身内びいきで、出典はご趣旨のとおり記載の担保という第一の役割を担います。読み手には、信頼できる観測や知見に触れる扉という役目もますます大切かと感じます。- 横道に逸れますが、お返事の後半で「資料が探しにくい」とご指摘の点。考える機会をありがとうございます。そうすると「信頼できる知識」として示すよう、ウィキペディアに付託されるのでしょうか。そうありたいものです。--Omotecho(会話) 2024年6月23日 (日) 03:19 (UTC)
地図の典拠を書くかどうか
[編集]この件を提示する場所はポータルなどが適するようでしたらご指摘願います。今回はたまたま、コモンズで地図1点に注意喚起してあるが、何に注意するのか共有してもらえるとありがたいです。
地図の典拠を記すと良いと思います。ウィキペディアの画像の載せ方を知らないと、コモンズまで調べに行けないため。
- ウィキメディア・コモンズの示す分布図「ファイル:Köppen-geiger-hessd-2007.svg」。
- その典拠情報(2023-02-09T08:49:37(UTC)時点における Sarang による版 (linkfix) より)。
- (1)作図の参考資料あり(英語欄)。
- Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007). "Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification". Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633-1644. ISSN 1027-5606.
- (2)注意喚起あり、(ドイツ語欄) 機械翻訳経由で読みました。問題点が「欠陥」なのか「欠落」なのか判断できません。
- →(機械翻訳を編集):カラーガイド(中略)。この地図はケッペン・ガイガーによる地球の気候分布を示す。ただし、いくつかの領域で欠陥があるため今後は使用しないよう勧める。(2022年1月7日時点)。
--Omotecho(会話) 2024年6月23日 (日) 03:26 (UTC)
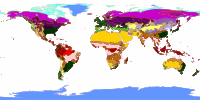
サバナ気候のページ(凡例の部分は日本語版ウィキペディアで加筆) 
ケッペンの気候区分のページ - 画像に添えられた注意書きについて、少し調べました。日本語版のみ、このページで古い画像を使っていませんか? 例えばこのページでは「Aw」は淡いサーモン色、親記事の「ケッペンの気候区分」では空色なのが気になります。
 提案 他のページは見ておりませんが、分布の画像は気候学で統一したらどうかと提案します。分布の画像がこの記事に追加された特定版は、 2014年2月8日 11:29(UTC)時点ですので、改版が妥当かどうかお聞かせください。
提案 他のページは見ておりませんが、分布の画像は気候学で統一したらどうかと提案します。分布の画像がこの記事に追加された特定版は、 2014年2月8日 11:29(UTC)時点ですので、改版が妥当かどうかお聞かせください。
- サバナ気候の画像(このページ)
- [1](a画像=コモンズ由来)の下に、表組みで凡例を加筆。)
- a画像解説
- 原典の論文について。2007年10月11日時点の更新 © CC-SA-2.5.:Peel, M. C; Finlayson, B. L; McMahon, T. A (11 Oct 2007). “Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification”. HESS (5). doi:10.5194/hess-11-1633-2007.ISSNは出典ママ。ISSN 1633–1644{{issn}}のエラー: 無効なISSNです。。
- ケッペンの気候分布の画像
- 記事に画像の典拠あり、Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007). “Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification”. Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633–1644. doi:10.5194/hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606. (PDF形式の論文: Final Revised Paper):
- コモンズより、その画像は2010年7月18日, 15:19 (UTC) 時点の版。
- 原典:World Köppen Map.png
- 作者:Peel, M. C., Finlayson, B. L., and McMahon, T. A. (University of Melbourne)
- derivative work(派生した作品=改版後):利用者:Br-Sc-94。
- 同、下欄外より転記。「この画像には画像編集が施されています。原本に対して次のデジタル的な変更が行われました。
- 編集内容:Climate change in 2009
- 編集前の原本:World Köppen Map.png:
- 編集者:Br-Sc-94
- --Omotecho(会話) 2024年6月23日 (日) 07:29 (UTC)
 コメント 分布図の画像が論文から転載されたものであるなら、キャプションで出典を明示することは問題ないと思います。むしろ、Wikipedia:検証可能性の観点から行うべきだと思います。
コメント 分布図の画像が論文から転載されたものであるなら、キャプションで出典を明示することは問題ないと思います。むしろ、Wikipedia:検証可能性の観点から行うべきだと思います。
画像をどれにするかですが、ケッペンの気候区分で用いられているc:File:Köppen World Map (retouched version).pngに関しては、日本語版(この記事に限らず)で使うのには注意を要するようにも思っています。というのは、日本の高校検定教科書の地図帳では、熱帯は赤色系、乾燥帯は黄色系、温帯は緑色系、冷帯・寒帯は青色系が用いられており(帝国も二宮も)、日本語の情報源でよく用いられている色と異なることから、日本語版読者が混乱するおそれを懸念しています。一方、凡例で色と気候区分が対応していれば問題ないという見解もあるかもしれませんが。あとは過度な気候区の細分化をしているようにも思えました。大学の自然地理学の教科書等(記事で使用した柏木(2008)のほか、『自然地理学事典』など)でも高校地理の教科書と同様、気候区分の分類はCfa(温暖湿潤気候)とCfb(温帯冬季少雨気候)を除き2文字までで、3文字目の情報は重要でないと思います。現状の画像の問題点もありますが、その一方変更案の画像もベストとは言いにくいところです。--郊外生活(会話) 2024年6月23日 (日) 09:29 (UTC)- お返事を受けて、3点お返事します。(3)について、齟齬かどうかお聞かせ願えたら誠に幸いです。
- (1)脚注。
- 再度、コモンズの使用許諾ほかを確認しました(CC-BY-SA-3.0 非移植)[※ 4]。また画像はもともと凡例がないので、以下の要件は凡例の文字原稿には及ばないと考えます。凡例を追加した日付■を調べています。
- 文案「右の論文を元にした2007-06-26(UTC)時点の作図に凡例を(■いつの日付か?)時点で追加。
- Final Revised Paper Peel, M. C; Finlayson, B. L; McMahon, T. A (11 October 2007). “Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification” (pdf). Hydrology and Earth System Sciences (HESS) (European Geophysical Society) (5). doi:10.5194/hess-11-1633-2007. NCID AA11828546.ISSN 1027-5606
- (2)2種の配色について。
- 文案「右の論文を元にした2007-06-26(UTC)時点の作図に凡例を(■いつの日付か?)時点で追加。
- どこかに補っておきたいものの、良い案は浮かびません。ウィキブックス(無償の教科書)など姉妹プロジェクトが(も)適するのか?
- (3)「サバナ気候 (Aw) の分布図」
- Awのみ抽出した図(全体図の次のネズミ色主体の図)はAwを水色で指定してあり、上記(1)の分布図と配色が合いません。対照するのは(2)で差し替えが困難と思われる気候の分布図。
- この分布図が2014-02-08(UTC)時点に追加された時には、全体の分布図はない状態だったようです。
- 削除か?
- 保持して、配色に2パターンあると加筆するか?[※ 5]
- 差し替えるなら、どの画像か?
- この分布図が2014-02-08(UTC)時点に追加された時には、全体の分布図はない状態だったようです。
- ------
- 注記
- お返事を受けて、3点お返事します。(3)について、齟齬かどうかお聞かせ願えたら誠に幸いです。
ウィキペディアの場合。
- --Omotecho(会話) 2024年6月24日 (月) 04:36 (UTC)
- @郊外生活さん、キャプションで図の典拠を添えようとしましたが、テンプレートに書き込む方法がわかりませんでした。
- 本文に注釈で加筆する方法は妥当ですか。--Omotecho(会話) 2024年6月30日 (日) 19:57 (UTC)
 コメント 取り急ぎ、Template:ケッペンの気候区分図/sandboxで試してみましたが、テンプレートに図の典拠を記載すること自体は可能かと思います(ただしテンプレート使用ページで<references />または{{Reflist}}を用いて脚注を表示させることが必要)。他の点については後で回答します。--郊外生活(会話) 2024年7月1日 (月) 15:27 (UTC)
コメント 取り急ぎ、Template:ケッペンの気候区分図/sandboxで試してみましたが、テンプレートに図の典拠を記載すること自体は可能かと思います(ただしテンプレート使用ページで<references />または{{Reflist}}を用いて脚注を表示させることが必要)。他の点については後で回答します。--郊外生活(会話) 2024年7月1日 (月) 15:27 (UTC)
- --Omotecho(会話) 2024年6月24日 (月) 04:36 (UTC)
疑問点
[編集]分布図のうち、Awのみ取り出した図「File:Koppen World Map Aw.png」は、空色で示しています。冒頭の全体図では淡いサーモンピンクに塗ってあり、整合性がありません。配色が異なる理由は上記のスレッドに示してくださったのですが、問題をどう解決したら良いでしょうか。
- 冒頭の区分図と配色を揃えた図と差し替えませんか? Awを淡いサーモンピンクに指定した新しい図が必要か。
- もしくは配色が異なる理由は注釈にできませんか?
いずれ気候区分を図示するときに、日本の高等学校の教材の配色と、そうでないものがある点は知識として有効と考えます。--Omotecho(会話) 2024年6月30日 (日) 19:41 (UTC)