利用者‐会話:Tomo9856
一括投稿のお願い
[編集]初めまして。Tomo9856さんが同じ記事に対して節ごとに分けて何度も投稿されているようなので、一括投稿のお願いに参りました。Wikipedia:同じ記事への連続投稿を減らすにある通り、同じ記事への連続投稿はウィキペディアのサーバーに負荷を掛ける上、私たち他の利用者にもエラーが出て編集がしにくくなったり、履歴の見通しが悪くなったりと、いろいろな面で不便になります。細かい節がたくさんある場合は、節ごとに細かく投稿をするのではなく、上位の節または項目全体の編集を行い、一括して投稿していただくようお願いいたします。

その際に細かいところでミスを起こすのではないかとご心配な場合は、投稿するボタンの右隣にある「プレビューを実行」ボタンをご活用いただくことをお勧めします(画面右側の図を参照)。投稿される前に「プレビューを実行」のボタンを押すと、成形結果を先に見ることができます。これを使うことで、
等を予めチェックし、訂正した上で記事を投稿することができますので是非ともご活用下さい。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。--Suisui 2006年8月15日 (火) 22:53 (UTC)
ウィキペディアにようこそ!
[編集]こんにちは、Tomo9856さん、はじめまして!Suisuiと申します。ウィキペディアへようこそ!
- ウィキペディアで活動する際にはガイドブックを是非ご一読ください。きっとご参考になるものと思います。
- よろしければ自己紹介してみてください。
- お隣の利用者ページは、ご自身の自己紹介の他、作業用のスペースなどとして利用することができます。
- 執筆の際には中立的な観点および著作権にご留意ください。
- 何か疑問点がありましたらWikipedia:井戸端で質問することができます。
あなたが実り多き活動をされることを楽しみにしております。--Suisui 2006年8月16日 (水) 04:41 (UTC)
ドレスコードについて
[編集]Tomo9856 さん、初めまして。Koba-chanです。ウィキペディア日本語版にようこそ。
早速ですが、表記の件。Tomo9856 さんが寄稿されたドレスコード (ディスコ)の解説文でエッセイ的な記述が目立ったために全面リライトをさせていただきました。つきましては、セクション名について自信があまりないため、あらためてドレスコード (ディスコ)をご覧頂き、推敲をしていただけたらと思います。なお、ウィキペディアは百科事典を目指しているプロジェクトのため、複数の意味をもつ項目は今回のように「ドレスコード→本来の意味、派生した意味、分野毎の意味」のような分割を辿り、「ドレスコード (ディスコ)」のような括弧書きの記事名に修正されることが往々にしてあります。できますれば、新たな記事を立稿される際には関連語句の存在を確認して頂き、できるだけ客観的な表現に努めていただけますと、今回のドレスコード (ディスコ)のようなことは起きにくいと感じます。それでは、今後もウィキペディアでご活躍ください。Koba-chan 2006年8月16日 (水) 06:02 (UTC)
ドレスコードについて、再び
[編集]Tomo9856 さん、こんにちは。精力的な編集作業を有り難うございます。
早速ですが、Tomo9856 さんがウィキペディアにおけるガイドラインの一部に抵触する行為をされているようなのでご注意申し上げます。既にここのページ冒頭でSuisuiさんからプレビュー機能がお知らせされているように同一執筆者による短時間の部分的な編集の繰り返しはシステムの都合上、余計な版を作製していってしまいます。その原因の多くは編集者の推敲や校正が甘いためであると私自身は考えます。つきましては、複数の人が同時に加筆をする傾向の強い記事とは思えないため、オフラインで十分に文章を練ってから投稿していただくようにお願い申し上げます。加えて、加筆されている文章を拝見しますと、過剰とも思える同一文章、、例えば「風采のあがらない中年男性も接待等で支払い額が多ければ入場が可能だったのである。」、「ダサい奴は入店させない」等が散見し、解説に散漫な印象を与える要素にもなると感じます。更に、セクション名につきましても冗長性があり、当該項目がディスコという業態を解説しているのに、あらためて「ディスコの云々」と表現する点は百科事典項目としては安っぽい印象を受けます。どうぞ、当時のことを十分にご存知であるのでしたらゆっくりと良いものを少ない手数でされていくことを念頭に置いていただけたら、と思います。なお、ノートページは伝言機能だけでなく、意見交換の張として利用されますので、その点も配慮されて今後の活動をされていくことを期待しますKoba-chan 2006年8月16日 (水) 08:53 (UTC)
御世話おかけしました パラパラのページでサブ項目の作り方を知らず、サブ項目にすべきところを全部メイン項目 にして節をちょん切ってしまったので、つなげてサブ項目にする過程で6-7回修正せざるを 得なくなってしまいました。以後気をつけます>Tomo
項目の分割
[編集]項目の分割の際は履歴の関係からWikipedia:記事の分割と統合内の分割の手順を読んで、初版の文章中ではなく、初版の要約欄に分割元の項目と分割した版を記入してください。ラインダンスについては即時削除を貼らして頂いたので、削除後方針に従ってまた再投稿してください。--Mois 2006年8月19日 (土) 07:07 (UTC)
こんにちはー。項目ではなく、要約欄に分割元の項目と分割した版(具体的に書くと[[カントリー・ミュージック]]2006年8月15日 (火) 03:05(UTC)より分割)を書いてください。ラインダンスについては、記事に{{db|全部の版の投稿者依頼。投稿しなおします}}とでも書いていただければ消させていただきます。よろしくお願いいたします。--すぐり 2006年8月19日 (土) 07:58 (UTC)
スタイルについて
[編集]こんにちは。精力的な執筆ありがとうございます。ところで、ご執筆された記事を見てみたところ、wikipediaで推奨されているスタイルになっていないものが見受けられましたので、お知らせに参りました。ぜひwikipedia:スタイルマニュアルやwikipedia:スタイルマニュアル (導入部)をご覧になってみて下さい。これに従って書いていただくと幸いです。あなたさまのWikipediaLifeが充実したものでありますように、お祈りしております。--PeachLover ももがすき。 2006年9月21日 (木) 13:18 (UTC)
投稿内容改善のお願い
[編集]上記のPeachLoverさんや、ノート:中国人民解放軍でのTETRAさん、ノート:潜水艦でのLos688など、多くの方から注意を受けている事と思いますが、投稿内容の改善を強くお願いいたします。
Tomo9856さんの投稿されたいくつかの記事から具体的に問題点を挙げてみると、
- 724型エアクッション揚陸艇(初版}})
- 「中国揚陸艦隊の現況」という節で、724型の解説そっちのけで中国海軍の揚陸戦力の拡大が論じられていますが、この記事はあくまで724型が主題のはずです。きちんと主題について論じられておらず、散漫な文章になっています。
- さらにその節の下方では、日本の兵力の質にまで議論が及び、話があちらこちらに飛びすぎの印象が否めません。
>揚陸艦については個艦を解説するだけでなく、「群れとしての輸送力」を解説しないと木を見て森を見ずになりますが、724は揚陸艦と浜の間を往復する「揚陸艇」なので、 これにまで書いたのは不適切だったと思っています。 変更ありがとうございました --Tomo9856 2006年9月26日 (火) 20:52 (UTC)
OOOOOOOOOOOOOOOOO
- ジュブル型高速エアクッション揚陸艦(Tomo9856さんの編集された最終版)
- Wikipediaでは記事名についてのスタイルガイドがございます。ご覧になったことはあるでしょうか。
>勉強中です。改善しますが、Jubrの場合、スペックを並べるだけでなく、使用法も解説しないと軍事的な意味が読者に伝わらないので、スペックだけ並べた一般的スタイルにならず、Wikiスタイルと、内容の解説の折り合いをつけるので苦しんでおります。--Tomo9856 2006年9月26日 (火) 21:07 (UTC)
- Land to Land、Ship to Landなど専門用語が断りも解説もなしに出てきます。Wikipediaは百科事典であって、軍事(専門)事典ではありません。読者に対する配慮がかけているように見受けられます。
- 特徴の解説で「高速性」を挙げておられるのですが、そのためには客観的な数字を挙げれば充分です。多くの方からご指摘いただいている通り、個人的な妄想・空想を例に挙げることは、百科事典記事の執筆としては不適切であり、読者の理解の助けにもなりません。
>揚陸に於ける高速性というのは時速何キロ出せるか・・ということではありません。
- 1)LCACもZubrも時速100kmだせますが、Zubrは時速100kmで海を渡れるが、時速36kmのおおすみに時速100kmのLCACを積んでも海を渡る速度は時速36kmでしかない
- 2)母船が沖にいてピストンで浜上げすると何往復もせねばならないが、母船自体がホバークラフトで浜に乗り上げるなら一遍に中の戦車をあげられるから揚陸完了は早い。特に台湾海峡のように航海時間が短い場合、荷揚げに掛かる時間短縮のほうが重要になってきます。
- 3)それら総てが、西側ではなじみの薄い、東側のLand TO Landの電撃的な揚陸戦術をささえている
- ・・・という事が、時速を書いただけで読者にわかるでしょうか?
- あなた様が不必要といっている「高速性」の項目が「Land TO Land]の解説になっているのです。
- 特にZubrは西側のLCACを見慣れた目には、「船に積めないホバークラフト」にしか見えず。どう使うのかよくわからない道具だから、使用法の解説は必要です。実際あなた様の書いた文の内容を読むと「単に船に積めないホバーです」と書いてあります。これは指導の問題というよりあなた様の東側兵器に対する個人的価値観が私と合わないという問題ではないでしょうか?
- --Tomo9856 2006年9月26日 (火) 20:52 (UTC)
OOOOOOOOOO
- 「歩兵戦闘車IFV」というのは明らかに冗長な表現です。
直しました、ありがとうございます。--Tomo9856 2006年9月26日 (火) 20:52 (UTC)
OOOOOOOOO
- 「ピストン輸送」の節で述べられていることは、エアクッション方揚陸艇一般について言えることであり、わざわざ書く必要のあることでしょうか。
- >一般読者は浜に乗り上げる観音開きの揚陸艦が満潮まで離岸できず、あまりピストンに向かないのは知らないと思ったほうがよいと思います
- >それと、海を渡って侵攻する道具である「揚陸艦」と 沖合いにある「揚陸艦」から浜に荷揚げする搭載艇である「揚陸艇」の両概念が失礼ながらあなた様の頭の中では混ざっているように思えます。Zubrはエアクッション揚陸「艦」であり、LCACはエアクッション揚陸「艇」です。Zubrで山東半島から韓国へ揚陸作戦はできますが、LCACでそれはできません。 LCACでは樺太から稚内ですらキツイでしょうし、それは設計想定外の使用法です。
- --Tomo9856 2006年9月26日 (火) 21:07 (UTC)
OOOOOO
- YJ-8 (ミサイル)(同上)
- 不必要かつ過度に多用された強調のせいで、安っぽい印象を与える文章になっています。
- 他記事に同じく、個人的な妄想・空想が目立ちます。
>YJ85の存在については評判のよいソースが報じており、事実と思われます
- 妄想と仰るのは誤解があり、実際の侵攻例、使用例で説明したほうが理解が容易ということで例解したものです。ただ百科事典的格調の高さよりイエロージャーナリズム的になったのは問題で、改善したいと思っており、助言いただければと思います--Tomo9856 2006年9月26日 (火) 19:59 (UTC)
- >あとトマホークは現在の米軍の「初期」精密打撃力の中核になっている重要装備ですがその理由はミサイルのスペックが良いからだけではありません
- 潜水艦からも水上艦からも幅広いプラットホームから発射できる
- 無人攻撃手段だからトマホークが撃墜されても米軍に人的被害が生じない。したがって敵の防空網がまだ生きている「初期」には非常に重要で使用頻度が高い
- 弾道弾と違ってピンポイント精密打撃が可能
- という三点が重要だと思います
- YJ8が水上艦、航空機、潜水艦に広く使われている対艦ミサイルだからこそ、その対地版のYJ85は「中国版トマホーク」になりえる条件を持っています(射程は全然短いでしょうが)
- また、対艦ミサイルは飽和攻撃といって雨のように沢山のミサイルを一斉に浴びせるのが普通ですが、中国産対艦ミサイルYJ8/YJ83をベースに対地巡航ミサイルYJ85を作られて、雨のように浴びせかけられては隣国はたまったものではありません。しかも、台湾対岸に配備している短距離弾道弾より安くて弾数がそろい、命中精度も良いのです。衛星に撮影されないので配備数も短距離弾道弾より曖昧にできる。普通に考えて、今後、短距離弾道弾以上にYJ85が備蓄されても不思議ではない。
YJ85のスペックは平凡ですが、そのスペックを並べてもYJ85の安全保障上の問題は説明できません。どうやって記述したらよいでしょう?--222.228.90.109 2006年9月26日 (火) 23:32 (UTC)
OOOO
- 概要の2段落目(「発射重量2tに及ぶ…」)以下の文だけでも
- (1) 「発射重量2t」なのがYJ-8なのかそれ以前のミサイルのことなのか一読して分かりにくい(どちらにも読めてしまう)
>* スティクス・シルクワーム・C-600系(発射重量2tに及ぶ)とは全く別設計のミサイルで、に修正しました--Tomo9856 2006年9月26日 (火) 19:43 (UTC)
OOOOOOOO
- (2) 「YJ-85」の2段落目。だらだらと長く1文が続きすぎです。どの言葉がどの言葉にかかるのか修飾関係が不明瞭で、内容の読み取りがひどく困難です。一部分だけでも挙げると、YJ-85は「YJ-7にTVシーカーを積んだ、米SLAM 露Kazooに近い鋭画像巡航ミサイル」と書くのと「YJ-7にTVシーカーを積んだ米SLAM 露Kazooに近い鋭画像巡航ミサイル」とでは意味が異なることはお分かりいただけると思います。前後の文脈から前者の意だろう、と私などには推測できますが、軍事知識に疎い読者は困惑するかもしれません。
- YJ85については未だ情報が少ない。
- YJ-83をベースにYJ81の技術を使って有翼化して射程を更に延伸しYJ-7のTVシーカーを積んだ、米SLAM 露Kazooに近い新鋭画像巡航ミサイルであるという説、
- YJ-83の誘導部をGPS/TERCOMに変更しただけという説、
- 海軍でYJ-83への換装が進んだ結果余剰になったYJ-8にロシアのKent用のTERCOMとGPSを装着して対地巡航ミサイルに改造して再利用したという説
- 等、情報が錯綜しており、構造についての決定的な報道はまだない。
- しかし空軍に配備が始まってはいるらしい。また空軍はH-6爆撃機の延命改修に取り掛かっておりC602巡航ミサイルなど巡航ミサイル母機としてH6爆撃機を使い続ける予定である。に修正しました--Tomo9856 2006年9月26日 (火) 19:54 (UTC)。
OOOOOOO ずいぶんあれこれと指摘をしてきましたが、複雑な主題についての長大な文章(例えば人民解放軍の記事)を書く以前に、基本的な文章技術に改善の余地があると指摘せざるを得ないように思います。
- 主題を決め、決めた主題に焦点を絞って書く
- 誤読をまねかない書き方をする
- 自分と前提知識の異なる読者に配慮する
- いちど書き上げたら推敲をする
Wikipedia固有の問題についてもずいぶん指摘を受けておられるようですが、しかし、こんなことははWikipediaの記事の書き方とかスタイル以前の問題ではないでしょうか。人民解放軍の記事案についても厳しい評価が寄せられているようですが、私としてもそうした評価に同意せざるを得ません。あれらの記事案---失礼を承知であえて申し上げればミリオタのホームページのごとき稚拙な文章---が百科事典の記事として公開される、という事態が望ましいことだとはどんな意味でも言えないように思えてなりません。
大きな主題に挑戦されようという意欲は賞賛に値しますが、それに必要な技量というものがあると存じます。半ば自戒を込めて申し上げますが、いま少し文章を書く技術について基本的な研鑽を積まれてから取り組まれることをお勧めします、と申し上げたいと思います。ご一考ください。--ikedat76 2006年9月26日 (火) 15:56 (UTC)誤リンク訂正。--ikedat76 2006年9月26日 (火) 15:57 (UTC)
- >人民解放軍記事案はノートのところを読めば判ると思いますが、軍事知識のない読者に、対レーダーミサイルはどうやって使う、Zubrはどうやって使う、という用法を例解するために台湾侵攻作戦例を書いたもので、個別兵器についてリンクがたくさん引いてあるのがわかるはずです。それら多数の個別兵器記事の殆どを私が至急執筆しないと人民解放軍を説明できない状態だったので、やや推敲が甘いのは認めますが、Wikipediaは皆で完成させてゆく百科辞典なのでは?
- それにあれは記事案(工事中)とあったはずです。百科事典的でないのは認めますが、読者にわかりやすく解説するための方式を「試行錯誤している最中」ですので、百科事典的な記述のしかたについては助言をよろしくお願いします。
- なお、「外見的に」整っただけの記事を書くだけなら、他の艦の記事を元にスペックだけ直せばよいのですが、LivedoorのWikipediaと情報が重複するだけですし、中国の兵器については向こうのほうが遥かに先行しています。同じものを後追いで、写真無しで、書くのは読者に対する当Wikipediaの価値を高める事にはならないと思いますがいかがでしょうか?
- 全般的にですが、私がWikiになれていないとか、私の文章力の問題もありますが、
- (エアクッション揚陸「艦」のような)「見慣れない道具」を使用法から読者に説明したり、
- 「個艦のスペックだけ書いても木を見て森を見ずになる揚陸艦」を読者に説明する
- 「スペックはたいしたことないが、発射できるプラットホームが幅広すぎるから、配備が進めば中国軍が一斉射撃できる弾数が無茶苦茶増えてしまうYJ85巡航ミサイル」
- 等を読者に説明するのは、従来のような開発史とスペックだけ並べる兵器記述方式では限界があって苦しんでいます。是非皆様のお知恵を拝借いたしたく。
「中国人民解放軍」記事について
- 特に、対レーダーミサイル、巡航ミサイルの運用能力が近代戦に不可欠であることや、Su27/30x400がMig19x1000より遥かに脅威である理由、東側の揚陸ドクトリンなどを読者にわかりやすく説明する方法について困っています
- 対レーダーミサイルはSEADにリンクを貼るにせよ、「航空撃滅戦」という記事を作ってそこで「最近の戦争では巡航ミサイルやGPS精密弾道弾で敵の航空兵力を離陸不能に追い込んでから、空襲で敵の航空基地を叩いて一気に制空権を握るのを目指すのが普通」という記述をして、そこにリンクはるべきでしょうか?
- また戦闘機の質の違いの解説は困難を極めそうで困っています。
- 中国がMig19x3000機を F15/16世代戦闘機x1000+F4世代戦闘攻撃機x1000+J7x400に買い換えるのは3000から2400へ数が減るから一見 軍縮だが、実際はとんでもない軍拡である事実をどうやって説明すればよいのか
- 「戦闘機の世代差」という記事を書いてもよいでしょうか? それとも「戦闘機」をいじるべきなんでしょうか
- 皆様のお知恵拝借いたしたく--Tomo9856 2006年9月26日 (火) 22:10 (UTC)
--Tomo9856 2006年9月26日 (火) 21:31 (UTC)
OOOOOOOO
大筋、WIKIの書き方や規則にのっとる書き方を推奨する方向性については同意しますが…。さすがに「ミリオタのホームページのごとき稚拙な文章」というのは言いすぎではないでしょうか?失礼と承知なら使うべき表現ではありません。Ikedat76様WIKIに常日頃から貢献しておられる方だとは思いますが、やや過激な表現が多いと思われます。文章についての研鑽を推奨するならば、あまり過激な表現は慎むことを強く推奨します。 --Edoo 2006年9月26日 (火) 17:38 (UTC)
- 言葉遣いのキツさについてはお詫びします。その上で簡単に数点コメントすると、
- (1) 旧「東側の揚陸ドクトリン」などは、中国軍のことを書くためだけでなく、それら単独でも記事化する価値のあることだと思います。書くのであれば(人民解放軍記事のためだけでなく)、軍事一般の記事として書いたほうがよいように思います。
- (2) 「対レーダーミサイル、巡航ミサイルの運用能力が近代戦に不可欠であること」など、それぞれの個別記事で記述をした上で、そうした要点に絞って再度言及すれば充分ではないでしょうか。
- 下記返信と重複を避けたいのであまり書きませんが、何もかも一つの記事で説明しなければならないわけではありません。それから、「百科事典的な記述のしかた」と仰せですが、そういうことよりももっと手前、「論文」(とまで行かずとも「解説文」や「説明文」)と呼ばれる類のものの書き方にまず習熟することが必要だ、と言うのが私の指摘の趣旨です。分かりにくかったら申し訳ない。--ikedat76 2006年9月27日 (水) 16:06 (UTC)
お願い
[編集]どうもはじめまして。早速失礼しますが、「Mig19」とか「F16」という書き方は、ja:wikipediaのこの方面のページの中では推奨されていません。「Mig19」と書いても間違えではありませんし、ロシア人も平気で「Миг19」と書いていたりしますので個人的にはどちらでもよいと思うのですが、ひとつのスタイルですので他と合わせていただけないでしょうか。あなただけが「Mig19」とか「Su27」とか「F15」とか「J7」とか書いているわけではないかもしれませんので、名指しでお願いに上がるのは失礼だったかもしれませんが、ちょっとした問題ですのでご協力お願い致します。--ПРУСАКИН 2006年9月27日 (水) 10:33 (UTC)
補足です。どう直して欲しいのか書くのを忘れました。それぞれ、「MiG-19」、「F-16」、「Su-27」、「J-7」などの表記に改められることを期待します。--ПРУСАКИН 2006年9月27日 (水) 11:18 (UTC)
了解しました。気をつけます--Tomo9856 2006年9月27日 (水) 11:28 (UTC)
ありがとうございます。--ПРУСАКИН 2006年9月27日 (水) 12:34 (UTC)
Re:投稿内容改善のお願い
[編集]ikedat76です。上記の件についてご理解いただきありがとうございました。
1.まず、個別記事についてから。ズーブル型揚陸艦の件ですが、
(1) 中国揚陸艦隊の兵力増強云々の件を書くのは違和感があります。ズーブル型は旧ソ連・ロシア海軍だけでなく、旧東側数ヶ国のほか、Sinodefence記事によればギリシャあたりでも使われている兵器であり、そこに中国軍のことが長々と述べられていると、この型についての記述がぼやけてしまいまい、焦点の定まらない記事になってしまいます。
(2) ズーブル型が西側には無い概念と構想にもとづいて運用される兵器であることは承知しています。(「想定シナリオ」抜きで)試しに書いてみたものです。
ズーブル型高速エアクッション揚陸艦(Zubr class air cushion landing craft、Project 1232.2)は、旧ソ連・ロシア海軍が建造した高速エアクッション揚陸艦。ロシア側名称は、プロイェクト1232.2ポモルニク級中型揚陸艦。
エアクッション揚陸艦艇としては世界最大で150tのペイロードを搭載でき、1隻にMBTなら3両、歩兵戦闘車なら8両を搭載することができる。LCACのように揚陸艦から発進し着上陸するのではなく、自力で陸上から発進し着上陸するという運用形態をとる。
== 概要と運用 ==
本型の特徴はその高速性と重武装にある。本型の最高速度は63kt(約113km/h)に達し、その速力を生かした迅速な侵攻が可能である。また、自衛用のAK-630 30mm機関砲、イグラ-M地対空ミサイルだけでなく、多連装ロケット発射装置により着上陸部隊に火力支援を与えることもできる。
こうした特性をズーブル型に与えた旧東側の運用構想は、西側には類例の無いものである。
ズーブル型は米揚陸艦隊のような遠征を目指したものではない。実際、その進出能力は300海里(540km)程度であり、LCAC同様、海象(シーステート)にも制約を受ける。しかし、本型の運用が想定されているのは波の穏やかな内海や近距離での作戦と言った限られた条件下であり、そうした条件下では本型の特性は大きな重要性を持つことになる。
単に迅速な奇襲性のみを追及するのであれば空挺降下にまさるものはない。しかし、第2次大戦のいくつかの作戦で教訓が得られている通り、大部隊や、戦車・重砲などの重装備をまとまって展開させるには空挺降下は適さない。それゆえ、空挺部隊は一般に軽装備にとどまらざるを得ず、戦闘能力とりわけ火力と装甲防御を欠くために、重装備を備えた敵防御部隊に対しては脆弱にならざるを得ない。また、着上陸戦においても、揚陸艦から展開する揚陸艇は重装備の運搬が可能ではあるものの、(在来型であれホバークラフト型であれ)積載・航走・着上陸・航走(帰艦)・再積載……のサイクルに時間を要し、迅速性・奇襲性を欠く場合がある。
本型は、そうした迅速性・奇襲性と、攻撃側の戦闘能力との両立という背反する要求を、限定された条件下ではあるものの実現することができるのである。すなわち、本型の進出能力の範囲内であれば、時速100kmを越える速力により迅速性・奇襲性を実現するとともに、戦車や歩兵戦闘車すら運搬可能であることにより、敵の反撃に耐えてさらに侵攻に転じるだけの火力・防御力を伴った重装備とともに着上陸部隊を展開させることが可能になるのである。
この後ろに、要目・同型艦一覧・外部リンク・参考文献…等が続けば充分でしょう。納得していただけるかどうかはともかく、私のノートに書いていただいた分、そのほか含めて、「想定シナリオ」なしでもこれだけ書けます。よろしければこのままCopy&Pasteしていただいてもかまいません。
2. YJ-85など、他の記事の指摘部分についての改稿を拝見しました。だいぶ改善した様に思います。
3. 実際の侵攻シナリオを挙げた方が理解しやすい、というのは一面の事実ではあろうと認めます。しかし、そうした「シナリオ」なるものが独自研究の排除などの指針に照らして問題があるのも確かです。また、ご自身も仰るとおり「イエロージャーナリズム的」な記事は、せっかく書いても、意に反して“つまらぬ記事”と軽視されてしまうでしょう。そうなってはモッタイないと思われませんか?
一つの記事内で関連するありとあらゆる事を書こうとする必要はないし、百科事典とはそうしたものでもないと思います。ある事柄を説明するのに、前提となる事柄についての記事や、必要な概念についての記事が無い、とお考えでしたら---例えば、対レーダー・ミサイル(ARH)、飽和攻撃、着上陸作戦など、旧東側の着上陸作戦ドクトリンetc.etc.---他の記事を作ればよいと考えます。
しかし、「推敲の甘い」段階の記事が掲載されてしまうことで、有意な情報量の増加よりではなく体裁を整える(推敲する)ために他のユーザーの労力が使われてしまう、と言う状態が「共同で執筆する」と呼ぶに値することなのか疑問に感じます。
4. 「開発史とスペックだけ並べる兵器記述方式では限界があって」とあるものについても答えは簡単である気がします。上記のズーブル型のように、運用構想から説き起こせばよいでけではないでしょうか。兵器(に限らず道具は)、「どんなことがしたいか」(=運用構想)があって、そこから個々の性能なり特性なりを導き出す形で開発してゆくわけですから、そうするより無いと思うのですがいかがでしょう。
以上、ご検討ください。
追記 他の方の書いた文の中にご自身の応答を割り込ませて書くのはできればやめましょう。誰が何を書いたのか分かりにくくなって、第3者が読んだとき話の流れがつかみにくくなります。--ikedat76 2006年9月27日 (水) 15:52 (UTC)
一括投稿のお願い
[編集]初めまして、TETRAと申します。Tomo9856さんが同じ記事に対して節ごとに分けて何度も投稿されているようなので、一括投稿のお願いに参りました。 Wikipedia では投稿・更新された文章について、全ての版を保存するシステムを採用しており、例えば、ある記事に3回の編集を行ったときには、最新の状態の他に過去3回の状態がそれぞれ保存されます。このときの編集には実際の編集の量、範囲は関係なく、別々の節にそれぞれ細かい編集を施し、投稿した場合でも、投稿一回につき記事全体が古い版として保存されます。
このように同じ記事への連続投稿はウィキペディアのサーバーに負荷を掛けるほか、履歴の見通しが悪くなったりと、いろいろな面で不便になります。(詳しくはWikipedia:同じ記事への連続投稿を減らすをご覧ください) これを避けるため、同じ記事の複数の節に投稿する際は、節ごとに細かく投稿をするのではなく、上位の節または項目全体の編集を行い、一括して投稿してくださるよう願いします。

その際に細かいところでミスを起こすのではないかとご心配な場合は、投稿するボタンの右隣にある「プレビューを実行」ボタンをご活用いただくことをお勧めします(画面右側の図を参照)。投稿される前に「プレビューを実行」のボタンを押すと、成形結果を先に見ることができます。これを使うことで、
- 文字の太字、斜体、見出し付け
- リンク
- 誤字脱字
等を予め確認し、訂正した上で記事を投稿することができますので是非ともご活用下さい。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
なお、このメッセージはお知らせ用の定型文(履歴)を利用して表示させていただいています。上記をご理解いただけたらこのメッセージは削除していただいて結構です。
以上が今後のTomo9856さんの活動の助けになれば幸いです。失礼します。 ― TETRA 2006年9月27日 (水) 19:22 (UTC)
わかりました、。潜水艦の機関の項目が分かれていたのを項目ごとに投稿してすみませんでした。 ごめんなさい。--Tomo9856 2006年9月27日 (水) 19:25 (UTC)
プレビュー機能のお知らせ
[編集]こんにちは。ウィキペディアへのご寄稿ありがとうございます。Tomo9856さんが同じ記事に対して短時間に連続して投稿されているようでしたので、プレビュー機能のお知らせに参りました。投稿する前に「プレビューを実行」のボタンを押すと、成形結果を先に見ることができます。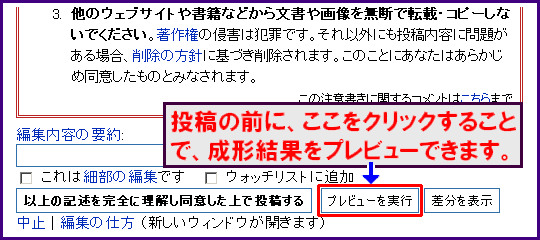
これを使うことで
などを予めチェックし、修正してから投稿していただくことにより、同じ記事への連続投稿を減らすことができます。この利点については同じ記事への連続投稿を減らすに説明がありますので、よろしければお読みください。また、ガイドブックにウィキペディア全体のことについて分かりやすく解説されていますので、あわせてお読みいただけると幸いです。ご理解とご協力をよろしくお願いします。--Tiyoringo 2007年5月16日 (水) 17:00 (UTC)
ドレスコード (ディスコ)について
[編集]はじめまして。ドレスコード (ディスコ)を日本のディスコにおけるドレスコードに改名後、ディスコに統合しました。統合の経緯はノート:日本のディスコにおけるドレスコードにあります。ドレスコード (ディスコ)は移動後の不要な曖昧さ回避(WP:CSD#R3-1)として即時削除に提出する予定です。Tomo9856さんが初版投稿者でいらっしゃったので、念のためお知らせにあがりました。よろしくお願いいたします。--Focaccia(会話) 2018年5月9日 (水) 13:04 (UTC)
