保科氏
| 保科氏 | |
|---|---|
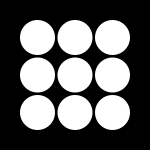 | |
| 本姓 |
称・清和源氏井上氏流 諏訪氏流(神人部宿禰姓) その他諸説あり |
| 家祖 | 保科忠長 |
| 種別 |
武家 華族(子爵) |
| 出身地 | 信濃国高井郡保科 |
| 主な根拠地 |
信濃国 陸奥国 上総国 東京府東京市 |
| 著名な人物 |
保科正之 保科正直 保科正俊 |
| 支流、分家 | 飯野保科家(武家・子爵) |
| 凡例 / Category:日本の氏族 | |
保科氏(ほしなし)は、武家・華族だった日本の氏族。信濃国高井郡保科に発祥した土豪で、初め武田氏に仕え、正直・正光の代に徳川家康に仕えた。徳川秀忠の庶子正之が正光の養子に入って継ぎ、松平に改姓して親藩大名の会津松平家となった。一方正光の弟正貞の系統は保科姓のまま譜代大名として廃藩置県まで続く。明治にいたり両家とも華族の子爵家に列する[1]。
概要
[編集]保科氏の出自と小領主時代
[編集]清和源氏井上氏の一族と伝えられる。氏族名の由来ともなった信濃国高井郡保科(現・長野県長野市若穂保科)に広がる保科荘は古来からの荘園で、保科氏の祖は長田御厨[2]の荘官を務めたとされる。このことから古代氏族の他田部氏の系統とする説がある。また「信濃史源考」では他田氏と同祖とされる諏訪氏の庶流としている。若穂保科の広徳寺寺歴では平安時代に川田一帯を支配していた保科氏は一旦絶えて井上氏から分かれた井上忠長が保科氏を再興したとしている。
長元元年(1028年)の平忠常の乱を平定して東国に勢力を扶植した源頼信の二男頼季が信濃国高井郡井上に住し、井上氏が北信濃に勢力を拡大する過程でその家人となって武士団化したと思われる。
治承・寿永の乱では井上氏の総領井上光盛に従い源氏方として活躍、『平家物語』に光盛に率いられた「保科党三百余騎」として登場する(星名党とも記され、初期の横田河原の戦いでは源氏方ではなく、敵方の越後平氏城氏の軍勢の中に星名権八の名がある)。元暦元年(1184年)7月10日、井上光盛が源頼朝に誅殺された際に捕らわれた侍に「保科太郎」がいるが、同月25日に許されて御家人に取り立てられている。このことは比企朝宗が奉行した(『吾妻鏡』)。また承久の乱に「保科次郎」父子が出陣したことが知られる。
鎌倉時代から南北朝・室町時代における保科氏の動向は史料が少なく、確かなことは判明しておらず、諏訪大社の祭祀記録である「御符礼之古書」などに保科姓が散見される程度である。しかし建武2年(1335年)には中先代の乱において、北条方残党を擁立する諏訪氏や滋野氏に同調した保科弥三郎が北条氏知行地に属していた四宮左衛門太郎(諏訪氏の庶流と伝えられる武水別神社神官家)・関屋氏(皆神山神職)・夏目氏らと共に室町幕府の守護所(千曲市小船山)を襲い、青沼合戦を引き起こして敗走する。そして足利方の守護小笠原貞宗や市河氏らの追撃を受けて、八幡河原、福井河原、四宮河原を転戦した。だが鎌倉において足利方が勢いを盛り返し、保科氏らは清滝城に篭城して抵抗したが攻略された。守護方は四宮氏を滅ぼして反転し、この後牧城へ向けて攻撃を加えている。その後の保科氏は諏訪氏らとともに南朝勢として活動している。
武田家臣時代から近世大名化
[編集]戦国時代になると、南信濃の高遠城主諏訪頼継の家老として「保科弾正」(あるいは筑前守、保科正則)の名が登場する。本来は北信濃の霞台城を本拠とする保科氏が南信濃に移った時期や理由などについては、長享年間に村上顕国との抗争に敗れて高遠に遷移したと見る向きもあるが、今日も真相は不明である。ただし、鎌倉時代以来諏訪神党の一つに数えられたことから、諏訪氏と密接な関係が築かれていたと考えられ、正則の跡を継いだ保科正俊は[3]高遠氏家臣団では筆頭の地位にあったとされる。
天文21年(1552年)に旧主の高遠氏が武田氏の信濃侵攻により滅亡すると、正俊以下の旧家臣団は武田氏の傘下となる。正俊は軍役120騎を務める高遠城将として数々の戦いで軍功を挙げ(高坂逃げ弾正、真田攻め弾正と保科槍弾正の武田軍三弾正と謳われた)、跡を継いだ嫡男の正直も高遠城将として、武田氏滅亡時の高遠城主仁科盛信と共に奮戦している。
正直は高遠城落城の際に落ち延び、本能寺の変で信濃の織田勢力が瓦解した後、後北条氏を後ろ盾に高遠城奪還に成功する。そして後北条氏と徳川氏が信濃の旧織田領を巡って対立すると、徳川方に与して高遠城主としての地位を安堵される。
正直の子正光は小牧・長久手の戦い・小田原征伐に出陣、徳川氏の関東入府に際して下総国多胡で1万石を与えられ、大名に列した。関ヶ原の戦いの後には旧領に戻って高遠城主として2万5千石を領した。さらに大坂の陣での戦功により3万石に加増される。
松平氏一族化した宗家
[編集]正光の養嗣子として家督を相続した保科正之は、2代将軍徳川秀忠の庶子で、寛永13年(1636年)に17万石加増されて出羽国山形藩主(20万石)となり[4]、さらに寛永20年(1643年)に3万石加増されて陸奥国会津藩(23万石)に移封され[4]、元禄元年(1696年)に正容の代に松平姓の使用が許された[5]。以降、同藩は親藩大名として幕末まで存続したが、明治元年(1868年)に容保の代に王師に反逆して改易となった[5]。しかしその後明治2年に容大に陸奥国斗南藩3万石が与えられたことで家名再興を許され華族に列し[5]、版籍奉還後の明治3年に斗南藩知事に転じたのを経て、明治4年の廃藩置県を迎えた[5]。
版籍奉還の際に定められた家禄は現米で738石[6][注釈 1][7]。明治9年の金禄公債証書発行条例に基づき家禄の代わりに支給された金禄公債の額は1万8456円60銭1厘(華族受給者中242位)[8]。
明治17年(1884年)に華族令施行で華族が五爵制になると容大は旧小藩知事[注釈 2]として子爵家に列した[10]。2代子爵保男は少将まで昇進した海軍軍人で予備役入り後には貴族院の子爵議員に当選して務めた[11]。
同松平子爵家の邸宅は昭和前期に東京市小石川区第六天町にあった[11]。
飯野藩主家→華族の子爵家の保科氏
[編集]一方、正之の入嗣により世子の座を廃された正貞(正光の実弟)は、別家を興して上総国飯野藩主(1万7000石)に封じられた。延宝5年(1677年)の加増で都合2万石となった。以降明治維新まで譜代大名として存続し、最後の藩主正益は明治2年に版籍奉還で飯野藩知事に任じられるとともに華族に列し、明治4年(1871年)の廃藩置県まで藩知事を務めた[5]。
版籍奉還の際に定められた家禄は、現米で750石[12][注釈 1][7]。明治9年(1876年)の金禄公債証書発行条例に基づき、家禄と引き換えに支給された金禄公債の額は、2万6761円41銭8厘(華族受給者中179位)[13]。
明治前期の頃の護久の住居は東京市芝区愛宕下町にあった。家扶は進藤健造[14]。
明治17年(1884年)に華族が五爵制になると正益は旧小藩知事[注釈 3]として子爵家に列した[15]。2代子爵保科正昭は帝室林野局や朝鮮総督府に官僚として勤務した後、貴族院の子爵議員に当選して務め、院内会派研究会に所属した[16]。
同保科子爵家の邸宅は昭和前期に東京市牛込区市谷中之町にあった[16]。
旗本→士族の保科氏
[編集]正貞の外孫で当初正貞の養子となっていた正英も、分家して2500石の旗本となる。同家より山田奉行の保科正純や幕府陸軍歩兵頭並やパリ万国博覧会使節団を歴任し、明治以降には陸軍に入隊して歩兵大佐まで昇進した保科正敬(俊太郎)が出ている。
系譜
[編集]- 実線は実子、点線(縦)は養子、点線(横)は婚姻関係。
| 井上家季 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常田光平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑洞光長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保科忠長1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長直2 | 井上経長 | 井上光朝 | 井上光清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長時3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光利4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正知5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正利6 | 正満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正則7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正俊8 | 正保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正直9 | 内藤昌月 | 正勝1[17] | 正賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正光10 | 正貞 | 正重 | 北条氏重 | 女 | 小出吉英 | 正近2 | 正辰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正之11 | 正重 | 正貞 | 保科正英 | 正長3 | 女 | 西郷元次 | 正具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正経12 | 正頼 | 正純 | 松平正容 | 正景 | [旗本] 正英➀[18] | 西郷近房4→6 | 正興5 | 近房 | 正貫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松平正容 | 正賢13 | 小出英勝 | 正静➁ | 近方7 | 近天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会津松平家 | 正殷14 | 正寿 | 正純➂[19] | 近張8 | 房成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正寿15 | 正勝④ | 正倫 | 近致9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正温 | 黒田直儀 | 大岡清定 | 九鬼隆晁 | 正率16 | 正倫⑤ | 近義10 | 近寧11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正徳17 | 正盈⑥[20] | 近光12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正丕18 | 石河貞明 | 正恒⑦ | 近思13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正益19 | 正棟⑧ | 近悳(西郷頼母)→保科頼母14 | 山田直節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横田某 | 楠田咸次郎 | 正昭20 | (数代略) | 西郷四郎15[21] | 有鄰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正虎(光正)21[22] | 栄次郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正興22 | 正敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正宣23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『保科氏』 - コトバンク
- ^ 吾妻鏡では「保科御厨」
- ^ 『甲陽軍鑑』では槍弾正として真田氏・高坂氏と並び「武田の三弾正」に名を連ねている
- ^ a b 新田完三 1984, p. 570.
- ^ a b c d e 新田完三 1984, p. 574.
- ^ 霞会館華族家系大成編輯委員会 1985, p. 23.
- ^ a b 刑部芳則 2014, pp. 105–106.
- ^ 石川健次郎 1972, p. 52.
- ^ a b 浅見雅男 1994, p. 150.
- ^ 小田部雄次 2006, p. 336.
- ^ a b 華族大鑑刊行会 1990, p. 241.
- ^ 霞会館華族家系大成編輯委員会 1985, p. 21.
- ^ 石川健次郎 1972, p. 47.
- ^ 石井孝太郎『国立国会図書館デジタルコレクション 明治華族名鑑』深沢堅二、1881年(明治14年)。
- ^ 小田部雄次 2006, p. 355.
- ^ a b 華族大鑑刊行会 1990, p. 219.
- ^ 会津藩筆頭家老。
- ^ 分家し子孫は2000石の旗本となる。
- ^ 岡部勝政の子
- ^ 戸田氏常の子
- ^ 会津藩士志田貞二郎の三男。
- ^ 大東亜省秘書官、阿波丸事件により水難死
参考文献
[編集]- 浅見雅男『華族誕生 名誉と体面の明治』リブロポート、1994年(平成6年)。
- 石川健次郎「明治前期における華族の銀行投資―第15国立銀行の場合―」『大阪大学経済学』第22号、大阪大学経済学部研究科、1972年、27 - 82頁。
- 刑部芳則『京都に残った公家たち: 華族の近代』吉川弘文館〈歴史文化ライブラリー385〉、2014年(平成26年)。ISBN 978-4642057851。
- 小田部雄次『華族 近代日本貴族の虚像と実像』中央公論新社〈中公新書1836〉、2006年(平成18年)。ISBN 978-4121018366。
- 霞会館華族家系大成編輯委員会『昭和新修華族家系大成 別巻 華族制度資料集』霞会館、1985年(昭和60年)。ISBN 978-4642035859。
- 霞会館華族家系大成編輯委員会『平成新修旧華族家系大成 下巻』霞会館、1996年(平成8年)。ISBN 978-4642036719。
- 華族大鑑刊行会『華族大鑑』日本図書センター〈日本人物誌叢書7〉、1990年(平成2年)。ISBN 978-4820540342。
- 田中豊茂「信濃中世武家伝」信濃毎日新聞社 2016年
- 新田完三『内閣文庫蔵諸侯年表』東京堂出版、1984年(昭和59年)。
外部リンク
[編集]- 武家家伝「保科氏」
- http://keizudou.web.fc2.com/daimyou/hoshina.html 大名家の系図を現代までつなげてみる「保科氏」]

