利用者:Darkmagus/workspace
詩学
『詩学』(Περι Ποιητικησ )は、古代ギリシアの哲学者アリストテレスの著作。 『詩学』は詩(とりわけギリシア悲劇)の根拠や機能、構造、形式などの考察を主題とする。 ここでいう詩とは悲劇、喜劇、叙事詩などの、韻律を用いて書かれた文学作品全体のことである。 冒頭でアリストテレスは媒体や対象、方法などによって詩をさまざまなジャンルと構成要素に分類しているが、現存する部分の中心をなすのは第6章から始まる悲劇についての考察であり、そのあとに続いていたと伝えられる喜劇についての叙述は散逸している。
文学・美学に関するアリストテレスの著作としては他に『詩人たちについて』『ホメーロスの諸問題』『詩作の諸問題』などが名前のみ伝えられているが、現存するのはこの『詩学』と『弁論術』のみである。 また、作中で取り上げられている作品には今日では失われてしまったものや断片しか残っていないものも多く、文献学的な史料としての価値も見逃すことができない。
ミーメーシス(第1-3章)
[編集]アリストテレスの時代、文学作品のほとんどは韻律を用いて書かれていた。文学以外のジャンル(哲学、自然科学など)でも韻文は書かれていたが、これらの韻文と文学を分ける規準として提示されるのが、本書においてのみならず以後の美学、文芸理論において重要な位置を与えられるミーメーシスである。 ミーメーシスはふつう「再現」「模倣」と訳され、ある対象の模写像を作ることを意味する。 プラトンもこのミーメーシスという語を用いているが、その場合には文字通りの物真似に近い意味で、対象の本質を表すことまではできないものとして使われている。 しかしアリストテレスは普遍的なものをも提示することのできるものとして、より積極的な意味をこの語に与え、『詩学』では「何かを再現したものを見る喜びこそ詩作を発展させてきた原動力である」といい、作中で最も重要な概念としてこれを用いている(なぜ人間が再現されたものから喜びを得るのかについては第4章で述べられる)。
アリストテレスはここで、韻律を用いた文章で人間の行為を再現するものが詩であり、それを作るものが詩人であると定義する。 再現には叙事詩や悲劇、喜劇のほかにもさまざまな種類があるが、それらは再現をする媒体・対象・方法の差異によって分類される。
再現の媒体(第1章)
[編集]色と形、楽曲とリズム、韻文と散文、およびそれらの媒体を用いた再現の具体例などが示される。
再現の対象(第2章)
[編集]ミーメーシスは人間の行為の再現であるから、その対象はいうまでもなく行為する人、特定の性格をもった一人物である。この人物の性格がわれわれよりも優れたものであるならばその詩作は叙事詩や悲劇に、われわれよりも劣ったものならば喜劇になるといえる。
再現の方法(第3章)
[編集]同じ媒体で同じ対象を再現するときにも、いくつかの異なる方法がありうる。
- ホメロスの方法
- 作者がある時は一叙述者として、ある時は自分以外の一登場人物として再現する。
- ホメロス以外の叙事詩の方法
- 作者自身が一叙述者としてそのまま再現する。
- 悲劇・喜劇の方法
- 作者が複数の登場人物すべての活動を行為するものとして再現する。
悲劇・喜劇がdramaと呼ばれるのは、それが行為する(dran)ものの再現だからであり、さまざまな文学ジャンルのうち劇的(dramatikos)といわれるのは叙事詩だけである(悲劇・喜劇は劇そのものであるから劇「的」とは呼ばれない)。『詩学』が取り上げるのがこの3種のみであり、劇的な再現ではない抒情詩や教訓詩を扱わないところからも、アリストテレスがいかにミーメーシスに重きを置いていたかがうかがわれる。
詩作の起源(第4章)
[編集]詩を生み出した起源として、アリストテレスはミーメーシスと音楽(詩の韻律=リズムも含む)、正確にいえば、それを楽しむという人間の性質を挙げる。これらはいずれも人間が本性的に備えたものであるとアリストテレスはいう。 なぜ人間は再現されたものを楽しむのか。 日本語の「学ぶ」が「まねぶ(=真似をする)」を語源とするように、例えば美しい風景を再現した風景画を鑑賞するとき、人は美しい風景についてそこから学ぶことができる。 したがって、「人間は本性的に知ることを欲する」(『形而上学』冒頭、アリストテレスの一番有名な言葉として知られる)という、その本性的な欲求が満たされる歓びを得られるからである。
こうした本性的に人間に備わっているものから即興的に作品が生まれ、徐々に発展してきたと考えられるが、その後詩作は大きく二つに分かれる。 すなわち、高貴な人間の行為を再現する即興作品から賛歌・頌歌が生まれ、そこからホメロスの『イリアス』『オデュッセイア』を経て悲劇が生まれた。一方、劣った人間の行為の再現から諷刺詩が生まれ、『マルギーテース』(作者不詳。アリストテレスの時代にはホメロス作と伝えられていた)を経て喜劇が生まれたのである。
第6-
[編集]アリストテレスは、悲劇を「一定の大きさで完結した、一つの全体としての高貴な行為の再現(ミメーシス)であり、それによって感情の浄化(カタルシス)をもたらすもの」と定義する。すべての悲劇がもつ要素は以下の六つである。
- 再現の対象
- 1.筋(逆転、認知、苦難)
- 2.性格
- 3.思想
- 再現の方法
- 4.視覚的装飾
- 再現の媒体
- 5.語法
- 6.歌曲
| 文学 |
|---|
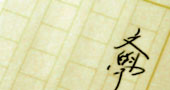 |
| ポータル |
|
各国の文学 記事総覧 出版社・文芸雑誌 文学賞 |
| 作家 |
|
詩人・小説家 その他作家 |

フョードル・ミハイロビッチ・ドストエフスキー(Фёдор Михайлович Достоевский, 1821年10月30日(新暦11月11日) - 1881年1月28日(新暦2月9日))はロシアの小説家、思想家。レフ・トルストイやアントン・チェーホフとともにロシア文学を代表する文豪である。彼の小説は19世紀末のロシアを舞台とした政治的・社会的・心理的な症例報告である。その主人公たちはおおむね何らかの形でアウトサイダーであり、精神に虚無主義、無神論、社会主義、神憑り的な信仰心、民族主義など何かしら極端なものを抱えている。とても実在するようには思われないが、にもかかわらずあらゆる読者がその内に自分自身や隣人の似姿を見ずにはいられないこれらの人物が織り成す物語を描くことによって人間精神を細密に分析し、実存主義をはじめとする後世の文学・哲学にきわめて大きな影響を与えた。
略歴
[編集]デビュー前
[編集]フョードル・ドストエフスキーは、1821年10月30日(新暦11月11日)、モスクワの帝国養育院附属マリヤ貧民救済病院で働く軍医ミハイル・アンドレーヴィチと商人の娘マリア・フョードロヴナの第2子として、父の勤める病院で誕生した。7人兄弟で、1歳年上の兄ミハイルのほか、のちに産まれた弟アンドレイ、ニコライ、妹ワルワーラ、ヴェーラ、アレクサンドラがいる(ヴェーラと双子の妹リュボフィは生後まもなく死亡している)。1831年には父がトゥーラ県のダローヴォエ村とチェルマーシニャ村を避暑用の領地として購入し、毎年夏をここで過ごすことになり、のちの短編『百姓マレイ』などはこの村での体験を題材としている。1837年、母を結核で亡くしたのと同じころ、敬愛するプーシキンも死去したことを知り悲嘆にくれる。同年5月から兄のミハイルとともにサンクト・ペテルスブルクの予備校で陸軍工科学校の入試に備え、翌年には同校へ入学。

1839年、領地で隠居生活を送っていた父ミハイルが殺害される。詳細は不明であるが、アルコール中毒の発作で暴れたミハイルを静止しようとした領地の農奴が、業を煮やしてミハイルの口へ無理やりウォッカを注ぎ込んで窒息死させたものと伝えられている(一方、ミハイルの死は自然なものだったのであるが、領地の境界線の引き方に関してミハイルと諍いを起こしていた近隣の地主がこの土地を安く買い上げるために「このあたりでは農奴による叛乱が起きやすい」といった不穏な物語を捏造したのだという説もあるが、具体的な証拠はない。いずれにせよ地元でかなりの反感を買っていたことだけは間違いない)。
サンクト・ペテルスブルグ陸軍工科学校時代のドストエフスキーはあまり優秀な学生ではなく、特に大嫌いな数学の成績が悪かったという。その代わりこのころから文学への関心を強め、バルザック、ホフマン、ゲーテ、ユーゴー、ジョルジュ・サンド、プーシキン、ゴーゴリらの作品を愛読する。とりわけバルザックに対してはのちにその作品『ウージェニー・グランデ』をみずからロシア語に翻訳して雑誌『パンテオン』に発表するほど傾倒していた。執筆を始めたのもこのころで、1841年には野戦工兵少尉補資格試験に合格した兄ミハイルの送別会で自作の戯曲『マリア・ステュアルト』』『ボリス・ゴドゥノフ』を朗読している(いずれも現存しない)。
文壇進出
[編集]1844年ごろからデビュー作となる『貧しき人びと』(書簡体の中編小説)の執筆を開始。すでに少尉に昇進してペテルブルク工兵隊に配属されていたが、創作に専念するために依願退役し、1845年4月に完成する。『貧しき人びと』の原稿は、予備校時代からの友人グリゴローヴィチを通じて詩人のネクラーソフの手へ渡る。何気なく初めの数ページを読み出したネクラーソフはそのまま原稿を置くことができずに夜通し読み続け、読了後は感激のあまり朝の4時であることも忘れてドストエフスキー宅を訪ねていったという。ひとしきり賛嘆の念を伝えたネクラーソフはその足で批評家のベリンスキー宅へ行き、「新しいゴーゴリが現れましたよ!」と叫んだ。「また?」といいながら半信半疑で原稿を受け取ったベリンスキーだったが、一読するや目を丸くして「今すぐこの作家に会わせてくれ!」と、昂奮を隠せなかった。数日後に面会しに来たドストエフスキーに、ベリンスキーは「あなたはきっと偉大な作家になれるでしょう」と太鼓判を押した。ドストエフスキーはこのときのことを「自分の人生で最も感動的な瞬間だった」「シベリアへ流刑になっていたときも、このときのことを思い出しながら自分を励ました」と語っている(『作家の日記』1877年1月号)。『貧しき人びと』は1846年1月21日、ネクラーソフ編集の雑誌『ペテルブルク文集』にツルゲーネフやベリンスキーらと名を連ねて発表される。執筆から発表までの半年余りのあいだに、ドストエフスキーは第2作『分身、ゴリャートキン氏の冒険』や短編『九通の手紙にもられた小説』などを執筆。またツルゲーネフと知り合ったのもこのころで、ベリンスキー宅においてドストエフスキーが『分身』を朗読したさいにはツルゲーネフも出席している。『分身』は1月28日に脱稿、わずか4日後の2月1日には雑誌『祖国雑記』に掲載される。翌3月には『貧しき人びと』を大絶賛するベリンスキーの批評がこの『祖国雑記』に掲載され、新進気鋭の作家としてドストエフスキーの名は一躍ロシア文学界に知れ渡ることとなる。
この年には10月5日にゲルツェンと知り合ったほか、『プロハルチン氏』や中篇『剃り落とされた頬髯』、『廃止された役所の話』の執筆などに励む(ただし、このうち発表されたのは『プロハルチン氏』(『祖国雑記』10月号)のみ、『廃止された役所の話』は未完成のまま放棄、また『剃り落とされた頬髯』は難渋の末に完成してベリンスキーもゲルツェン宛書簡(1846年1月2日、2月6日)でドストエフスキーが近々この中篇を発表する予定であると報告しているが、未発表のまま原稿は失われて現存していない)。またその後の作品に関する構想も着実にまとまり始めており、新人作家としてはまずまず順調な滑り出しであるといえる。しかしその一方で、『貧しき人びと』を大絶賛してドストエフスキーを世に送り出したベリンスキーとネクラーソフは『分身』や『プロハルチン氏』にはあまり感心しなかったらしく、ドストエフスキーの方でも彼らの文学観に疑問を抱くようになり、早くも見解の相違が現れはじめる。やがてベリンスキーは自ら編集人を務める雑誌『現代人』(1847年1月号、『九通の手紙にもられた小説』と同時掲載)で『プロハルチン氏』を酷評し、両者は完全に決裂する。ドストエフスキーは1849年に逮捕される(次節参照)までに『ペテルブルク年代記』(『サンクト・ペテルブルク報知』1847年4月~6月)、『家主の妻』(『祖国雑記』1847年10、11月号)、『弱い心』(同誌1848年2月号)、『ポルズンコフ』(『絵入り文集』1848年2月)、『世なれた男の話』(『祖国雑記』1848年4月号)、『クリスマス・ツリーと結婚式』(同誌1848年9月号)、『嫉妬ぶかい夫』(同誌1848年11月号)、『白夜』(同誌1848年12月号)、『ネートチカ・ネズワーノワ』(同誌1849年1、2、5月号)などを旺盛に発表し続けるが、ベリンスキーらの反応は徹底的な酷評か、さもなければ黙殺であった。1848年5月28日、あいだの溝を埋められないままベリンスキーは死去してしまう。
