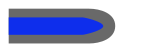利用者:Ran Ayase/せんしゃ
この記事は製作が全く進んでいないか、編集者のやる気が不十分です。 一向に記事をを完成させようとしない編集者に、スンスンおじさんは悲しんでいます。 |
この記事は製作が全く進んでいないか、編集者のやる気が不十分です。 一向に記事をを完成させようとしない編集者に、ウィキペたんは怒っています。 |
はっ、早くこの記事を完成させなさいよ、このバカ!! べっ、別にあんたの書いた記事を見たいだなんて、ちっとも思っていないんだから!!(やけくそ) |
戦車(せんしゃ、各国での呼称については#各国の名称を参照)とは、軍用車輛における装甲戦闘車輛の一種で、直射火砲を搭載した旋回砲塔を有する装甲した装軌式の戦闘車輌[1]を指す名称である。 [注釈 1]
概要
[編集]



戦車は第一次世界大戦中、塹壕戦による戦況の膠着状態を打開するためイギリスとフランスによって開発された。1916年のソンムの戦いでイギリス軍が初めて戦車を実戦投入し、以降各国の軍隊で戦車の導入が進められるようになった。 戦車の開発は戦間期においてやや停滞したが、先見的な将校たちによって戦車の運用方法が確立され始めたのもこの時期である。第二次世界大戦においては歩兵や砲兵などとともに、戦車は地上戦力の一翼を担った。とりわけドイツ軍は1940年のフランス侵攻時、戦車の機動力を最大限に生かしてフランス軍の弱点を突き、攻撃開始から約1ヵ月で当時の陸軍大国であったフランスを降伏させた。これが「電撃戦」(blitzkrieg)である。
戦後も(はじめこそ核兵器の登場により戦車は不要と唱えられたが)朝鮮戦争や中東戦争などの地域紛争に戦車は投入された。歩兵がもつ対戦車火器の発達によって戦車の有用性が一時危ぶまれることもあったが、複合装甲の開発など技術革新により戦車は地上戦力としての地位を維持することができた。とはいえ冷戦が終結し、国家の正規軍同士による大規模な地上戦の可能性がほぼ無くなった中、例外的に大規模な地上戦が行われた1991年の湾岸戦争は「史上最後の戦車戦」[2]とさえ評される等戦車の有用性にふたたび疑問が呈されている。おもな戦争の形態が正規軍同士の戦闘から正規軍とテロ組織などとの戦闘(非対称戦争)に移行した21世紀の戦場において、たしかに戦車がその性能を最大限に発揮できる機会は以前に比べて少ない。しかしそこでも歩兵部隊を物理的・心理的な側面から支援する強力な「動くトーチカ」として戦車は利用されている上、戦車を完全に代替しうる性能を持つ軍用車輛というものは今のところ存在していない。戦車を地上戦力のひとつとして扱い、性能をより向上させる試みは現在も各国で続いている。
そもそも戦車とは何だろうか。一見すると砲塔と履帯(キャタピラ、クローラー、無限軌道とも[注釈 2])をもつ軍用車輛はいずれも戦車であるかのように見える。だが「砲塔と履帯をもつ」という条件は必ずしも戦車だけに当てはまるものではない。自走砲や歩兵戦闘車は戦車と同様「砲塔と履帯をもつ軍用車輛」で、そのほか駆逐戦車や対空戦車は(少なくとも日本語では)「戦車」の名を冠しているにもかかわらず、これらの車輛は各国の軍隊で戦車と別の車輛として扱われている。なぜなら、これらの車輛が戦車に課せられる役割を完全に果たすことはできないからである。その一方で、砲塔の無いStrv.103やVT-1は
では、どのような条件を持って戦車は戦車たり得るのか。現在では次のような構造的特徴をもち、また運用的特徴という「戦車に課せられる役割」を果たすことができる軍用車輛が(一般的な)戦車と見なされている。もっとも、この問いは今なお曖昧なものであり、時代や国によって変化する。以下に述べるのはあくまで現代から見た戦車の定義であり、そこに至るまで一世紀の試行錯誤を重ねた歴史上の戦車には必ずしも―むしろほとんど―この定義が当てはまらないことに注意が必要である。
- 構造的特徴
戦車は、、2本のとエンジンを搭載した車体(ハル、Hull[注釈 3])の上に火砲や機関銃などの武装を搭載した砲塔(タレット、Turret)を全周旋回するよう搭載し、砲塔・車体に装甲を施すという構造をしている。この構造を詳しく見ていくと以下のようになり、戦車は攻撃力・防御力・機動性の三点において単に「砲塔と履帯をもつ」ほかの装甲戦闘車輛とは一線を画する性能を持つ[4]。
- 攻撃力として - 直接照準射撃によって敵戦車などの点目標を破壊できる火砲を搭載した、全周旋回可能な砲塔を有する。
- 防御力として - 戦車全体に装甲が施され、最も防御力が高い部位では火砲や対戦車火器による攻撃に耐え、その他の部位でも機関銃弾や砲弾の破片に耐えるだけの防御力を有する。
- 機動性として - 履帯による荒れ地などの不整地における高い走破能力を持っている。
- 運用的特徴
戦車は、複数の戦車(戦車部隊という)によって歩兵部隊や砲兵部隊などとともに陸上戦力の一翼を担い(諸兵科連合)、戦車をはじめとするの敵陸上部隊と直接交戦し、打撃力と機動力をもって「衝撃効果による戦闘」[5]を行う攻撃的部隊として運用される。攻撃的役割以外には、 防御・延滞・後退行動、戦果の拡張における追撃、防御時や空挺・ヘリボーン攻撃における反撃の役割[6]などがある[7]。いずれにせよ、戦車の持つ打撃力と機動力を活用するのが戦車の特性に最も合った運用方法であるといえる。
「打撃と恐怖」
戦車の区分
[編集]戦車は重量や任務によって次のように分類することができる。
重量別
[編集]第二次世界大戦期からしばらくするまで使われた戦車の重量による区分。ただしこの区分は国や時代によって変化する[8]きわめて曖昧なものであり、明確な重量区分があるわけではない。以下に挙げる重量もおおよその目安である。
- 豆戦車 (Tankette) - カーデン・ロイド豆戦車、L3/33 (C.V33)、九四式軽装甲車など
軽戦車よりも軽量・低コストな戦車。攻撃力・防御力はほぼ皆無で、戦闘任務よりむしろ兵員輸送や火砲の牽引といった汎用車輛としての任務で活躍した。
- 軽戦車 (Light Tank) - M3軽戦車、LT-38(38(t)戦車)、九五式軽戦車、AMX-13など
重量5~20t[9]程の小型軽量な戦車。中戦車に比べれば攻撃力・防御力は高いとは言えないが、機動性が高く、コストも低いため大量生産に適した。数的に主力の戦車として使われることもあれば、偵察や追撃等に使われることもあった。
- 中戦車 (Medium Tank) - V号戦車パンター、T-34、M4中戦車、九七式中戦車チハなど
重量15~50t程の攻撃力・防御力・機動性をバランスよく(各国により性能差はあるが)組み合わせた戦車。第二次世界大戦では戦車部隊の主力として活躍し、戦後は主力戦車に発展した。
重量40~80t程の大型で重量のある戦車。攻撃力・防御力の高さにより陣地突破や対戦車戦闘で真価を発揮したが、重いため軽・中戦車に比べると機動性や運用性に欠け、コストも高かった。
- 超重戦車 (Super-heavy Tank) - ツァーリ・タンク(レベテンコ)、マウス、シャール 2C、オイ車など
重戦車よりもさらに重量のある戦車。攻撃力と防御力(さらに機動性や運用性の悪さ)は重戦車をも凌駕するが、ほとんど生産されなかったか試作に終わった戦車が多い。
-
豆戦車
TKS(ポーランド) -
軽戦車
T-26(ソ連) -
中戦車
T-34/76(ソ連) -
重戦車
ARL-44(フランス) -
超重戦車
マウス(ドイツ)
任務別
[編集]- 主力戦車(Main Battle Tank,MBT)
第二次世界大戦後、中戦車から発展する形で登場した戦車部隊の「主力」となる戦車。21世紀現在、各国の陸軍が装備する戦車の大半は主力戦車に分類される。 主力戦車は開発時期や仕様により、おおむね次のような世代分けがされる。しかし改良により世代が曖昧な戦車も存在し、この世代分けが絶対的なものではないことには注意が必要である。
1940年代後半~1950年代に登場。第二次世界大戦における中戦車が主力戦車に分類し直された程度の戦車である。口径90~100mmクラスの主砲を搭載し、 400馬力級のエンジンで最高速度40km/h前後、重量40~50t前後。砲塔が避弾経始(後述)を考慮した流線型の構造をしていることが多い。
- 第2世代主力戦車(Second generation Main Battle Tank)
- M60パットン(2.5世代とも)、T-62、T-72(2.5世代とも)、メルカバMk.I/II、レオパルト1(A6以降は2.5世代とも)、Strv.103、チーフテン、AMX-30、74式戦車など
1960~1970年代に登場。ほぼすべての戦車で避弾経始が考慮された構造となった。 レオパルト1、AMX-30、74式戦車は防御力を若干犠牲にしてでも機動性を確保しているが、 チーフテン、メルカバMk.I/IIのような防御力を重視した戦車もある。なお、 第2世代主力戦車のなかでも後期のFCSや暗視装置の強化が図られている戦車を第2.5世代主力戦車とすることもまれにある。
1980~1990年代に登場。高度な射撃管制装置(FCS)によって制御される120~125mm滑腔砲、複合装甲を採用し、 1,500馬力クラスのエンジンで最大速度60~70km/時で走る。
- 第3.5世代主力戦車(Advanced Third generation Main Battle Tank)
- ルクレール、メルカバMk.IV、M1A2/SEP、K2、10式戦車など
1990年代から現在にかけて登場。車輛間データリンクシステムの搭載により、ほかの戦車と敵味方の位置などの情報の共有が容易となっている[注釈 5]。 戦車そのものの外見・性能は第3世代主力戦車とほとんど変化がないが、
-
第1世代主力戦車
69式戦車(中国) -
第2世代主力戦車
74式戦車(日本) -
第3世代主力戦車
M1A1(アメリカ) -
第3.5世代主力戦車
K2(韓国)
- 歩兵戦車(Infantry Tank)/
- 歩兵戦車Mk.IIマチルダII、歩兵戦車Mk.IIIバレンタイン、歩兵戦車Mk.IVチャーチルなど
重戦車に相当。
- 巡航戦車(Cruiser Tank)/騎兵戦車(Char de cavalry)/快速戦車(Быстрый танк)
- 巡航戦車Mk.VIクルセーダー、ソミュアS35、BT-7など
軽戦車・中戦車に相当。
-
巡航戦車Mk.IV(手前)と歩兵戦車Mk.IIマチルダII
-
ルノーR35騎兵戦車
各国の名称
[編集]

各国の「戦車」にあたる語は、以下のとおりである。
- 日本語: 戦車(せんしゃ)
- もともと「戦車」という言葉は、中国同様に漢文中の古代戦車を意味していた[注釈 6]が、日本史上ではほとんど使われたことが無い兵器だった[注釈 7]。近代戦車については1917年(大正6年)の陸軍省調査書において『近迫戦に専用する「タンク」と称するものあり』と記され[10]、1918年(大正7年)に日本陸軍へ導入された当初は英語のtankをそのまま音写して「タンク」あるいは装甲車と呼んでいたが、程なくして戦車と呼ばれるようになった。はっきりとした時期は定かでないが、1922年(大正11年)発行の論文中に戦車の訳語が登場する[11]。また陸軍の会合の席上である大尉が思いつきで戦車と呼ぶのはどうかと提案したところ、その場の皆の賛同を得て受けいれられたという話もある[12][13]。1925年(大正14年)陸軍歩兵学校制作の「歩兵操典草案」では兵卒向けの心得の中で戦車という語を用いつつ「一般にタンクと称する」と説明し[14]、一般向けの冊子と思われる「学校案内」においても同様な表現を用いている[15]。第二次世界大戦後に発足した自衛隊は当初、戦車という軍事用語を忌避して「特車」(とくしゃ)と呼称していたが、1962年(昭和37年)1月からは「戦車」と呼ばれるようになった[16]。「主力戦車」(しゅりょくせんしゃ)は「Main Battle Tank」の訳語であるが、直訳の「主戦闘戦車」(しゅせんとうせんしゃ)という語が使われることもある[17][18]。
- 朝鮮語: 전차(チョンチャ)/탱크(テンク)
- ハングルでは、日本語と同様古代戦車・近代戦車ともに「전차」(チョンチャ、戰車)と呼ぶが、緊圧茶(磚茶)や電車(電気機関車)も同じ表記である。朝鮮人民軍では、 tank を音写した「탱크」と呼んでいる。「主力戦車」は「주력전차」(チュリョクチョンチャ)。
- 英語: Tank(タンク)
- イギリスでは当初近代戦車の開発時に名称として「陸上艦」(Landship)という語が使われており、最初期の戦車であるビッグ・ウィリーもイギリス艦艇風に「HMLSセンチピード」(HMLS Centipede)などと呼ばれていたが、戦車の開発を秘匿するために都合のいい名称が必要となった。当初は「(ロシア向け)水運搬車」(Water Carrier)という名前がつけられ、戦車の開発委員会も"Water Carrier"を省略して「W.C.開発委員会」と呼ばれたが、"W.C."(すなわちトイレ)は「(ロシア向け)トイレ」や「トイレ開発委員会」と読むこともでき、格好が悪いだけでなくかえって怪しまれる可能性もあった。そこでより単純に「水槽」(Tank,タンク)と呼ぶようになり、開発委員会も「T.S.委員会」(Tank Supply,水槽=戦車供給委員会)という名称にかわった[19][20]。なぜ戦車を水槽に例えたかについてはこれ以外の説もあるが、以降「タンク」が戦車の名称として定着している。「主力戦車」は「Main Battle Tank (MBT)」(メイン・バトル・タンク)と呼ばれる。
- 中国語: 坦克(タンク)
- 「戰車」(ヂァンチゥー、「战车」とも)は多くの場合古代戦車を意味するので、近代戦車は「Tank」を漢字に置き換えて「坦克」(タンク)と呼んでいる。ただし、台湾では日本語と同様に「戰車」と呼んでいる。「主力戦車」は「主力战车」(ヂゥーリィーヂァンチゥー)か「主力坦克」(ヂゥーリィータンク)、または「主戦坦克」(ヂゥーヂァンタンク)。
- ヘブライ語: טנק(タンク)
- 英語の「Tank」をヘブライ文字に置き換えたもの。なお古代戦車は「מרכבה」(メルカバ)と呼ばれ、イスラエルの主力戦車、メルカバにその名が使われている。「主力戦車」は「טנק המערכה」(タンク・ハ=マラカ)。
- ロシア語: Танк(タンク)
- 英語の「Tank」をキリル文字に置き換えたもの。「主力戦車」は「Основной боевой танк」(アスナブノイ・ボエヴォイ・タンク)。
- ドイツ語: Panzer(パンツァー)
- ドイツでは近代戦車を「panzer」(パンツァー、直訳で「装甲」の意)と表記される。英語上ではPanzerは「ドイツの戦車」全般を意味する語として取り入れられている。第二次世界大戦期のドイツ戦車の制式名につく「PanzerKampfwagen」(パンツァーカンプフワーゲン)は「装甲戦闘車輛」という意味だが、「PanzerKampfwagen III」などの場合「III号戦車」のように訳されることが多い[注釈 8]。「主力戦車」にあたる語は「Kampfpanzer (KPz)」(カンプフパンツァー)。
- フィンランド語: Panssarivaunu(パンサリバウヌ)/Tankki(タンキ)
- かつてはドイツ語同様近代戦車は「PanzerKampfwagen」(「装甲戦闘車両」の意)と呼ばれていたが、第一次大戦以降装甲車など戦車以外の「装甲戦闘車両」が出始めたので、近代戦車を指す語はやはりドイツ語から「panzer」の語を借りて「Panssarivaunu」(パンサリバウヌ)という語に代わった。口語的には「Tankki」(タンキ)とも。「主力戦車」は「TaisteluPanssarivaunu」(タイステルパンサリバウヌ)。
- スウェーデン語: Stridsvagn(ストリッツヴァグン)
- 直訳で「戦闘車輛」。スウェーデンの制式戦車の名称につく「Strv.」とは、この語の略称である。
- フランス語: Char de combat(シャール・ド・コンバ)
- フランス語では古代・近代戦車のことを総称して「Char」(シャール)と呼ぶが、とくに近代戦車を指す際には「Char de combat」(シャール・ド・コンバ、直訳で「戦闘戦車」)と表記される。「Char de bataille」(シャール・ド・バタイユ)や「Char d'assaut」(シャール・ダッソー)とも表記される。「主力戦車」は「Char de combat principal」(シャール・ド・コンバ・プリンシパル)か「Char de bataille principal」(シャール・ド・バタイユ・プリンシパル)。
- イタリア語: Carro armato(カッロ・アルマート/カルロ・アルマート)
- 直訳で「装甲車輌」。単に「Carro」(カッロ)とも。「主力戦車」は「Carro armato da combattimento」(カッロ・アルマート・ダァ・コンバッティメント)。
- ポーランド語: Czołg(チョウク)
- もとは「這う」の意。戦車が地上を這うように進むことから1919年ごろにつけられた[21]。「主力戦車」は「Podstawowy Czołg」(ポスタヴォヴィ・チョウク)。
- アラビア語: دبابة(ダッバーダ)
戦車の名前について
[編集]戦車の名前といっても、制式名だけでなく通称や社内開発番号、軍による整理番号などがあり、同じ戦車でも複数の呼び方がされることがある。全戦車の名称の由来すべてについて述べるのは困難であるが、以下に一部の例を載せた。
- シャーマンVC ファイアフライ
- シャーマンV - 「シャーマン」はイギリス軍がアメリカから供与されたM4中戦車につけた通称(南北戦争での北軍の将校、ウィリアム・シャーマンに由来)で、「V」(ローマ数字の「5」)がこの場合、イギリス軍がつけた30気筒マルチバンク・エンジン搭載型のM4A4に対する呼称(M4→シャーマンI、M4A1→シャーマンII…)。
- C - イギリス軍が17ポンド砲搭載のM4中戦車の名前につけた呼称。同じように76mm砲搭載型は「A」、105mm砲搭載型は「B」という文字がつけられた。
- ファイアフライ - 通称。「蛍」(Firefly)から。
- M1A2SEP エイブラムス
- M1 - 「M」は「型式」(Model)、「1」がこの場合、アメリカ軍が戦車に対しつけた通し番号(M60戦車からリセットされた)。試作時には「XM1」(「試作」(eXperiment)から)と呼ばれていた。
- A2 - 「A」は「改良型」(Advanced)。「2」がこの場合、車輌間データリンクシステム搭載型。
- SEP - 「システム向上パッケージ」(System Enhancement Package)。車輌間データリンクシステム性能向上+旅団内データリンクシステム搭載型。
- エイブラムス - 通称。第二次世界大戦時に戦車兵として活躍し、本車の開発を推進した陸軍参謀総長、クレイトン・エイブラムス(Creighton Abrams)大将から。
- VI号戦車E型 ティーガーI (Sd.Kfz.181)
- VI号戦車E型 - ドイツ語なら「PanzerKampfwagen(Pz.Kpfw) VI Ausf.E」。「VI号」が戦車の開発順[注釈 9]。なぜいきなり「E型」なのかは不明である(ティーガーIIは「VI号戦車B型」)。
- ティーガーI - 通称。「虎」(Tiger)から。ティーガーIIが登場するまでは、単に「ティーガー」と呼ばれていた(チャレンジャー1についても同じ)。日本では英語読みの「タイガー」や「Tiger」をそのまま読んだ「ティーゲル」という呼び方もある。
- Sd.Kfz.181 - ドイツ陸軍兵器局が制式の全装甲戦闘車輌につけた制式番号。「特殊車輌番号」(Sonderkraftfahrzeug)の略。
- 九七式中戦車 チハ
- 九七式 - 皇暦2597(1937)年採用を表す。戦後の日本の戦車や中国の戦車も、同じように西暦で「~式戦車」と呼び表している。
- チハ - 中戦車の「チ」といろは順の「ハ」を組み合わせた語。
- AMX-30[23]
- AMX - 戦車の製造を担当したイシー=レ=ムリノー兵器廠(Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux)の略。
- 30 - 30t級戦車の意(AMX-30の重量は厳密には37tだが)。
- FV4201 チーフテン
- FV4201 - イギリス軍の装甲車輌理番号(詳細はFVシリーズの軍用車両リスト参照)。「FV」は「戦闘車輛」(Fighting Vehicle)。
- チーフテン - 通称。「族長・酋長」(Chieftain)から。
戦車の歴史
[編集]約一世紀前に実用的な戦車が登場して以来、戦車は二度の世界大戦、冷戦期における地域紛争、そして21世紀の戦争でも活躍し、そのつど変遷を重ねてきた。しかし同時に戦車の有用性に疑問が呈されたことも一度ならずあった[24]。しかし攻撃力・防御力・機動性のすべてにおいて戦車を代替しうるだけの性能をもつ陸上兵器はいまだ登場しておらず、今後も戦車は姿を消すことなく地上戦力の一翼を担うであろうとされている[25]。
前史:装甲と履帯
[編集]
戦車は第一次世界大戦で初めて登場したが、その際まったくのゼロから開発されたというわけでもない。第一次世界大戦以前にも「装甲された兵器」というアイデアは存在し、その一部は実際に戦車開発への下地となったのである[注 1]。 そして農作業用トラクターに使われていた履帯が「装甲された兵器」の走行手段として採用されると
「装甲を施した車輛」は戦車以前にも存在する。画家にして発明家でもあるレオナルド・ダ・ヴィンチは1500年ごろに傘型の円形装甲を施し、全周に火砲を搭載した「戦車」を考案し、文禄・慶長の役での攻城戦には「亀甲車」という現在の装甲工兵車のような兵器が投入されている。これらの車輛は人力駆動であり、実用化には限界があったが、19世紀に蒸気機関が実用化され自動車が登場すると「装甲を施した自動車」すなわち装甲車が考案されるようになり、のちのガソリンエンジンの開発によってより実用的な装甲車が登場した。1902年にイギリスの機械技師、フレデリック・シムズが考案した全周装甲の装甲車を皮切りに、第一次世界大戦前夜までに各国の軍隊は装甲車をこぞって配備したが、車輪駆動であるがゆえに不整地での走破性に乏しかった。装甲車は最前線の荒地で活躍することはできず、もっぱら後方警備等に使われた[26]。
無限軌道(キャタピラ)は18世紀末の発明家、リチャード・エッジワースが1770年代に設計したポータブル・レイルウェイにまでその起源を求めることができる[27]。その後19世紀を通して無限軌道とそれを使った蒸気機関トラクターが様々に考案・設計されるが、実用性と信頼性の高さにおいてはアメリカの発明家、ベンジャミン・ホルトが1906年に製作したトラクター(ホルト・トラクター)の搭載する無限軌道に勝るものはなかった。またSF作家H.G.ウェルズの1903年の作品、「陸の甲鉄艦」(The Land Ironclads)には100ft(30m)長の鋼鉄の箱に火砲や歩兵を乗せ、8組の無限軌道で走行する「甲鉄艦」なる兵器が登場する。のちに戦車の開発で中心的役割を占めることになるアーネスト・D・スウィントン中佐(後述)も「陸の甲鉄艦」から刺激を受けたといわれる[28]。
-
レオナルド・ダ・ヴィンチの考案した円形戦車。
-
「陸の甲鉄艦」でH.G.ウェルズが描いた甲鉄艦。
第一次世界大戦:戦車登場
[編集]

第一次マルヌ会戦が終結した後 互いの側面につこうと延翼競争を繰り広げた結果、スイス国境から英仏海峡まで互いに塹壕を掘ってにらみあう塹壕戦の様を呈した。 そのため敵陣突破のためには塹壕への正面攻撃が不可欠であった。
しかし塹壕陣地を攻撃するには、「集団自殺」とまで評されるほどの多大な犠牲を覚悟しなくてはならなかった。塹壕(および塹壕内に設けられた待避壕)に籠もった兵士に対しては数日に及ぶ激しい準備砲撃も決定的な効果を及ぼすには至らず、鉄条網と組み合わさって配置された機関銃の前に攻撃側はほとんどの場合撃退された。万一塹壕を占領した場合でも、突破距離はせいぜい数kmに過ぎなかったのである。
さらに激しい砲撃の結果、味方の塹壕から敵の塹壕までの平原(無人地帯という)は砲撃跡によって荒地と化し、車輪で走行する装甲車の機動を困難にした。
イギリス篇
[編集]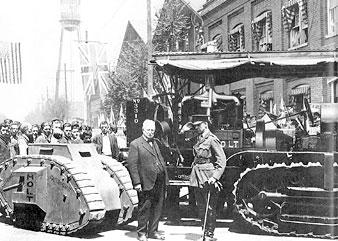
当時連絡将校としてフランスに派遣されていたイギリスのアーネスト・スウィントン中佐は、ホルト・トラクターをヒントに履帯で走る戦闘車両のアイデアを得た。
1915年2月にはホルト・トラクター
さて中戦車Mk.I~Mk.Vは
第一次世界大戦で主戦場となったヨーロッパ西部(西部戦線)ではマルヌの戦い以降、英仏軍とドイツ軍双方がヨーロッパ大陸を南北に縦断する形で塹壕を設営してにらみあう、塹壕戦の様を呈した。有刺鉄線や機関銃で固めた敵の塹壕陣地に生身の歩兵が突撃することは「単なる集団自殺」[29]とさえ称された攻撃側が著しい損害を出すだけの行為であり、互いに塹壕陣地を突破する決め手を欠いたまま戦闘は膠着することとなった。さらに対峙する両軍は互いに激しい砲撃の応酬を行ったため、両軍陣地間にある無人地帯は砲弾跡があちこちに残る不整地と化し、装甲車など装輪式車輛の機動は困難であった。
これらの閉塞状況を打破するため、塹壕陣地を突破できる新たな装甲車輛が求められた[30]。その結果登場した兵器が戦車である。 このとき注目されたのが、前述のホルト・トラクターであった。ホルト・トラクターは西部戦線での資材運搬や火砲の牽引に利用されていたが、このホルト・トラクターを出発点に、イギリス、フランスなどが戦車の開発をスタートさせた。
イギリスではアーネスト・D・スウィントン陸軍中佐がホルト・トラクターから着想を得て機関銃搭載車として用いることを考えたが、このアイディアは実現されなかった。その一方、飛行場警備などに装甲自動車中隊を運用していたイギリス海軍航空隊のマーレー・スウェーター海軍大佐が陸上軍艦 (Landship) の提案を行った。1915年3月、この海軍航空隊の提案を受けて、当時海軍大臣であったウィンストン・チャーチルにより、海軍設営長官を長とする「陸上軍艦委員会」が設立され、装軌式装甲車の開発が開始された。
陸上軍艦委員会による幾つかのプロジェクトののち、フォスター・ダイムラー重砲牽引車なども参考にしつつ、1915年9月にリトル・ウィリーを試作した。リトル・ウィリー自体は、塹壕などを越える能力が低かったことから実戦には使われなかったが、のちのマーク A ホイペット中戦車の原型となった。リトル・ウィリーを反省材料とし、改良を加えられた「マザー」ことビッグ・ウィリーが1916年1月の公開試験で好成績を残し、ビッグ・ウィリーを発展させる形でマークI戦車が登場した。

マークI戦車は1916年9月15日、ソンムの戦いにおいて49輛が戦車を用意し、稼働できたのは18両、そのうち実際に戦闘に参加できたのは5両だけだった。
マークI戦車の初実戦、ひいては戦車が史上初めて実戦に参加したソンムの戦いであったが、マークI戦車の戦果は「大活躍」とまではいかなかった。機械的信頼性の低さにより戦車が行軍中に次々と脱落、
は局地的には効果を発揮したものの、歩兵の協力が得られず、またドイツ軍の野戦砲の直接照準射撃を受けて損害を出した。
結局イギリス軍は幅8km、深さ2kmの戦線を確保できたにとどまった(もっとも、イープルの戦いでは7kmの前進に数十万の犠牲と数十日の時間が費やされている)[31]。
第二次ヴィレル・ブレトーニュの戦いでは史上初の戦車同士による交戦が行われている。
当初想定されていた戦車の運用法では大量の戦車による集団戦を行う予定であった。しかしこのソンムの戦いでイギリス軍は結局、膠着状態を打破することはできずに連合国(協商国)側の戦線が11kmほど前進するにとどまった。
その後、1917年11月20日のカンブレーの戦いでは世界初となる大規模な戦車の投入を行い、300輌あまりの戦車による攻撃で成功を収めた。その後のドイツ軍の反撃で投入した戦車も半数以上が撃破されたが、戦車の有用性が示された攻撃であった。第一次世界大戦中にフランス、ドイツ等も戦車の実戦投入を行ったものの、全体として戦場の趨勢を動かす存在にはなり得なかった。

さてフランスではジャン・B・E・エスティエンヌ砲兵大佐の主導のもと、ホルト・トラクターの構造をほぼ流用する形で戦車を開発した。この結果誕生したのがシュナイダー戦車とサン・シャモン突撃戦車であるが、フランス戦車の初陣となったシュマン・デ・タームの戦いでは投入されたシュナイダー戦車132輛のうち計76輛が撃破されるなどして行動不能になり、3週間後に投入されたサン・シャモン突撃戦車16輛は車長の大きさに起因する超壕性能の欠陥を露呈するなど、両車の性能は決してよいとはいえなかった。エスティエンヌはこれを受けてシュナイダー、サン・シャモン両車の生産中止を決定、開発中のルノーFT-17の配備を進めることを決定した[32]。このルノーFT-17は、それまでの車台に箱型の戦闘室を載せる形ではなく、直角に組み合わせた装甲板で車体を構成し、横材となる間仕切りで戦闘室とエンジン室を分離することでエンジンの騒音と熱気から乗員を解放した。小型軽量な車体と幅広の履帯、前方に突き出た誘導輪などによって優れた機動性を備えており、全周旋回砲塔は良好な視界と共に1つの砲で360度の射界を持っていた。
FT-17は3,000輛以上生産され、当時もっとも成功した戦車となった。第一次世界大戦後には世界各地に輸出され、輸出先の国々で最初の戦車部隊を構成し、また初期の戦車設計の参考資料となった。
第一次世界大戦から第二次世界大戦の間、各国は来るべき戦争での陸戦を研究し、その想定していた戦場と予算にあった戦車を開発することとなった。敗戦国ドイツも、ヴェルサイユ条約により戦車の開発は禁止されたものの、農業トラクターと称してスウェーデンで戦車の開発、研究を行い、また当時の国際社会の外れ者であるソ連と秘密軍事協力協定を結び、赤軍と一緒にヴォルガ河畔のカザンに戦車開発研究センターを設けた。
第一次世界大戦中から第二次世界大戦直前までに開発された戦車は、第一次世界大戦において対歩兵戦闘に機関銃が大いに活躍したことから機関銃を主武装にするものが多く見られた。これは当初、想定された戦場が塹壕戦であったためであるが、第二次世界大戦初期には砲を主武装にした戦車に移行した。
-
「マザー」ことビック・ウィリー。
-
A7V。
-
Mk.Aホイペット戦車。
戦間期
[編集]
1918年11月、第一次世界大戦が終結すると各国では軍事予算の削減が図られ、大戦中に生産された戦車が大量に余剰となったという点もあり(上田、2014、p25)、戦車の開発は停滞することとなった。 さて、多くの国では第一次世界大戦同様、将来の戦争は塹壕戦になるだろうと予想していた。戦車はあくまで歩兵を援護して塹壕を制圧するための「支援火器」(その結果、イギリスでは歩兵戦車というジャンルが登場した)であり、戦車は歩兵部隊の中に分散して配備されていた(テク、p10)。
一方、戦車を集中運用すると同時に歩兵や砲兵を機械化(移動手段を徒歩や馬によらず、自動車等にすること)することで、戦車の機動性を最大限発揮するよう主張した将校も現れた。ドイツのハインツ・グデーリアン、イギリスのジョン・F・C・フラー、アメリカのアダナ・R・チャーフィーJr.、フランスのシャルル・ド=ゴール、ソ連のミハイル・トゥハチェフスキーである。ド=ゴールは1933年に発行した著書、『職業軍の建設を!』(職業的軍隊をめざして)のなかで次のように述べている。
戦車は戦術を一変する。戦車によって奇襲が再生する。機械の特性が如何なく発揮される奇襲が。戦闘の細部に至るまで機動が復活する。なぜならば、戦車は砲火をくぐって正面にあるいは側面に姿を現し、射撃しながら前進も方向転換もできるからである。戦闘集団は、永久に失われたかに思えていたあの動的防護手段を戦車によって再度手にすることになる。 — シャルル・ド・ゴール(小野繁 訳)、『職業軍の建設を!』74~75頁。
しかしフランスやイギリスではこのような意見は多くの場合、軍の保守派からの反対を受けてほとんど顧みられることがなかった。 フラーはのちに「戦車は敵に対してのみならず、我が軍の伝統及び因習に対しても戦わなければならなかった」[33]と述べている。

この「戦間期」において各国で「流行った」戦車が豆戦車(タンケッテ)と多砲塔戦車である。ギフォード・L.Q.マーテル少佐が自宅のガレージで様々な廃品を使って製作したモーリス・マーテル豆戦車やカーデン・ロイド豆戦車に代表される豆戦車は、調達コストが低いことから各国の軍隊が製作・輸入し、ヴィッカース・A1E1インディペンデントに端を発する多砲塔戦車は砲塔を多数搭載することで火力の向上を図ったのである。しかし豆戦車は戦闘任務にはあまりに非力で、むしろ兵員輸送や火砲の牽引といった汎用車輛としての任務の方が適していた(カーデン・ロイド豆戦車から発展したユニバーサル・キャリアなど)。多砲塔戦車は性能があまりに低く、

アメリカの発明家、ジョン・W・クリスティーが開発した一連の戦車
とくにM1931 T3は独自開発のサスペンションを搭載し、高速走行を実現した。クリスティーの戦車はアメリカ本国ではほとんど顧みられなかったが、イギリスとソ連がT3をそれぞれ購入、特にソ連ではBT戦車を経て、T-34(後述)の開発につながることになる。
-
LT-38(38(t)戦車)。
-
T-35。
第二次世界大戦期
[編集]第二次世界大戦において、戦車は歩兵や砲兵、航空機などをはじめとするほかの兵科・部隊とともに活躍した。戦争の経過につれ戦車の攻撃力と防御力は爆発的な増大を見せたが、第一次世界大戦時よりさらに本格的となった戦車戦において攻撃力・防御力のみならず、無線機の有無や乗員の配置といった「カタログデータに載らない」性能差なども戦車の優劣を分けた。さらに各国の戦車の運用方法も戦闘の勝敗を左右した。

1940年のフランス戦当時、ドイツ軍の保有したI号、II号、II号、IV号戦車や35(t)、38(t)戦車に対してフランス軍のS-35やシャールB1bis.は攻撃力や防御力だけを見れば決して劣っているわけではなく、むしろフランス戦車の方が優れていた。だがドイツ軍が戦車を「電撃戦」を担うべき「機動兵器」としてとらえ、戦車間での連携を重視していたのに対し、フランス軍にとって戦車とは「歩兵の支援兵器」であり、戦車同士による連携はさほど重視していなかった。その現れとしてドイツ戦車には無線機が標準装備されており、また砲塔要員が3名(I号/II号は1名だが)で戦車長は主砲の発射、装填は砲手や装填手に任せ、戦車長自らは指揮下の戦車の指揮に専念できた。一方でS-35やシャールB1bis.の砲塔要員は1名で、戦車長は戦車の指揮のみならず、主砲の発射や装填も行わなければならなかった。無線機の装備率も低く、戦車同士で連携して動くということは困難であった。結果として個々の戦闘を見れば(ストンヌ攻防戦においてシャールB1bis.1輌で13輌の戦車を撃破したピエール・ビヨット大尉など)フランス戦車がドイツ戦車を圧倒した例もあるものの、フランス軍がドイツ軍を押しかえすことはなかった。

しかしそのドイツ軍にとっても、1941年の東部戦線におけるソ連軍のT-34の出現には驚愕せざるを得なかった。「第二次世界大戦における戦車の最高傑作」[34][35][36][37]とたびたび称されるこのT-34は実際のところ車内スペースが小さいなど居住性がひどく、砲塔要員は2名で戦車長は砲手兼任、生産当初は照準器やエンジンの部品精度が劣悪でカタログデータ通りの性能が出せないなど、欠点も多かった。しかし76.2mm砲による攻撃力、傾斜装甲による防御力、幅広の履帯とV-2ディーゼルエンジンによる機動性、すべてにおいて高い完成度をもち、当時のドイツ軍が所有する大半の戦車・火砲にとってT-34に対抗することは困難であったのである。またT-34は(ソ連の工業力を考慮しても)生産性が高く、76.2mm砲搭載型が約35,000輌、85mm砲搭載型(T-34-85)が約29,000輌の合わせて約6万輌[35]が生産された。第二次世界大戦の激戦地、スターリングラード(現ヴォルコグラード)もまた戦中・戦後を通して戦車の一大生産地であった。
このT-34もドイツ軍の侵攻を完全に押しとどめられたわけではないが、「T-34ショック」を受けてドイツ軍はT-34に対抗できる戦車の改良、開発を急いだ。その結果登場したのが、より強力な主砲を搭載したIV号戦車、傾斜装甲を採用するなどT-34から大きな影響を受けたパンター、そしてティーガーIである。ティーガーIはその攻撃力と防御力は、T-34をはじめとした連合軍戦車のそれを凌駕しており、後継車のティーガーIIともども東部戦線・西部戦線で連合軍戦車に対して猛威をふるい、ミヒャエル・ヴィットマンSS大尉やオットー・カリウス少尉といったドイツ軍の「エース」もティーガーIの乗員であることが多かった。しかし一方で機動性は戦術的・戦略的機動性両方で低く、信頼性・整備性も悪かった。何より製造コストが高く(IV号戦車3輌分)、生産数が少なかった。ティーガーIはドイツ軍の主力となるべき戦車ではなく、その役割はIV号戦車とパンターであった。

アメリカ軍が主力としたM4中戦車(シャーマン)は、戦車の性能こそIV号戦車と同等という程度で、パンターやティーガーIといった戦車に比べれば見劣りした。車高が高くて見つかりやすく、被弾するとすぐ炎上するので、当時アメリカで流行していた一発で火がつくロンソン社のライターにちなんで「ロンソンライター」という不名誉なあだ名がつけられることもあった。しかし一方で車高を高くとったことで居住性は良好であった上に、各種エンジンを大きな改造なしに搭載できるだけのスペースがうまれ、この点はアメリカにおけるM4中戦車の大量生産に貢献し、アメリカ軍は大量のM4中戦車を用意することができた。派生形も多く、歩兵支援用にティーガーI以上の最大装甲厚(152mm)を誇るM4A3E2ジャンボ、非常に強力な17ポンド砲を搭載したファイアフライ(イギリス軍の改造によるもの)、そして全体的性能を引き上げた最終型、M4A3E8イージーエイトなどが存在する。
第二次世界大戦においては、各国で多種多様な戦車、および戦車に準ずる装甲戦闘車輌が開発・投入された。しかし各国の戦車部隊の主力をつとめたのは結局、各国によって性能差はあれど、T-34、IV号戦車やパンター、M4中戦車、97式中戦車チハといった「中戦車」であった。第二次世界大戦後ほどなくして軽戦車・重戦車はしだいに姿を消してゆき、代わりに中戦車が戦車の主力を占めるようになる。「主力戦車」の登場である。
-
III号戦車。
-
シャールB1bis.
-
V号戦車パンターA型。
-
M4シャーマン。
(写真はファイアフライ)
冷戦期
[編集]主力戦車は時代別により、「第1世代主力戦車」「第2世代主力戦車」「第3世代主力戦車」の三つに大別され、さらに世代間により「第3.5世代主力戦車」等の区分が存在する。
第1世代主力戦車(1950年代)
[編集]
朝鮮戦争序盤、北朝鮮軍の第105戦車旅団が装備するT-34-85は、韓国軍やアメリカ軍さえも圧倒した。
しかしアメリカ軍がM26やその改造型、M46を投入するとT-34-85は全くの無力で、「キャビアの缶詰」などと嘲笑された。
第1世代主力戦車は、基本的に第二次世界大戦末期の中戦車、ないし重戦車クラスの戦車を「主力戦車」として分類し直したものが多い[38][39]。90~100mm口径の主砲を搭載し、避弾経始を重視した丸型の鋳造砲塔を持つ。技術的にも第二次世界大戦期から若干進歩した程度といえるが、砲身安定装置や光学式測距儀、射撃用のコンピューター、赤外線投光器などを搭載した車輌もあり、装備のハイテク化が始まっている[39]。

T-34の流れをくむT-44の発展型として完成したT-54/55(ソ連)は戦車のなかで史上最多の約9万6,000[40]~10万輌[38]が生産された。T-54/55は世界各国に輸出され(59式戦車(中国)などライセンス生産もなされた)、数多くの紛争に参加、現在でも改良を加えながら第一線装備とする国は多い。
第二次世界大戦末期に「重巡航戦車」として開発されたセンチュリオン(イギリス)もまた、登場以来数々の実戦に参加した。第二次世界大戦での実戦参加こそかなわなかったが、朝鮮戦争では国連軍戦車のなかで最強最良との評価を得た(もっともイギリス軍が戦車戦を行う機会は少なかったが)[41]。堅実な設計で発展の余地があったために武装をはじめとする強化も行われ、中にはショット(イスラエル)やオリファント(南アフリカ)といった徹底的改良が施された車輛も存在する。
-
M48A3。
-
センチュリオン(写真はイスラエルのショット・カル)。
第2世代主力戦車(1960~1970年代)
[編集]1960年代に発生したベトナム戦争では当初、「ベトナムの戦場はジャングルだから戦車は役に立たない」などと言われていた[42]。事実、戦局を左右するような戦車戦こそなかったが[43]、アメリカ軍のM48パットンはケサン攻防戦などで「動くトーチカ」として活躍した。そして1975年、サイゴンに突入した北ベトナム軍はT-54、および59式戦車を装備していた。

1973年の第四次中東戦争では、「クルスク以来」[44]ともされる大規模な戦車戦がゴラン・スエズの両戦線で繰り広げられたが、同時に戦車がもはや無敵の存在でないことを世界中に印象づけられた戦争でもあった。戦争初期、スエズ方面においてイスラエル軍の戦車部隊は9M14 マリュートカ(AT-3 サガー)対戦車ミサイルをはじめとする対戦車火器を装備したエジプト軍の歩兵部隊によって大損害を被ったのである。
「戦車不要だよね」→複合装甲ですが?
1960~1970年代に現れたのが第2世代主力戦車である。なかでも第3世代主力戦車に匹敵するFCS(射撃管制装置)などの改良が施された第2世代主力戦車をまれに第2.5世代主力戦車に分類することもある[45]
相当 第2世代主力戦車は105~115mm口径(チーフテンのみ120mm)の主砲を搭載し、より低く流線型の砲塔をもつ。また本格的な射撃管制装置や暗視装置を備えた車輛もある。
当時は成形炸薬弾の発達や対戦車ミサイルの登場により、戦車の防御力が攻撃力に対し立ち遅れていた時代でもあった。したがってレオパルト1(西ドイツ)やAMX-30(フランス)という防御力よりも機動性を重視した戦車が西側には多かった。レオパルト1は出力重量比21hp/t、最大速度65Km/hが出せたものの、最大装甲厚は70mmであった(これでもAMX-30より最大装甲厚は大きかった)[46]。ただし、レオパルト1には改良型のA3から防御力強化のため空間装甲が追加されている。

そういった西側戦車の「機動性重視」の潮流に対して「防御力重視」の路線で開発されたのがチーフテン(イギリス)である。砲塔正面で200mm、車体前面で120mm[47](その上砲塔・車体ともにかなり傾斜がつけられている)の最大装甲厚をもっていたほか、武装としても諸外国よりひとまわり強力な 120mm砲を搭載した。反面、機動性は出力重量比14hp/t、最大速度48Km/hという第2世代主力戦車のなかで最低レベル[48]であった。
第2世代主力戦車のなかには、特徴的な構造をもった戦車もある。スウェーデンのStrv.103(Sタンク)とイスラエルのメルカバである。Strv.103は砲塔を車体に固定(限定旋回式ではなく、文字通り直接固定した)し、砲塔がないかつての「駆逐戦車」と呼ばれた車輛に似ているが、これは武装中立を貫くスウェーデンが待ち伏せ戦闘のコンセプトを徹底的に追求した結果のデザインであり、あくまで「主力戦車」であることに注意が必要である。Strv.103は特徴的な構造での戦闘を可能にするため、姿勢制御可能な油気圧式サスペンション、自動装填装置、(補助動力としての)ガスタービンエンジン搭載を行うなど、技術面でも特徴的である。
メルカバは第三次中東戦争のあおりでイギリスからのチーフテン導入を一方的に打ち切られたイスラエルが独自に開発した戦車で、エンジンを車体後部に配置するという一般的な戦車のスタイルに反し、エンジンを車体前部に搭載(Strv.103も同様)して防御材としての役割を狙うなど防御力と生残性を徹底して重視した設計となっている。
60年代末に現れたソ連のT-64と、アメリカ・西ドイツ共同開発のMBT/KPz.70は、ともに当時の最新鋭技術を投入した野心的な戦車であった。両車とも自動装填装置と主砲発射型ミサイルを搭載し、T-64は初めて複合装甲を、MBT/KPz.70はStrv.103同様に姿勢制御用に油気圧式サスペンションのほか、高度な射撃管制装置を備えていたのである。しかしコストが上昇したほか信頼性にも問題が発生し、T-64は(ソ連戦車としては珍しく)ソ連軍にのみ配備され、MBT/KPz.70は開発計画そのものが中止になるという不遇の結末もまた同じであった。だがT-64はT-80に発展したほかT-72に技術が流用され、MBT/KPz.70はM1エイブラムスやレオパルト2という第3世代主力戦車の開発につながることになる。

ソ連のT-72は開発系譜としては「廉価版」であるT-62の後継でありながら、「高性能版」であるT-64の技術も取り入れて製作された。結果、(T-62が初めて搭載した)滑腔砲と(T-64が初めて採用した)複合装甲を備え、第2世代主力戦車でありながら第3世代主力戦車にも近い性能を有する[49](2.5世代主力戦車としたり、そもそも第3世代主力戦車に分類することもある[50])戦車として完成した。T-72は中東諸国にも輸出されたが、第一次レバノン戦争ではメルカバMk.Iに、湾岸戦争ではM1A1、チャレンジャー1に対して惨敗した。乗員の練度の違いやそもそもイラク軍の保有したT-72が輸出用にわざと性能を落としてあるT-72M/M1(複合装甲未搭載)であった等の理由はあるにせよ(もっとも「純正版」のT-72も西側第3世代主力戦車に対して見劣りするのだが)、
-
AMX-30B。
-
M60A3パットン。
-
T-62。
-
T-64。
-
MBT/KPz.70。
-
メルカバMk.I。
第3世代主力戦車
[編集]1970年代末に現れた第3世代主力戦車は、次のような特徴を持っているということになる…のか?
- 120mm級滑腔砲の搭載
- 120mmライフル砲 L11を搭載したチャレンジャー1/2やアージュン、当面は105mmライフル砲 L7で良しとしたM1・K1の初期型を除き、第3世代主力戦車には西側で120mm、東側で125mm口径の滑腔砲を搭載している。
- 複合装甲の採用
- 1,500馬力級エンジンの搭載
- 射撃管制装置の搭載
- パッシブ式暗視装置、自動計算式弾道コンピューター、各種センサーなど。命中率が砲手の「腕」によって左右されることは少なくなった。
これらの結果、50t超というかつての重戦車クラスの重量・それに見合った防御力をもちながら出力重量比30hp/t、最高速度70km/hというかつての軽戦車クラスの機動性を有している。また第2世代主力戦車までは停車中の射撃が基本だったのに対して、第3世代主力戦車は行進間射撃(移動中の射撃)においても高い初弾命中精度を獲得、第1・第2世代主力戦車とは隔絶した性能をもつにいたった。
それを実証したのが1991年の湾岸戦争である。73イースティングの戦いではT-72の戦車大隊(26輛)がM1A1の一個中隊(9輛)に一方的に撃破され、他の戦区では各坐したM1A1が3輛のT-72を返り討ちにしたこともある。結局多国籍軍が装備したM1A1エイブラムスやチャレンジャー1は、イラク軍の戦車に対し400対1のキルレシオを達成した。前述のようにイラク軍のT-72Mは複合装甲がなく、射撃管制装置もわざと精度を下げてある輸出用だったという点があるにしても、これ以降T-72の国際的評価はガタ落ちしてしまった。

西ドイツの'レオパルト2やアメリカのM1エイブラムスなどが西側における代表的な第3世代主力戦車
ソ連T-80がくどくど。T-72がクズすぎた→T-90。ERAとかのおかげで外観がゲテモノだよね
第3.5世代主力戦車(1990年代~現在)
[編集]
第3世代主力戦車の後継となるべき第4世代主力戦車(後述)の開発が冷戦終結により停滞すると、各国は既存の第3世代主力戦車に戦術データ・リンクシステムなどの電子機器、すなわちベトロニクス(ヴェトロニクスとも、「車輛」(Vehicle)と「電子機器」(Electronics)を組み合わせた造語)を搭載し、戦車の電子化・デジタル化・自動化を図った。これらの改良が加えられている第3世代主力戦車は特に第3.5世代主力戦車と呼ばれる。 第3.5世代主力戦車の先駆けとなったのがAMX-56ルクレール(フランス)である。レオパルト2やM1エイブラムス等に比べれば後発だったが、最初から電子機器の搭載を前提として開発されていたので
- 装輪戦車で戦車は代替できない

写真のチェンタウロ偵察戦闘車等に代表される装輪装甲車は必ずしも戦車を代替するものではない。
装輪装甲車のなかには、チェンタウロ(イタリア)やルーイカット(南アフリカ)をはじめとする、口径50~105mmという戦車並みの主砲をもった装輪戦車(機動砲、戦闘偵察車とも)というカテゴリーが存在する。第二次世界大戦時にはすでにSd.Kfz.234/2(ドイツ)等が存在し、装輪戦車は現代になって急に現れたわけではないが、
経済的に主力戦車を導入できない国がその代替としてを導入する場合や(中米・アフリカ諸国の多くが採用したAML装甲車など)
21世紀に入ってストライカーMGSや機動戦闘車など、戦場まですばやく移動できるという戦略的機動性の高さを重視して配備されることが多い。
しかしこれら装輪「戦車」は、必ずしも戦車を代替できるものではない。装輪戦車は路上機動性では戦車にも勝り、長距離自走や空輸により戦場まですばやく移動できるという戦略的機動性の高さが大きな利点であるが、一方で装輪式であるがゆえに不整地走破能力は装軌式の戦車に及ばず、装甲は戦車に比べて極めて薄く、良くて14.5mm機関銃弾~20mm機関砲弾の直撃に耐えられる程度でしかない(装甲を厚くしようとすれば車重が増え、戦略的機動性の高さが失われる)。主砲自体の火力はともかく、装輪戦車は車重が軽いため主砲発射の衝撃を抑えきれず、さらに変形しやすいタイヤを用いているので命中精度が戦車に比べ劣る。
よってストライカーMGSは歩兵中隊の対戦車火力として配備され、
車などがあるが、他にも各国で多くの車両の開発・配備が進められており、日本の防衛省も機動戦闘車と呼ばれる105 mm 砲搭載装甲車の開発を進めている。 経済的に主力戦車を導入できない国がその代替として機動砲を導入する場合や、空輸での利便性が評価されて導入が進む場合が多いが、装輪装甲車が対戦車用に備える火力としては、軽量・無反動で射程が長く破壊力も大きい対戦車ミサイルの方が有効であり、機動砲はむしろ陣地破壊や狙撃手の掃討といった、高価なミサイルを使っていては費用対効果の悪い任務にも対応できる多用途性が求められている(さらにミサイルやロケットランチャーは最低攻撃距離が長く、発射までに時間を要する為に即応性が悪く突発的遭遇戦には向かない)。 装甲防御力が圧倒的に不足している事から真っ向な対戦車戦は望めず戦車の完全な代替には成り得ないという意見が強いが、相手が旧世代の戦車しか配備していない国、または戦車を所有しないゲリラやテロリストの様な非正規勢力である様な場合はその限りでは無いともされ、今後の推移が注目される[出典 13]。とはいえ、RPGのような近接対戦車兵器は途上国でもよく普及しており、ストライカー装甲車では戦車のような歩兵の盾としての役目は果たせない(イラク戦争におけるストライカーはRPGへの対策からカゴ状の追加装甲を取り付けることを強いられている)。さらにタイヤでは射撃時の安定性が大きく劣るため、精度が悪く、射撃後の揺動が長時間つづく欠点がある(さらに走破性も悪く、長時間停車していると空気が抜けてしまう)。結局のところ機動砲は火力支援のための自走砲であって、戦車の代用とはなりえないのである。
-
AMX-56ルクレール。
-
T-80U。
21世紀の戦車
[編集]
-
K2。
-
メルカバMk.IV。
未来の戦車
[編集]

20世紀の内にも登場するはずであった第3世代および3.5世代主力戦車の後継となるはずの戦車、すなわち第4世代主力戦車は21世紀になっても10式戦車をたまに第4世代とすることを除けば、なお登場していないとされている。(りゆうつらつら)。
どのような特徴をもって第4世代主力戦車とするかは定説こそないものの、3.5世代主力戦車ですでに実用化されている車輌間データリンクシステムなどのバトル・マネジメントシステムの搭載はほぼ確実視され、また軽量化やステルス性も考慮されるのではないかとされる[51]。
また第4世代主力戦車になる「はずだった」(どちらも開発中止となった)アメリカのMCS(Mounted Combat System,車載戦闘システム)とロシアのT-95はどちらも無人砲塔を採用して乗員全員が車体に搭乗し、アクティブ防御システムの搭載が予定されていた点が共通する。2015年に登場した、T-95の開発資産が生かされた(とされる)T-14もやはり無人砲塔であったが、ディスプレイに映し出された画像だけで本当に戦車長が外部の状況を把握し切れるのかなど、実戦に投入されなければわからない未知数な部分もある。またMCSはMGV(Manned Ground Vehicles,有人地上車輌)、T-14はアルマータ共通戦闘プラットフォームという基本的に同じ構造の車体で戦車・兵員輸送車・自走砲を製作しようというプロジェクトのもと製作された戦車であった。
-
MCS(2006年度版予想図)
-
T-95(想像図)。
-
XM1201 RSV(偵察車型)
-
T-15歩兵戦闘車

- 主砲
- 火力の強化については、ドイツのラインメタル社などが140 mm 砲を開発しており、「第4世代主力戦車」の主武装になると期待している。ただし140 mm 級の砲を純粋に搭載すると、反動を抑えるのに必要な重量は70トンから80トンに達すると想像され、現在の技術で取り扱える重量限界を超えてしまう。その為、ラインメタル社では反動低減のための研究が進行中である。
- 砲弾の大きさ及び重量も同時に増加することで、砲への装填や戦車への搭載が人力で行なうには戦車兵に対して過度の負担になると考えられる。前者については自動装填装置の採用で解決できると思われるが、後者は砲側給弾車といった新たな機械的搭載装置の必要性が検討される。更に、砲弾の大型化で携行弾数が少なくなる可能性があり、これを解決するためには砲弾そのものを改良する必要があると考えられる。
- 既にドイツではレオパルト2の強化案として同140 mm 砲の搭載テストを行ったが採用は見送られ、現在は120 mm 径のままで砲身長の延長や弾薬の改良などによる火力強化を図っており、他国もこれに追従する動きを見せている。なお10式戦車では、主砲の反動を計算して圧力を調整し反動を吸収するアクティブ・サスペンションの導入により44トンの車体に120 mm 砲の搭載を実現しており、今後同様の手法で重量を抑えつつ140 mm 級主砲を搭載した車輌が出現する可能性も考えられる。
- 主砲の新技術として液体装薬も期待されたが、実用化にはまだ遠い[出典 1]。また、リニアモーターの原理で弾体を磁気の力で加速して打ち出す静電砲(リニアガン/コイルガン)や、ローレンツ力を利用した電磁投射砲(レールガン)も、まだ実験の域を出ていない。
- 防護
-
- 電磁装甲も、未来技術であり実用化の目処はたっていない。
- アクティブ防護システム
- 装甲の強化に代わる新しいタイプの防御方法も模索されている。そのひとつに、対戦車ミサイルなどの接近をレーダーやセンサー類で探知し、自動的にジャミングで無力化したり飛翔体やミサイルで迎撃するアクティブ防護システム(Active Protection System:APS)がある。ソ連・ロシアは既に1980年代に一部で導入しており、最近ではイスラエルのラファエル社の開発したトロフィーAPSのメルカバMk.4への採用が公表され、欧米でも同種のシステムの開発・採用を進めている。一方で、探知用のレーダー波で自らの位置を暴露してしまうことや地上は空中や海上に比べて干渉要素が多くレーダー探知が有効に機能しにくいこと、ミサイルを迎撃するための反撃に、戦車付近に展開している随伴する歩兵を巻き込む恐れがあることなどから、複合装甲など十分な受動防御の技術をもつ国々はアクティブ防護の導入に熱心でない。
- 重量
- 現在の西側各国の主力戦車の重量は55-65トン程度ある。重量は装甲や防護力に直結している一方で自走可能な航続移動距離や速度、燃費などとトレードオフの関係にある。これ以上の重量増加は戦車の行動力を著しく損なう上、貨車やトランスポーターによる輸送、橋梁など架空構築物上の移動における重量制限、あるいは被害・故障車輌の回収などの点で困難になってしまう。
- 陸上自衛隊の90式戦車は50トンだが、長距離輸送を考えた場合、大型のタンクトランスポーター(戦車輸送車輌)や大型RO-RO船が不足しており、北海道以外での平時における運用が難しいとされている。
- 対抗兵器
- 対戦車ヘリコプターの出現や対戦車ミサイルが猛威をふるったことにより、一時は「戦車不要論」も唱えられていたが、湾岸戦争・イラク戦争は戦車が依然として陸上戦の主役であることを見せつけた。ヘリは機動性と攻撃力は優れているため攻撃的運用には適しても、飛行時間に制限があり装甲も脆弱で飛行安定性も悪く直撃でなくても近接での爆発による圧力で墜落する可能性も高いので、敵の攻撃を受けてもなお留まる防御/制圧的な運用には適していないという偏った能力を備えるためである。戦車は攻守両面でバランスが良いとしてその有用性が認められ、「戦車不要論」は勢いを失っている。
- 情報の即時共有化
- 複数の戦闘車両や戦闘用航空機、艦船や兵員1人1人までもが情報技術の利用によって互いの情報を共有し、戦闘現場での状況が実時間で上級司令部にまで届き、逆に上級司令部の命令が遅れることなく戦闘現場まで届けられ、戦闘現場内においても相互の情報連結によって意思疎通が行なえるようにする。こういった情報共有の能力を持った戦闘部隊はその戦闘力を何倍にも高められるという考え方がある。戦車でいえば、攻撃力より機動性を優先して、複数の戦闘車両を互いに連携させる事で、敵部隊に対してより柔軟に対応できるとするものである。
- ロボット化
- 陸上兵器のロボット化は、航空兵器などに比べて技術的ハードルが大きく、本格的な実用化はまだ先の話である。
- 遠隔操作
- 遠隔操作であれば無人偵察機や無人攻撃機が実戦に投入されたように、遠隔操作の無人戦車も研究されている。現在取り入れられているものは戦車と言うより治安維持用の装置と言うほうが正確だが、即席爆発装置 (IED) の除去や無力化に、遠隔操作される小型ロボットが一部で使われている。
- アメリカ軍では現在Armed Robotic Vehicle (ARV) として、試作車両の製作と実験にまでこぎつけている[52]。アメリカ以外の国での開発は不明だが、中国やロシアが開発しているとの噂はある。
- 低強度紛争への対応
- 近年、戦車に新たに求められているのが、低強度紛争(Low Intensity Conflict:LIC)への対応能力である。テロリストやゲリラの対戦車兵器に対する防御と、それを駆逐制圧する火器システムを備えた騎兵車輌としての能力も同時に求められており、この事がさらに開発を困難な物にしている。逆に、冷戦終結により戦車同士が撃ち合う従来の戦車戦の機会自体が失われつつあり、こうした時勢を反映して、今後の陸軍戦力の整備のあり方として、戦車と歩兵戦闘車や装甲車にヘリコプターなどを密接に統合運用する、近代的な諸兵科連合戦術に対応した戦車が求められている。
日本の戦車
[編集]
第一次世界大戦の後、他の列強諸国同様、日本もまた登場した新兵器・戦車に注目しており、1915年(大正4年)には輜重兵第一大隊内に軍用自動車試験班が設立され、1918年(大正7年)には欧州に滞在していた水谷吉蔵輜重兵大尉によってイギリスからMk.IV 雌型 戦車が1輌輸入された。1919年(大正8年)には新兵器の発達に対処するために、陸軍科学研究所が創設された。以降1919年(大正8年)から1920年(大正9年)にかけて、日本陸軍はルノー FT-17 軽戦車とマーク A ホイペット中戦車を試験的に購入して、研究している。当初は「戦車」と言う言葉が無く、「タンク」や「装甲車」と呼んでいたが、1922年(大正11年)頃に「戦う自動車から戦車と名付けては」と決まったようである。1923 - 24年(大正12 - 13年)頃には戦車無用論も議論されたが、1925年(大正14年)の宇垣軍縮による人員削減の代わりに、2個戦車隊が創設された。陸軍では当時(大正後期)の日本の不況経済や工業力では戦車の国産化は困難と考えられ、ルノーFTの大量調達が計画されていたが、陸軍技術本部所属で後に「日本戦車の父」とも呼ばれた原乙未生大尉(後に中将)が国産化を強く主張、輸入計画は中止され国産戦車開発が開始される事となった。

原を中心とする開発スタッフにより、独自のシーソーバネ式サスペンションやディーゼルエンジン採用など独創性・先見性に富んだ技術開発が行われ、それらは民間にもフィードバックされて日本の自動車製造などの工業力発展にも寄与している。こうして1927年に完成した試製1号戦車を経て、八九式中戦車、九五式軽戦車 、九七式中戦車などの車輌が生産された。しかし、自動車産業の発展に出遅れていた当時の日本では、技術的な問題から後継車両の開発が遅延を重ねたため、太平洋戦争において日本戦車はアメリカ軍戦車との対戦車戦闘で一方的にほふられる結果となった。幸いにも本土決戦用に温存されていた車輌と共に、原中将はじめ開発・運用要員の多くは終戦まで生き延び、戦後の戦車開発にも寄与する事となった。
戦後、共産主義勢力の台頭と朝鮮戦争の勃発により日本に自衛力の必要性が認められて警察予備隊(後の自衛隊)が組織され、アメリカより「特車」としてM4中戦車などが供給された。また朝鮮戦争中に破損した車輌の改修整備を請け負った事などで、新戦車開発・運用のためのノウハウが蓄積されていった。戦後初の国産戦車となった61式戦車は、当時の工業生産技術の限界もあり他国の水準からはやや遅れていたが、続く74式戦車、90式戦車は、世界最高水準に到達した主力戦車であった[出典 2]。

2000年代に開発された10式戦車は、全国的な配備を考慮して90式戦車よりも小型軽量化しつつ同等以上の性能を有しているとされ、特に射撃機能やネットワーク機能などべトロニクスの進歩による戦闘能力の向上が著しい。10式戦車は耐用期限到達に伴い減耗する74式戦車の代替更新として2010年度から調達が開始された。一方、2013年に25大綱と26中期防が閣議決定されたことで、今後、本州配備の戦車は廃止され、戦車は北海道と九州にのみ集約配備、本州には戦車とは異なる新たなタイプの車両の機動戦闘車のみが配備される。機動戦闘車は装輪車のため10式戦車と比して火力と防護力だけでなく戦術機動性に劣るが、逆に戦略機動性は優れており、路上を高速で自走することにより74式戦車と同等の火力を素早く展開できる。本州配備の74式戦車が担っていた役割の一つ、普通科部隊への射撃支援については、機動戦闘車が引き継ぐことになる。
2015年4月現在、防衛省では有人戦闘車両の無人砲塔化と、有人戦闘車両と無人戦闘車両の連携に関するべトロニクスシステムの技術研究が行われている。この研究は2020年度まで行われる。
74式戦車には74式戦車(G)という近代化バージョンもあり、パッシブ式暗視装置や履帯脱落防止装置の搭載を行っているが、予算の関係により4輌が改良されたにとどまっている。
90式戦車は第3世代主力戦車に相当し、120mm滑腔砲・複合装甲の搭載はもちろん、世界初の赤外線追尾装置の搭載により目標の「ロックオン」が可能になるなど諸外国の主力戦車と比べても遜色ない性能を有していた。アメリカ陸軍機甲科発行の季刊紙、「ARMOR」(1999年夏号)による戦車ランキングで90式戦車が10位中3位に挙げられたこともある(1位レオパルト2A6、2位M1A2、4位ルクレール、5位チャレンジャー2)[53]。 しかし90式戦車は車重が50tに達し(これでも第3世代MBTとしては軽い)、輸送には90式戦車専用のトレーラー(特大型運搬車)に積むか、砲塔と車体を分離して2台の73式特大型セミトレーラにそれぞれ搭載する必要があるなど、日本において運用するには限界があった。さらに第2戦車連隊の所属車輌が搭載している戦車連隊指揮統制システム(T-ReCs)を除けば、諸外国の第3世代のように本格的な車輌間データリンクシステムを搭載できるだけの構造的余裕はなかった。
旧式化が目立ち始めた74式戦車の後継として、なおかつ90式戦車の性能をさらに引き上げた戦車として開発されたのが10式戦車である。攻撃力・防御力・機動性において90式戦車の性能を全体的に引き上げ、車輌間データリンクシステムを搭載し、それで重量44tでつらつら。74式戦車用のトレーラに積むことが可能となった。
今後は装輪戦車である機動戦闘車ともども
-
ホイベットMk.A。
-
89式中戦車。
-
61式戦車。
-
74式戦車。
-
90式戦車。
構造
[編集]- 戦車の構造
|
|

4: 発煙弾発射機 5: 砲塔 6: エンジン 7: キューポラ
8: 同軸機銃 9: 車体 10: 操縦席
大半の戦車は大まかにエンジンや履帯を搭載した車体(Hull)の上に火砲をはじめとする武装を搭載した砲塔(Turret)を乗せるという構造をしている。車体のうち、履帯がある部分をとくに「足回り」と呼ぶこともある。
戦車の性能は「攻撃力」「防御力」「機動力」の三点から評価されることが多いが、このほか視察装置や無線機、電子装置も戦車の性能を左右する要素のひとつである。 もし仮にこれらの条件がすべて満足いくレベルであっても、機械的信頼性が低かったり居住性が悪ければ「戦争の道具」として役に立たず、コストが高ければ調達ができない。
-
車体
-
足回り・サスペンション
-
砲塔
-
主砲
砲塔の構造
[編集]
砲塔の旋回方式には手動式、電動式、油圧式が存在する。第四次中東戦争時、イスラエル軍が装備したマガフ3/6A(M48/M60)は油圧式であったが、被弾時にオイルが引火して二次火災が多発した(マガフ(מגח)は「焼死体運搬車」(מוביל גופות חרוכות)(モビル・グフォット・チャルコット) の略だというジョークが生まれた)。
砲塔のサイズが大きくなれば前面投影面積(正面から見た面積)が増えて被弾しやすくなるが、砲塔サイズを小さくし過ぎると主砲の俯角が取れなくなる。
- 第一次世界大戦で登場した極初期の戦車は、車体に火砲を直接搭載したり車体左右の張り出しに搭載していたが、第一次世界大戦末期にフランスで開発されたルノーFT戦車が、車体上部に360度旋回する砲塔を世界で最初に搭載した。死角を減らしたこの設計思想を持つ同戦車は、それ以降のほとんどの近代戦車の原型となった。
- 第二次世界大戦に入るまでは複数の砲塔を持つ多砲塔戦車もあったが、非効率性や高コストが明らかとなり、360度旋回可能な砲塔1基を持つものが主流となった。砲塔前部には主砲が装備され、後部は弾薬庫として使用されることも多い。砲塔内には車長、砲撃手、装填手の座席があることが多い。第二次世界大戦前半までは全てを車長一人が行うものや二人で行うものも存在したが、車長が戦闘指揮に専念できる三人用砲搭が一般化した。
- 車体同様リベット留めの問題があり、現在では溶接式か鋳造式が用いられている。
- 戦車の中で最も被弾率の高い部位であり、なるべく形状を低く抑える事が望ましいが、T-62ではそのために主砲の俯角がほとんど取れず、中東戦争では地形を利用した伏せ撃ち射撃ができず却って撃破されてしまった事例がある。
- 無人砲塔
| 画像外部リンク | |
|---|---|
|
military-today.com | |
|
defence.pk | |
|
defence.pk |
防護性能の向上では、被弾する可能性が最も高い砲塔の露暴面積を縮小する努力が払われている。これまでも、主砲の操作に関わる乗員を車体側の固定座席に座らせることで砲塔を小さくした無人砲塔戦車や、自動装填・遠隔操作の頭上砲 (Overhead Gun) をほとんど無装甲で搭載した無砲塔戦車が構想された。こういった設計も、米国が開発中のMCSやロシアが開発中と言われるT-95など以前から情報は伝わってくるが実用化には至っていない模様である。
全面投影面積が減って被弾しにくくなる、乗員が 自動装填装置が故障した際どうするのか、[54]
- 主砲を操作する乗員を砲塔リングより下の砲塔バスケット内に配置して砲塔を小型化する低姿勢砲塔(Low Profile Turret:LPT)については、ヨルダン陸軍の主力戦車「アルフセイン」(輸出されたチャレンジャー1)の最新改良型に、南アフリカの企業と共同開発した「ファルコン2」砲塔を搭載した事が発表され、今後の運用が注目されているほか、装甲車ではM1128ストライカーMGSで先んじて実用化されている。即応弾の搭載場所は、ファルコン2が主砲の後方、MGSは砲塔バスケット内である。
- 揺動式砲塔

- AMX-13(フランス)、および派生形のSK105キュラシェーア(オーストリア)は揺動式砲塔という特殊な構造の砲塔を採用している。揺動式砲塔は砲塔が上部と後部に分かれ、下部砲塔が左右に、上部砲塔が上下にそれぞれ旋回する。威力の大きい火砲が装備でき、自動装填装置が採用しやすいという利点もあるが、上部、下部砲塔の隙間が大きくNBC防護や潜水渡渉に支障ができるうえ、被弾にも弱く、揺動式砲塔を採用した戦車はAMX-13とAMX-50等のフランス戦車とAMX-13の派生形以外には、アメリカがT54E1などの試作重戦車に採用した程度である[55]。
車体の構造
[編集]- 強固な装甲で守られている。初期の戦車においては当時の溶接技術が低かったため、装甲板がリベット留めされた車体が大半であった。しかし、被弾時に千切れたリベットが車内を跳ね回り、乗員が死傷する事故が相次いだ。また、近くでの爆発による衝撃波にももろく、装甲板がバラバラになることもあった。第二次大戦前のフランス戦車には分割された溶接車体をボルトで接合したものもあったが、貫通しなくても被弾の衝撃でボルトが折損し装甲が脱落することがあった。そのため点ではなく線で接合される溶接式か一体鋳造式、または鋳造部品の溶接接合で製造されるようになった。
- 第3世代主力戦車においては、複数の装甲材をサンドウィッチ状に重ね、防御力の向上を狙った複合装甲が主流である。これは車体や砲塔の前面等の主要部に用いられるが重量があり、1990年代以降の主力戦車の総重量は50-70トン程度であることが多く、これに対して1,000-1,500馬力級のエンジンで機動性を確保している。
(:車体前部にあり、普通の自動車同様、アクセル・ブレーキ・クラッチで操縦する。運転は中心から伸びた左右のレバーを前後に操作する古い方式(乾式クラッチ式からシンクロメッシュ方式まで様々)と、自動車やバイクのようなハンドルを用いるオートマチック式がある。速度が遅いので停止の際はアクセルを緩めれば、キャタピラと地面の摩擦によってすぐに止まるという。戦闘中の視界は、かつては小さな覗視孔付きの小窓から直接覗くしかなかったが、その後ペリスコープや最近ではカメラによる間接視認法が用いられている。 )
攻撃力に関する構造
[編集]主砲
[編集]
| 画像外部リンク | |
|---|---|
|
(主砲反動の試験用) deuxiemeguerremondia.forumactif.com |

戦車は普通、口径20mm以上の火砲を一門しか搭載しない。マークIといった初期の戦車や多砲塔戦車のみならず、冷戦期でさえVT-1という火砲を複数搭載した試作戦車が存在した。だが多砲塔戦車は多数の砲塔を乗せた結果重装甲でないのにもかかわらず車重が増加し、結果として防御力・機動性はきわめて低かった。さらに旋回範囲の関係などからすべての火砲を効率的に使用できるわけではなかった[57]。VT-1は高度なFCSにより行進間射撃も可能であったが、主砲が固定されているという構造ゆえに蛇行機動を行いつつ、主砲を敵戦車に向けるという複雑な運用方法を取らなくてはならなかったことが不採用の大きな原因となった[58]。結局のところ、砲塔を複数積むのは火力増大というメリットよりも、特殊な構造を原因とした運用性の悪化というデメリットの方が大きいのである。
さて戦車が主に使用する火砲、すなわち主砲は(回転砲塔に搭載された火砲で)20mm~125mmまでの
砲身には主砲身の熱による歪みを防ぐサーマルジャケット(サーマルスリーブ、遮熱カバー)の装着が見られる。戦車砲弾は発砲時に煙と一酸化炭素などの有毒ガスが発生するため、排莢時に砲身から戦闘室内へこの発射ガスが逆流しないようエバキュエータ(排煙器)と呼ばれる空洞部が砲身に取り付けられている。
砲身の先端には以前の戦車なら反動抑制用のマズルブレーキ、現代の戦車なら砲身のゆがみを測定する~が付いている。
マズルブレーキからのガスとそれによって生じる土煙が視界を遮るのが嫌われ、駐退複座機の性能も向上したため[59]、現代の戦車の多くはマズルブレーキ未装備である。さらにAPDSやAPFSDS(後述)の装弾筒が引っかかるというのもマズルブレーキ未装備の原因のひとつとされているが、17ポンド砲のSVDS(=APDS)や105mm BK MECA (F2)(AMX-10RC偵察戦闘車が装備)用F3 APFSDS[60]、ブッシュマスター30mm機関砲用のAPFSDS[61]など、マズルブレーキ付の火砲から撃てるAPDS、APFSDSは存在する。
主砲には砲身内部の違いにより、内部に施条(ライフリング)のあるライフル砲と施条が無い滑腔砲(かっこうほう[注釈 10]、smoothbore rifle)に大別できる。ライフル砲は施条により砲弾を回転させることで弾道の安定を得るが、滑腔砲はそれができないので発射する砲弾に安定翼を付ける必要がある。しかも風の影響を受けやすく、射距離2,000mを越えると命中率が急激に下がる。
チャレンジャー1/2やアージュンを除き、第3/3.5世代主力戦車は滑腔砲を搭載している[注釈 11]。
-
マズルブレーキ
(写真は17ポンド砲) -
105mmライフル砲 L7 L/51の砲身
-
120mm M256 L/44の
エバキュエーター
(落書きがしてある) -
120mm滑腔砲 Rh120 L/44の砲身内部
-
サーマルスリーブ
(写真は120mm L11A5)
砲弾
[編集]
運動エネルギー弾
[編集]- 運動エネルギー弾 (Kinetic energy penetrator,KEP) ≒ 徹甲弾 (Armor Piercing,AP)
- 砲弾のもつ運動エネルギーで装甲を貫徹する。運動エネルギー弾は貫徹後、車内を跳ねまわることで内部を破壊し、乗員を殺傷する。[62]貫徹力は目標までの距離が遠くなるにつれて(速度が落ちるため)低下する。なお、弾頭に炸薬を仕込んで遅延信管により貫徹後に爆発するようにした(貫徹力は通常の徹甲弾より若干劣る[63])徹甲弾は徹甲榴弾(AP-HE、ドイツ語: Panzergranate,Pzgr)と呼ばれ、弾頭の底部に曳光剤を詰めて弾道が見えるようにしてある砲弾はとくにAP-T(TはTracerの略)等と呼ばれる[64]。ひとくちに徹甲弾といっても、以下のようなものがある。
-
徹甲弾。
-
徹甲榴弾。赤いものが炸薬。
- 被帽付徹甲弾 (Armor Piercing capped,APC) / 尖頭被帽付徹甲弾 (Armor Piercing Capped Ballistic Capped,APCBC)
- ただの鋼鉄製の塊であった初期の徹甲弾は装甲に命中した際、先端に運動エネルギーが集中することで弾頭が潰れて最終的に滑り、貫徹しないことがあった。砲弾の先端を鋭角にせず、鈍角にすれば弾頭が潰れることはないが、そのままでは空気抵抗で速度が落ち、運動エネルギーが失われる。[65]そこで弾頭の先端に軟鉄製のキャップを付け、運動エネルギーを弾頭の肩部に分散させるとともに弾頭が滑るのを止めるようにしたのが被帽付徹甲弾(APC)であり、さらに被帽付徹甲弾の先端に中空のキャップを取りつけて空気抵抗を減らしたのが尖頭被帽付徹甲弾(APCBC)である[64]。
-
被帽付徹甲弾
-
尖頭被帽付徹甲弾
- 高速徹甲弾 (High Velocity Armor Piercing,HVAP) / 徹甲尖弾 (Armor Piercing Composite Rigid,APCR)
- 装弾筒付徹甲弾 (Armor Piercing Discarding Sabot,APDS) / 装弾筒付翼安定徹甲弾 (Armor Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot,APFSDS)
- どちらも基本的には、「細長い」(120mm砲用M829A1で22mm[66])貫徹体(侵徹体とも、Penetrator)を装弾筒(Sabot、フランス語で「木靴」の意)で包むという弾頭構造をしている。発射後、砲身のなかでは貫徹体と装弾筒は一緒にいるが、砲身を飛び出すと空気抵抗の差により装弾筒が離れ、貫徹体だけが目標に向かっていく。発射時に貫徹体と装弾筒とで得た弾頭の運動エネルギーを、軽く、空気抵抗の小さい貫徹体だけで持っていくのである。ライフル砲用が装弾筒付徹甲弾(APDS)でだが、APDSは貫徹体をむやみに細長くして威力を上げることができなかったので(後述)、滑腔砲[注釈 12]で発射するために貫徹体へ安定フィンをつけたのが装弾筒付翼安定徹甲弾(APFSDS)。
- 貫徹体には多くの場合、タングステン合金が使われるが、アメリカ軍は湾岸戦争以来、原子炉の燃料棒の生産時に出たウラン238(劣化ウラン)とモリブデン、チタンの合金[68]を貫徹体に使用している(劣化ウラン(DU)弾)。タングステン合金製の120mm用D23が密度17.1g/cm³とされるのに対し、劣化ウラン弾は密度が18.6g/cm³[69]と鉄の2.5倍、鉛の1.7倍の比重[70]をもっており、タングステン合金の貫徹体より1~2割高い貫徹力をもつ[68]。さらに装甲貫徹後、摩擦熱により貫徹体や粉末状に飛散した劣化ウランが発火するという徹甲榴弾のような効果もある。しかし一方で、劣化ウラン弾の粉末を吸い込んだ場合、健康被害が出る可能性もあり、劣化ウラン弾がいわゆる「湾岸戦争症候群」や「バルカン症候群」の原因のひとつであるとされている[70]。また世界保健機関(WHO)の報告によれば、「体内に入った劣化ウランの95%は排泄され、体内に入った場合も67%が24時間以内に腎臓でろ過され、尿として排泄される」とされる[70][71][72]が、劣化ウラン弾の人体に及ぼす影響の詳細は不明である。
- APDS、APFSDSの性能は「細長さ」、厳密には貫徹体の長さ(Length)を口径(Diameter)で割ったL/D比で決まるといえる。理論上、同じ運動エネルギーを持った砲弾はその口径が小さいほど装甲の抵抗が低くなり貫徹力が増大するためである[73]。APDSでは貫徹体の安定を保つ(あまりL/D比が大きいと歳差運動を起こす可能性がある)ためにL/D比5~6程にしかできず、初期のAPFSDSでもL/D比8程度にすぎなかったが、L/D比は次第に大きくなっていき現在ではL/D比30(劣化ウラン弾)のものもある。しかしL/D比30を越える貫徹体を作るのは劣化ウランを使用しても難しく、口径を小さくしすぎると貫徹中に貫徹体が折れたり[74]、貫徹後も破壊力が不足するという点もある[75]。
-
貫徹体と装弾筒が分離した瞬間。
化学エネルギー弾
[編集]- 化学エネルギー弾 (Chemical energy penetrator,CEP)
- 化学エネルギー弾(後述)の金属ジェットが小さな穴を開けたり、金属片が軽くはじけさせたりするだけで終わってしまうことがあるの比べ、撃破の確実性は運動エネルギー弾が上である。
- 成形炸薬弾 (Shaped Charge)あるいは対戦車榴弾 (High Explosive Anti Tank,HEAT)


| 画像外部リンク | |
|---|---|
|
tankandafvnews.com |
(ジェット噴流が装甲を貫徹するのであって、「高熱のジェット噴流で装甲を溶かす」わけではない)
これに対してフランスはAMX-30(M51スーパーシャーマンにも搭載)の105mmライフル砲 CN-105-F1用にG弾(Obus G,「G」は「ゲスナー」の略だが、何を指すかは詳細不明[76])という特殊なHEATを開発した。G弾は弾殻の外側がボールベアリングになっており、発射時に外側だけが回転することで貫徹力の低下を抑えるのを狙ったのである。しかし弾頭部分が小さくなったために貫徹力が通常のHEATに比べて劣り[注釈 13]、AMX-30にはG弾しか搭載しないとしたフランス軍もAMX-30用APFSDS(OFL-105-F1)の開発に追われることとなった。
対戦車擲弾発射機や対戦車ミサイルが使用するHEAT弾のなかにはRPG-7対戦車擲弾発射機用のPG-7VRなど、弾頭を二重(タンデム弾頭)にして爆発反応装甲の無効化を図ったものがある。戦車砲弾にもタンデム弾頭は存在し、ロシアの125mm滑腔砲用3BK29は三重の弾頭をもつ(爆発反応装甲を三重に施した戦車も存在するが、爆発反応装甲の効果が相殺し合うためそれほど効果はないとされる[80])
- 粘着榴弾 (High Explosive Squash Head,HESH もしくは High Explosive Plastic,HEP)


- 「ホプキンソン効果」(鋼板や岩石などに爆薬を密着させて爆破した際、その裏面が剥離する現象)を利用した砲弾。可塑性の炸薬をプラスチックで覆っており、弾頭底部に信管がある。戦車の装甲板に命中した時、弾頭が潰れて装甲板に張り付き、のちに信管によって起爆する。こうすることで戦車内部の装甲板が剥離し、車内の人員・装備に損傷を与える。一応「榴弾」なので非装甲目標にも効果があるが、HESHは概して弾速が遅く、弾道が低伸しないので命中精度が悪い[81][82]。(さらに威力もさほどではない)[注釈 14]。HESHを搭載する戦車は74式戦車(D)をはじめとする105mm L7を搭載した戦車と、チーフテン・チャレンジャー1/2・アージュンといった120mmライフル砲を搭載する[注釈 15]戦車程度であるが、近年はコンクリート製陣地などに対する「バンカーバスター」としての役割が再評価され、ストライカーMGSや機動戦闘車にHESHが搭載されている。
その他
[編集]- 榴弾 (High-explosive,HE)
- 西側ではHEAT-MPが榴弾に取って代わっているが、アメリカ軍はXM1069 LOS-MP(Line-of-Sight Multi-Purpose)という砲弾を開発している。XM1069は実質的には高性能信管を搭載した榴弾で[85]、アメリカ陸軍がM1戦車に装備する成形炸薬弾、キャニスター弾の機能を一つにまとめ、これらを代替する砲弾として期待されているが、2011年の地点で開発中である[86](2016年現在で制式化されたのかは不明)。
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
YouTube |
- (榴)散弾
- ショットガンのごとくくどくど。散弾のもつ子弾はただの鉄球なので、(子弾も爆発する)クラスター爆弾とは別物であることに注意が必要である。
- 対戦車ミサイル・誘導砲弾
- 一方で西側は戦車へミサイルを搭載した例は少ない。アメリカのシェリダン空挺戦車やM60A2、MBT-70の装備した152mmガンランチャーはHEAT弾のほかにシレイラ対戦車ミサイル…
もっとも、メルカバやアージュンで採用されているイスラエル開発のLAHAT対戦車ミサイルは大きな改修無しにラインメタル社製120mm砲から発射できるとされる。
XM943 STAFF(小型目標用撃ちっ放し式(砲弾)(Smart Target-Activated Fire and Forget)の略)という誘導砲弾を試作していたが、予算不足等により2000年に開発中止となったこれみろ。
-
SS.11(青いもの)対戦車ミサイルを搭載したAMX-13
-
MGM-51シレイラMBT-70
副武装(機関銃・機関砲)
[編集]
戦車は主砲のほかに、
- 同軸機銃

と呼ばれる機関銃を主砲とペアで砲塔に搭載していることが多い。歩兵や軽装甲車両といった目標には主砲より使い勝手がいいのである。機関銃は多くの場合7.62~7.92mmクラスのものが使われる(ルクレールは12.7mm)。
- 車体機関銃
- 第二次世界大戦期までの戦車の多くは車体前面にも機銃(車体機銃)を搭載していたが、大して効果がない上に被弾時に弱点になりやすく、
- 対空機関銃
(:主砲の横にあって同じ方向を向くように装備された機関銃であり、歩兵や軽装甲車輌といったソフトターゲットに対して使用することで主砲砲弾の消費を抑えるよう計られた。主砲発射に先んじて同軸機銃を射撃し、その着弾を見て照準を微調整する、スポッティングライフルとして利用されていた戦車もあった。)
-
MBT-70に搭載された20mm機関砲
-
主砲上部に12.7mm M2機関銃を取りつけたメルカバMk.III Baz。
- その他
-
チーフテンのスポッティングライフル(かなり見づらいが主砲の真上にある)
照準器・射撃管制装置(FCS)
[編集]| 画像外部リンク | |
|---|---|
|
英語版ウィキペディア |


射撃管制装置(射撃統制装置、射撃指揮装置とも)
自動装填装置
[編集]| 画像外部リンク | |
|---|---|
|
www.fprado.com |
砲弾・ミサイルを自動で主砲に装填する装置。戦車砲用の自動装填装置は第二次世界大戦頃から試作例が存在したが、実用的な自動装填装置を搭載した戦車が現れたのは戦後で、ロシアではT-64以来T-14に至るまですべての戦車に、西側もAMX-13(ただし手動で操作する)やルクレール、90/10式戦車、またStrv.103に搭載されている。
装填手に装填を行わせた場合、砲弾を1発装填するのに練度によって5~10秒と左右されるのに対し、自動装填装置では(カタログデータとはいえ)T-72で8発/分(1発につき7.5秒、ただし~)、ルクレールで15発/分(1発につき4秒)と比較的高い発射レートを維持できる。
だが、自動装填装置は、乗員を死傷させ「人喰い装置」などと酷評されたソ連の初期のものはともかく信頼性が大幅に上昇した現在のものでも、人間である装填手と同様に確実に砲弾を装填してくれるという絶対の信頼がおけるわけではない[注釈 16]。また、乗員が1名減ることで整備や周辺警戒にも悪影響が出ると指摘されている。もっとも自動装填装置を導入するメリットとデメリット、どちらに重点を置くかは各国の用兵思想しだいなので一概には言えず、「戦場で戦車が生き残るには最低4人必要」(メルカバを開発したイスラエル・タル少将の言)とするイスラエルもメルカバMk.IVに自動装填装置こそ載せていないものの、「半自動装填装置」と呼ぶべき装填手用補助システムを搭載している(ドイツでも同様の装置が研究されたことがある[88])。また将来の140mm砲は人力での装填がほぼ不可能なので自動装填装置の搭載を前提としている[89]。
自動装填装置、あるいは装填手を乗せるそれぞれの利点をまとめれば、次のようになる[89]。
- 装填手を乗せる利点
-
- 熟練した装填手なら最初の数発くらいは自動装填装置より早く装填できる
防御力に関する構造
[編集]装甲
[編集]ドイツ語で戦車を「Panzer」(直訳で「装甲」)と言ったり、日本語でも戦車部隊のことを「機甲」(「機械化装甲」の略という説がある)というように、装甲は戦車の本質のひとつであるといえる[90]。戦車が砲塔や車体に施す装甲は、おおむね火砲や機関銃弾の直撃、榴弾の破片に耐えられるようになっている。 装甲がどれだけの砲弾に耐えられるかは、極端にいえば装甲板の厚さ(複合装甲では、どれだけの装甲板の厚さに相当するか)で決まる。しかし戦車のどの部分にも同じ厚さの装甲を施したのでは、車重が増加して運用性が悪化する。そこで多くの戦車は、次のようにして装甲厚をを変えている。
- 前面
- 戦車の部位のなかでもっとも敵弾が当たる可能性が高い[注釈 17]のは砲塔前面、次いで車体前面である。現代の戦車なら、複合装甲となる。
- 側面
- 砲塔側面の前半分は敵弾のあたる可能性がやや高いが、前面ほどではない。
- 後面
- 薄い!そもそも後部の装甲を厚くするとエンジン。
- 上面
- 前面等に比べれば極めて薄い。戦車が航空機や対戦車ミサイルのトップアタックに対して脆弱な理由でもある。現用の戦車でさえ、30mmクラスの機関砲弾は前面なら貫徹されることはないが、対地攻撃機などにより上面から射撃された場合、貫徹される可能性が高いのである。西側の第3世代主力戦車では、ブローオフパネル(後述)のために砲塔上面の後部の装甲ををわざと薄くしてある。
- 底面
(M1エイブラムスやC1アリエテの前面装甲板が傾斜しているのは空間装甲のスペースを稼ぐため)。
-
避弾経始の考慮されていない直立状の構造をしたIV号戦車。
-
傾斜装甲を施したパンター戦車。
-
お椀状の砲塔をもつT-62戦車。
-
複合装甲の開発により、直立状の構造にもどったレオパルト2戦車。
-
モジュラー式中空装甲を採用した10式戦車。
ただ装甲を厚くするだけが装甲のレベルを向上させる手段ではない。装甲の配置や材質を変えることで装甲を厚くするのと同等の効果が得られることもある。

- 中空装甲
-
レオパルト1A5。鋳造砲塔から一転、中空装甲を砲塔前面・側面に装備した
- 爆発反応装甲

ただし、随伴歩兵に危険が及ぶなどの
-
M60A1「マガフ6B」。

アクティブ防護システム
[編集]
1. 防御弾格納筒 2. レーダー 3. 防御弾の破裂 4. 飛来する対戦車誘導ミサイル 5. 探知波
図では1方向にのみ防御弾の破片が描かれているが、実際には周囲へも飛散するため歩兵を随伴させた場合は危険が伴う。

発煙弾発射機
[編集]
煙幕を展開し、敵の視界(可視光線)を遮る装置。発煙弾そのものは白リン弾(黄リン弾)が広く使われていたが、現在は赤外線も遮蔽可能な赤リン発煙弾に置き換えが進んでいる。90/10式戦車や「シュトーラ」アクティブ防護システムではレーザー検知器と連動して測遠・照準用レーザの照射を受けた際、自動で煙幕が発射されるようになっている。
(多くの戦車で見られ、防御戦闘時に、随伴歩兵の進撃を支援したり、ミサイル防御に用いられたりと用途は様々である。一部の車輌には、エンジン排気に燃料を吹き付けて煙幕を発生させる機構を装備する物もある。詳細は発煙弾発射機を参照。)
-
10式戦車ではステルス性向上のため、くどくど。
-
発煙弾が展張した瞬間。
-
T-62

レイアウト
[編集]

気密性
[編集]
その結果
低視認・ステルス性
[編集]



機動性に関する構造
[編集]
エンジン
[編集]使用する燃料によって次の3つに分類できる(Strv.103やルクレールなど、2つのエンジンを併用していることもある)。
冷却方式によって次の2つに分類できる。
機関方式によって次の2つに分類できる。
- エンジン部は給排気と放熱のために装甲によって閉鎖されるのには向かないために脆弱となり、通常は被弾による損傷を防ぐために車体後部に収められる。現在では多くの戦車がターボチャージャーの付いたディーゼルエンジンを搭載しと:ディーゼルエンジンはガソリンエンジンより油種を選ばず、軽油以外でも灯油やジェット燃料などが使用できて運用が楽である。ディーゼル燃料である軽油はガソリンに比べると発 火点や引火点が高いので比較的安全であるが、絶対に引火しない訳ではない。加速性に優れるガスタービンエンジン装備の戦車もあるが、燃費が非常に悪い上に技術的ハードルも高い[96]。
- 西側の戦車の多くは、現場でエンジンデッキを開放してエンジンや変速機を迅速交換できるパワーパック構造になっているが、東側の戦車ではそうした配慮はあまり行われていなかった。かつてはガソリンエンジンが使われることも多かったが、被弾時に引火・爆発しやすいため、第二次世界大戦後は次第に使われなくなった。
- 第二次世界大戦時には戦車用という大出力のエンジンは開発が難しかったため、航空機用エンジンで代替することもあった。大戦中の戦車の多くは車体後部のエンジンからドライブシャフトで前部の変速機に動力伝達する前輪駆動であったが、第二次世界大戦後はエンジンと変速機が直結した後輪駆動が主流となっている。一方でイスラエルのメルカバやスウェーデンのStrv.103の様に、乗員保護を優先してあえてエンジン・変速機を車体前方に配して装甲の一部としている例もある。
履帯
[編集]
戦車は無限軌道(履帯、商標名でキャタピラ)で走行する。起動輪と誘導輪があるのは共通だが、転輪には様々な形が存在する。普通は1列に並べてあるが、かつてのドイツ重戦車の場合、転輪が千鳥型に2重になっていたり、3重に並べたり、荷重を分散するようにしていた。ただし保守が困難な上、手間の割に効果的とは言えなかったため第二次世界大戦後は、そのような形式は採用されていない。
- 転輪には騒音と振動を軽減する目的で周辺にゴム製のソリッドタイヤを装着するが、ゴム資源が不足していた第二次世界大戦中のドイツ・ソ連では、転輪内部や車軸にゴムを内蔵したり、やむを得ず全くゴムを用いない鋼製転輪を使用する場合もあった(イスラエルの戦車は砂漠でゴムタイヤの破損が激しいため一部に完全鋼製転輪を使用している)。
- 無限軌道の連結には金属製のピンが用いられるが、走行時の抵抗を低減するために、ピンとピン穴の間にゴムブッシュを設けることがある。
サスペンション(懸架装置)
[編集]

- 初めて実戦投入されたMk.I戦車にはサスペンションは存在しなかったが、その後におけるサスペンション形式はさまざまで、スプリングの種類も、リーフスプリング、コイルスプリング、渦巻きスプリング、クリスティー式(コイルスプリングと大型転輪の組み合わせ)、横置きトーションバー、縦置きトーションバーなどがある。
- 現用戦車では主に横置きトーションバーが採用されている。スウェーデンのStrv.103は前後左右の油圧を変えることで車体の角度を変えられる油気圧(ハイドロニューマチック・サスペンション)を史上初めて実用装備した。陸上自衛隊の74式戦車も同様の油気圧式サスペンションを採用しているが、この機能は地形を利用した待ち伏せ砲撃に有利であり、専守防衛を旨とする両国の防衛策に適していたと言える。また、90式戦車や韓国のK1は横置きトーションバー式と油気圧式を混合装備している。
- いくらエンジン出力の大きな車両でも、サスペンションの性能が悪ければ車体や乗員の負担が大きくなり十分な機動性は発揮できず、逆にエンジンが非力であっても、サスペンションの改良により機動性を向上させることが可能である。
乗員
[編集]戦車は戦闘機やのように一人で操作できる兵器ではなく、複数の乗員を必要とする。現代の戦車の乗員は、一般的に次の4名からなる。すなわち、
- 戦車長(車長、Commander)
- 戦車や戦車部隊の指揮を行う。車外の索敵も戦車長がおもに担当する。
- 砲手(照準手、Gunner)
- 砲塔の旋回、主砲や同軸機銃の照準・発射を担当する。
- 操縦手(運転手、Driver)
- 戦車の操縦を担当する。キャタピラの保守点検も操縦手の責任である。
- 装填手(Loader)
- 主砲弾の装填を行う。戦車長とともに車外の索敵やその他雑用を行うことも多い。
しかし自動装填装置を搭載した戦車は装填手がおらず、乗員は戦車長・砲手・操縦手の3名となる。MCSに至っては戦車長と操縦手の2名しかいない。この点については運用上の問題も指摘されているが、各国の軍隊で考え方は変わるため、一概に自動装填装置を搭載して乗員を減らすことが悪いとはいえない。
第二次世界大戦時には以上の4名に加え、車体機銃や無線機を操作する通信手(無線手、Radioman)あるいは副操縦手(Co-Driver)という乗員もいた。しかし戦後各国で車体機銃が廃止され、無線機も戦車長が取り扱えるレベルに小型化・発展すると通信手は不要になった。
- 乗員の服装
-
第一次世界大戦時に戦車の乗員が着用していた鎖帷子(くさりかたびら)。
-
第二次世界大戦時のドイツの戦車兵のユニフォーム。
-
ロシア独特の戦車帽をかぶったソ連の戦車兵(戦車はT-50である)。
-
戦車兵用のつなぎとイスラエル独特の戦車兵用ヘルメットをかぶったイスラエル軍の女性戦車教官。
-
120mm砲弾を装填する装填手。
-
タンカーブーツ。
-
WWII期のイギリス戦車兵の装備、すなわちベレー帽とヘッドフォンをかぶり、無線機のマイクを使用するウィンストン・チャーチル。
- 車載装備品(On Vehicle Material,OVM)


-
- 西側現用戦車における一例[97]
- 主砲砲弾 - 40~65発
- 機関銃弾 - 3,000~7,000発(7.62mm弾+12.7mm弾)
- 自衛小火器銃弾 - 300~500発
- 信号弾 - 20~40発
- 修理用部品30~50品目(履板、転輪、銃身など) - 50~80個
- 土木工具 - 5~7種
- 機械工具 - 50~80種
- 給油・給水具 - 10~20個
- 信号旗 - 4~6本
- 対空布板 - 1式
- カムフラージュネット - 1枚
- 車輛シート - 1枚
- 双眼鏡 - 1~2個
- 懐中電灯 - 2~4本
- 小型ビデオカメラ(湾岸戦争から登場) - 1台
- 自衛用小火器(短機関銃・自動小銃) - 1~2挺
- 個人装備
- ヘルメット - 各自1個
- 水筒・炊事用具 - 各自1~2セット
- 背嚢(着替え衣類や日用品収納) - 各自1式
- 携帯糧食 - 各自2~3日分
- 拳銃 - 各自1挺
- 携帯バーナー - 1~2個
- テント - 1式
- 寝袋および野外マットレス - 各自1式
- ガスマスクおよび防護スーツ - 各自1式
- 戦闘地域の環境によって搭載
- NBCキット、極寒地用キット、防寒装備、スキー
その他の構造
[編集]視察装置
[編集]
(従来から司令塔、または車長展望塔とも呼ばれ、車長や装填手の外部視認用に砲塔上面に設けられた半球状などの突起が備わっていたが、20世紀末以降の戦車では、キューポラの形状は旧来の突出したものよりも低くなっている。防弾ガラスごしに直接覗くものや、鏡を使ったペリスコープがあった。キューポラには機関銃が備えられるものが多く、近接攻撃や対空攻撃用に搭載されていた。)
[[

コミュニケーション設備
[編集]無線機やデータリンクシステムなど。これらの設備の有無が戦車の性能を直接左右するわけではないが、



第一次世界大戦時における初期の戦車には無線機がなく、連絡手段には伝書鳩が使われたが戦車の居住性があまりにも劣悪なため鳩までバテて飛ばないこともあった
運用
[編集]

改修
[編集]


対戦車兵器
[編集]歩兵携行式
[編集]- 対戦車ライフル

14.5mmPTRD対戦車ライフルを構えるポーランド兵。 - 対戦車擲弾発射機
RPG-29。第二次レバノン戦争やイラク戦争で、メルカバMk.IVやチャレンジャー2といった西側第3世代主力戦車の前面装甲を貫徹したことがある。 - 対戦車砲

「ラッチュ・バム」こと76.2mm ZIS-3。
対戦車ミサイル
[編集]航空機
[編集]


脚注・注釈
[編集]脚注
[編集]- ^ 葛原 2009, p. 34.
- ^ 河津 2011a, p. 11.
- ^ 白石 2013, p. 128
- ^ 『戦車100年史 その発達の跡をたどる』アルゴノート社、2016年、24頁。ISBN 978-4-914974-17-6。
- ^ 松村劭『戦術と指揮 命令の与え方・集団の動かし方』PHP文庫、2010年、40頁。ISBN 4-569-66596-9。
- ^ 田村尚也(文)、野上武志(イラスト)『萌えよ!戦車学校VII型 フィリピン決戦&マーケット・ガーデン作戦』イカロス出版、2014年、150頁。ISBN 978-4-86320-904-6。
- ^ 葛原 2010, p. 31.
- ^ 木俣滋郎『戦車戦入門 世界篇』光人社NF文庫、1999年、19頁。ISBN 4-7698-2230-8。
- ^ 大波篤司 2008, p. 14~15.
- ^ 陸軍省臨時軍事調査委員『欧洲交戦諸国ノ陸軍ニ就テ(増補再版)』陸軍省、1916年6月、第九 欧州戦ニ於ケル兵器ノ趨勢 24頁。
- ^ 大正11年「偕行社記事」4月号に掲載された「作戦上に於ける自動車の利用について」という論文に戦車の語が確認できるという。佐山二郎『機甲入門』光人社NF文庫、2002年。70ページ ISBN 4-7698-2362-2
- ^ 奥村恭平大尉(陸士21期・輜重、のち陸軍少将)が軍用自動車調査会の席上で「戦車」と呼称することを提案した
- ^ 扇広 (1982). 日本陸軍の戦車発達史 (1)、『戦車マガジン』1982年6月号. 株式会社戦車マガジン. pp. 88 - 89
- ^ 細見惟雄、重信吉固『中隊教練ノ研究 歩兵操典草案 下巻』陸軍歩兵学校将校集会所、1925年3月、附表第二。
- ^ 陸軍歩兵学校准士官下士集会所編『陸軍歩兵学校案内』陸軍歩兵学校准士官下士集会所、1925年8月、六 戦車 19頁。
- ^ 日本の陸軍、『Jグランド』vol.18. イカロス出版. (2008). pp. 41. JANコード 4910151760288
- ^ 大波篤司 2007, p. 29.
- ^ 白石光 2013, p. 18.
- ^ 学習研究社編集部 2008, p. 47.
- ^ 白石 2013, p. 12.
- ^ “Czołgające się smoki” (ポーランド語). Piotr Bojarski. 2016年1月28日閲覧。
- ^ sss
- ^ 清谷「新・世界の主力戦車カタログ」P51。
- ^ 『戦車100年史 その発達の跡をたどる』アルゴノート社、2016年、22頁。ISBN 978-4-914974-17-6。
- ^ 清谷「新・世界の主力戦車カタログ」P3。
- ^ 野神『図解 軍用車両』46頁。
- ^ 上田『世界の戦車メカニカル大図鑑』14頁。
- ^ 学研『現代戦術への道』44頁。
- ^ 学習研究社編集部 2008, p. 6.
- ^ ピーター チェンバレン、クリス エリス. 世界の戦車 1915~1945 (初版 ed.). pp. 114
- ^ 学習研究社編集部 2008, p. 36.
- ^ 学習研究社編集部 2008, p. 51.
- ^ 葛原和三 2009, p. 13.
- ^ 齋木『図解 戦車の秘密』160頁。
- ^ a b 坂本明 2013, p. 54~55
- ^ 葛原和三 2009, p. 35.
- ^ 野神明人 2015, p. 44.
- ^ a b 毒島『M1エイブラムスはなぜ最強といわれるのか』162頁。
- ^ a b 上田『世界の戦車 メカニカル大図鑑』151~152頁。
- ^ 清谷「新・世界の主力戦車カタログ」P174。
- ^ 上田「現代戦車戦史」P13。
- ^ 上田『現代戦車戦史』29頁。
- ^ 清谷『新・現代戦車のテクノロジー』12頁。
- ^ Chaim Herzog (2009). The War of Atonement:The Inside Story of the Yom Kippur War. A GreenHill Book. p. 205. ISBN 978-1-935149-13-2
- ^ 『戦車対戦車 コンバット4』アルゴノート社、2015年。ISBN 978-4914974114。
- ^ 田村、野上『萌えよ!戦車学校』85~86頁。
- ^ 清谷『新・世界の主力戦車カタログ』217頁。
- ^ 清谷『新・世界の主力戦車カタログ』219頁。
- ^ 毒島『M1エイブラムスはなぜ最強といわれるのか』165頁。
- ^ 清谷「『新・世界の主力戦車カタログ』159頁。
- ^ 清谷『新・現代戦車のテクノロジー』235~238頁。
- ^ [1]
- ^ “Armor,July-August 1999 Edition”. Fort Benning. 2016年2月24日閲覧。
- ^ 『月刊PANZER』2016年2月号。
- ^ 竹内昭 2003, p. 26.
- ^ 名城『ドイツ連邦戦車開発小史』115頁。
- ^ 齋木『図解 戦車の秘密』74頁。
- ^ 名城『ドイツ連邦戦車開発小史』133頁。
- ^ 大波篤司 2007, p. 53.
- ^ “105mm APFSDS F3 105mm AMMUNITION FOR AMX-10 RC GUN” (英語). 2016年2月14日閲覧。
- ^ “United States 30 mm (1.2") Bushmaster II Mark 46 Mod 1 40 mm (1.57") Bushmaster II” (英語). 2016年2月14日閲覧。
- ^ 田村、野上『萌えよ!戦車学校』34~35頁。
- ^ 清谷『新・現代戦車のテクノロジー』72頁。
- ^ a b 清谷『新・現代戦車のテクノロジー』73頁。
- ^ 小林源文『武器と爆薬 悪夢のメカニズム図鑑』大日本絵画、2007年、59頁頁。ISBN 978-4-499-22934-0。
- ^ 毒島『M1エイブラムスはなぜ最強といわれるのか』55頁。
- ^ 篠尾『現代兵器入門』84頁。
- ^ a b 毒島『M1エイブラムスはなぜ最強といわれるのか』54頁。
- ^ 清谷『新・現代戦車のテクノロジー』76頁。
- ^ a b c 毒島『M1エイブラムスはなぜ最強といわれるのか』82頁。
- ^ “劣化ウラン:原因、被曝および健康への影響 ― 概要 ―”. TriNary. 2016年2月16日閲覧。
- ^ “劣化ウランの健康影響”. ATOMICA. 2016年2月16日閲覧。
- ^ “離脱装弾筒付翼安定徹甲弾”. 2016年3月18日閲覧。
- ^ 清谷『新・現代戦車のテクノロジー』39頁。
- ^ 清谷『新・現代戦車のテクノロジー』82頁。
- ^ 『月刊グランドパワー』2016年3月号、p.31。
- ^ 清谷信一 2011a, p. 53
- ^ 名城犬朗『レオパルト1vsT-62 独ソ第二世代戦車比較』pk510、2016年、p.10頁。
- ^ “日本周辺国の軍事兵器 T-62戦車(天馬号)”. 2016年3月18日閲覧。
- ^ “T-72戦車 戦車研究室”. 2016年3月18日閲覧。
- ^ 浪江『陸上自衛隊現用戦車写真集』123頁。
- ^ 清谷『新・現代戦車のテクノロジー』81頁。
- ^ 木元『本当の戦車の戦い方』230頁。
- ^ 清谷『新・世界の主力戦車カタログ』204頁。
- ^ 毒島『M1エイブラムスはなぜ最強といわれるのか』62頁。
- ^ “120mm Line-of-Sight Multi-Purpose (LOS-MP) Munition S&T” (英語). Jesse Sunderland LOS MP Engineer, RDECOM ARDEC. 2016年2月15日閲覧。
- ^ 清谷「新・世界の主力戦車カタログ」P121。
- ^ 名城「ドイツ連邦戦車開発小史」P96。
- ^ a b 毒島「M1エイブラムスはなぜ最強といわれるのか」P30。
- ^ 清谷『新・現代戦車のテクノロジー』29頁。
- ^ 竹内昭 2003, p. 23.
- ^ 大波篤司 2008, p. 103.
- ^ “PL-01 Concept Direct Fire Support Vehicle”. Army Recognition. 2013年9月20日閲覧。
- ^ “Parametry Wozu Wsparcia Bezpośredniego PL-01 Concept” (ポーランド語). defence24 (2013年9月4日). 2013年9月18日閲覧。
- ^ “PL01 CONCEPT PL”. OBRUM YouTube (2013年9月5日). 2013年9月20日閲覧。
- ^ 21世紀現在では、戦闘用装甲車輌であってもセンサー類やC4Iシステムといった多数の電子機器を常時稼動させる必要があり、停車時に主たるエンジンを停止する間の補助電源としてAPUを搭載する必要が生まれている。
- ^ 坂本明 2013, p. 63.
注釈
[編集]- ^ 本記事ではおおよそ以上の特徴をもつ「戦車」を中心に扱い、戦車からの派生車輛(駆逐戦車、対空戦車など)は補助的な記述にとどめる。
- ^ 「キャタピラ」 (catapiller、ケムシ)はキャタピラー社の商標登録で、「無限軌道」はイギリスの技師ジェームズ・ボイデル が1846年に特許を取得した「エンドレス・レールウェイ・ホイール」(Endless Railway Wheel)の訳語とされる[3]。以下、本記事では「履帯」で統一する。
- ^ 「タレット」や「ハル」といった語は船舶用語から取られている。後述するように戦車が当初「陸上艦」として開発されていたためである。
- ^ 第二次世界大戦中は重戦車扱いだったが、戦後に中戦車に分類し直された。
- ^ 歩兵や航空部隊といった他兵科との情報共有までを目指したのはM1A2SEPの搭載するフォース21旅団間情報共有システム
- ^ 近代戦車が登場する直前の辞書大日本国語辞典(大正4年8月発行) には「せんしゃ【戰車】 戦争に用ふる車。軍用の車。兵車」とある。
- ^ 中国大陸では青銅器時代には古代戦車が主力兵器とみなされるほど重視されていたものの、時代が下ると歩兵と騎兵に地位を奪われて廃れていった。日本では山がちな地勢や大陸から伝わった鉄器や騎馬の技術によって古代戦車の時代を経ること無く歩兵と騎兵の時代に移行したため、ほとんど使われなかった
- ^ 兵器の制式名としてPanzerkampfwagenではなくPanzerだけで「戦車」を意味するようになったのが確認できるのは、IV号駆逐戦車の長砲身型であるIV号戦車/70 (Panzer IV/70) が最初である。
- ^ もっとも、ティーガーIは元をたどれば戦前の1937年から開発されていた車輛が原点であり、「V号戦車」(パンター)の方が開発開始は後の1942年になる。[22]
- ^ 「かっくうほう」と読むこともある。
- ^ チャレンジャー2が主砲として搭載する120mm L11A5の分離式砲弾の生産が終了したため、チャレンジャー2の主砲を滑腔砲に換装しようという計画もあったが、予算の関係により没になった。
- ^ ライフル砲でも装弾筒にスリッピング・バンドを付け、装弾筒だけが回転するようにすればAPFSDSは発射可能。[67]
- ^ G弾(OCC-105-F1)の貫徹力は360mm(垂直装甲板)、105mmライフル砲L7(西側戦車で主流だった)の使用するHEAT(M456)は貫徹力432mm(条件不明)[77]。115mm滑腔砲U-5TS(T-62に搭載)のHEAT弾(BK-4M)も貫徹力は432mm(RHA換算)である[78][79]。
- ^ 自衛隊が74式戦車の105mm L7用APDS、HEAT、そしてHESHでT-62の砲塔正面を模した装甲板を射撃したところ、APDS、HEATはそれぞれ装甲を貫徹したのに対し、HESHは内部装甲板をわずかに膨らませただけで剥離しなかったことがある[83]。
- ^ これらの120mm L11は分離式砲弾を利用しているが、粘着榴弾は徹甲弾に比べ、半分の装薬で発射できる[84]。
- ^ アメリカでは140mm砲用自動装填装置に95~99%の機械的信頼性を要求している[87]。
- ^ イギリス軍が第二次世界大戦時に破壊された1,600輛の戦車の被弾箇所を調べたところ、命中弾の4割が戦車前面に集中し、うち65%が車体に、35%が砲塔に命中していた。またアメリカ軍がM26の前面を射撃したところ、命中弾の32%が砲塔防盾に、39%が車体前面上部に命中するというデータが得られた[91]。他のアメリカ軍の第二次世界大戦におけるデータやイスラエル軍の中東戦争によるデータによれば、命中弾の80%が砲塔に命中するとされる[92]。
主要参考文献
[編集]- ピーター・チェンバレン; ヒラリー・L・ドイル『ジャーマンタンクス』富岡吉勝(翻訳監修)、大日本絵画、2006年。ISBN 4-499-20533-6。
- フルビオ・ミグリア 著、江畑謙介 編『万有ガイド・シリーズ(17) 戦車』森尾総夫(訳)、小学館、1982年。ASIN B000J7O40Q。
- 清谷信一 編『新・現代戦車のテクノロジー』アリアドネ企画、2011a。ISBN 978-4-384-04439-3。
- 清谷信一 編『新・世界の主力戦車カタログ』アリアドネ企画、2011b。ISBN 978-4-384-04410-2。
- 上田信『世界の戦車 メカニカル大図鑑』大日本絵画、2014年。ISBN 978-4-449-23136-7{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。
- 上田信『現代戦車戦史 進化するモンスターたち』大日本絵画、2012年。ISBN 978-4499230926。
- 大波篤司『F-Files No.012 図解 戦車』新紀元社、2007年。ISBN 978-4775305867。
- 葛原和三 著、戦略研究学会 編『ストラテジー選書10 機甲戦の理論と歴史』川村康之(監修)、芙蓉書房出版、2009年。ISBN 978-4-8295-0450-5。
- 河津幸英『湾岸戦争大戦車戦 (上) 史上最大にして最後の機甲戦』イカロス出版、2011a。ISBN 978-4-86320-416-4。
- 河津幸英『湾岸戦争大戦車戦 (下) 史上最大にして最後の機甲戦』イカロス出版、2011b。ISBN 978-4-86320-417-1。
- 河津幸英『図解 超陸戦兵器 FUTURE COMBAT SYSTEMS 21世紀の戦場を支配する近未来兵器と米陸軍改革の全貌』アリアドネ企画、2006年。ISBN 978-4384040975。
- 齋木伸夫『図解 戦車の秘密』PHP研究所、2013年。ISBN 978-4-569-81252-6。
- 坂本明『最強 世界の戦闘車両図鑑』学研パブリッシング、2013年。ISBN 978-4-05-405618-3。
- 白石光『歴群[図解]マスター 戦車』学研パブリッシング、2013年。ISBN 978-4054058187。
- 竹内昭(監修) 編『学研の大図鑑 世界の戦車・装甲車』学習研究社、2003年。ASIN 978-4054016965。
- 野神明人『F-Files No.049 図解 軍用車両』新紀元社、2015年。ISBN 978-4-7753-1324-4。
- 田村尚也(文); 野上武志(イラスト)『萌えよ!戦車学校 戦車のすべてを萌え燃えレクチャー』イカロス出版、2005年。ISBN 978-4087149-692-6{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。
- 田村尚也(文); 野上武志(イラスト)『萌えよ!戦車学校II型』イカロス出版、2006年。ISBN 4-87149-769-0。
- 毒島刀也『M1エイブラムスはなぜ最強といわれるのか 実戦を重ねて進化する最新鋭戦車の秘密』SBクリエイティブ、2012年。ISBN 978-4-7973-5470-6。
- 名城犬明『ドイツ連邦戦車開発小史』イカロス出版、2013年。ISBN 978-4-86320-757-8。
- 浪江俊明『陸上自衛隊現用戦車写真集』大日本絵画、2014年。ISBN 978-4-499-23139-8。
- 学習研究社編集部『歴史群像アーカイブ3 ミリタリー基礎講座Ⅱ 現代戦術への道』学習研究社、2008年。ISBN 978-4-05-605199-5。
- 『オスプレイ・ミリタリー・シリーズ 世界の戦車 イラストレイテッド』各巻、大日本絵画。
- 『月刊PANZER』各号、アルゴノート社。
- 『軍事研究』各号、ジャパン・ミリタリー・レビュー。
- 『月刊グランドパワー』各号、ガリレオ出版
外部リンク
[編集]



引用エラー: 「注」という名前のグループの <ref> タグがありますが、対応する <references group="注"/> タグが見つかりません
引用エラー: 「出典」という名前のグループの <ref> タグがありますが、対応する <references group="出典"/> タグが見つかりません