利用者:Y.Otani/sandbox
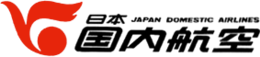
日本国内航空(にほんこくないこうくう、英語:Japan Domestic Airlines、略称:JDA)は、かつて日本国内で定期旅客便を運航していた航空会社である。1964年4月15日設立。
1971年5月15日、東亜航空と合併し、東亜国内航空のちの日本エアシステムとなった。
概要[編集]
戦後の民間航空解禁と同時に誕生した中小地域内ローカル航空会社は多くが経営不振に陥っていた。そういった中で経営不振の脱却のため幹線参入を希望していた日東航空(1952年7月4日設立)、富士航空(1952年9月13日設立)、北日本航空(1953年6月30日設立)の3社に対し、運輸省(現・国土交通省)が幹線参入の条件として合併を指示し、1964年4月15日に設立された。3社はいずれも近鉄や東急と資本関係が強く全日空への統合が困難であったとされる。
1965年3月に大型ジェット機のコンベア880で念願の幹線である東京~札幌、東京~福岡線に参入、また1966年5月には同じく幹線用としてボーイング727を導入するなど積極的な動きを見せた。しかし元来の累積赤字や脆弱な路線網に加え1964年の東海道新幹線開通などにより経営は難航し、日本航空と国内線大手の全日本空輸という大手2社に阻まれ経営不振に陥った。最終的には大型ジェット機は日本航空へウェットリースされ、YS-11が主要機材となった。
運輸省は日本国内航空を日本航空に、また同じく経営不振に陥っていた東亜航空を全日本空輸に統合させ需給を調整する方針であり、コンベア880やボーイング727の日本航空へのリースはこの統合作業の過程で行われたものであった。しかし、日本国内航空の親会社である東京急行電鉄の社長五島昇は、東急の海外進出を狙い、日本国内航空の存続に拘り、東亜航空の親会社不二サッシの社長佐野友二に両者の合併を説いた。またいざなぎ景気による経営黒字化も後押しとなり、五島は運輸省の意に反して日本国内航空と東亜航空の合併を実現させ、国内第三位の航空会社である東亜国内航空誕生させた。
なお、東亜国内航空は日本エアシステム(JAS)→日本航空ジャパンと改称ののち日本航空インターナショナル(現 日本航空)と合併した。
世界初のYS-11就航[編集]

戦後初の国産民間旅客機であるYS-11は、1965年(昭和40年)4月に東亜航空に引き渡された量産型2号機が初の納入機であったが、当機を定期航空路で初めて就航させたのは日本国内航空であった。同4月の東京(羽田) - 徳島 - 高知線で運用を開始したYS-11であったが、メーカーの技術不足による機材トラブルが相次ぎ、日本国内航空の経営を逼迫する一因となった。
→YS-11も参照。
日本航空羽田空港墜落事故[編集]

日本国内航空は幹線用として当時最大級の大型ジェット機コンベア880(コンベア880-22M、機体記号JA8030)を「銀座」号として導入したが、経営悪化にともない路線ごと日本航空へリースした。1966年8月26日、日本航空による訓練飛行中に羽田空港を離陸直後墜落、全乗員が死亡した。「日本航空羽田空港墜落事故」である。事故後、当機の補償として日本航空からボーイング727「ふじ」号(JA8318、日本航空時代は「たま」号)が無償譲渡された。なおこのJA8318も後に機体番号G-BDANとしてイギリスのダン・エアに売却され、カナリア諸島のテネリフェ・ノルテ空港で墜落している。
→日本航空羽田空港墜落事故も参照
使用機材(回転翼機除く)[編集]
富士航空・日東航空・北日本航空の3社から機材を引き継いだため小型機と、幹線参入の方針で導入したコンベア880やボーイング727を所有していた。
- パイパーPA-18カブ
- パイパーPA-23アパッチ
- グラマンG44スーパーウィジョン
- ダグラスDC-3A
- ノール262A-14
- コンベアCV-240
- デハビランドDHC-2ビーバー
- デハビランドDH114-1Bヘロン
- デハビランドDH114タウロン
- コンベア880-22M
- ボーイング727-100
- YS-11
- セスナ170
- セスナ170B
- セスナ172B
- セスナ172C
- セスナ172D
- セスナ175B
- セスナ195
関連項目[編集]
- 日本エアシステム
- 日本航空羽田空港墜落事故
- YS-11
参考資料[編集]
- YouTube『東急の空への夢・東急視点のJASの歴史』,akamomo,2019.9(https://www.youtube.com/watch?v=eWfU1Ivwar0)
 |
ここはY.Otaniさんの利用者サンドボックスです。編集を試したり下書きを置いておいたりするための場所であり、百科事典の記事ではありません。ただし、公開の場ですので、許諾されていない文章の転載はご遠慮ください。
登録利用者は自分用の利用者サンドボックスを作成できます(サンドボックスを作成する、解説)。 その他のサンドボックス: 共用サンドボックス | モジュールサンドボックス 記事がある程度できあがったら、編集方針を確認して、新規ページを作成しましょう。 |
