「瀬戸内寂聴」の版間の差分
デビューなど |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{文学}} |
{{文学}} |
||
'''瀬戸内 寂聴'''('''せとうち じゃくちょう'''、女性、[[1922年]][[5月15日]] - )は、日本の[[小説家]]、[[天台宗]]の[[尼僧]]。 |
'''瀬戸内 寂聴'''('''せとうち じゃくちょう'''、女性、[[1922年]][[5月15日]] - )は、日本の[[小説家]]、[[天台宗]]の[[尼僧]]。旧名は'''瀬戸内 晴美'''('''せとうち はるみ''')。 |
||
[[僧綱|僧位]]は[[僧正|権僧正]]。[[1997年]][[文化功労者]]、[[2006年]][[文化勲章]]。[[学歴]]は徳島県立高等女学校(現:[[徳島県立城東高等学校]])、[[東京女子大学]]国語専攻部卒業。[[学位]]は[[学士|文学士(東京女子大学)]]。[[称号]]は[[徳島県]][[徳島市]][[名誉市民]]。元[[天台寺]][[住職]]。元[[敦賀短期大学]][[学長]]。代表作には『夏の終り』や『場所』『現代語訳 源氏物語』など多数。近年では『[[源氏物語]]』に関連する著作が多い。これまでの著作により多くの文学賞を受賞した。[[2007年]][[8月11日]]、館長を務める徳島県立文学書道館(徳島市)での講演で、右目の視界が大部分見えなくなったことを明かした |
[[僧綱|僧位]]は[[僧正|権僧正]]。[[1997年]][[文化功労者]]、[[2006年]][[文化勲章]]。[[学歴]]は徳島県立高等女学校(現:[[徳島県立城東高等学校]])、[[東京女子大学]]国語専攻部卒業。[[学位]]は[[学士|文学士(東京女子大学)]]。[[称号]]は[[徳島県]][[徳島市]][[名誉市民]]。元[[天台寺]][[住職]]。元[[敦賀短期大学]][[学長]]。代表作には『夏の終り』や『場所』『現代語訳 源氏物語』など多数。近年では『[[源氏物語]]』に関連する著作が多い。これまでの著作により多くの文学賞を受賞した。[[2007年]][[8月11日]]、館長を務める徳島県立文学書道館(徳島市)での講演で、右目の視界が大部分見えなくなったことを明かした。 |
||
== 経歴 == |
== 経歴 == |
||
[[徳島県]][[徳島市]]東大工町の仏壇店を営む[[瀬戸内商店|瀬戸内家]]に |
[[徳島県]][[徳島市]]東大工町の仏壇店を営む三谷家の次女として生まれ、後に父が従祖母の家である[[瀬戸内商店|瀬戸内家]]養子となり、女学校時代に晴美も瀬戸内に改姓。 |
||
[[東京女子大学]]在学中に結婚し、夫の任地[[北京市|北京]]に同行。1946年に帰国し、夫の教え子と恋に落ち、夫と長女を残し家を出る。正式に離婚をし |
[[東京女子大学]]在学中に結婚し、夫の任地[[北京市|北京]]に同行。1946年に帰国し、夫の教え子と恋に落ち、夫と長女を残し家を出て京都で生活。大翠書院などに勤めながら、初めて書いた小説「ピグマリオンの恋」を[[福田恆存]]に送る。1950年に正式に離婚をし、東京へ行き本格的に小説家を目指し、'''三谷晴美'''のペンネームで少女小説を投稿し『少女世界』誌に掲載され、'''三谷佐知子'''のペンネームで『ひまわり』誌の懸賞小説に入選。[[少女世界社]]、[[ひまわり社]]、[[小学館]]、[[講談社]]で少女小説や童話を書く。また[[丹羽文雄]]を訪ねて同人誌『文学者』に参加、解散後は『Z』に参加。長女とは後年和解する。 |
||
[[1956年]]、処女作「痛い靴」を『文学者』に発表、[[1957年]]に「女子大生・曲愛玲」で[[同人雑誌賞|新潮同人雑誌賞]]を受賞<!--この辺英文とちがうなぁ-->。その受賞第1作『花芯』で、[[官能小説|ポルノ小説]]であるとの批判にさらされ、「[[子宮]]作家」とまで呼ばれるようになる。その後数年間は文芸雑誌からの執筆依頼がなくなり、『[[講談倶楽部]]』『[[婦人公論]]』その他の大衆雑誌、週刊誌等で作品を発表。1959年から同人誌『無名誌』に『田村俊子』の連載を開始。並行して『[[東京新聞]]』に初の長編小説『女の海』を連載。この時期の不倫の恋愛体験を描いた『夏の終り』で[[1963年]]の[[女流文学賞]]を受賞し、作家としての地位を確立する。以後数多くの恋愛小説、伝記小説を書き人気作家となるが、30年間、純文学の賞も大衆文学の賞ももらえないという秘かな不遇のうちにあった。[[1992年]]、西行を描いた『花に問え』で[[谷崎潤一郎賞]]を受賞した。『[[源氏物語]]』の現代語訳でもその名を知られている。 |
|||
1973年に |
1973年に[[今東光]]大僧正の導きにより[[中尊寺]]にて[[天台宗]]で[[得度]]、法名を寂聴とする。これにより戸籍上も氏名は「瀬戸内寂聴」となる。尼僧としての活動も熱心で、週末には青空説法(天台寺説法)として、法話を行っていた。 |
||
[[テレビドラマ]]『[[女の一代記]]』 |
[[2005年]]には、彼女を主人公とした[[テレビドラマ]]『[[女の一代記]]』が放映された。この中でも、東京に住みだした後、二人の男性と恋愛関係にあった、と語っている。僧侶になったあとは男性との関係をいっさい断って真面目な信仰生活を送っている。地方講演などでは主に「笑うこと」が大切であるということを説いていることが多い。麻薬で逮捕された[[萩原健一]]の更生に尽くしたことや、[[徳島ラジオ商殺し事件]]の再審支援などの活動でも有名。[[山岳ベース事件]]等で死刑判決を受けた[[永田洋子]]や、[[連続ピストル射殺事件]]で死刑執行された[[永山則夫]]とも親交があり[[死刑廃止]]論者とも一部からは見られたが死刑制度そのものは是認している。一方、[[脳死]]による[[臓器移植]]には反対している。[[同時多発テロ]]の報復攻撃に抗議し短期間の[[ハンガーストライキ]]を決行した。 |
||
「金を取る宗教は偽物」を自らの持論としている。 |
「金を取る宗教は偽物」を自らの持論としている。 |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
=== 年譜 === |
=== 年譜 === |
||
*[[ |
*[[1957年]] 『女子大生・曲愛玲』で新潮同人雑誌賞受賞 |
||
*[[1961年]] 『田村俊子』で[[田村俊子賞]] |
*[[1961年]] 『田村俊子』で[[田村俊子賞]] |
||
*1963年 『夏の終り』で女流文学賞を受賞 |
*1963年 『夏の終り』で女流文学賞を受賞 |
||
2008年7月20日 (日) 00:44時点における版
| 文学 |
|---|
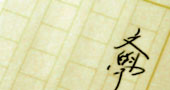 |
| ポータル |
|
各国の文学 記事総覧 出版社・文芸雑誌 文学賞 |
| 作家 |
|
詩人・小説家 その他作家 |
瀬戸内 寂聴(せとうち じゃくちょう、女性、1922年5月15日 - )は、日本の小説家、天台宗の尼僧。旧名は瀬戸内 晴美(せとうち はるみ)。
僧位は権僧正。1997年文化功労者、2006年文化勲章。学歴は徳島県立高等女学校(現:徳島県立城東高等学校)、東京女子大学国語専攻部卒業。学位は文学士(東京女子大学)。称号は徳島県徳島市名誉市民。元天台寺住職。元敦賀短期大学学長。代表作には『夏の終り』や『場所』『現代語訳 源氏物語』など多数。近年では『源氏物語』に関連する著作が多い。これまでの著作により多くの文学賞を受賞した。2007年8月11日、館長を務める徳島県立文学書道館(徳島市)での講演で、右目の視界が大部分見えなくなったことを明かした。
経歴
徳島県徳島市東大工町の仏壇店を営む三谷家の次女として生まれ、後に父が従祖母の家である瀬戸内家養子となり、女学校時代に晴美も瀬戸内に改姓。
東京女子大学在学中に結婚し、夫の任地北京に同行。1946年に帰国し、夫の教え子と恋に落ち、夫と長女を残し家を出て京都で生活。大翠書院などに勤めながら、初めて書いた小説「ピグマリオンの恋」を福田恆存に送る。1950年に正式に離婚をし、東京へ行き本格的に小説家を目指し、三谷晴美のペンネームで少女小説を投稿し『少女世界』誌に掲載され、三谷佐知子のペンネームで『ひまわり』誌の懸賞小説に入選。少女世界社、ひまわり社、小学館、講談社で少女小説や童話を書く。また丹羽文雄を訪ねて同人誌『文学者』に参加、解散後は『Z』に参加。長女とは後年和解する。
1956年、処女作「痛い靴」を『文学者』に発表、1957年に「女子大生・曲愛玲」で新潮同人雑誌賞を受賞。その受賞第1作『花芯』で、ポルノ小説であるとの批判にさらされ、「子宮作家」とまで呼ばれるようになる。その後数年間は文芸雑誌からの執筆依頼がなくなり、『講談倶楽部』『婦人公論』その他の大衆雑誌、週刊誌等で作品を発表。1959年から同人誌『無名誌』に『田村俊子』の連載を開始。並行して『東京新聞』に初の長編小説『女の海』を連載。この時期の不倫の恋愛体験を描いた『夏の終り』で1963年の女流文学賞を受賞し、作家としての地位を確立する。以後数多くの恋愛小説、伝記小説を書き人気作家となるが、30年間、純文学の賞も大衆文学の賞ももらえないという秘かな不遇のうちにあった。1992年、西行を描いた『花に問え』で谷崎潤一郎賞を受賞した。『源氏物語』の現代語訳でもその名を知られている。
1973年に今東光大僧正の導きにより中尊寺にて天台宗で得度、法名を寂聴とする。これにより戸籍上も氏名は「瀬戸内寂聴」となる。尼僧としての活動も熱心で、週末には青空説法(天台寺説法)として、法話を行っていた。
2005年には、彼女を主人公としたテレビドラマ『女の一代記』が放映された。この中でも、東京に住みだした後、二人の男性と恋愛関係にあった、と語っている。僧侶になったあとは男性との関係をいっさい断って真面目な信仰生活を送っている。地方講演などでは主に「笑うこと」が大切であるということを説いていることが多い。麻薬で逮捕された萩原健一の更生に尽くしたことや、徳島ラジオ商殺し事件の再審支援などの活動でも有名。山岳ベース事件等で死刑判決を受けた永田洋子や、連続ピストル射殺事件で死刑執行された永山則夫とも親交があり死刑廃止論者とも一部からは見られたが死刑制度そのものは是認している。一方、脳死による臓器移植には反対している。同時多発テロの報復攻撃に抗議し短期間のハンガーストライキを決行した。
「金を取る宗教は偽物」を自らの持論としている。 平野啓一郎を〝豊潤な才能〟と評し、金原ひとみの『蛇にピアス』を「(谷崎潤一郎の)『刺青』が霞んで見える」と評した。
年譜
(「慎吾」は前衛小説家、小田仁二郎(おだ じんじろう)。「涼太」は3歳年下の実業家)
- 1973年 岩手県平泉町の中尊寺で得度、尼僧となり瀬戸内寂聴に
- 1987年 岩手県浄法寺町(現・二戸市)の天台寺住職に就任
- 1988年 敦賀女子短期大学学長就任
- 1992年 『花に問え』で谷崎潤一郎賞、敦賀女子短期大学学長退任
- 1995年 芸術選奨文部大臣賞(文学部門)※小説『白道』の成果による
- 1997年 文化功労者に選ばれる
- 1998年 NHK放送文化賞受賞。『現代語訳 源氏物語』全20巻完結
- 2000年 徳島県徳島市名誉市民
- 2001年 『場所』により野間文芸賞受賞
- 2002年 徳島県立文学書道館が竣工し、館内に瀬戸内寂聴記念室が設置される。同時に母校の徳島県立高等女学校(現徳島県立城東高等学校)が100周年を迎え、『君の夢に100万円』という奨学金制度に全面的に協力を表明する
- 2005年6月 天台寺の住職を引退
- 2006年2月 オペラ『愛怨』の台本を手がける
- 2006年3月 第73回NHK全国学校音楽コンクール高等学校の部の課題曲『ある真夜中に』を作詞(合唱曲。作曲者は千原英喜)
- 2006年11月 文化勲章を受章
- 2006年12月31日 第57回NHK紅白歌合戦の特別審査員になる
- 2007年3月 延暦寺の直轄寺院「禅光坊」の住職に就任
- 2008年 憲法9条京都の会 結成
主著
- 白い手袋の記憶 朋文社 1957 のち中公文庫
- 花芯 三笠書房 1958 のち文春文庫
- 田村俊子 文芸春秋新社 1961 のち角川文庫、講談社文芸文庫
- 夏の終り 新潮社 1963 のち文庫
- 女徳(高岡智照尼がモデル)新潮社 1963 のち文庫
- 女優 新潮社 1964 のち文春文庫
- 妻たち 新潮社 1965 のち文庫
- かの子撩乱 講談社 1965 のち文庫(解説:上田三四二)
- 輪舞 講談社 1965 のち文庫
- 瀬戸内晴美自選作品 全4巻 雪華社 1966-67
- 美は乱調にあり(大杉栄・伊藤野枝)文芸春秋 1966 のち角川文庫、文春文庫
- 煩悩夢幻(和泉式部)新潮社 1966
- 朝な朝な 講談社 1966 のち文春文庫
- 瀬戸内晴美傑作シリーズ 全5巻 講談社 1967
- 鬼の栖(本郷菊富士ホテル)河出書房 1967 のち角川文庫
- 愛の倫理(エッセイ)青春出版社 1968 のち角川文庫
- 祇園女御 講談社 1968 のち文庫
- 彼女の夫たち 講談社 1968 のち文庫
- あなたにだけ サンケイ新聞社出版局 1968 のち文春文庫
- 妻と女の間 毎日新聞社 1969 のち新潮文庫
- お蝶夫人(三浦環)講談社 1969 のち文庫
- 蘭を焼く 講談社 1969 のち文庫(解説:亀井秀雄)、文芸文庫
- 遠い声(管野スガ)新潮社 1970 のち文庫
- 恐怖の裁判 徳島ラジオ商殺し事件 富士茂子共著 読売新聞社 1971
- 恋川(桐竹紋十郎)毎日新聞社 1971 のち角川文庫
- 純愛 講談社 1971 のち文庫
- ゆきてかえらぬ 文芸春秋 1971 のち文庫
- 輪環 文芸春秋 1971 のち文庫
- 余白の春(金子文子)中央公論社 1972 のち文庫
- 瀬戸内晴美作品集 全8巻 筑摩書房 1972-73
- 京まんだら 講談社 1972 のち文庫
- 瀬戸内晴美長編選集 全13巻 講談社 1973-74
- 中世炎上(後深草院二条)朝日新聞社 1973 のち新潮文庫
- ひとりでも生きられる(エッセイ)青春出版社 1973 のち集英社文庫
- いずこより(自伝小説)筑摩書房 1974 のち新潮文庫
- 色徳 新潮社 1974 のち文庫
- 瀬戸内晴美随筆選集 全6巻 河出書房新社 1975
- 嵯峨野より 講談社 1977 のち文庫
- まどう 新潮社 1978 のち文庫
- 草宴 講談社 1978 のち文庫
- 比叡(純文学書き下ろし特別作品)新潮社 1979 のち文庫
- 嵯峨野日記(随筆)新潮社 1980 のち文庫
- 続瀬戸内晴美長編選集 全5巻 講談社 1981-82
(以後、晴美名義と寂聴名義が混在)
- ブッダと女の物語 寂聴 講談社 1981 のち文庫
- 伝教大師巡礼 寂聴 講談社 1981 のち文庫
- インド夢幻 晴美 朝日新聞社 1982 のち文春文庫
- 私の好きな古典の女たち 晴美 福武書店 1982 のち新潮文庫
- 人なつかしき 晴美 筑摩書房 1983 のち文庫
- 諧調は偽りなり(「美は乱調にあり」続き)晴美 文芸春秋 1984 のち文庫
- ここ過ぎて 北原白秋と三人の妻 晴美 新潮社 1984 のち文庫
- 名作のなかの女たち 前田愛、晴美共著 角川書店 1984 のち文庫、岩波同時代ライブラリー
- 青鞜 晴美 中央公論社 1984 のち文庫
- ぱんたらい 晴美 福武書店 1985 のち文庫
- 瀬戸内寂聴紀行文集 全5巻 平凡社 1985-86
- 愛と命の淵に 寂聴、永田洋子 福武書店 1986 のち「往復書簡」として文庫
- とわずがたり現代語訳・後深草院二条 晴美 新潮文庫 1988
- 女人源氏物語 全5巻 寂聴 小学館 1988-89 のち集英社文庫
- 瀬戸内寂聴伝記小説集成 全4巻 文芸春秋 1989-90
- わが性と生 瀬戸内寂聴、瀬戸内晴美 新潮社 1990 のち文庫
(以後寂聴で統一)
- 『花に問え』中央公論社、1992年、谷崎潤一郎賞 のち文庫
- 寂聴・猛の強く生きる心 梅原猛 講談社 1994 のち文庫
- 愛死 講談社 1994 のち文庫
- 白道(西行)講談社 1995 芸術選奨文部大臣賞 のち文庫
- 『現代語訳源氏物語』全10巻、講談社、1997-98 のち文庫
- つれなかりせばなかなかに 妻をめぐる文豪と詩人の恋の葛藤(谷崎潤一郎・佐藤春夫)中央公論社 1997 のち文庫
- 孤高の人(湯浅芳子)筑摩書房 1997 のち文庫
- 文章修業 水上勉共著 岩波書店 1997 のち光文社知恵の森文庫
- 人生万歳 永六輔共著 岩波書店 1998
- いよよ華やぐ 新潮社 1999 のち文庫
- 『場所』(自伝小説)新潮社、2001年、野間文芸賞受賞 のち文庫
- 瀬戸内寂聴全集 全20巻 新潮社 2001-02(解説・秋山駿)
- 『釈迦』新潮社、2002 のち文庫
- 人生への恋文 石原慎太郎共著 世界文化社 2003 のち文春文庫
- 秘花(世阿弥)新潮社、2007
瀬戸内寂聴を演じた女優
関連項目
- TBS「いのちの響」
