「神農本草経」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
CommonsDelinker (会話 | 投稿記録) Túrelio によってCommonsから削除された Shennong_bencao_jing.jpg を除去。理由: Copyright violation: Copyrighted book cover.. |
m Bot作業依頼: Template:Zh2を廃止、統合 - log |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{wikisourcelang|zh|神農本草經|神農本草経}} |
{{wikisourcelang|zh|神農本草經|神農本草経}} |
||
{{東洋医学}} |
{{東洋医学}} |
||
『'''神農本草経'''』({{ |
『'''神農本草経'''』({{Lang-zh | t=神農本草經| s=神农本草经| p=Shén nóng běn cǎo jīng |w =Shennung Ben Ts'ao King| first=t}} しんのうほんぞうきょう<ref name="gaisetsu">{{Cite book|和書|author=長濱善夫|title=東洋医学概説|year=1961|publisher=[[創元社]]|series=東洋医学選書|isbn=4-422-41301-5|pages=p.38}}</ref><ref name="nyumon">{{Cite book|和書|author=[[日本東洋医学会]]学術教育委員会|title=入門漢方医学|year=2002|month=12|publisher=南江堂|isbn=4-5242-3571-X|pages=p.9}}</ref><ref name="pharm">{{Cite web|date=2007-10-11|url=http://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E7%A5%9E%E8%BE%B2%E6%9C%AC%E8%8D%89%E7%B5%8C|title=薬学用語解説:神農本草経|publisher=[[日本薬学会]]|accessdate=2010-08-20}}</ref>、しんのうほんぞうけい<ref name="nyumon"/><ref name="pharm"/> または {{要出典範囲|しんのうほんぞうぎょう|date=2010年8月}})は、[[後漢]]から[[三国時代 (中国)|三国]]の頃に成立した[[中国]]の[[本草学|本草]]書である{{Efn|紀元5年ころという説もある<ref>{{Cite book|和書|author=山田慶児|year=1923|title=中国医学の思想的風土|publisher=潮出版社|pages=P.42}}</ref>。}}。 |
||
== 概要 == |
== 概要 == |
||
2021年9月28日 (火) 09:21時点における版
| 中国医学-漢方医学-韓医学/高麗医学 |
| 東洋医学 |
|---|
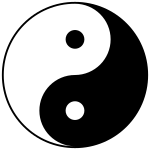 |
| 理論 |
| 古典 |
| 証 |
| 内治法 |
| 外治法 |
| 薬剤 |
|
|
『神農本草経』(繁体字: 神農本草經; 簡体字: 神农本草经; 拼音: Shén nóng běn cǎo jīng; ウェード式: Shennung Ben Ts'ao King しんのうほんぞうきょう[1][2][3]、しんのうほんぞうけい[2][3] または しんのうほんぞうぎょう[要出典])は、後漢から三国の頃に成立した中国の本草書である[注釈 1]。
概要
『神農本草経』は神農氏の後人の作とされるが、実際の撰者は不詳である。個々の生薬(漢方薬)について解説したもの。中国最古の薬物学書であるとされる[5]。365種の薬物を上品・中品・下品(上薬・中薬・下薬ともいう)の三品に分類して記述している。上品は無毒で長期服用が可能な養命薬、中品は毒にもなり得る養性薬、下品は毒が強く長期服用が不可能な治病薬としている[3][6]。
500年(永元2年)、南朝の陶弘景は本書を底本に『神農本草経注』3巻を撰し、さらに『本草経集注』7巻を撰した。陶弘景は内容を730種余りの薬物に増広(ぞうこう)している。
こうして中国正統の本草書の位置を占めるようになったが、現在みることができるのは敦煌写本の残巻や『太平御覧』への引用などにすぎない。
その復元を図ったものとしては、明代の盧復、清朝の孫星衍、日本の森立之によるものなどがある。
注釈
脚注
- ^ 長濱善夫『東洋医学概説』創元社〈東洋医学選書〉、1961年、p.38頁。ISBN 4-422-41301-5。
- ^ a b 日本東洋医学会学術教育委員会『入門漢方医学』南江堂、2002年12月、p.9頁。ISBN 4-5242-3571-X。
- ^ a b c “薬学用語解説:神農本草経”. 日本薬学会 (2007年10月11日). 2010年8月20日閲覧。
- ^ 山田慶児『中国医学の思想的風土』潮出版社、1923年、P.42頁。
- ^ 小曽戸洋『新版 漢方の歴史――中国・日本の伝統医学――』大修館書店〈あじあブックス076〉(原著2018年10月1日)、43頁。ISBN 9784469233162。
- ^ 大塚敬節『漢方医学』(第3版)創元社〈創元医学新書〉、1990年2月1日(原著1956年7月25日)、p.p.38-39頁。ISBN 4-422-41110-1。
