利用者‐会話:Alex K/土倉壱
ウィキペディアにようこそ!
[編集]こんにちは、Alex Kさん、はじめまして!Suisuiと申します。ウィキペディアへようこそ!
- ウィキペディアで活動する際にはガイドブックを是非ご一読ください。きっとご参考になるものと思います。
- よろしければ自己紹介してみてください。
- お隣の利用者ページは、ご自身の自己紹介の他、作業用のスペースなどとして利用することができます。
- 執筆の際には中立的な観点および著作権にご留意ください。
- 何か疑問点がありましたらWikipedia:井戸端で質問することができます。
あなたが実り多き活動をされることを楽しみにしております。--Suisui 2006年10月12日 (木) 17:18 (UTC)
こちらこそ
[編集]こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。私も自分の勉強不足のためと、日本で入手できる資料の限界のため、数々の間違いや勘違いを書いていることもあると思いますので、お気づきの点がございましたらどうかご指摘下さい。また、わからないことを質問させていただくこともあるかもしれません。どうぞよろしくお願い致します。--ПРУСАКИН 2006年12月23日 (土) 00:45 (UTC)
ウクライナ語の「Г」について
[編集]日本語では、原則として「ハ行」で表すのがよいと思われますし、ウクライナ語を真面目にウクライナ語として書いている日本の文書では実際に「ハ行」で書き表されています。ロシア語のように「ガ行」で表すこともありますが、日本語では「ハ行」(h)と「ガ行」(g)の発音はまったく別の発音だと考えられていますので、ウクライナ語の発音を重視すればやはり「ハ行」で表す方がよいでしょう。例えば、「ボフダン」と「ボグダン」とでは、ウクライナ語話者にとっては両者は同じような発音に感じられるのかもしれませんが、日本語母語話者はまさか両者が同じものを指しているのだとは気付きません。日本語母語話者の耳には、ウクライナ語の「Г」の音は「ガ行」ではなく「ハ行」に聞こえるので、「ガ行」で書くのには違和感があります(ウクライナ語名ではなくロシア語名として書いているのだと感じられます)。
日本語では「Ф」(f)やこれに近い発音は存在しませんので、「Г」(h)と「Ф」(f)とが区別できなくなってしまうのは仕方のないことでしょう。「フ」を「fu」と書くことはありますが、これは便宜的な表記であって実際の発音は空気を吹き出すだけの「фu」です(日本語学的には、「フ」は「fu」ではなく「hu」で表記すべきだとされています)。従って、おかしいということを指摘するのならばむしろ「Ф」(f)を「フ」で転写することの方がよりおかしいのであって、比較的「フ」に発音イメージが近い「Г」(h)を「フ」と転写するのは却って構わないと思います。困るのは「ги」(hy)のような例でして、機械的に「フ + ウィ」で「フィ」と書いてしまうとあたかも「fi」であるかの如くなってしまうのです。もし「フィ」と書いてあった場合、たとえウクライナ語を知っている日本語話者が見たとしても「hy」と読むことはできず、「fi」だと思ってしまいます。これには本当に困ったものですが、「フイ」と書くなどしてごまかすしかないと思います。
すでにご存知かもしれませんが、日本語の「ハ行」には言語学的にはまったく異なる3つの発音が混在してしまっているのが現状です(昔は違いましたが)。ひとつは「h」の発音で、「ハ・ヘ・ホ」で、ウクライナ語の「га・ге・го」に比較的近い音です。二つ目は「[ç]」の発音で、「ヒ」がこの発音をします。それに加えて、「ヒャ・ヒュ・ヒェ・ヒョ」も同様の発音が用いられます。三つ目は、「[ɸ]」で、「フ」がこの発音をします。日本語では、「ファ・フィ・フェ・フォ」も「fa・fi・fe・fo」とは発音されずにこの発音になります(従って、厳密に言えばウクライナ語で「ф」を用いる音はすべて日本語では正しく表記することはできません)。発音に関して、詳しくは各文字のリンク先をご参照下さい。ただし、私もこの程度の知識しかなく、多くの日本語話者はリンク先のページあるような詳しい説明は知らずに話しています。
こうしたことからご推察いただけるように、日本語で適切な転写となることが期待できるのは一つ目の発音に適合する「га・ге・го」だけで、それ以外のウクライナ語の「г」を用いる発音は完全には適切に表現することができません。従って、ある程度の妥協が必要になりますが、日本語話者には「ハ行」がもっとも近い発音であると感じられるので、原則「ハ行」とするのが最善の策ではないでしょうか。不都合も生じますが、それはそのときに考える、という方針以上に良い考えがないように思います。前述の通り、「ガ行」では日本語話者にはウクライナ語として感じることができなくなってしまいますので。
ひとつ付け加えると、すでに「ху」と「Фу」も区別なく「フ」と書かれることは定着してしまっているので、もうひとつ区別できない「гу」が加わってもどうせおなじことという気もします。これら3つは日本語では区別して書くことはできません。さらに言えば、母音なしの「х」や「ф」も「フ」としか書けませんしね。
やや説明がくどくなってしまいましたが、失礼しました。またご質問下さい。--ПРУСАКИН 2006年12月23日 (土) 17:56 (UTC)
セルデューク拝見いたしました。ところで、ウクライナ語の発音を日本語に移すと「セルヂューク」が最も近く、ただ現代日本語では「ヂ」はあまり使わないので「セルジューク」とするのが適当であると思われます。英語読みのようなセルデュークでページ名を決定したのは何ゆえでしょうか?--ПРУСАКИН 2006年12月25日 (月) 17:03 (UTC)
ウクライナ語の「dyu」は日本語では「ヂュ」もしくは「ジュ」となります。日本語では「ju・dyu・diu・zhu」は区別なく「ジュ」とかかれます。フランス語や英語の転写として用いられる「デュ」とウクライナ語の「ヂュ(ジュ)」は発音がまったく異なるので、フランス語や英語のような「デュ」をウクライナ語に用いるのは好ましくないと思います。セルジューク朝との混同は{{otheruses}}や曖昧さ回避で解決できます。--ПРУСАКИН 2006年12月26日 (火) 11:23 (UTC)
「フランス語や英語のような「デュ」をウクライナ語に用いるのは好ましくない」とはなぜでしょう。ウクライナ語話者から見ると、フランス語と英語の「デュ」はウクライナ語の「dyu」と同様な音である。ロシア語のやわらかい「dyu」は確かに日本語の「ジュ」に近いかもしれません。しかし、ウクライナ語とロシア語の発音では多少の違いがあるので、それを日本語ではっきり示さなければならないと思います。
又、「日本語では「ju・dyu・diu・zhu」は区別なく「ジュ」とかかれます」という異見にも賛成できません。日本語ではそういう区別がなければ、「デュ」という音も発生しなかったのでしょう。戦前の日本語ではteaも「チー」と書いていたが、戦後は「ティー」と書くようになったのです。それは、日本語はだんだん外国語の発音に適応していく証である、と考えざるを得ないでしょう。ですから、外国語の発音をもっと忠実に伝えられる表記があったら、古い表記にこだわる必要はないと思います。
Templateで曖昧さ回避で解決できるとわかっておりますが、「セルデューク」(Serdyuk)と「セルジューク」(Seljuq)にはかなりの発音の違いがありますので、一緒にするのはよくないという視点からそのtemplateを使用しなかったのです。--Alex K 2006年12月26日 (火) 11:52 (UTC)
いや、早い話が日本語ではどちらも「セルジューク」になりますので(コサックのほうのSerdyukも普通はセルデュークではなくセルジュークと転写されます)、テンプレートは適当かと思います。--ПРУСАКИН 2006年12月26日 (火) 13:02 (UTC)
- 補足)日本語の「デュ」をウクライナ語の表記で表すことは難しいと思いますが、少なくとも「дю」ではありません。無理に表そうとすれば、「д'ю」とか「дею」などという表記・発音がもっともイメージに近いところでしょうか。いや、無理ですね。
- また、日本語では「dyu」と「ju」の発音の違いより「ジュ」と「デュ」の発音の違いの方が重視されるようです。「dyu」と「ju」の発音を書き分けたければそれぞれ「ヂュ」、「ジュ」となります。「ヂュ」と「デュ」もまた全然別の発音なので混同されることはありません。なお、日本語では旧来より「じゅ」、「ぢゅ」という発音はありましたが、「デュ」という発音・表記は近代になってフランス語や英語の転写が必要になってきてから現れた、日本語固有ではない発音だと考えられます。「дю」に最も近い表記として「ヂュ」は用いられることはありますが、「ヂ」という表記は現代ではあまり使われないため、「ヂュ」のかわりに「ジュ」と書くことが多いようです。
- 従って、「Сердюк」の発音転写としては、結果として「Seljuq」と同じになってしまいますが、「セルジューク」が最も無難かつ適当なところかと思われます。日本語では「seljuq」も「serdyuk」も、あるいはもし「Seluzhuuku」だったとしても、表記上の区別する機能がないので書き分けられないのは仕方がありません。日本語では、残念ながらどれでも「セルジューク」になってしまうのです。がんばって「セルデューク」という表記を考えてみても、この表記を日本語話者が読んだ場合より一層「Сердюк」という発音からは遠ざかってしまうので、努力が却って仇になってしまいます。--ПРУСАКИН 2006年12月26日 (火) 14:16 (UTC)
まったく賛成できません。10人の日本人の友達にウクライナ語の「Сердюк」を言って日本語で表記するように頼んだところ、みんなが、「セルデューク」と書きました。「セルジューク」と書いた人は一人もいなかったのです。現代の日本人はちゃんと(ju)と(dyu)という音を分けているらしいからです。ロシア語の教科書では(dyu)を「ジュ」として転写すべきと記されているかも知れませんが、そのような転写のしかたは戦前の英語の転写のしかたと同様なもで、現代において不適当であると思います。--Alex K 2006年12月27日 (水) 08:39 (UTC)
- おかしいですね。「дю」は「ヂュ」であって「デュ」ではありませんよ。
多分ウクライナ語を勉強して日本語を勉強しなかった日本人なのではないでしょうか?(←これは本当に冗談です。)昔の日本語の発音を流用して表記すれば「ヂュ」が正しいが、現代日本語では「ヂ」は「ジ」と書き慣わしているので「ジュ」となるということです。「ju」と「dyu」の書き分けというよりは単に日本語の正書法(とは普通言わないがそのようなもの)の問題です。 - ひとつ言うと、日本で販売されている唯一のウクライナ語教科書はウクライナ語の発音をかなりおかしくカタカナ転写しているので、恐らくその影響ではないでしょうか?(「и」も「і」も「ї」も全部「イ」と書くし、「ти」も「ті」も「ティ」と書くというのは、他のスラヴ語の転写と比較してかなり異端。)知っておいた方がよいと思いますが、日本語の「デュ」とウクライナ語の「дю」は残念ながらまったく別の発音です。--ПРУСАКИН 2006年12月27日 (水) 16:43 (UTC)
- ところで、ウクライナ語等スラヴ系の「дю(dyu)」「дзю(dzyu)」「джу(dzhu)」「жу(zhu)」「зю(zyu)」等と日本語の「じゅ(ju)」「ぢゅ(dyuまたはju)」「デュ(ローマ字不明)」、フランス語の「デュ(du)」「デュー(dieu)」などの書き分けについてはどうお考えですか?--ПРУСАКИН 2006年12月27日 (水) 17:13 (UTC)
- 「多分ウクライナ語を勉強して日本語を勉強しなかった日本人なのではないでしょうか?」と書いたのは、本当にまったくの冗談です。どうかお気を悪くなさらないで下さい。たいへん失礼なことを書いてしまいました。あなたと、あなたのお友達がこれで不快な思いをされるとすれば、たいへん申し訳なく思います。昨日は忘年会等で2ℓほどアルコール飲料をいただき、本人は正気のつもりでしたが多分少し酔っ払って気が大きくなっていたのではないかと思います。どうかお許し下さい。
- どうしても7時4分のバスに乗らねばならぬため、今日は取り急ぎこれだけにて失礼致します。--ПРУСАКИН 2006年12月27日 (水) 21:58 (UTC)
私は少しも怒っていません。友達の事を冗談だとお書きなったのだから、平気で見逃しました。心配は無用でございます。しかし、やっぱり、私は、「セルデューク」という転写の方が正しいと思います。--Alex K 2007年1月3日 (水) 15:59 (UTC)
- お怒りでないとのこと、ありがたく存じます。ああ、よかった。
- 「セルデューク」に関してですが、「дю」は軟音ですよね?となると、日本語では「D」の軟音は「ヂ」または「ジ」で表すことになっていますから、「дю」も「ヂュ」または「ジュ」となります。これは、ウクライナ語に関して個別にどうという問題ではなく、飽くまで日本語の表記上のルール(傾向)の問題で、「D」の軟音は「ヂ」または「ジ」で表すという原則に則ったものです。(従って、ウクライナ語の「дю」が軟音でないのならば話はまた別です。)
- なお、旧い新しいの問題で言えば、日本で発売されているウクライナ語の教科書はソ連時代のもので、ご覧になるとおわかりになると思いますが、なんとその本の中ではまだウクライナは独立していません!古いといえば、どう考えても他のスラヴ系言語の教材・書籍よりこちらの方が古いのではないかと思いますが……。--ПРУСАКИН 2007年1月4日 (木) 10:20 (UTC)
- 調べていたのですが、なんてことはない、初めから辞書を見るべきでした。この場合「デュ」と表記するのは英語式だそうです。フツウにウクライナ語・英語辞書に書いてありました(^-^;)))--ПРУСАКИН 2007年6月28日 (木) 11:07 (UTC)
すみません。日本語で失礼します。本来ならウクライナ語版に書かなければならないのですがウクライナ語がまったく書けませんので日本語で失礼します。ウクライナ語版にあるuk:Зображення:Yamato.pngを参考にしてimage:yamato.pngとimage:yamato en.pngを作成しました。本来なら本人に許諾をいただかなければいけないものを勝手に作成しました。大和時代の勢力図が大和時代の説明でわかりやすかったので勝手に翻訳して作成してしまいました。Alex Kさんが削除を希望するのであるならば削除申請しますがいかがいたしましょうか?--Forestfarmer 2007年1月1日 (月) 06:22 (UTC)
作成して頂いた画像を削除する必要はないと思います。(ところで、image:yamato.pngは私の図と関係無いようです。)その画像は読者に役に立てばそれでいいでしょう。Forestfarmerさんの図は私の画像そのものではないから、私の許可がなくても自由に利用できるのだと思います。--Alex K 2007年1月3日 (水) 16:08 (UTC)
- 日本語版はimage:yamato_ja.pngでした。ありがとうございます。早速GFDLにさせていただきます。年始早々失礼しました。--Forestfarmer 2007年1月4日 (木) 03:09 (UTC)
Гетьман
[編集]いつもお世話になっております。質問があるのですが、「Гетьман」の力点(アクセント)はどこにあるのでしょうか。図書館にあるウクライナ語・英語辞書では「Ге́тьма́н」となっていました。そのため、ウィキペディアのページ名も「ヘーチマーン」となっております。一方、私の持っているウクライナ語・日本語辞書やウクライナ語・ロシア語辞書では「Ге́тьман」となっています。ウィキペディアのカテゴリー名も「ヘーチマン」となっています。どちらがより正しいのでしょうか。それともどちらでも構わないのでしょうか。ご教授下さい。--ПРУСАКИН 2007年1月4日 (木) 12:52 (UTC)
御質問有難う御座います。ウクライナ国語辞典[1]によると、"Гетьман" という用語には二つの発音があります。普段は「ヘーチマン」と発音しますが、詩作においては「ヘチマーン」という発音することもあります。[2]。「ヘーチマーン」とう発音は全く無いようです。--Alex K 2007年1月5日 (金) 01:34 (UTC)
ありがとうございました。英語の辞書は間違っているんでしょうかね?不思議です。今後は、ウィキペディアでは「ヘーチマン」で行くことにしましょう(あえて詩的にしてもいいですが、その必要はないでしょう)。なお、称号の扱いですが、ヘーチマンはやはり人名のあとに来るようです。理由はわかりませんが、逆に言うと人名の前に持ってこなければ理由も全くないので、あとでよいでしょう。私のノートをご参照下さい(結局よくわからんとか書いてあってなんですが)。--ПРУСАКИН 2007年1月6日 (土) 15:50 (UTC)
ボルシチ
[編集]すみません。また質問があります。ボルシチですが、ウクライナ料理なのでしょうか。最近の編集でボルシチはウクライナ料理ではないということになってしまったのですが、どうなんでしょうか。--ПРУСАКИН 2007年1月31日 (水) 06:03 (UTC)
それは何かの間違いでしょう。ボルシチは元々ウクライナの料理です。しかし、その料理は、ウクライナを長年に支配してきたリトアニア・ポーランド・ロシアなどの国の料理においても使用されているのです。また、ボルシチはウクライナと結びつきが強い東ヨーロッパのユダヤ人の料理においても作られています。まあ、国際化のオカゲで「料理の起源」は少しつつ分からなくなっていくのでしょう・・・--Alex K 2007年2月1日 (木) 10:24 (UTC)
一般的に日本では、「××の起源は、××だ」という民族は非常に嫌われます。東欧・中欧で一般に食されている料理を特定の国の料理として良いのでしょうか?ポーランド語版pl:Barszcz (potrawa)では、ポーランド料理とされ、他国の実情については書かれていません。だからといって、日本語版で他国のことを排除して、ポーランド料理のみとして良いのでしょうか?遠い欧州の民族対立を日本に持ち込まないで欲しい。--元諜報員 2007年2月1日 (木) 21:16 (UTC)
1. 元諜報員さん、そんなに感情的にならないでほしい。落ち着いてください。だれが、どこで「遠い欧州の民族対立を日本に持ち込」んでいるのでしょう?あなたが見たいことだけを見、読みとりたいことだけを読みとっているのではありませんか?勝手に私がかいたことを解釈しないでください。
2.ボルシチ料理の起源はウクライナにあるのはしょうがない。それは事実である。他国ではボルシチが食べられている事は、昔からウクライナという地域と交流が盛んであるからです。だから、「ボルシチの起源は、ウクライナだ」という言い方はおかしくないと思います。たとえば、スシも世界中で食べられているが、「スシの起源は、日本だ」(「××の起源は、××だ」)といってもおかしくはないでしょう。
3.「一般的に日本では、「××の起源は、××だ」という民族は非常に嫌われます。」というフレーズが嗤笑です。おそらく、あなたは日本の事を余り知らないのでしょう。もっと勉強してください。日本料理の起源についても…--Alex K 2007年2月2日 (金) 08:42 (UTC)
- 毎度、いろいろなところでお世話になっております。問題提起だけして休業してしまい無責任この上ないことでした。どうぞお許し下さい。さて、ボルシチの件ですが、できれば「いつ・どこで・(誰が)」作り出した(と言われている)のか、書き加えることは不可能でしょうか。
- 例えば、「ウクライナ・ベラルーシの民族料理である」というのはたいへん尤もらしいのですが、ウクライナ・ベラルーシと言っても広大な土地なので、たとえばリヴィウで始められたのかオデッサで始められたのかミンスクで始められたのかではえらい違いがあります。もし、実際「ウクライナ・ベラルーシ発祥の料理である」ならば、どこの町・地方で始められたと考えられているのか、説明可能なはずです。
- また、それと同様に「いつ頃」からボルシチがあったとされているのか、これも説明可能なはずです。例えば、ウクライナがポーランド王国領であった時代にウクライナで作られたのであれば、ポーランド人が「ボルシチはポーランドで作られた」と言っても納得がいきます。たんに「昔から伝統的にウクライナ人は食べていた」では説得力がありません。私もウクライナ人は昔からボルシチ食べてたんだろうなあとは思うのですが、いかんせん10年前も「昔」ですし、10万年前も「昔」です。
- もしこうしたより細かな情報を書き加えていただけると、編集競合も避けることができますし、情報も充実したいへん有益かと存じます。
- 一般的に日本では、「××の起源は、××だ」という民族は非常に嫌われますというのは、何のことを言っているのか私もよくわかりませんが、というか日本人自身がしばしば「きしめんの起源は名古屋だ」とかいう類のことを言ったりするので、それでは一般に日本では、「××の起源は、××だ」という民族は非常に嫌われると言って自己嫌悪に陥っているという結論になってしまい、ますます意味と目的がわからなくなりますが、まあそれはそれでそういうこともあるとして、兎にも角にも「××の起源は、××だ」ということを言うためにはそれなりの根拠付け(データ)が必要、ということでしょう。また、削除されたようですが、元諜報員さんの書かれた「ボルシチは日本では一般にロシア料理だと思われている」というのも列記とした事実です(とはいえ、アンケート調査をやったわけではないので、飽くまで世間常識の感覚的な「事実」としか言えませんが)。こうした誤った言説を打ち破るためにも、「ボルシチはウクライナ・ベラルーシ発祥である」という根拠となるデータが必要です。
- 東欧・中欧で一般に食されている料理を特定の国の料理として良いのでしょうか?については、それ自体は私も同感なのですが、ただこれは元諜報員さんが議題を取り違えていらっしゃるようで、私が申したかったのは「もともとどこから出てきた料理なのか」ということなのです。今は世界中で食べられているのは誰でも知っていることですし(日本でも売ってます)、それを否定なさるつもりはあなたにも他の誰にもないはずです。
- むしろ、例えば現代寿司が世界中で食べられているからといって、これを日本料理ではないと定義付ける専門家や、寿司は世界中で食べられているのだから寿司を日本料理とするのは不適切だと唱える専門家がどこにいるでしょうか。しかし、これは寿司が明らかに日本料理であるから言えるのであって、現状のウィキペディアのボルシチの項では「ボルシチはウクライナ・ベラルーシ発祥の料理である」と有無を言わせず納得させる具体的なデータ(発祥はいつ・どの地方・町でか)が欠けています。
- ローマ発祥説については、それはそれで書いておいてもよいのではないでしょうか。そういう説もあると。ローマ発祥説、ウクライナ・ベラルーシ説、中東欧一般説、どれが尤もらしく読者に訴えかけることができるか、それは執筆者の努力次第です。
- 一番安全な書き方は、「ウクライナでは~~~と考えられている。」「ポーランドでは~~~と考えられている。」云々と、条件を限定して述べるやり方ですが、それではご不満かもしれません。
- 少々おしゃべりが過ぎましたが、お許し下さい。今後ともよろしくお願い致します。--ПРУСАКИН 2007年5月6日 (日) 13:01 (UTC)
•ボルシチの発祥地については今のところ詳しい情報はございません。ローマ起源説はあくまでも戯言でございじましょう。さような「豚でもない」噂はウクライナ・ポーランドの「学者」のあいだに人気意があることは事実です。しかし、その説は根拠興がまったくないのです。古代ギリシア・ローマ文明にあこがれている現代のウクライナ人・ポーランド人のただの「お話」にすぎません。ローマの料理関係の文献では「ボルシチ」は登場しておりません。
•寿司は日本料理であると国内で主張しているが、韓国ではそれは韓国料理だというふに紹介されていることもある(海苔巻きなど)。ですから、「ボルシチ・寿司はわれわれのものだ」と言出したら、絶対に隣の国ではそれを否定し、「いや、われわれのものだ」と強調しはじめるのでしょう。ボルシチの歴史を具体的に研究した人類学者はほとんどいないと思います。存在しているのはただの言語学的空論のみ。ですからボルシチはいづれ・いづこに現れたかということについては具体的な答えはないのです。--![]() Alex K 2007年5月7日 (月) 07:53 (UTC)
Alex K 2007年5月7日 (月) 07:53 (UTC)
- なるほど、起源に関する詳しい情報はないのですか。それは残念です。研究者がいないのならば仕方がありません。
- 私もローマ起源説はそのようなことだろうと思いましたが(きっとコサックのエネイが持ってきたのさ)、そういう「お話」も本文内で紹介するとおもしろいと思います。もし各国でこの種の発祥物語があるとしたら、それこそページ内で紹介すべき情報です。
- 韓国も、というか魚をとって食べている国ならばどこでもそうだと思いますが、「寿司」みたいなものがあるのはまったく不思議ではありません。ただ、韓国ではそれを「寿司」と名付けなかっただけです。名前が違えば似ていても別物です。ボルシチは、各国で同じ名前で呼ばれているので問題なのです。--ПРУСАКИН 2007年5月7日 (月) 15:39 (UTC)
トルィズブの件
[編集]トルィズーベツィは「ウクライナ語では余り使われておりません。」とのことですが、使っている人がいるのは紛れもない事実ですから、消すには及ばないでしょう。以前これはなんというのだと聞いたところ「トルィズーベツィだ」と私に教えたのはウクライナ人です。こちらにも一応載ってます。
すみません、「長音記号はアクセントの位置には決めておりません。トルィズーブとトルィーズブも使用可能」は仰る意味がわかりません。わからないので一般論として書きますが、ウクライナ語では「トルィズーブ」とも「トルィーズブ」とも発音するのでしょうか。こちらでは「トルィズーブ」しか書いてありません。文章の意味がわからないというのは「長音記号はアクセントの位置には決めておりません。」の部分なのですが、この文章だと『「決めておりません」というからには主語があるはずですが、誰が決めてないんでしょうか?』ということになってしまいますよ!すみません、単純に文章の意味がわかりかねます。言い直してみていただけますか?--ПРУСАКИН 2007年5月11日 (金) 14:34 (UTC)
アクセントの位置は決めておりませんと書こうと思っていましたが。。。すみません。ご指摘ありがとう御座います。今度気をつけます。
1)確かに、トルィズーベツィはウクライナ語では存在しておりますが、ウクライナの国章の場合は、主にトルィズーブしか使われておりません。
2)略しようと思ったらやっぱりだめでした。。。。ウクライナ語では「トルィズーブ」は正しいとされておりますが、たまに「トルィーズブ」というふうに発音することもあります。後者は間違いであるが、口語ではしばしば使います。
たとえば、日本人の会話では「もうしわけありません」とよく聞きますが、それは日本語からみる間違いであり、正しい言い方は「もうしわけない」、「もうしわけなく思います」。つまり、間違いとされている言い方はだんだん会話の規則となっていくのです。
考えて見れば、日本の言葉においても方言によってアクセントが異なっておりますね。--![]() Alex K 2007年5月11日 (金) 16:12 (UTC)
Alex K 2007年5月11日 (金) 16:12 (UTC)
- 仰っている意味がわかりました!よかったよかった!
- つまり、「(ウクライナ人は)アクセントの位置は決めておりません」ということですね。日本語では、この場合「受身文」にして「アクセントの位置は決められていません」と言った方が意味が通じ易くなります。逆に、ウクライナ語では「アクセントの位置は決めておりません」という言い方の方が普通なのでしょうね。勉強になりました。もし、この場合日本語で「能動文」で書きたい場合には、「決めていない」動作主となる「(ウクライナ人は)」をきちんと書いておかないと、ちょっと混乱して文章の意味がわかりにくくなります。
- さて、本題ですが;
- 1) 確かに「トルィズーブ」が正式であるというのはわかります。一方、ウクライナの国章を表す口語もしくは通称・俗称として「トルィズーベツィ」が用いられることはないのでしょうか。
- 2) 後者は間違いであるが、口語ではしばしば使います。→もしページ内に「トルィーズブ」を復活させるとしたら、この旨書き添える必要があります。私は知りませんでした。少し物知りになりました。
- 3) 「もうしわけありません」ですが、これは多分「申し訳がありません」、若しくは「申し訳のしようもありません」の略であり、「申し訳がない」、「申し訳がなく思います」で文章が略されているのと同じ現象です。「が」を省略するのは日本語として間違いではない(昔はあまり書かなかった、その名残)と思いますが、もし仮に「もうしわけありません」が間違いだとすれば他のすべてが違いですし、正しいといえばすべて正しいと思います。
- 4) 日本語では方言によってイントネーション、発音、語彙、アクセントが大きく異なり、下手をすると話が通じないくらいです。私は父が西の方の出身であるため西日本の日本語には違和感がないのですが、東北・北海道の日本語はウクライナ語みたいに聞こえます(笑)職業柄、東北や北海道出身の人と話す機会が多いのですが、相手が正真正銘の「日本語」を話しているのにも拘らず単語を拾うのにも苦労して結局何言っていたのかわからなかった、ということはしょっちゅうです。以前、高校の頃、初めて青森に行ったときに列車の中で同年代の女の子の話しているのを聞いていて、何を話していたのかまったくわからなかったときにはある種カルチャーショックを受けました。まあ、これでは困るから明治初期に「共通語」なるものを制定したのですけどね。ウクライナ語の方言については、ウクライナ語辺りで解説していただけるととても勉強になるのですが……。--ПРУСАКИН 2007年5月11日 (金) 16:48 (UTC)
コメントありがとうございます。
- 1)「トルィズーベツィ」は口語で用いられることはあるが、一般的ではありません。おそらく、その言葉はロシア語の「トレズーベツ」に近いので、ウクライナ人に嫌われているかも知れません。普段は「トルィーズブ」をいう人が多いといえる。
- 3) 「もうしわけありません」ということば2つの方法で捉えることができると思います。日本国語大辞典によれば「申訳がない」と「申訳がない」という二つのことがあります。後者は「あぶない」のような形容詞で口語では用いられます。形容詞の場合は、「申し訳御座いません」と間違いであります。
- 4)ウクライナ語も同じくアクセントやイントネーションなどはばらばらです。自分はキイフ出身なので、できる範囲でウクライナ語の方言については教えてあげましょう。しかし、その分野ではあまり詳しくないのです。--
 Alex K 2007年5月12日 (土) 10:09 (UTC)
Alex K 2007年5月12日 (土) 10:09 (UTC)
- いつもありがとうございます。取り急ぎ1点のみ;
- 1)わかりました。その上で提案ですが、本文には「トルィズーブ」について「口語ではしばしば「トルィーズブ」と呼ばれる。また、「トルィズーベツィ」という名も使われることがあるが、ロシア語の「トリズーベツ」からの影響が指摘されており、ウクライナ語としてはあまり使われないとされる。」等の解説を入れてもよいのではないでしょうか。例えば、ウクライナに行って「トルィーズブ」や「トリズーベツ」などの単語を聞いてきた人がこのページで勉強しようと思った際に、こうした説明がないと困惑する可能性があります。もし、ウクライナ人の方から見てこうした説明は妥当だと(あって害になるものではないと)判断していただけるようでしたら、入れておきたいと思うのですが。いかがでしょうか。--ПРУСАКИН 2007年5月13日 (日) 20:31 (UTC)
「トリズーベツ」はかならずしもロシア語の影響を受けているということではないと思います。もともとはウクライナ語には存在する単語です。たとえば、ウクライナ語ではポセイドンのドウグのことを「トリズーベツ」であるのです。ただ、国章の場合は「トリズーベツ」あまり用いられていません。国章は普通の「トリズーベツ」とは違うもんだ意識が働いているかもしれません。--![]() Alex K 2007年5月17日 (木) 18:11 (UTC)
Alex K 2007年5月17日 (木) 18:11 (UTC)
- そうですよね。ウクライナ語ですよね。では、関連項目として「トルィズーベツィ」について触れる必要があるでしょう。つまり、あの三叉の鉾型の図形は(国章に限定しなければ)「トルィズーベツィ」とも「トルィズーブ(トルィーズブ)」とも呼ばれる可能性があるわけですよね?であれば、一種の「曖昧さ回避」的な案内が必要です。
- 「トルィズーブ」という単語はウクライナの国章の名前ですから、本文内で解説する必要があります。そして、ウクライナの国章の名前が「トルィズーブ」であることを知っている人はいますから(少ない?)、それにも配慮しなければなりません。「ウクライナの国章は「トルィズーブ」と呼ばれる。これが正式な名称であるが、口語では「トルィーズブ」と呼ばれることもある。一方、これと同じ形の図形を指す「トルィズーベツィ」という名称は、国章についてはあまり使用されない。」という感じの説明ではいかがでしょうか。無難なところではこんな感じかと思うのですが、「国章は普通の「トリズーベツ」とは違うもんだ」というのはなるほどと思うのですが、実際これが理由で単語が使い分けられているという確証がないとちょっと本分には記載しづらいですね。どうでしょうか。--ПРУСАКИН 2007年5月18日 (金) 12:15 (UTC)
そのコメントを記事につけてもいいいと思います。「トルィズーブ」はヴォロデーメル1世の独自の「トルィズーベツィ」だという意味かも知れません。ですから、国章のことを「トルィズーブ」しかいわないのです。--![]() Alex K 2007年5月18日 (金) 18:53 (UTC)
Alex K 2007年5月18日 (金) 18:53 (UTC)
- では、OKをいただけましたので上の太字の部分を調整して本文へ反映させてみました。安直に脚注にしてしまいましたが、本文を崩すことなく挿入できたのでまあよいかなと思います。ところで、もしよければ、ここでの話し合いを丸々ノート:ウクライナの国章へコピーしておいてはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。(途中でお寿司の話とが混じってますが(笑))ご同意いただければコピーしておいた方がのちのち都合がよいかと思います。--ПРУСАКИН 2007年5月18日 (金) 19:12 (UTC)
いいですよ。かまいませんよ(笑)。
:私の下手な日本語で書かれた論文を御修正くだっさること、ありがたく思います。今後もよろしくお願いいたします。--![]() Alex K 2007年5月18日 (金) 19:18 (UTC)
Alex K 2007年5月18日 (金) 19:18 (UTC)
こちらこそいつもありがとうございます。
ご承諾が得られましたので、コピーしておきました。寿司の話はボルシチのところでしたね(笑)よかったよかった。--ПРУСАКИН 2007年5月18日 (金) 19:25 (UTC)
新しい質問です。
[編集]トルィズブとはまったく別件ですが、また質問があります。たびたびすみません。いろいろ教えていただいて、ついご好意に甘えてしまいます。あまりに頼りすぎてお気を悪くされないかちょっと心配です。
実に恐縮ですが、これはロシア語の合成語で、ある油槽船の名称なのですが、「Азнефть」、「Грознефть」のアクセント位置は第一音節にあるのでしょうか、第二音節にあるのでしょうか、どちらだと思われますか?1年半くらい調べているのですがわからず、また他に聞ける人もおらず、また私などはロシア語やウクライナ語の音感は感覚的にわからないため困っています。ウクライナ語ではなくよりによってロシア語ですが、もしよかったらアドバイスを下さい。ウクライナ語だと「ネフチ」でなくて「ナフタ」だそうですので(少し日本語に近いですね。日本語でも「ナフタ○○」などというものがある)少し勝手が違うかもしれませんが、少なくともAlex Kさんのほうが私よりロシア語が感覚的にわかると思いますので……。意味は、「アゼルバイジャン石油」と「(チェチェンの?)グローズヌィイ石油」だと思います。ずっと「アゾフ石油」だと思っていたのですが、「アゼルバイジャン」のようです。特殊な合成語なので読みが不明なのかもしれませんが、項目名に関わることなので、「このつづりを見てウクライナ人だったら普通どう読むか」程度のアドバイスだけでもよいので助けていただけるとありがたいです。日本人には、知らないロシア語やウクライナ語の単語を見て正しく読むことは実に至難の業なのです。知らない漢字はきちんと読めなくても感覚的にわかるのですが……。--ПРУСАКИН 2007年5月18日 (金) 18:41 (UTC)
御役に立てて嬉しいです。「Азнефть」・「Грознефть」のアクセント位置は第2音節にあります。「ネーフチ」になります。Азнефтьはアゼルバイジャンの会社だそうです。--![]() Alex K 2007年5月18日 (金) 18:50 (UTC)
Alex K 2007年5月18日 (金) 18:50 (UTC)
おお、なんとこれらについてご存知でしたか!結構有名なのでしょうか(日本では誰も知りませんが)。
親切に教えていただきありがとうございました。大変助かりました。なにせ1年半悩んでましたから(笑)--ПРУСАКИН 2007年5月18日 (金) 18:53 (UTC)
コノトプの戦いの「ザポロッジャの要塞」とは、ザポリッジャのシーチのことですか?--ПРУСАКИН 2007年5月19日 (土) 10:56 (UTC)
一応、そうです。シチは「城」「砦」「要塞」「要害」「足懸」と意味があるから、そいうふに訳しました。--![]() Alex K 2007年5月19日 (土) 11:00 (UTC)
Alex K 2007年5月19日 (土) 11:00 (UTC)
なるほど、わかりました。しかし、日本語文献ではたいてい「ザポロージエ・シーチ」と書かれており、この名称で定着していると思われます。その道では結構有名なので、それに合わせた方がよいと思います。まあ、なんで「ロシア語名 + ウクライナ語名」なのかわかりませんが。「Запоріжжа」がカタカナに転写しにくいから、逃げたかな?(特に「жж」が難題。日本語的には「ッジュ」?「ジュジュ」?「ジュ」?わからない。)--ПРУСАКИН 2007年5月19日 (土) 11:10 (UTC)
元々は、ロシア語の「ザポロージエ」でもなく、ウクライナ語の「ザポリッジャ」でもないんです。正解は古ウクライナ語の「ザポロッジャ」です。その地名は当時の文献にもでています。要塞をシーチにしてもかまいません。どうせも、まだ「シーチ」についての論文はないからです。また、今度書きましょう。。。ヘーチマン国家を完成させて秀逸な記事に選ばれたら、シーチに着いて書きましょう。。。--![]() Alex K 2007年5月19日 (土) 12:12 (UTC)
Alex K 2007年5月19日 (土) 12:12 (UTC)
- そうでしたか。翻訳については「要塞」ではなく「シーチ」がよいでしょうね。もし無理に漢字名にしたければ、コサックの場合は「要塞」ではなく「根拠地」という単語が使われることが多いようです。つまり、「ザポロッジャ(ザポリッジャ、ザポロージエ)の根拠地」と翻訳されることはないこともないです。ですが、この「シーチ」については(なぜかわかりませんが)日本語文献では「ザポロージエ・シーチ」と翻訳するのが最も一般的なようです。「セーチ」ではなく「シーチ」とするのはよいのですが、じゃあなんで「ザポロージエ」にしたのでしょうね?いっそ「ザポロージエ・セーチ」の方がまだ意味がわかりますよね(たんにロシア語名にしただけか、と)。ページを作成される場合には、どうしますか?
- ヘーチマン国家や「シーチ」についての新しいページは、期待しております。そこの「シーチ」と「コサック」は極めて重要であるにも拘らず、まだページがありません。あまりに重要だったので私は逃げていた、ということもあるのですが(笑)作成されるようでしたら、私も協力できるは協力しましょう。まあ、多分「てにをは」を直すくらいしかできませんが(苦笑)--ПРУСАКИН 2007年5月23日 (水) 10:00 (UTC)
工房について
[編集]Ridenと申します。申し訳ございませんが、利用者:Alex K:工房というページは存在しない利用者の利用者ページになってしまっていたため、利用者:Alex K/工房に移動させて頂きましたので、ご了承下さい。--Riden 2007年5月20日 (日) 07:05 (UTC)
忝く存じます。--![]() Alex K 2007年5月20日 (日) 07:46 (UTC)
Alex K 2007年5月20日 (日) 07:46 (UTC)
ページの移動について
[編集]ウクライナの都市や州の表記に関してあなたの行っている移動について、ウクライナ語名に沿って、なおかつその実際の発音重視で行っているようですが、私はその方針には反対しませんが、ただ、いちおうノート:リヴィウやノート:ハリコフをご覧になればわかるように、ページ名に関しては様々な意見があり、独断でページの移動を行ってしまうと思わぬ問題が生じる可能性があります。それを予防するため、いちおう手順に従い、ページ本文冒頭に{{kaimei}}を貼り付けた上で当該のノートページに「移動する必要性」(移動を行う理由)を説明し、改名提案を行って一定期間様子を見てから移動を行うようにして下さい。無断で移動を行っているようなので、下手をすると、全ページ差し戻される危険性があります。もし私が反対派であれば、喜び勇んで即刻無条件に差し戻すでしょう。どうかご注意下さい。
きちんと提案を行っていただければ、私は原則賛成すると思いますので、ただ手順だけはルールに則っていただかないと危険です。つまり、のちのち誰かがそのページ名を気に食わなかった場合、履歴を見て「移動提案なしの移動」であるということがわかった時点で、即刻元のページ名に差し戻すことができてしまうのです。もしノートで提案がしてあれば、反対派の人間もきちんとノートで提案しなおさなければなりませんし、その際にはあなたにも反論の余地があるでしょう。また、ノートで私等幾人かの賛成を得た上で移動を行っていれば、非常に正当なページ名として反対派に対し強い立場を獲得することができます。
経験上言いますが、移動だけは形だけでもきちんと手順を守った方が何かと有利です。--ПРУСАКИН 2007年5月21日 (月) 07:37 (UTC)
あ、あとついでに書きますが、移動後のリダイレクトの処理はなるべく完了するようにして下さい。私はそれが嫌であまりページは移動しないのですが……。--ПРУСАКИН 2007年5月21日 (月) 07:40 (UTC)
御説明有難うございます。私は英語などのwikipediaのルールに従って自由に記事を改名してしまいました。もし、日本語版のWikipediaではさような改名のルールがあれば、従います。今後とも御指図・御説明いただければ、幸いです。--![]() Alex K 2007年5月21日 (月) 07:47 (UTC)
Alex K 2007年5月21日 (月) 07:47 (UTC)
そうでしたか!逆に私は英語版のルールは知らないので……。
日本語版では、以下のような手順で移動を行うと安全です。
- 本文冒頭(ページの最初)に{{kaimei}}タグを貼り付けます。
- そのページのノートで「移動の必要性」(移動しなければならない理由)について説明します。但し、「今のページ名は不適切だから」とか「こっちの方がよいから」などというだけでは理由になりません。なぜ不適切なのか、なぜ提案するページ名がよいのか、多くの人が納得できるような理由を考えて必要十分に説明して下さい。
- 反対や他の案が出されれば、(冷静に)話し合います。話し合いで解決するのが最善ですが、場合によっては投票を行うこともあります。
- 賛成多数の場合は合意に沿って移動します。
- 一定期間(2、3日~1週間くらいが目安)経過後も何もコメントが出されなかった場合も、「反対なし=消極的賛成」と看做して移動してよいそうです。文句があるなら言え、というわけですね。(逆に、ノーコメントのページには賛成でも面倒だからコメントしないこともあり得ます。)
- 移動後はページ内の記述の修正(必要に応じて解説を変える、主として用いられる表記を前のページ名のものから新しいものに変更する、など)を行います。この際、ページ冒頭の{{kaimei}}タグは外して(削除して)下さい。
- リダイレクトの処理はなるべく行います。但し、二重リダイレクトの処理は必ず行って下さい。二重ではリダイレクトが機能しません。
この手順を踏まないと、編集合戦が起こる可能性があります。つまり、こちらが「ジトームィル」がよいと思って独自に移動してよいとなると、「ジトーミル」がよいと思う人も同様に独自に移動してよいわけです。これでは、皆が自分の見解に従って独自に移動を繰り返し、収拾が付かなくなる可能性があります。この「編集合戦の防止」がこの面倒な手順の最大の実際的な目的だと思われます。
間違ったら多分誰かが指摘してくれるので大丈夫です(?)。心配でしたらどこかのページにきちんと書いてありますので、探してください(私はどこにあるのか知らない、すみません)。--ПРУСАКИН 2007年5月21日 (月) 08:27 (UTC)
なお、単純な間違い(キーボードを討ち間違えた等)や個人的なミス判断・勘違い等によるものであれば、この提案なしで即決で移動することは可能です。
例えば、たまにありますが、日本語訳のないものに関し自分で翻訳や表記を考えてページを作ったが、よく考えると不適切だったり、間違っていたりすることにページを作ってから気付くことは起こりがちです。その場合は移動の際に要約欄に個人的なミスである旨書いて移動すれば差し戻される心配はほとんどありません。--ПРУСАКИН 2007年5月21日 (月) 08:40 (UTC)
了解いたしました。--![]() Alex K 2007年5月22日 (火) 05:37 (UTC)
Alex K 2007年5月22日 (火) 05:37 (UTC)
- 移動について再び申し上げますが、日本語版ウィキペディアでは提案なしの移動は無効です。特にドレヴリャーネ族/デレヴリャーネ族は他の方が立ち上げたページですから、例え正しい方針であったとしても、Alex Kさんお一人の考えで移動する権限はありません。特に、この場合、一般のユーザーや閲覧者にとってなぜ移動の必要があるのかは明白でありません。ノートで移動の必要性について説明しなければなりません(要約欄だけでの移動理由説明は無効です)。移動する前に本文に{{kaimei}}を貼り付け、ノートで提案を行うようにして下さい。そうすれば、ドレヴリャーネとデレヴリャーネの間を安易に移動で行ったり来たりする事態も避けられたでしょう。どうぞよろしくお願い致します。--ПРУСАКИН 2007年5月26日 (土) 13:34 (UTC)
知っております。だから、戻したのです。--![]() Alex K 2007年5月26日 (土) 13:35 (UTC)
Alex K 2007年5月26日 (土) 13:35 (UTC)
- わかりました。--ПРУСАКИН 2007年5月26日 (土) 13:37 (UTC)
私は気にしません。ただし、デレヴリャーネの日本における知名度という物も考慮すべきではないでしょうか。もっとも、ドレヴリャーネ族自体の知名度も限られたものになっていると思いますが…。難しい問題です。 --Rider 2007年5月26日 (土) 13:48 (UTC)
古いルーシ語の表記について
[編集]初めまして、Qともうします。Alex Kさんの広い知識にはいつも驚かされています。
ところで、題名の通り、古いルーシ語の綴りについてなのですが、「イジャスラフ・ダヴィドヴィチ」の項目で 私はИзяслав III Давыдвичと直しましたが、Alek Kさんは更に「Изѧславъ III Двд҃вичъ」に訂正されました。 これについて、2点ほど。
1)Изѧславъのつづりは、基本的にはAlex Kさんの綴りでいいと思うのですが、小生は「ѧ」の文字は、これを表記できないパソコンもあるかと思い、控えてきました。厳密にやるなら「ѧ」ですが、どうすべきですかね。それと、ここで厳密にやるなら、直しを入れる項目が増えそうですね。
2)Двд҃вичъについて、もちろんこうした綴りはありますが、これはあくまで、貴重な羊皮紙や紙を有効に使うための省略形ですから、少なくとも「Давыдвичъ」にすべきかと思いますが、 いかがでしょうか。一応、イパーチエフ写本には省略しない綴りもありますし。
今後も、よろしくお願いします。
- 上の匿名の方に続いて、古い表記についてですが、新しい表記との併記にしていただけないでしょうか。私のバカのパソコンでは古い文字が表示されず、もれなく小さい□になってしまいます。「何語表記か(何語の文字を使うか)」といった問題はあるとは思いますが、その辺は寛大に、たいていの機器で表示可能な文字表記も残しておいてくれるとありがたいと思います。--ПРУСАКИН 2007年5月22日 (火) 05:06 (UTC)
壱)古いルーシ語の表記を使用したほういいと思います。そうでなければ、少なくともウクライナ語・ベラルーシ語・ロシア語の三つの表記を書かなければならなくなります。そうすると、記事は読みづらくなると思います。それを避けるために、古いルーシ語の表記は尤もであると考えなければなりません。原語ですから。たとえ、「ѧ」などの文字が表記できない場合があるとしたら、サポートを使って表記できるようなソフトをダウンロード可能です。
- ウクライナのパソコンは多く漢字のサポートがないですが、ウクライナ語のwikipediaでは日本に関する記事を書くとき、必ず漢字表記を使います。見えるか見えないかユーザのパソコンの問題であり、それに記事をあわせるのはよくないとされています。いつでもソフトを下載できるからです。特に日本では・・・--
 Alex K 2007年5月22日 (火) 05:30 (UTC)
Alex K 2007年5月22日 (火) 05:30 (UTC)
弐)「Давыдвичъ」に関しては賛成です。イパーチエフ写本には省略しない綴りは見当たらなかったので、Двд҃вичъと書き入れました。![]() --
--![]() Alex K 2007年5月22日 (火) 05:34 (UTC)
Alex K 2007年5月22日 (火) 05:34 (UTC)
- しかし、ウクライナ語版ではすべての記事でその時代に使われた漢字の旧字体や異体字が書かれているのでしょうか?そんなのは日本のパソコンでも表示困難ですけど。
- 我々はしばしば外字ソフトを用いてプログラム中に存在しない漢字を作成しますが、日本語版ウィキペディアでは外字はおろか、たいていのパソコンに登録されている機種依存文字も排除されています。つまり、「㎝」は使用不可で「cm」と書かなければならない。また、漢字についても同様で、例えば日本で非常に有名な「草彅剛」という人名も「草なぎ剛」としなければならない(漢字の使用制限についてはページ名に限った話ですが)。{{機種依存文字}}や{{Unicode}}などといった表示機能に関するテンプレートもわざわざ作成されているくらいです。パソコンの機種によって表示されない可能性のある文字(つまり拡張されていないソフトでは表示されない文字)は極力排除するというのが日本語版の方針ではないでしょうか。
- そこで、私が言いたかったのは、「最も正式」と思しき表記と、多くのパソコンで「見えやすい」表記を併記するということです。今回に関しては、見えるか見えないかに記事をあわせるとは言っていません。見えるか見えないかわからないけど「最も正しい」と思われる表記はもちろん書く必要があり、しかしそれだけではあまりに利便性が悪いので(利用者は、小さい□になってしまった文字が何であるのかを調べるために、他の紙資料に当たらなければならないのですか?)便宜的に「見えやすい」表記も併記したほうがよい、ということです。また、このウィキペディアをから他のネット上の情報を探したいと思った際にも、より幅広く使用されている表記が書いてあった方が便利でしょう。恐らく、日本のパソコンで小さい□になってしまうような文字は世界的に(つまりネット上で)最も幅広く使用されている表記ではないと思いませんか?
- 関連ですが、現在日本語版ではロシア語やウクライナ語を用いるほぼすべての記事について現代的な表記が用いられています。私はそれでいいのかと思っていましたが、今後はその時代に正式であった表記に改めていった方がよいのでしょうか?--ПРУСАКИН 2007年5月22日 (火) 06:15 (UTC)
私は日本で日本のパソコンを使っています。古ルーシ語のサポートなしで、「ѧ」ははっきり見えます・・・
- 今回の問題は以下の通り解決したほうがいいと思います。原語の表記は必ず書かなければなりません。それは、ルーシの大公たちは本当にどういう名前を持っていたか分かりませんが、少なくとも「年代記」に書かれた名に近いと思われているからです。それに、利用者の利益を考えて、ウクライナ語・ベラルーシ語・ロシア語の表記も追加しなければなりません。ただし、多少は読みづらくなるかもしれません。一般人は外国語の表記にはあまり興味ないですから・・・--
 Alex K 2007年5月22日 (火) 06:31 (UTC)
Alex K 2007年5月22日 (火) 06:31 (UTC)
- 残念ながら、私のパソコンでははっきり「□」に見えるのですよ(;_;)本当にばかなパソコンです。執筆中に勝手に電源切れたりするし。
- まあ、日本語版ではこのようなばかなパソコンでも見える文字以外は極力使用を控え、使用する際にはそれなりのフォローをすることが求められている、ということです。
- そこで、私はAlex Kさんのその方針が最良であると思います。ただ、私はじめ多くの人間はその3言語による名前を網羅できませんから、Alek Kさんはじめ一部のわかる方のお力に頼きりになってしまいそうです。
- 読みづらくなることは残念ですが、あらゆるページの冒頭に日本語名・原語名・日本語名のバリエーション・各原語表記・その読み仮名を列記して読みにくくしている私が言えたことではありません(汗)最悪、<ref></ref><references />を用いて最低限必要な表記以外は脚注にまわすとか、各言語による表記は項目分けして説明するとかすることも考えられます。とりあえずはページ冒頭に列記してしまって構わないでしょう。他のページはたいていそうなっていますし、出版されている日本語の辞書・百科事典の基本スタイルはページ冒頭なので。--ПРУСАКИН 2007年5月22日 (火) 06:49 (UTC)
Qです。小生も賛成です。それにしても、特定文字が読めないというのは、OSが古いとか、そういう問題なんでしょうかねえ。すみません。この辺詳しくないので。「ѧ」がどのくらいのパソコンで見えているんですかね。小生はMAC OSXで読めています。WINだと95系統(MACだとOS9以前)はサポートなしでは読めないかも知れませんね。
- これはXPです。調整したら見えるようになるかも。でもその前にパソコン死にそう。--ПРУСАКИН 2007年5月22日 (火) 07:06 (UTC)
ヨーロッパ世界について
[編集]ヨーロッパ世界について、東ヨーロッパについても加筆をしました。ロシアに詳しそうなご様子。よろしければ執筆していただき思います。--蘭陵笑笑先生 2007年5月24日 (木) 11:48 (UTC)
ロシアには詳しくはないです。ウクライナ・ポーランドにについて多少知っております。時間が許せば、書きます。--![]() Alex K 2007年5月24日 (木) 11:52 (UTC)
Alex K 2007年5月24日 (木) 11:52 (UTC)
ロシアについて
[編集]ロシアの冒頭部分についてです。
あれをくっつけたのは私です。というのは、残念ながら、ウィキペディアでは公式には「ロシア」でないものに対し「ロシア」でリンクが付けられることが極めて多かったからです。現在ロシアのページは「現代のロシア連邦」のページとなっておりますが、このページにリンク付けされているページを見ると、実際には「ロシア帝国」にリンク付けすべきものであったり、「モスクワ公国」にリンクすべきものであったり、「ソ連」だったり、ひどいものだと「ルーシ/キエフ大公国」にリンクすべきものであったりする場合があったのです。
本来であればそれらの不適切なリンクをすべて修正すべきだったのですが、あまりにその数が多く、私は途中で投げ出してしまいました。そこで、もういいやと思って応急措置として「ロシア連邦のページ」の冒頭にあのような曖昧さ回避を設けたのです。
決して、あなたの心配されるような「ルーシを全部ロシアだと思っている」などということではないのです。
私が最善と思うのは、現在の「ロシア」を「ロシア連邦」へ移動し、「ロシア」は曖昧さ会費のページとすることです。「ロシア帝国」を「ロシア」と略称することは普通ですし、「モスクワ公国」は現在のロシアにありましたから通称として「ロシア」と呼んでも日本語的には間違いではないのです。しかし、それが「ロシア連邦」へのリンクとなっていると非常に不適切であると私は思います。
こうした私が最善と思う措置をとっていない理由は、たんに「面倒だから」、「時間がもったいないから」というだけです。--ПРУСАКИН 2007年5月25日 (金) 17:06 (UTC)
曖昧さ会費のページを作成する必要はないと思います。「日本国」と「日本」という二つの違った記事はないからです。曖昧さを避けるためにはOtherusesを使って「ロシア」という単語を含む記事の題名のみを載せれば良いと思います。モスクワ公国は確かにロシアにあったですが、その記事の題名は「ロシア」という単語はないため、曖昧さはありません。--![]() Alex K 2007年5月25日 (金) 17:24 (UTC)
Alex K 2007年5月25日 (金) 17:24 (UTC)
- 確かにそうとも言えます。ただ、本来モスクワ公国へリンクさせるべきものがロシアへリンクされている現状を見て、私は「実用上」otherusesに載せておくことが好ましいだろう、と思ったのです。希望的に考えると、例えば本来モスクワ公国へリンクさせるべきリンクがロシアへ来ているのを見て、修正してくれる人もいるかもしれませんし、少なくとも、「このページではロシアと書かれているが、本当はモスクワ公国のことではないか」と閲覧者が正しい知識を得る助けになると思います。
- 曖昧さ回避の件ですが、日本については日本と日本_(曖昧さ回避)、日本国_(曖昧さ回避)の3つが立てられております。私の意見は特異なものではありません。たんに、私は「ロシア」と「ロシア_(曖昧さ回避)」とするよりは「ロシア連邦」と「ロシア」にした方がよいだろう、と思っただけです。--ПРУСАКИН 2007年5月25日 (金) 17:46 (UTC)
コザック国家について
[編集]作業室をちょっとのぞかしていただきました。「コザック国家のヘーチマン」のテンプレート、すばらしいですね。最近、日本語版でとても精力的な活動を行ってくださっていること、感激と言っていいほどありがたく思っています(特に、私はこのような奇麗な「表」(しかも画像付き)に弱い)。
ところで、このテンプレートはどこへ用いるおつもりでしょうか。とりあえずは「ヘーチマン国家」へ貼り付けられるのであろうと思うのですが、ヘーチマンというページもありますので、そちらへもいかがでしょうか。ご相談ですが、私はかねてよりこのヘーチマンをウクライナのヘーチマン限定のページに改編し、ポーランド等のHetmanはヘトマンで新規作成してはどうかと考えているのです。現在、ヘーチマンはたいへん中途半端な内容でぜひAlex Kさんにそのうち修正していただきたいのですが、その際にページ内容を「ウクライナのヘーチマン」のページへ改編していただけませんか?英語版等を見るとウクライナのヘーチマンとポーランド等のヘトマンは別ページで立っており、日本語版でも分けてもよいかと思います。「ヘーチマン」という表記はウクライナ語名ですので、現在のページ名のまま内容を改編し、おいおい「ヘトマン」を立てればよいかと存じます。
いかがでしょうか。(ところで、ページ名は「ヘーチマン国家」、テンプレート名は「コザック国家」というのは、何か意図あってのことでなければ統一した方がよいと思うのですが……。)--ПРУСАКИН 2007年5月25日 (金) 17:22 (UTC)
ありがとう御座います。チョコチョコやろうかと。。。テンプレートをヘーチマン国家で使用したいと思います。ヘトマンの記事に関しては、やぶさかではありませんが、「ヘーチマン」という記事を改名せずにその儘残しても良いかなと思います。--![]() Alex K 2007年5月25日 (金) 17:47 (UTC)
Alex K 2007年5月25日 (金) 17:47 (UTC)
- 期待しております。
- ヘーチマンについてはちょっとごちゃごちゃ書きすぎましたね。
- 私の意見は、①「ヘーチマン」は改名せずにそのまま残し、ただページ内容はウクライナのヘーチマンについてのものに改編する、②「ヘトマン」を新たに立て、ポーランド等のヘトマンについて記述する、というものです。
- 現在のヘーチマンではほとんどウクライナのヘーチマンについて書かれているのですが、それだけというわけでもなく中途半端な感じですので、どうかと思うのです。それに、ポーランドのHetmanが日本語で「ヘーチマン」と表記されることは絶対にあり得ませんし、いっそ英語版等に倣って別ページにしてしまってはどうかと思うのです。--ПРУСАКИН 2007年5月25日 (金) 17:52 (UTC)
古ルーシ語について
[編集]こんにちわ、Alexさん。 記事における古ルーシ語での記述にはѧと表示不可能な文字コードがあります、私は環境はWindowsXPprosp2英語版と非常にポピュラーな物ですのでおそらく多くの方も同じ体験をすることになると思います。とりあえず、どのようなプラグインをインストールすれば表示できるようになるか教えていただけないでしょうか。一応調べましたが見つかりませんでした。 --Rider 2007年5月26日 (土) 14:36 (UTC)
こんにちは、Riderさん。[3]をみてください。ウクライナ語で申しわけないですが、是非も御座いません。そこのページで ЗАВАНТАЖИТИ ШРИФТ (276K) か ZIP (172K) をクリクして、フォントをダウンロードすれば、ѧのような文字が見えるようになる筈です。よろしくお願いします。--![]() Alex K 2007年5月26日 (土) 14:45 (UTC)
Alex K 2007年5月26日 (土) 14:45 (UTC)
教えていただきありがとうございます。 しかし、フォントをダウンロードしてC:\WINDOWS\Fontsにコピーしてリブートして、結果としてѧのままです。教えていただいたページにあるサンプル絵にあるは美しく、見れることを期待していたのですが本当に残念です。あれからおよそ2時間ほど費やしいろいろ検索をかけてその答えを求めましたが無駄に終わりました。 --Rider 2007年5月26日 (土) 16:19 (UTC)
お願い
[編集]スラブ人ですが、スラヴ人、東スラヴ語群、スラヴ語派などメインとなるページがすべて「スラヴ」で立てられていますので、Template等も合わせていただけますか?不必要なリダイレクトの発生は避けるべきですし、特に理由がなければ統一した方がよいでしょう。
あるいは、現在「スラヴ」で作成されているページすべてを「スラブ」に移動することも可能ですが、その方がよいでしょうか。ウィキペディアでは「v」の表記が統一されておらず、モルドバ人、ソビエト、ペトロパブロフスクなど「バ行」でページが作成される一方、モルドヴィン人、ヴォルゴグラード、ブラゴヴェシチェンスクなど「ヴ」でページが作成されているのです。(しかし、「スラヴ」は原則すべて「スラヴ」のようです。)--ПРУСАКИН 2007年5月26日 (土) 14:53 (UTC)
ありがとう御座います。気がつかなかったんです。既に直しました。
こちらこそ、非常に迅速なご対処、ありがとうございました。--ПРУСАКИН 2007年5月26日 (土) 14:56 (UTC)
質問です
[編集]すみません、また質問させてください。ひとつは、個人的興味からですが、ウクライナ語版を見ていたところ「日本国」の訳として「Держава Японія」を用いていました。なぜ「Українська держава」のように「Японська держава」にはならないのですか? 「Держава Японія」と「Японська держава」とでは、何か意味・ニュアンスの違いがあるのですか? それとも、たんに習慣や決まりの問題ですか?
もうひとつ質問させてください。「Червона Україна」という名称は、「Червона Русь」の別名として用いられる可能性はありますか? ウクライナ語版を見る限り、「Підкарпатська Русь」のかわりに「Карпатська Україна」と呼んだりすることはあるようですが。--ПРУСАКИН 2007年6月6日 (水) 15:54 (UTC)
御質問ありがとうございます。 私のウクライナ語の語感によれば、「Японська держава」は「日本の国」あるいは「日本人(和人)の国」であって、「Держава Японія」は「日本という国」であるということです。つまり、私は帰属意識を重視しない訳を選んだわけです。、「Японська держава」と「Держава Японія」と違いは、あまりにも微妙な違いなので、ウクライナ人でさえ気づかない場合が多いです。
「Червона Україна」についてはあまりきたことがない。直ぐ、共産党の「赤」が頭にポッと浮かび上がります。おそらく、「Червона Русь」の代わりに使用しないでしょう。
「Підкарпатська Русь」は地域の名前であり、「Карпатська Україна」はその地域に20世紀におこった国家の国号である。ですから、「Підкарпатська Русь」と、「Карпатська Україна」は同義語として用いることが多いです。--![]() Alex K 2007年6月6日 (水) 16:39 (UTC)
Alex K 2007年6月6日 (水) 16:39 (UTC)
- 一つ目の質問について→そういう意味の違いがあるのでしたら、私も「Держава Японія」がよいように思います。日本語でもやはり「日本という国」という意味だと思いますので。「日本人の国」という意味ではないと思います。つまり、「日本人」というのは「日本国の国民」という意味ですから(日本国民ではない外国籍の人種的日本人は普通「日本人」ではなく「日系人」と呼ばれます)。ですから、「日本人の国」という意味では結局「日本国の国民の国」「日本国の国民の国の国民の国…」となってしまいナンセンスなのです。「日本列島という場所にある国」という可能性はありますが(そしたら「Японська держава」ですね)、「日本国」の文字面だけからはそこまでは判明しませんので、名称を単純に文字通りに訳せば「日本という国」という訳が最適だと思います。在ウクライナ日本大使館のページでは「日本国」はたんに「Японія」としか書かれておりませんね。ウクライナ語では「日本国」の定訳はまだないのでしょうか。「Держава Японія」が定着すればよいと思います。
- 二つ目の質問について→「Червона Україна」の件についてはわかりました。「Підкарпатська Русь」の件については、何となくわかったと思います。しばしばクリミア汗国を地域名のクリミア(半島)で呼んだり、オスマン帝国をトルコと呼んだりしますが、そのようなものでしょうか。
- ところで、「Карпатська Україна」は「Держава」をくっつけて呼ぶことはないのでしょうか。確か、どこかでそのように書いているものがあったような気がするのですが(多分、ウクライナ語版ウィキペディアのいずれかのページです)。日本語では「カルパト・ウクライナ」と翻訳されることが多いのですが、正式名称は「Держава」なしの「Підкарпатська Русь」でよろしいのでしょうか。もし「Держава」が付くのが正式なのであれば、日本語訳も「カルパト・ウクライナ国」としなければなりません。--ПРУСАКИН 2007年6月6日 (水) 17:15 (UTC)
また書き忘れたことが在ります。Японська державаと訳したら、державаを重視することになるがが、Держава Японіяと訳したら、Японіяを重視することになります。日本の「は」と「ガ」の相違に似ています。--![]() Alex K 2007年6月7日 (木) 05:30 (UTC)
Alex K 2007年6月7日 (木) 05:30 (UTC)
- なるほど、それはわかる気がします。アドバイスありがとうございます。--ПРУСАКИН 2007年6月9日 (土) 14:28 (UTC)
質問弐
[編集]- 度々失礼致します。たいへんお世話になっております。また教えていただきたいことがあります。
- ウクライナ語の発音でわからないものがあります。ウクライナ語のдсという綴りは、何と発音されるのでしょうか。ロシア語のдсはтсやцと同じ発音になりますね。ポーランド語でもdsはcと同じ発音になると思います。しかし、ウクライナ語では子音の清音の前の濁音は濁音のままの原則だと思うので、よく考えたらдсは何と発音するのかわからなくなってしまいました。
дсはそのまま文字通りдс(ド・ス)と発音されるのでしょうか。それともポーランド語やロシア語のようにцやcのような発音(ツ)になるのでしょうか。教えていただけると助かります。
- もうひとつ、別件があります。「画像:Flag of Ukrainian People's Republic.svg」なのですが、22x20pxの旗アイコンサイズにすると何故か表示されなくなってしまいます。私はパソコンの画像処理に無知であるため、原因が皆目検討もつきません。私のパソコンがおかしいのでしょうか。Alex Kさんのパソコンではきちんと表示されますか? なにか思い当たる解決法がございましたら、ご助言くださると助かります。(参考→問題の画像の22x20px版「
 」本来であれば、「」の間に国旗アイコンが表示されているはずです。私のパソコンでは全く見えません。)
」本来であれば、「」の間に国旗アイコンが表示されているはずです。私のパソコンでは全く見えません。) - ちなみに、現在ウィキペディア(コモンズ)にはウクライナ国の国旗画像は存在しないようですね……。--ПРУСАКИН 2007年6月16日 (土) 15:27 (UTC)
お返事を待たせいたしました。
- дсの発音についたはよくわかりません。дсが入っていることばはゼンゼン思い出せません。「ツ」になるかもしれません。私の専門は言語学ではなく歴史でありますから、本当によくわかりません。役立たずに申し訳ありません。
- 私のパソコンもFlag of Ukrainian People's Republic.svg|22x20pxを無視しているようです。まったく見えません。これはsvgというファイルと関わる問題だと思います。数字を変えれば、見えます(たとえば23px⇒
 ・・・見えるでしょう)
・・・見えるでしょう) - そうです。これから作成しようかと考えております。--
 Alex K 2007年6月19日 (火) 16:02 (UTC)
Alex K 2007年6月19日 (火) 16:02 (UTC)
お返事ありがとうございます。
- дсですが、実例を出さなかった私が失敗でした。例えば、日本でも割と有名なヘチマンのСкоропадськийです。これは「スコロパーツィクィイ」となるのでしょうか「スコロパードスィクィイ」となるのでしょうか。70年くらい前の日本語の本では「スコロパドスキイ」のように紹介してあり、最近(1990年代)は「スコロパーツキイ」(←これではロシア語名と区別がつきませんが)とか「スコロパーツィキイ」のようです。
また、似ている問題としてтридцятьのдцも「トルィーッツャチ」でしょうか「トルィードツャチ」でしょうか。よく考えたら、私はこんな基本的なことがわかりませんでした。まあ、口に出して発音する際にはあまり変わらないので問題なかったのですが……。 - 22を23にしてごまかすしかないようですね。他のsvgは見えるのに何ででしょうね。まあ、取敢えずは23とかでごまかすようにしましょう。
- 作成ぜひよろしくお願いします。--ПРУСАКИН 2007年6月19日 (火) 17:44 (UTC)
- ついにウクライナ語版にも日本の飛行機が現れましたY(^-^)Y D4Y「彗星」艦爆は、靖国に一一型か一二型の実物が展示されていますので、もし東京を尋ねられることがありましたら、せっかくですから記念に是非ご覧下さい。もっとボロイかと思うと意外に立派な飛行機ですよ。--ПРУСАКИН 2007年6月23日 (土) 18:00 (UTC)
- そうですね。でも記事とようりもスタブだけです。私は軍事においてはあまり詳しくはないからです。東京にいくようなことになったら、靖国に是非ともに見学に行こうと思います。ところで広島県の呉でいくつかの立派な台が置いてあります。飛行機ではないですが。。。(^-^)--
 Alex K 2007年6月25日 (月) 14:28 (UTC)
Alex K 2007年6月25日 (月) 14:28 (UTC)
- そうですね。でも記事とようりもスタブだけです。私は軍事においてはあまり詳しくはないからです。東京にいくようなことになったら、靖国に是非ともに見学に行こうと思います。ところで広島県の呉でいくつかの立派な台が置いてあります。飛行機ではないですが。。。(^-^)--
キエフ地下鉄について
[編集]初めまして。LERKと申します。ウクライナにある地下鉄のひとつ、キエフ地下鉄の路線記事を分割して作成しています(1号線と2号線を先ず分割しました)。訳語やカナ転写などに不適切な部分がありましたら、ご指摘をお願いいたします。- LERK (会話 / 投稿記録) 2007年9月7日 (金) 09:32 (UTC)
- やってみましょう!--
 Alex K 2007年9月8日 (土) 14:16 (UTC)
Alex K 2007年9月8日 (土) 14:16 (UTC)
- 遅くなりましたが、ありがとうございます。3号線もいずれ作成する予定です。そのときはよろしくお願いします。- LERK (会話 / 投稿記録) 2007年9月14日 (金) 12:29 (UTC)
プレビュー機能のお知らせ
[編集]こんにちは。ウィキペディアへのご寄稿ありがとうございます。Alex Kさんが同じ記事に対して短時間に連続して投稿されているようでしたので、プレビュー機能のお知らせに参りました。投稿する前に「プレビューを実行」のボタンを押すと、成形結果を先に見ることができます。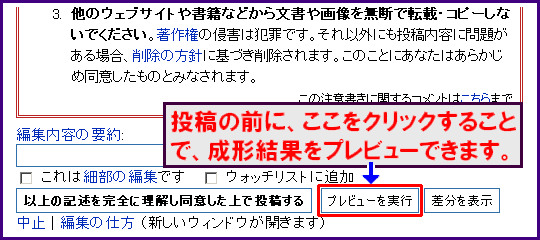
これを使うことで
などをあらかじめチェックし、修正してから投稿していただくことにより、同じ記事への連続投稿を減らすことができます。この利点については、同じ記事への連続投稿を減らすに説明がありますので、よろしければお読みください。また、ガイドブックにウィキペディア全体のことについて分かりやすく解説されていますので、あわせてお読みいただけると幸いです。ご理解とご協力をよろしくお願いします。--L26 (会話・履歴) 2007年9月25日 (火) 05:45 (UTC)
- ありがとうございます。Wikipedia:同じ記事への連続投稿を減らすという妙な記事は日本語版のみに存在するですか?私は自分にやり易いようにやっているだけです。なるべく気を付けます・・・--
 Alex K 2007年9月25日 (火) 06:05 (UTC)
Alex K 2007年9月25日 (火) 06:05 (UTC)
ポーランド分割の改名提案について
[編集]こんばんわ。ポーランド分割の改名提案ですが、一週間以上新たな意見が出ていませんので、告知の終了処理をしていただけますでしょうか。よろしくお願いします。--Charlesy 2007年10月12日 (金) 18:42 (UTC)
聖ソフィア大聖堂のカテゴリについて
[編集]同意しかねる点がありましたので聖ソフィア大聖堂のノートページに投稿しておきました。ご一読下さい。 関連する各ページについても同様の疑問が御座います。 カテゴライズは、所有関係を表すものではありません。Kliment A.K. 2007年10月24日 (水) 17:39 (UTC)
:カテゴライズは、所有関係を表しているからこそ、削除させていただきました。--![]() Alex K 2007年10月24日 (水) 17:49 (UTC)
Alex K 2007年10月24日 (水) 17:49 (UTC)
それでは、アヤソフィアに東方正教会のカテゴリがなされている事についても「所有関係を表している」のでしょうか?カテゴリについて前提のお考えが間違っているように思います。Kliment A.K. 2007年10月24日 (水) 17:55 (UTC)
ウクライナ正教会の記述について
[編集]- いつもお世話になっております。ウクライナ正教会への加筆をありがとうございます。実はUOC-KPが多数派だというのは風聞には聞いておりましたが、信徒数概要等のデータがどうしても見当たらなかった為に、圧倒的少数派であるUAOCについてのみ「少数派」という記述をしておいたのです。ところでUOC-KPが多数派だという、そのソースはどちらですか?後学の為に御教示頂ければ幸甚です。出来ましたらUOC-KPのみならず、UOC(MP)とUAOCの概算信徒数もご存知でしたら御教示頂ければと思います。今後のページ作りの参考にさせて頂きますので。
- それと、後程修正させて頂こうかと考えているのですが、「コンスタンティノポリス総主教の下にあるキエフ府主教」というのは存在しない筈です。詳細はノート:コンスタンティノポリ総主教庁にて。
- ウクライナ正教会の信徒数はここにあります。--
 Alex K 2007年10月25日 (木) 15:46 (UTC)
Alex K 2007年10月25日 (木) 15:46 (UTC)
- 大変興味深いデータをありがとうございます!関連データを探していたのですが、なかなか見付からず困っていたところでした。Kliment A.K. 2007年10月25日 (木) 15:55 (UTC)
- ただし、このデータをそのまま信用してはいけません。私が知っている限り、ウクライナでは宗教に関する大規模なアンケート調査が一度も行った事は有りません。CIAの統計は何に基づいているかわかりません。ウクライナの政府は、宗教に関するデータを持っておりますが、そのデータは信者数を表しているではなく、それぞれの宗派に属している信者集団数をあらわしているのです。信者集団とは、OO宗派が管理する10人已上からなる地域的集団のことです。その集団数を見ると、UOC(MP)の方が多数派となっております。でもやっぱり、信者集団は特定の信者数を表していないので、ウクライナ正教会の諸宗派における具体的な信者の人数はいまなお不明です。CIAとウクライナ政府の統計データ以外はUOC(MP)とUOC-KPのデータもありますが、そのデータはものすごく危ないので使用しないほうがいいと思います。たとえば、UOC(MP)は自らの信者数は36.000.000人ぐらいいると主張していますが、この数字はウクライナで宗教を持っている人口よりはるかに多いです。--
 Alex K 2007年10月25日 (木) 16:19 (UTC)
Alex K 2007年10月25日 (木) 16:19 (UTC)
- ただし、このデータをそのまま信用してはいけません。私が知っている限り、ウクライナでは宗教に関する大規模なアンケート調査が一度も行った事は有りません。CIAの統計は何に基づいているかわかりません。ウクライナの政府は、宗教に関するデータを持っておりますが、そのデータは信者数を表しているではなく、それぞれの宗派に属している信者集団数をあらわしているのです。信者集団とは、OO宗派が管理する10人已上からなる地域的集団のことです。その集団数を見ると、UOC(MP)の方が多数派となっております。でもやっぱり、信者集団は特定の信者数を表していないので、ウクライナ正教会の諸宗派における具体的な信者の人数はいまなお不明です。CIAとウクライナ政府の統計データ以外はUOC(MP)とUOC-KPのデータもありますが、そのデータはものすごく危ないので使用しないほうがいいと思います。たとえば、UOC(MP)は自らの信者数は36.000.000人ぐらいいると主張していますが、この数字はウクライナで宗教を持っている人口よりはるかに多いです。--
- >UOC(MP)とUOC-KPのデータ(中略)ものすごく危ない
- その通りですね(笑)。そういうデータは結構色々なところに出回っているのですが、「どちらもこんなに自分で言うほど多いか?」と首をかしげざるを得ないようなデータだったと記憶しております。Kliment A.K. 2007年10月25日 (木) 16:36 (UTC)
- えーっと…
- Alex Kさんが「何に基づいているかわからない」とこちらで仰ったからこそ、私はウクライナ正教会のページから該当データに冠する記述を外し、「調査方法は不明」と書き込んだのですが…調査方法が明らかになったのでしたら、御教示下さい。--Kliment A.K. 2007年11月14日 (水) 16:34 (UTC)
- 了解しました。御教示をありがとうございます。--Kliment A.K. 2007年11月15日 (木) 00:11 (UTC)
ウクライナ関連の記事について
[編集]もうちょっと、日本における通説の状況を把握してから書いて頂けませんか?Alex Kさんには「独自研究」のケが非常に強く感じられます。せめて両論併記にして頂きたい。それから、「東西教会の分裂」が11世紀きっかりのものだなどという見解こそ時代遅れです。もうちょっと東西教会の関係史について勉強して頂きたく思います。--Kliment A.K. 2007年11月17日 (土) 15:14 (UTC)
- ルーシの歴史を知らずに、正教を中心に記事を編集することは「独自研究」でしょう。私は、「正教」を「キリスト教」に変えただけです。東西教会の関係史は、関係史であって、ルーシの歴史ではありませんので、そちらこそルーシの歴史について勉強してください。私は正教の役割を小さく見せようと思っておりませんので、ただ一方的にルーシにおける宗教に関する出来事を正教的な偏見で解釈することは、よろしからずと思います。--
 Alex K 2007年11月17日 (土) 15:35 (UTC)
Alex K 2007年11月17日 (土) 15:35 (UTC)
- >ルーシの歴史を知らずに、正教を中心に記事を編集することは「独自研究」でしょう。
- お話になりません。日本における通説を把握してから、バランスある記述をして下さい。問題は単純です。「ルーシの歴史云々」が問題なのではなく、「オリガ」と「ウラジーミル1世」の「洗礼」が「歴史的にどのような帰結をもたらしたか」「当時のキリスト教の東西分裂の状況はどのようなものだったか」という事実関係が問題になっているだけです。「ルーシの歴史」といった言葉を持ち出す必要性は全くありません。貴方は、事実関係を説明した文章を中傷をつけて削除されたのです。謝罪を求めます。--Kliment A.K. 2007年11月17日 (土) 15:40 (UTC)
- 当記事のトークへどうぞ。--
 Alex K 2007年11月17日 (土) 15:55 (UTC)
Alex K 2007年11月17日 (土) 15:55 (UTC)
- 当記事のトークへどうぞ。--
山川均について
[編集]ウクライナ語版に「赤旗事件」の項を設けて下さったようで、ご苦労様です。本項の主要人物の1人・山川均の読みは「やまかわ ひとし」ですので、ご連絡をいたします。この程度のことをわざわざ知らせるのも何ですが、後学のためということでご了承ください。Alex Kさんのウィキペディアでのご活躍を期待しています。--Lombroso 2007年12月1日 (土) 14:01 (UTC)
- お指摘ありがとうございます。ウクライナ語版のwikiでお礼とお返事を書かせていただきました。--
 Alex K 2007年12月28日 (金) 21:01 (UTC)
Alex K 2007年12月28日 (金) 21:01 (UTC)
お詫び
[編集]Kliment.A.K.さんのノートページでの私のコメント分につき、陳謝します。言いたいことがあればAlexさんに直接申し上げるべきでしたし、これまで必要がないと思って言ってこなかったことを他人のノートで触れ回ったのはたいへん無礼で卑怯な行為でした。反省しています。いろいろの、個々の問題についてはケースバイケースですが、今回の私のコメント分については一部非常に不適切な部分があり、なおかつその部分については非は全面的にこちらにあり、Alexさんに非常に不快な思いをさせてしまったことは本当に申し訳なく思います。今回の件につきましては、Alexさんがお怒りになる(もしくは呆れられた)のはご尤もで、こちらはもう平謝りするよりほかありません。
今後Alexさんに何か申し上げたいことがあれば直接ノートにお知らせしますし、そうでなければ影で何か言うような行為は慎みます。言い訳になりますが、私も人間ですのでしばしば過ちを犯します。Alexさんも、とりわけ私個人に対して苦情・批判等あれば私のノートにお知らせいただきたく存じます。すみませんでした。--ПРУСАКИН 2007年12月28日 (金) 17:26 (UTC)
まあ、たまに感情的になることは、いいことだと思います。私は少しも怒っていませんよ。「自分が許されたいほどに人を許そう」といういいルールがありますので、ПРУСАКИНさんのお詫びを受け取らざるえお得ません。前向きに生きていきましょう!よいお年を!!! (^V^)--![]() Alex K 2007年12月28日 (金) 20:59 (UTC)
Alex K 2007年12月28日 (金) 20:59 (UTC)
ありがとうございます。「自分が許されたいほどに人を許そう」は私も覚えておきましょう。いろいろあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いします。よいお年を!!--ПРУСАКИН 2007年12月29日 (土) 05:29 (UTC)
長い間、私がいい加減な日本語で書いた記事を丁寧に御修正いただき、多数の適切な御指摘いただいた事について、厚く御礼を申し上げます。来年もなにとぞ宜しく御願い致します。よいお年を!!!
IP
[編集]失礼ながら一点だけ質問させていただきたいのですが、Alex KさんはしばしばIPでも執筆活動されているようですが(勘違いだったらご容赦下さい)、それはなぜですか? 私としては、Alex Kさんのなさっているような正当な執筆活動ならばすべてログインして活動なされても特に不都合はないように思うのですが……。一般に、私を含め日本語版ウィキペディアユーザーは複数のログイン名を持っているユーザーや複数のログイン名やIPを用いるユーザー(可変IPを含む)には、なにかと不信感を抱きがちです(現実に、そのような手口で荒らしや荒らしまがいの行為を行う人物が多数いるからです)。このような前提で、最近複数のIPによる編集が問題になったことがしばしばあったため、いくばくかの不信感を抱きつつありました。いかがでしょうか。--ПРУСАКИН 2007年12月28日 (金) 17:26 (UTC)
私のIPは2つほどあります。133.41ではじまるやつ、202.249ではじまるやつです。自分はたまにログインするがめんどくさいから、IPから修正することがあります。しかし、日本語版のwikiでその修正はinterwikiとノートを中心となっております。--![]() Alex K 2007年12月28日 (金) 20:59 (UTC)
Alex K 2007年12月28日 (金) 20:59 (UTC)
事情はわかりました。今後そのように考えます。
ただ、事情を知らない者の立場にたって言えば、InterwikiくらいならIPでも別段問題ないかもしれませんが、ノートはやめたほうが良いですよ(^_^;。Wikipedia:多重アカウントでは不正に使用される別アカウント(通称:操り人形)が禁止されていますが、むやみに複数のIPを議論の場で使用することはそれに似た不信感を与えがちなのです。普通「操り人形」は明らかに不正な目的で使用されるのですが、Alex Kさんの場合は議論のやり方にそのような問題はありません。行動そのものには問題ないのですから、むやみに複数のIPを用いて無用な不信感を抱かれるのは損というものです。
日本語版ウィキペディアだけの特殊な事情なのかもしれませんが、日本語版では特に一部IPの悪辣さが目立っており(一部優秀な編集を行うIPもいますが)、その影響でIPに対する不信感はかなり高く(多分他言語版より高いでしょう)、そのため議論の場でIPを用いるとそれだけで批判されることがあるのです。ぜひ、議論の際は面倒でもログインされることをお勧めします。余計な問題が減ると思いますよ!--ПРУСАКИН 2007年12月29日 (土) 05:29 (UTC)
Wikipedia:多重アカウントは不正に使用される別アカウントについてのものであって、IPについてではありませんよね。しかし、もしIPも別アカウントとして意識されるのなら、これからなるべくログインしてからノートの議論に参加させてていただきます。ご指摘ありがとうございます。--![]() Alex K 2007年12月29日 (土) 12:23 (UTC)
Alex K 2007年12月29日 (土) 12:23 (UTC)
補足します。利用者‐会話:133.41.84.206をご覧になると推測していただけると思いますが、IPというのは常にそうであるとは限りません。の通り常に誰かひとりを表しているとは断定しがたいのです(きちんと調査すればわかるかもしれませんが、我々一般ユーザーには無理)。そのため、非可変IPであっても議論の際にはあまり好ましい印象は持たれません。あるユーザーとIPとの完全な一致が一目瞭然、ではない以上、IPは別アカウントとして認識され得る、ということです。また、私やKliment A.K.さんのようにもう事情を知っている者であれば支障はないのですが、Alex Kさんのこれまでの活動を知らず、初めて議論を見たような閲覧者はいったい誰が・何人が議論しているのかわからず、この点でも問題があります(あるIP番号が多分Alex Kさんだろう、ということは「内輪」の人間にしかわからない……)。
ご協力いただけるようですのでありがたく思います。--ПРУСАКИН 2007年12月29日 (土) 15:44 (UTC)
お礼
[編集]Alex K様
219.9.130.48と申します。ウクライナ語版の関西空港の記事の訂正、ありがとうございます。大阪周辺の記事がウクライナ語版記事に少なく、何とかウクライナの方々にも情報を提供したく、記事を起こしました。ウクライナ語がほとんど分からないので記事を書くことができませんが、京都市などのページで写真などを追加させて頂きました。間違い等あれば、お手数で恐縮ですが、訂正して頂ければ幸いです。 219.9.130.48 2008年2月10日 (日) 10:42 (UTC)
219.9.130.48さん
ウクライナ語版で記事を御修正頂き有難う御座います。大坂・京・関西空港などの記事をチェックさせて頂きます。これからも宜しく御願いいたします。--![]() Alex K 2008年2月11日 (月) 03:55 (UTC)
Alex K 2008年2月11日 (月) 03:55 (UTC)
Help!
[編集]Dear AlexK, I noted that you have contributed to the ウクライナ正教会 pages and would be very grateful if you would return to them and see some of the changes that are being discussed. As Mr. Kliment appears to respect your opinion, your input would be greatly appreciated.
Please help! Qe2 2008年2月13日 (水) 16:34 (UTC)
Klimentより
[編集]お戻りになられているようですね。色々と見解の違いはありましたが、今後とも宜しくお願いします。--Kliment A.K. 2008年3月5日 (水) 10:39 (UTC)
Template:ハールィチ・ヴォルィーニ
[編集]移動によりTemplate:ハールィチ・ヴォルィーニ大公国へのリダイレクトとなっているTemplate:ハールィチ・ヴォルィーニが、Wikipedia:リダイレクトの削除依頼/2008年3月#3月21日から25日に出ております。テンプレートのリダイレクトはサーバ負荷の観点から削除しようという依頼ですが、利用者サブページのリンクが切れているとびっくりなさるかと思い、念のためお知らせにあがりました。--Kurihaya 2008年4月7日 (月) 12:44 (UTC)
名古屋市
[編集]名古屋市の記事(uk:Наґоя)を作ってくださいまして、ありがとうございます。私にはウクライナ語は読めませんが、歴史や見所についてもしっかり書かれていて、つまらない一覧がいっぱいの日本語版の記事よりも良いのではないかと思うほどです。我々の多くにとってなじみのないウクライナ語で、これほど丁寧に故郷の記事を作っていただけ、本当に嬉しく思っております。本当にありがとうございます。--Peccafly 2008年5月22日 (木) 08:34 (UTC)
- ウクライナ語版の記事を御覧頂いたこと有難く存じます。名古屋は、私の憧れの都市なので、彼の記事を喜んで書きました。後程、経済や人口などについての情報を追加したいと存じます。御指摘が御座いましたら、宜しく御願い致します。--
 Alex K 2008年5月22日 (木) 12:10 (UTC)
Alex K 2008年5月22日 (木) 12:10 (UTC)
- Alex Kさんの、Wikipediaウクライナ語版での大変精力的な日本関連記事の執筆には敬服いたしております。私は普段はバルカン半島に関連する記事を書いておりますので、同じスラヴ系ということで、いつかご助力をお願いすることがあるかもしれません。その際は是非よろしくお願いいたします。--Peccafly 2008年5月22日 (木) 13:47 (UTC)
ありがとう!
[編集]修正ありがとう! いろいろあるかもしれませんが、もしよかったらまた日本語版でも活躍して下さると嬉しく思います。
ついでのようですみませんが、ヴァリャーグのページに(キリル文字表記が)ロシア語名しか書いていない点が気になります。もしかしたら当時のルーシ語でも同じ綴りなのかもしれませんが、ルーシ語の原語綴りとその読み方をお手すきのときにでも加筆していただけたらありがたく存じます。
これまであまり日本語版ウィキペディアを見てこなかったので最近になってようやく気付いたのですが、日本語版ウィキペディアは、何というか、重要なページほど質が劣るというか、誰かが何の利害関係があるのか知りませんが好き勝手な解釈を書き並べているという失望する現状があるような気がしますね。重要な(基本的な)ページがそのような状況であるなら、そこまで重要ではないページを作ることはなんとなく虚しい気がしないでもありません…。ですが、もしまたAlex Kさんがウクライナの都市や歴史、人物関係のページを作成して下さることがあれば、それはそれでたいへん嬉しく思います。
いずれにせよ、ウィキペディア上でも実生活上でも、今後ますますのご活躍と、心身ともにご健康であられることをお祈りいたします。なお、すみませんが、私も名古屋出身でした…。憧れに傷付けて申し訳ない。--PRUSAKYN (ПРУСАКИН) 2008年5月22日 (木) 16:50 (UTC)
今のところ、日本語版ウィキペディアで記事を書く事や編集することなどに興味はありません。日本語でうまく書けないので、控えた方がいいと存じます。記事を書いたとて間違いを誰も直してくれないし、日本語の勉強にもならいから、意味がありません。また、精神力を吸い取る無駄な空論が多いので、諦めた方がいいでしょう。日本語版ウィキペディアは他のウィキペディアと同様に素人の百科事典なので、自分が知っている事をここではなく、東欧研究の雑誌に公刊した方が効果的だと存じます。
憧れの傷付けなどは御座いませんから、御心配には及びません。私はただ日本語版ウィキペディアの雰囲気に疲れただけです。名古屋も、ПРУСАКИНさんも快く思います(^V^)--![]() Alex K 2008年5月23日 (金) 13:38 (UTC)
Alex K 2008年5月23日 (金) 13:38 (UTC)
- 過去ログに書き込んでよいものか迷いますが、失礼してまたコメントします(まだUTC23日だからよいかな、と)。寛大なお言葉ありがとうございます(最後の小さい文字の段落の話)。
- 東欧研究の雑誌に公刊した方が効果的 - そういう機会をお持ちの方でしたら、それは正統的な方針だと思います。長い目で見れば効果的だし、魅力的であります。ただ、残念なことに現代日本社会ではまじめな学術論文よりも、なんだかわけのわからない、風評めいたウェブサイトの情報の方が「即効的な」効果があるように思われます。逆接すれば、ウェブサイトであるウィキペディアに専門家の方が直に書き込みをして下さることは日本語社会にとって直接的な効果があることは期待できると思います。
- ただ、私事ですが、あまりに程度の低い思考を持った人に対処しなければならないのはめんどくさいですね(有限の人生の時間の無駄)。レベルの高い相手であれば、意見が違ったとしても話して得るところはあるのですが。
- 私は日本語でネット検索をするのは好きではありませんし、日本語のサイトはほとんど見ません。欲しい情報は少なく、むしろ他人の汚い言動を見せられて不快感を蒙ることの方が多いからです。
- 記事を書いたとて間違いを誰も直してくれないし - すみません、私がもっとがんばるべきでした。協力しないで失望させてしまったことについては、こちらも残念ですし、なんだか申し訳なく思います。ただ、私は「てにをは(助詞)」の間違え程度であれば、文意が通じればあえて修正しなくてもよいだろうという方針でしたし、Alex Kさんの作成されたページを見ていなかったわけではありません(まあ、自分も誤字脱字が多いので……)。初期の頃(コノトプの戦い等)はいろいろ直しを入れましたが、その後あまり訂正しなくなったのは「あえて直すほどの間違えがなかったから」です(日本語の文法的な意味で。書いてある内容の正誤は、素人の私には判断し切れない部分があります。そこは他の日本語版ユーザーでも同じことで、我々も勉強と努力はすべきですが、それでも追いつかない分についてはご了承願いたい部分です)。失礼を省みず正直申せば、Alex Kさんの日本語作文力は、最初のページを作成された頃と最後のページを作成された頃とでは段違いの進歩があります。だからあまり直す必要がなかった……。項目本文の記述についてはなかなか味のある、読んで面白い日本語文章だったと思います(それをもっと百科事典風に、無味乾燥に直すことはできたかもしれませんが、私はそのようには直したくなかった)。訳語も、私は「ポルボートク衆」は思いつきませんでした。「党」とか「派」の方が近現代史的には無難な気もしますが、私は「ポルボートク衆」は気に入っています。
- 名古屋は私も好きです(現在は住んでいないのですが)。ただ、名古屋近辺の空港は入国審査が厳しいようで、外国人の方はこれといった根拠なく犯罪者扱いされたり等の不快なできごとに出会う可能性が高いので、セントレア等、名古屋近辺の国際空港のご利用は絶対にお勧めしません。(まあ、尤も日本国の公式方針は「外国人=犯罪者」なのでどこでも同じかもしれませんが。2006年6月に国家関係者が記者会見でそのように明言していましたし、その後も修正の発言はないので多分現在でもそのような方針をとっているのでしょう。因みに、日本の法律上では「外国人は犯罪者でないということを自ら証明できない限り犯罪者と看做す」ということになっているのですが、たいへん日本らしい素晴らしい考えですね。)
- もしよろしかったら、私の記述にひどい間違えがあったら教えてくれたらありがたいです。私はよく外国語を誤読しますし、翻訳を間違えます。各所の議論についてですが、私はAlex Kさんは日本語を勉強してくれる外国の方だからという前提であまりいろいろ気にしないで来たのですが、人によっては細かい文章表現等を気にして反感を抱いた人もあったのかもしれません。ですから、私はもっとAlex Kさんに肩入れすべきだったかもしれません。Alex Kさんは他ならぬ、私の大好きなウクライナ人なのですから。いろいろ失望させたことをお詫びします。どうぞいろいろな分野でご活躍されることをお祈り致します(気が向いたらまた日本語版にも来て下さい!)長々と失礼しました。いろいろ教えて下さったこと、深くお礼申し上げます。--PRUSAKYN 2008年5月23日 (金) 15:41 (UTC)
- コメント有難う御座います。自分が暫く休憩を取りたいだけで、ПРУСАКИНさんを責めておりません。また、精神的に復活したら、日本語版ウィキで何かを書きましょう。
- 自分の専門は中世・近世史なので、思わず「Полуботківці」を「ポルボートク衆」にしました。ПРУСАКИНさんが仰るように、近代・現代史で用いられている「党」・「派」の方が相応しいかもしれません。自分が日本の近代・現代史についての本をあまり読んでませんから。
- キエフ空港も名古屋空港と同様に外国人にとって危ないところです。キエフ市内でさえ、外国人は白人でない限り、警察がその外国人をうるさく「接待」します。ですから、外国人に対する「防備姿勢」をとっているのは日本だけではないような気がします。
- 長間之御気遣忝存知居申候。(^v^)--
 Alex K 2008年5月24日 (土) 05:41 (UTC)
Alex K 2008年5月24日 (土) 05:41 (UTC)
- 長間之御気遣忝存知居申候。(^v^)--
- キエフ空港も名古屋空港と同様に外国人にとって危ないところです。キエフ市内でさえ、外国人は白人でない限り、警察がその外国人をうるさく「接待」します。ですから、外国人に対する「防備姿勢」をとっているのは日本だけではないような気がします。
- 自分の専門は中世・近世史なので、思わず「Полуботківці」を「ポルボートク衆」にしました。ПРУСАКИНさんが仰るように、近代・現代史で用いられている「党」・「派」の方が相応しいかもしれません。自分が日本の近代・現代史についての本をあまり読んでませんから。
- キエフではよく中国人と間違えられて「接待」を受けることがありますが、日本人だと証明できればそれほどでもないと思います(無論、ケースバイケース、運の良し悪しですが。でも少なくともモスクワより怖くない……)。そういえば、私は一度近所に出た際にパスポートを家に忘れて警官に捕まってまずったことがありましたが(苦笑)これは自業自得です。「ポルボートク衆」については私は翻訳者の意向を尊重して「衆」でよいと思います。「党」・「派」としている出典があるわけでもないと思いますし、日本語としておかしいわけでもありませんから。
- では、いろいろありがとうございました。どうぞご自愛下さい。私もしばしば休んでいます。Дуже дякую вам!--PRUSAKYN 2008年5月24日 (土) 06:21 (UTC)
ブロックいたしました。
[編集]ブロックされたIPユーザーのブロック破りとして、ブロックいたしました。ウィキペディアはどこまでいっても共同作業の場です。少し編集を休んでください。--海獺(らっこ) 2008年7月26日 (土) 14:26 (UTC)
- (追記)[4]や[5]など、プロジェクトへのマルチポストでご不満をおっしゃられるより、対処にご不満がある場合は、メーリングリストでお願いいたします。
- 私があなた(IPユーザーとしての編集のようです)をブロックした理由は、ここでの経緯の通り、プレビュー機能を有効にお使いになっていないと思い、その注意喚起をいたしましたが、公式な方針ではないという理由でその注意の発言そのものを差し戻したことによる、ウィキペディアという場所の共同作業そのものの理念に対してご理解をいただけていないこと。および、直後にアカウントユーザーとしてブロック破りをし、再度、注意を促す発言を除去したことによるものです。あなたの行為は公式方針ではないものは守る必要がないという態度を示す非常に強硬なものです。ご自身の行為を省みていただくことをお願いいたします。--海獺(らっこ) 2008年7月26日 (土) 15:36 (UTC)
- 私は間違った行動をとったら([6]、[7])、その行動を注意してどこが間違っているかを説明していただくことは、規則であり礼儀でもあると思います。海獺さんは注意も説明もせずに私をブロックしたことが如何なことかと思います。ウィキの日本語版で、管理者が編集者に対してこのような態度をとっているのは、残念に思います。「ブロックいたしました」というお知らせで私の会話頁を飾っていただいたこと、有り難く思います。--
 Alex K 2008年8月2日 (土) 15:53 (UTC)
Alex K 2008年8月2日 (土) 15:53 (UTC)
- 私は間違った行動をとったら([6]、[7])、その行動を注意してどこが間違っているかを説明していただくことは、規則であり礼儀でもあると思います。海獺さんは注意も説明もせずに私をブロックしたことが如何なことかと思います。ウィキの日本語版で、管理者が編集者に対してこのような態度をとっているのは、残念に思います。「ブロックいたしました」というお知らせで私の会話頁を飾っていただいたこと、有り難く思います。--
キーシュについて
[編集]お久しぶりです。私はパソコンの事情でずっとウィキブレイクしていますが、いくつか質問があります。
- 以前UNRのハイダマークィの記事を翻訳したことがあったのですが、その際「キーシュ」が近代軍隊ではどの単位に当たるのかに自信がなかったためアップロードしませんでした。片仮名で「キーシュ」と書けばよいと思いますが、実際「キーシュ」は師団(дивізія)に相当する単位なのでしょうか。となると、「Курінь」は旅団、いわゆる「百人隊」というのは大隊なのでしょうか。UNRの軍隊は部隊単位名称や軍人の階級呼称が独特でおもしろいのですが、他国の場合との対応関係がいまひとつわからず、私には難儀な部分があります。
- ところで、「Курінь」はウクライナ語版によれば「クーリニ」ですが、辞書では「クリーニ」になっていますね。どちらが正しいのでしょうか。
- また、「Гайдамаки」の単数形はウクライナ語では「Гайдамака」で女性形名詞だということになるのでしょうか(トルコ語では「ハイダマク」のようですが)。ウクライナ語版を見るとアクセント位置が「ハイダーマクィ」になっているのですが、「ハイダーマクィ」で「ハイダーマカ」なのでしょうか。辞書では「ハイダマーカ」ですね。
教えていただけると助かります。いつもありがとうございます。--PRUSAKYN 2008年12月1日 (月) 15:58 (UTC)
お久しぶりです。質問毎に返事させていただきたいと思います。
- 私は、現代史においてあまり詳しくおりませんので、ご勘弁を願います。
- クルィプヤケーヴィチ氏によると、1918年におけるウクライナ国の歩兵の師団(дивізія)は3つの連隊(полк)から構成され、各連隊は三つのクーリニから、また各クーリニは4つの百人隊から構成されていた、となっています。キーシュと師団という呼称が別々に存在していたが、キーシュは師団と同じく幾つかの連隊から構成されいたらしい。つまり、キーシュは師団と同様な軍事組織でしたかもしれません。(Крип’якевич І. та ін. Історія Українського Війська. – Львів, 1992. )しかし、カプスチャンスクィイ大将は『キエフ・オデサへのウクライナ軍の出陣』では、キーシュは師団ではなく、旅団であると述べている(Микола Капустянський, Ген-Штабу Генерал-Хорунжий.ПОХІД УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ НА КИЇВ-ОДЕСУ (короткий воєнно-історичний огляд))。
- クーリニについてはわかりません。時代が違いますが、1944年のガリチア師団のクーリニは大隊として位置づけられております。そうなると、百人隊は中隊に当たります。
- ここでは、1917年に存在していた自由コサック軍団(Вільне козацтво)に関する記事において、百人隊の構成員数は55人から700人までとなっており、あまり大隊らしくありません。幾つかの百人隊は、各郷(волость)毎にクーリニを構成し、幾つかのクーリニは連隊を、さらに、幾つかの連隊は「地域」(округ)キーシュを構成していたそうです。
- ネットの辞書のほうが正しいと思います。私の手元にあるウクライナ語同義語辞典においても「クリーニ」になっています。ただ、「クーリニ」と間違った発音と書き方する人がいます。私もその一人です。
- ウクライナ語同義語辞典によれば、「Гайдамака」は男性形名詞です。ウクライナ語では「ка」で終わる名詞は必ずしも女性形名詞ではありません。よく言われている例としては、「犬」「Собака」です。ロシア語では女性形名詞であるが、ウクライナ語では男性形名詞になっています(ロシア化されたウクライナ人がよく間違っているところです)。其の外に「ка」で終わる男性名詞は、「Посіпака」(メシツカイ), 「бурлака」(浪士)、「Вояка」(軍人)などがあります。
- називний гайдама́ка гайдама́ки
- родовий гайдама́ки гайдама́ків
- давальний гайдама́ці гайдама́кам
- знахідний гайдама́ку гайдама́ків
- орудний гайдама́кою гайдама́ками
- місцевий на/у гайдама́ці на/у гайдама́ках
- кличний гайдама́ко гайдама́ки
--![]() Alex K 2008年12月1日 (月) 20:41 (UTC)
Alex K 2008年12月1日 (月) 20:41 (UTC)
丁寧な解説、どうもありがとうございます。
- UNRの軍隊は時期による改編が多く、またもともと義勇軍から発しているためか編成内容にもばらつきがあり、同じ単位なのではないかと思われる(例えばキーシュとディヴィージヤ)が並存していたりして厄介です(そこがおもしろいとも言えますが)。キーシュが師団相当と見られる一方、明らかに旅団であると解説されている例もあるとなると、キーシュのまま片仮名表記で処理しておいたほうが無難かもしれません。この部隊が近代的なディヴィージヤではなく伝統的なキーシュという名称を用いていることもこの部隊の特徴ですし、無理に翻訳しなくても片仮名表記にすることに利点がありそうです。クーリニや百人隊についても同様の扱いがよいかもしれません。
- ネット辞書のほうが正しいとすれば、ページ名ではそちらの出典表記のほうを優先し、ページ内で「クーリニ」とも呼ばれる、と解説を加えるのがよさそうですね(もしクーリニ/クリーニのページを作る際には)。
- ウクライナ語の辞書を見ると、「子音で終わっていても女性名詞であったり、аで終わっていても男性名詞である場合があるので注意すること」と必ず書いてはありますが、さていざ単語を見た場合には知らない単語だと区別がつかないことが普通で、学習者にとってはひとつの壁です。格変化まで教えていただいてありがとうございました。もっとよく勉強します。
- ところで、козацьке військоというのは、日本語文献では「コサック軍」と訳しているほうが普通かもしれません。それに、「軍団」という日本語を軍隊の正式な部隊単位以外の用法で使うと、軍団の書かれている通りなんとなく妙に俗っぽいニュアンスが強く出てしまうような……。
機会があったらゴーンタらのハイダマークィやUNRのハイダマークィの項目も翻訳したいと思います。単数形でページを作るか複数形で作るかはちょっと迷うところではありますが、読みにくい「クィ」という表記を避けることができるという利点から言えば、単数形のほうがよいかもしれません。いまパソコンが壊れているためすぐには書けませんが、いつか取り組んでみたいと思います(いつになることやら)。何はともあれ、ありがとうございました。--PRUSAKYN 2008年12月2日 (火) 06:38 (UTC)
こちらこそ有難う御座います。
- UNRの軍隊の単位は、専門家でないウクライナ人にとっても本当にややこしいものです。それを研究している日本人に対して尊敬と同情を表すしかできません。ウクライナでもUNR時代は「開発中」の分野であるからです。答えより疑問の方が多いと思います。
- 多分、諸記事での「クーリニ」を「クリーニ」に改変したが適切だと思います。
- 「аで終わっていても男性形名詞である場合があるので注意すること」と書いてありますが、аで終わっているよりも、ака・якаで終わっていると、男性形名詞である可能性だということがわかる、という気がします。ここで書いてあるように、ака・якаという語尾は、名詞に粗末ないし軽蔑の色合いを与えているのです。またここでは、ака・якаという語尾は、男性形名詞のみでなく、話の内容によって男・女形性名詞に変わることも可能だと書いてあります。たとえば、相手を「豚野郎」と強調して罵りたいとき、相手が男子であろうが女子であろうがсвинякаという語を用いられます。ただし、相手が男子だったら、свинякаは男性形名詞になり、相手が女子だったら、свинякаは女性形名詞になるはずです。
- 「軍団」と書くようになったのは、ドイツ騎士団の呼称の影響です。つまり、コサックの「軍」と騎士団の「団」をあわせて用いていたわけです。たしかに、「軍団」という用語は、奈良時代の日本の固有軍事組織と、現代の普遍的軍事単位を表しているので、військоの訳として相応しくないという気がしないでもないんです。PRUSAKYNさんの助言にしたがって、「軍団」の代わりに「軍」という用語を用いることとします。今後とも御指摘の程よろしく御願いいたします。--
 Alex K 2008年12月2日 (火) 11:03 (UTC)
Alex K 2008年12月2日 (火) 11:03 (UTC)
- 助言していただきありがとうございます。ウクライナでの研究状況などを含むいろいろな情報をいただき、いつも勉強になります(UNRの研究はウクライナでもまだ発展途上である、など)。
- ああ、なるほど、「軍」+「団」という解釈だったのですね。そのまま「軍団」で解釈し上のようなコメントをしました。たしかにドイツ騎士団にならった呼び方と注釈が入れば合理的な翻訳だと理解できます。ただ、やはり一般の日本語話者(日本人)が注釈なしで「軍団」を見た場合にはまず「○○軍団」というよくある日本語の俗流の呼び方が思い起こされるため、ページ名という「注釈なし」の部分については軍団は避けたほうがよいかもしれません。ふつうの文章の中ではもう少しはばのある対応が選択肢としてあると思います。早速の対処、ありがとうございます。--PRUSAKYN 2008年12月2日 (火) 13:52 (UTC)
オデッサについて
[編集]オデッサについてですが、何点か問題があります。
- 焦って改名する必要はありません。Wikipedia:ページの改名をご参照ください。通常は改名提案から一週間程度の告知期間をおくことになっています。
- 移動先ページの履歴がリダイレクト一版のみの場合は「移動」機能で移動できます。ただし、オデッサについては既に版を重ねてしまっているため、Wikipedia:移動依頼が必要です。
- 削除依頼のやり方を誤っています。Wikipedia:削除依頼を熟読願います。Wikipedia:リダイレクトの削除依頼と勘違いなさっているのではないでしょうか。
以上です。できれば、関連する編集をご自分ですべて差し戻し、各種方針を熟読の上、改名提案からやり直すことをお勧めします。--郁 2008年12月11日 (木) 12:48 (UTC)
- オデッサ_(オデッサ州)については、改名提案に出しておきました。オデッサ_(曖昧さ回避)については戻せないので、後付的にですがこちらも改名提案しました。--PRUSAKYN 2008年12月15日 (月) 15:29 (UTC)
ウクライナ国
[編集]こんにちは。またしてもお邪魔します。
さて、1918年4月に成立したヘーチマンのウクライナ国について質問があります。この国は、私の解釈では白軍(uk:Біла армія)の勢力ではないと思っていたのですが、ウクライナ史研究ではどのような評価がされているのでしょうか。これは白軍の一派なのでしょうか、UNRの流れに含まれるのでしょうか、それともロシア人が言うようにまったくのドイツの傀儡政権なのでしょうか。もちろんいろいろな見方はできると思うので端的に評価をすることは難しいと思うのですが、1. 最近のウクライナ史研究での成果と主流の考え方、それから2. 最新ではなくいわば素人のウクライナ人一般がどのように思っているか、大雑把でよいので教えていただけますか?--PRUSAKYN 2008年12月15日 (月) 15:29 (UTC)
質問ありがとうございます。
1.残念ながら、最近のウクライナ史研究での成果について詳しくのべることができません。1990年代末の研究史においてウクライナ国は、庶民出身の社会主義者(いわゆる左翼派)が指導するUNRと違って、貴族・大商人・豪農出身の君主主義者(いわゆる右翼派あるいはヘートマン主義者)が指導するウクライナ人の国民国家である、というふうに大学で習っていました。ウクライナ国の支配者階級は、ウクライナのロシア連邦内の自治権ないし独立権を主張していたものの、旧ロシア帝国のエリートであったため、ウクライナの自治権も独立権も認めない白軍の「血筋のいい」指揮官に対して親しみを感じていたことが事実です(一方、ウクライナ国は白軍から「ドイツの傀儡政権」として嫌われていたそうです。それにしても、ウクライナ国はUNRの反乱軍によって滅亡されると、ウクライナ国の軍人は多く白軍に加わっりました。)つまり、ウクライナ国は、白軍ともUNRの一派ではなく、ウクライナ在住の上流階級の国であって、ロシア帝国主義とウクライナ社会主義と異なっる独自の原理でウクライナを発展させようとした組織であった、という見解が一般的でした。
2000年代の研究史は、どのようなものであるか分かりません。私の友人と同級生であったM.コヴァリチュクは、1917年‐1921年のウクライナの内戦期の若手研究者の一人ですが(2006年にこの本 ([8])を出しました)、彼は会話でウクライナ国に対して何時も批判的であったことを覚えています。というのは、コヴァリチュクは、ウクライナ国の支配階級が自国の未来をロシア連邦と結ぼうとしていたため、ウクライナ国は白軍と変わらんほどの「非ウクライナ的」存在であったと強調してました。残念ながら、コヴァリチュクと長い間あってませんので、彼の見解が変わったかどうか分かりません。その他の研究者の主張については何も言えません。
2.素人のウクライナ人の全員から言えないが、素人のウクライナ人の自分から言えます。私の見解は、1990年代末の研究史の見解とほとんど変わりません。それに、私の曽祖父がウクライナ国の軍人であったので、私はどっちかというとウクライナ国贔屓です。また私の友人の間でも、UNRの扇動政治家より軍事・科学・文化の面で成果を残したウクライナ国の統治者の方が人気があります。ウクライナ史上で独自の君主制は珍しいものであるので、君主制国であるウクライナ国に対して憧れを感じる人が少なくありません。しかし、そうとはいえ、UNRの存在を重視してウクライナ国の存在価値を否定する人もいます。上述したコヴァリチュクはその一人です。
あまりまともな答えになってませんから、御容赦ください。--![]() Alex K 2008年12月16日 (火) 09:40 (UTC)
Alex K 2008年12月16日 (火) 09:40 (UTC)
とても参考になります。ありがとうございます。なんと、曾お祖父様は当事者でいらしたのですね!ウクライナ国は、ウクライナ独立派からも大ロシア主義者からもとかく悪く書かれることが多い印象があったのですが、私の曽祖父も昔の政府の軍人(といいますか江戸時代の佐賀鍋島藩の侍)で、所謂日本の右派精神の源流、「葉隠武士」といって日本の軍国主義の元を作ったとして評判が悪い一団の一人なのですが、だからというわけではありませんが保守主義のウクライナ国というものに興味を抱きました。
日本にいると、UNR以上にウクライナ国のことはほとんど知ることができません。まして、当のウクライナ人たちがどう思っているかは、なかなか知ることができません。評判は必ずしも悪くはないようですね。日本人というのはどうしても「判官贔屓」なものですし、このような負けたけどそれなりに主義主張を持つ、芯のある国家・政権というものにはたいへん興味をそそられます。反対派から悪く書かれるというのは、逆に言えば反対派からは無視できない(あるいは強いて無視しなければならないような)重要な存在であったということにほかなりません。二月革命~十月革命後に成立した国家の多くが(建前にせよ)共和制をとっていた中で、明確に君主制を打ち出したウクライナ国には、その独特なスタンスで興味をひきつけられます。さらに、その理論を作ったのは著名な歴史家であり、よくある政治家や扇動家などではなかったという点に注目が行きます。これからせめて常識的な見解は知るよう、勉強したいと思います。
そのための入り口として、情報を与えてくださったことに感謝いたします。--PRUSAKYN 2008年12月16日 (火) 10:43 (UTC)
こちらこそ有難う御座います。曾お祖父様は佐賀藩士ですか?凄いですね!私は少年時代には葉隠のロシア語訳をよんだことあります。ウクライナの日本贔屓な若者、特に武道に関わりの人々の間では、その本の人気がかなり高いです。おそらく聖書より読まれていると思います(笑)。
ウクライナ国は確かに面白い存在で有りますが、現在の欧米世界は「民衆主義」・「<自由>主義」で動いているので、「君主主義」・「<保守>主義」にもとづいていたウクライナ国は次第に忘れらているのです。「流行はずれ」といえますか…。
まあ、そいうことなので、これからも宜しく御願いします。--![]() Alex K 2008年12月17日 (水) 08:46 (UTC)
Alex K 2008年12月17日 (水) 08:46 (UTC)
こちらこそよろしくお願い致します。こちらでは凄いも何も「葉隠」はもう忘れ去られていますし、過去の経験から言って、多分もう流行しないほうがよいと思います……。聖書より読まれているとは(笑)。日本では多分聖書のほうが読まれていると思います(笑)。
日本のエセ保守主義者が隠れアメリカファンなのと、ウクライナ国がロシアへ接近した事情に共通点が見出せるのか否か、どのような相違があるのか、多分ヨーロッパ人はこの観点からは研究しないでしょうし、日本的な見方というのもあると思います。過去数十年間、単なる「ドイツの傀儡政権」とか、もっとひどいと政権の存在すら無視して「ドイツ占領下のウクライナ」とかいう文言で片付けられてきたウクライナ国は、その時期と比べればむしろこれからもっと注目されると言えるのではないでしょうか。不運なのは、例えば白色フィンランドは生き残ったが、ウクライナ国は滅んでしまって有力な継承者がいなかった、という点でしょうか。どっちもドイツ軍との同盟でロシアを打ち破った右派の国家で、後者だけあとから悪く言われる筋合いはないと思うんですけどね。
「<自由>主義」は問題を露呈していますし、全否定されていた帝国主義でさえ現在では見直しが進んでいます(ただしこの場合、帝政はロシア的なものではなくオーストリア的なものを念頭においていると思いますが)。良きにせよ悪しきにせよ世界の保守化が起こると同時に必然的に歴史的な保守思想への注目・見直し(再評価)も行われるものと思われます。そうした中で、ウクライナでは自国の保守主義の研究が進むかもしれません。ただ、もし多くのウクライナ人がもっと<自由>で<民主的>なものが好きならば、結局ウクライナ国はあまり人気が出ないかもしれませんね……。--PRUSAKYN 2008年12月17日 (水) 15:07 (UTC)
ウクライナ語版の記事 Соборна Україна (лінкор)
[編集]あけましておめでとうございます。新年早速ですみませんが、また質問があります。
ウクライナ語版にuk:Соборна Україна (лінкор)という記事が作られたようなのですが、このページによればこの船はロシア帝国の「Лінійний корабель "Імператриця Марія"」のことだとなっています。
ですが、[9]やほかのひとつふたつのページを見ると、「Соборна Україна」の排水量は27 900 トンとなっており、「Імператриця Марія」の排水量とは一致せず、別の船「Император Николай I」の排水量とほぼ一致します。また、同リンクでは「Соборна Україна」の編入年を1918年としていますが、「Імператриця Марія」は第一次世界大戦中に完成しているので年が一致しません。
また、[10]には「Навесні 1919 року більшовики захопили Херсон, Миколаїв, Одесу, Крим. У травні, після двох тижнів підводних робіт, вони підняли з дна Севастопольської бухти найсучасніший лінкор «Імператриця Марія», підірваний німецькою агентурою 1916 року. «Марійку» було відбуксирувано до Миколаєва, у док. Там же, в Миколаєві, більшовики терміново добудовували крейсер «Гетьман Богдан Хмельницький», лінкор «Соборна Україна», низку міноносців.」と書かれているのですが、これはどういう意味でしょうか。私はムィコラーイウには«Гетьман Богдан Хмельницький»と«Соборна Україна»、それにいくつかのміноносецьがあって、そこに«Імператриця Марія»が持っていかれた(つまり«Імператриця Марія»と«Соборна Україна»は別の船)というように理解したのですが、読み違えている感じもします。
専門外の質問でご迷惑かとは思いますが、私もウクライナ語やロシア語の読解にあまり自信がありません。アドバイスしていただけるとたいへん助かります。
ところで、「Соборна Україна」というのはウィキペディアでも曖昧さ回避のページが作られるほどいくつも使用例がある名称のようですが、日本語訳するとどのような意味になるのですか?--PRUSAKYN 2009年1月5日 (月) 08:47 (UTC)
あけましておめでとう御座います。
かなり専門的質問なので、正確に答えることができません。
ただ、Dzerkalo Tyzhniaに登場する«Гетьман Богдан Хмельницький»、«Соборна Україна»とІмператриця МаріяについてのПРУСАКИНさんの見解は正しいと思います。この資料を読めば、«Імператриця Марія»と«Соборна Україна»は別の船であるとしか解釈できません。
また、排水量に関するПРУСАКИНさんの推測を見ると、確かに«Імператриця Марія»と«Соборна Україна»は異なった船であったという結論にいたります。
まぁ、当時の資料は手元にない限り、なんともいえません。インタネット上の個人サイトとヴィキをあまり信用できませんから。
役立たず申し訳なく思います。--![]() Alex K 2009年1月7日 (水) 00:12 (UTC)
Alex K 2009年1月7日 (水) 00:12 (UTC)
新年ならびにウクライナのクリスマス、おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
新年さっそくのご回答ありがとうございます。
私も実のところ軍艦にそれほど詳しくなく、そもそも日本ではウクライナ海軍はほぼ完全に無視されているので詳しくなりようがありません。その手のサイト以外に情報源がありませんし、得てして間違いや原因不明の食い違いもありますから(出典で«Імператриця Марія»がそれら戦艦の中で最良の船と書かれているのは間違いか、少なくとも誇張です。ヴォーリャやスヴォボードナ・ロシアも同じ型の船ですから、マリーヤだけとりわけ優れているということはありません)。
去年はウクライナ海軍90周年だったおかげで一昨年よりずいぶん情報が増えたようですが、結局「ソボールナ・ウクライナ」についてはわからず仕舞いでした。
今回の問題については、多分私のウクライナ語の読解は間違っていなかったということで、胸を撫で下ろしました(期末試験に合格?(笑))。なぜウクライナ語版のページは同じ出典を使いながら別の結果になったのかが気になるところですが、もしかしたら執筆者の方は別の、何か決定的な文献をお持ちなのかもしれません。ネット上の情報だけからの推測では、この数年間、私はずっと「ソボールナ・ウクライナ」は旧「ニコライ1世」のことだとばかり思っていました……。
アドバイスありがとうございました!別件ですが、ヘーチマンを書き直しました。ウクライナ語版が一覧だけだったのでロシア語版から翻訳して少し書き足しましたが、間違いもあると思いますので、お手すきのときにでも一読してくださると助かります(ウクライナ以外のヘーチマンについては、別のページで後日作るつもりです)。--PRUSAKYN 2009年1月7日 (水) 06:45 (UTC)
返答有難うございます。
ПРУСАКИНさんに12つの料理をご馳走したいですが、あいにくにインタネットはまだそこまで発達しておりません(^V^)。
現在はウクライナ海軍の存在は薄いため、その海軍に対する興味は関係者の方以外は高くありません。海戦をしない海軍は、画を描かない画家と同様です。残念ながら、近世のコサックの海賊行為の他に、ウクライナ海軍史では輝かしい場面が少ないです。日本の海軍には一目を置いています。。。
ヘーチマンは読んでおきます。問題がありましたら、記事の会話頁に書いときます。すごくいい記事が出来ましたな!--![]() Alex K 2009年1月7日 (水) 07:13 (UTC)
Alex K 2009年1月7日 (水) 07:13 (UTC)
ありがとうございます!インターネットがはやくそこまで発達するよう切に願っております(^_^)V。
自衛隊は、実戦を経験しないことを一番の誇りにしているそうですが……、なるほど海戦をしない海軍は、画を描かない画家と同じですか!まあ、戦をしすぎた海軍を持つ国民はそれも困りものだと思うわけですが、逆に戦をしない海軍の国から見ると、そう見えるのかもしれませんね。ちなみに、私の遠い親戚は海軍少佐で、戦時には帝国海軍の精鋭・第二水雷戦隊旗艦軽巡洋艦「神通」の水雷長でしたが、コロンバンガラ島沖海戦でやられてしまいました……。かわいそうに……。
日本で1918年ころのウクライナ海軍の存在が完全に黙殺されているのは、多分日本の軍事マニアにロシア・ファンやソ連シンパが多いせいでしょう。彼らは、「あれはロシア海軍であって、ちょっとドイツの占領軍に盗まれていた時期があっただけだ」と言うでしょう。いや、たんにウクライナのウの字を知らないだけか。
ヘーチマンへのコメント、ありがとうございました。--PRUSAKYN 2009年1月7日 (水) 16:28 (UTC)
こちらこそ、ありがとう御座いました。
自衛隊は、実戦を経験しないことを一番の誇りにしていることが驚きです。戦わずして軍隊の意義がなくなるはずです。そもそも、戦をしない、軍隊を持たないことが一番いいだと思いますが、隣国同士が戦いしまくると、自国では実戦を経験した軍隊を持った方が安全だと思います。
まぁ、そういうことで、ヘーチマンに移りたいと思います。--![]() Alex K 2009年1月8日 (木) 02:25 (UTC)
Alex K 2009年1月8日 (木) 02:25 (UTC)
現代日本の考え方によると、政治的交渉が失敗すると戦争になると考えるので、自衛隊の出番が来るというのは、その時点で日本国の政治が失敗したのだということを意味するのです。政治の失敗は、あまり名誉なことではありません。自衛隊は、政治交渉を省いて最初から武力で相手を屈服させるために出兵するためにあるどこかの国の軍隊のような意図では作られていませんから、おのずとこうなります。
それと、武力行使しないまでも存在するだけで「抑止力」となることがあります。自衛隊は、それを目指していると思います。自衛隊は、いかにも優秀で強そうに見えることに重要な意義があると思います。だれもやたら強そうな軍隊と戦争したがるひとはありませんから、無駄に周辺国と小競り合いをせずにすむというものです。
実際中国辺りと戦争をやって自衛隊が勝てるのかは知りませんが、中国人が「自衛隊とやると簡単には勝てないだろう」と思わせることが重要なのです。戦争してしまえば、勝っても負けてもお互い経済的・文化的に大きなダメージをこうむりますから、やらないですますにこしたことはない、というのが、恐らく戦後日本人の考え方でしょうし、大方の中国人もそれは理解していると思います。--PRUSAKYN 2009年1月8日 (木) 05:44 (UTC)
ウクライナ国歌の歌詞について質問があります。
「Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.」の箇所の「браття молодії」は呼格ですか?
「Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.」や「І покажем, що ми, браття, козацького роду.」の「браття」は呼格ですか?それとも「ми」との同格で主格ですか?
これまでの日本語訳が、よく見たらだいぶおかしかったので修正したのですが、この部分を主格ととるか呼格ととるかで日本語訳をまた大きく変えなければならないかもしれません。いま主格のように訳してあるのですが、よく考えたら呼格じゃないのかと思い、ただ自信がないので質問させていただきました。いつもすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。--PRUSAKYN 2009年1月8日 (木) 15:49 (UTC)
質問有難う御座います。お役に立てたら嬉しいです。
「браття молодії」と「браття」は呼格で、「ми」は主格です。呼格の言葉は、両側からコンマで囲まれております。「браття」への呼びかけをあらわしております。「若き兄弟たちよ(呼格)、われわれが(主格)○○です」といった感じになると思います。
こちらこそ宜しく御願いいたします。--![]() Alex K 2009年1月9日 (金) 00:35 (UTC)
Alex K 2009年1月9日 (金) 00:35 (UTC)
そうですね。私もそう思いまして、ただ「ми, браття,」の「браття」を最初主格「ми」と同格に読み違えてしまったので訳を誤りました。元の訳が「私たちの兄弟はコサックの民族であることを」などと書かれており、すっかりそれに引きずられてしまいました。「の」を抜いただけで済ましてしまって……。
ありがとうございます。修正しておきます。--PRUSAKYN 2009年1月9日 (金) 06:39 (UTC)
フメリヌィーツィクィイの乱
[編集]コメントありがとうございます。履歴等の問題もあるので、基本的には一度本文をアップしてしまい、それから私や他のユーザーが編集なり修正なりを加えるというスタイルだろうと思います。
その前に私に一度目を通してもらいたいかどうかはAlex Kさんのお考え次第です。一般には、個人のサブページというのは個人の領域だと思うので、特に依頼されるようなことがなければ私はそこへ「踏み込む」ことはしませんが、先に修正した方がよいのであればそうします。どっちがいいですか?(ただ、時節柄多忙のため、私の作業は遅くなるかもしれません。)
なお、ざっと見た限りではAlex Kさんの現在のページも読みにくいなどということはなく、日本語の間違いもごくわずかだと思います。たいへん素晴らしいページができましたね!--PRUSAKiN 2009年3月4日 (水) 08:24 (UTC)
ご返答大変有難く存じます。
記事を作成する前にПРУСАКИНさんは修正していただければ幸いです。長期修正になってもかまいません。ご時間が許すほどに直して頂ければ。
私は日本語でうまく書けないが、いい記事をつくってみたいので、敢えてПРУСАКИНさんの御援助に憑み申し出ました。いつもいつも助けていただいて御礼のことばも御座いません。この度も、何卒宜しく御願いします。--![]() Alex K 2009年3月4日 (水) 12:52 (UTC)
Alex K 2009年3月4日 (水) 12:52 (UTC)
- まず、単純な技術的問題です。日本語版では== ○○ ==の部分にリンクを作らないようにと決められているため、{{Main}}テンプレートの使用に切り替えました。
- ヤレーマ・ヴィシュネヴェーツィクィイは「大公」なのでしょうか?ウクライナ語版やポーランド語版を見たのですが、「公」か「公爵」のように思われます(選帝侯の「公」でしょうか?)。
- 長文のため作業に時間が掛かります。ひととおり終わったらご報告致します。最近の活動ページからすると1週間くらいはかかりそうですが、どうぞお待ち下さい(汗)。--PRUSAKiN 2009年3月10日 (火) 13:20 (UTC)
- 加えて質問です。
- まず単純に私が知らないだけの問いですが、キエフ・アカデミーとは、ペトロー・モヒーラのひらいたアカデミーのことですか?それとも別の施設ですか?
- イスリャム・ゲライ3世ですが、メングリ1世ギレイのような語順で書かれることがあります。ウクライナ語版もuk:Іслям III Ґерайですね。クリミア・タタール語ではIII İslâm Geray(3世イスリャム・ゲライ?)のようです。どの語順がよいのでしょうか?III İslâm Gerayだと、たしかにイスリャム・ゲライ3世」と訳せなくもなさそうですが。--PRUSAKiN 2009年3月10日 (火) 18:17 (UTC)
- 御修正と御指摘ありがとうございます。ПРУСАКИНさんの御都合が許す限り、御修正続けていただければ幸いです。
- 1. ヤレーマは確かに「公」であり、「大公」ではありません。私の書き違いでした。すみません。
- 2. キエフ・アカデミーはキエフ・モヒラ・アカデミーのことです。uk:Києво-Могилянська академія (1659—1817)。そもそも、カレッジであるが、当時は「アカデミー」と呼ばれました。17世紀のキエフでキエフ・モヒラ・アカデミーの他にアカデミーがなかったため、「キエフ・アカデミー」と省略させていただきました。日本人にとって読みづらいウクライナ語の単語をできるだけ少なくするためです。
- 3. イスリャム3世ゲライの語順に関しては、ポーランド国王の記事を参考にしました。例えば、ヤン2世カジミェシュ・ヴァーザ、ヤン3世ソビエスキなどです。つまり、「名前」・「番号」・「家名(苗字)」という形式をとったんです。
- 4.技術的修正が必要であれば、私に御知らせください。ПРУСАКИНさんの時間を奪わないため、こうした修正は私が遣りましょう。--
 Alex K 2009年3月10日 (火) 23:13 (UTC)
Alex K 2009年3月10日 (火) 23:13 (UTC)
- 1. 了解です。この場合の「公」は、「公爵」の意味でしょうか?
- 2. 日本語文献では「キエフ・モヒラ・アカデミー」で出てくるので、それでいいんじゃないかと思います。本文では、「キエフ・モヒラ・アカデミー|キエフ・アカデミー」の形にしようかと思います。
- 3. ではメングリ1世ギレイの語順でよいということですね。ただ、今の状態だと、確か「イスリャム・ゲライ3世」の語順で書かれている箇所があったと思います(全部かは把握していません)。
- 4. よくわからない部分があればお願いします。--PRUSAKiN 2009年3月11日 (水) 15:21 (UTC)
- 重ねて失礼します。ヴワディスワフ・ドミニク・ザスワフスキで「クラクフ県の知事」という記述を「県長」に変更なさっていますが、「県知事」という翻訳だと問題があるのでしょうか?私の記憶だと、確か日本語文献では「ヴォイェヴォダ」の類は「県知事」という翻訳が用いられていたような気がするのですが(「県長」という訳があったかは記憶にありません。調べないと)。
- フメリヌィーツィクィイの乱のほうで私は深く考えずに「県長」を「県知事」に書き換えてしまったので、もし何か不都合があるようでしたら戻さなければなりません。--PRUSAKiN 2009年3月11日 (水) 17:43 (UTC)
- ボフダンの子息の名前の表記は、ティモフィイとティモフィーイのどちらがよいですか?どちらでも日本語として問題はないと思うので、好きな方に統一していただけますか?ページによってはティーミシュと表記しているのもあるようですね。--PRUSAKiN 2009年3月12日 (木) 06:20 (UTC)
- この度のご修正ありがとうございます。さて、返答させていただきます。
- 「ヴォイェヴォダ」は「県知事」と翻訳されているのであれば、「県知事」にしましょう。私はただ、「ヴォイェヴォダ」を「県知事」で訳するのが相応しくないと思っていました。ヴォイェヴォダが「県」と訳される行政単位の首長であるので、市町村長に倣って「県長」にしていました。そうすると「県」(ヴォイェヴォドストヴォ)と「県長」(ヴォイェヴォダ)という、二つの用語の語義と語根の共通性が保たれます。「知事」は日本の県の首長のみに対して用いる単語であると思っていました。
- 「ー」を入れた方がいいと思います。「チェルノブィリ」のようなアクセントずれの発音にならないように。私の方から修正いたしましょう。
- 「ティモフィーイ」について記事が出来上がりましたら、「ティーミシュ」をredirectにしましょう。
- パソコンで変換すると、自然に「県長」の文字は出てくるのでそういう日本語はあるのだと思います。ただ、私の記憶では「ポーランドの○○県知事」という言い方が先にありました。ですがどちらがより一般的な翻訳なのか、自信がありません。もしかしたら「県長」の方が正しいのかもしれません。後日、日本語の本で調べてみたいと思います。ただ、少なくとも「知事」は日本以外についても普通に使われる用語です。例えば、現在の日本以外の国の州や県の首長について「○知事」と呼ぶことはごく自然です。
- そうなんですよね。日本のロシア関係の何人かの学者が主張していますが、気分で長音符を使ったり使わなかったり、挙句に間違った位置に好き勝手に使ったりしてるくらいなら、いっそ全部の単語に長音符を入れたほうがよい、ですよね。「ウクライーナ」と書かなかったせいで、私たちは「ウクライナ」と「ラ」にアクセントを置いて発音している(苦笑)
- 諒解です。そうしましょう。
- ひとつお詫びがあります。以前「コサック軍団という呼び方はしない」と言ってしまったのですが、どうもそれはあるようです。たまたま私がそれまで見ていた文章に「軍団」が出てこなかっただけのようです。今日オレンブルク・カザークについての論文を見ていたら、普通に「カザーク軍団」と書かれていました。私の浅学で間違ったことを教えてしまい、すみませんでした。ひとつだけ言い訳をすると、多分「コサック軍団」よりは「コサック軍」のほうがよく目にするかな、ということですね……。どうしましょう、以前改名してしまったページを元に戻しますか?こうなったら、主執筆者の方の「好み」の方でよいと思うのですが。--PRUSAKiN 2009年3月13日 (金) 17:02 (UTC)
- 日本国語大辞典には「県長」がないが、「県知事」が載ってあります。これから「県知事」を書くようにします。ご指摘ありがとうございました。
- 私は表記にこだわりませんが、表記には選択肢がありましたら、ウクライナ語の発音に近い表記をサポートします。「ー」でアクセントを示す書き方がいいかも知れません。
- 「コサック軍」にしましょう。「軍団」は現在の軍事単位と間違えやすいので、単なる「軍」にした方がいいと思います。--
 Alex K 2009年3月15日 (日) 18:32 (UTC)
Alex K 2009年3月15日 (日) 18:32 (UTC)
- 「対オスマン帝国の外交策」の節でモルドバ公のご息女の名がロザンダ・ルプになっていますが、これは何語で表記するのが妥当なのでしょうか。ルーマニア語版を見る限り「Ruxandra」なので「ルクサンドラ」か「ルグザンドラ」かと思います(濁るのか濁らないのかよくわかりません…)。一方、ウクライナ語版を見るとuk:Лупул-Хмельницька Розандаなので、「ルプ」じゃなくて「ループル」のようです。
- uk:Кисіль Адамの名前の表記が、ある箇所ではポーランド語名、別の箇所ではウクライナ語名になっていました。どちらで表記するのがよいのでしょうか。
- 「コサックの国家」の節で「ドイツ法」とあるのは、具体的には「マクデブルク法」のことでしょうか?
- 「物資郵送」というのがなんとなく郵便局な感じで変な感じがしたので「物資輸送」に修正したのですが、それに合わせて「軍の郵送官」も「軍の輸送官」に修正しました。もし間違っていたら戻して下さい。--PRUSAKiN 2009年3月16日 (月) 17:38 (UTC)
- ロザンダ・ルプはウクライナ語的表記です。ヤコヴェンコさんの論文では「Лупул」ではなく、「Лупу」と書いております([11])。ルマニア語でRuxandra (Руксандра)と書いているのなら、ルクサンドラ(ルクサンドラ・ドラゴミルのように)にしましょう。
- すみません。アダムは正教徒のウクライナ人(ルーシ人)であったため、ウクライナ語名にしましょう。日本の文献で彼の名前はどのように書かれているかがわかりません。
- 「ドイツ法」は「マクデブルク法」を意味しています。当時のポーランド・リトアニア連合の記録では「マクデブルク法」かわりに「ドイツ法」(німецьке право)という用語が使用されていたので、記事で「ドイツ法」と書きました。また、「マクデブルク法」という用語を現在の日本語の文献には見つからなたったんです。もし、日本語の文献では「マクデブルク法」が用いられているのであれば、「ドイツ法」を「マクデブルク法」に換えてもいいと思います。
- ご指摘ありがとうございました。「ゆそう」に「う」を入れてしまったせいで、「輸送」は「郵送」になってしまいました。恥ずかしいかぎりです。--
 Alex K 2009年3月17日 (火) 08:58 (UTC)
Alex K 2009年3月17日 (火) 08:58 (UTC)
- そうでしたか。出典確認しました。ありがとうございます。ルーマニア語表記は「Ruxandra」であっていると思うのですが、必要ならもう少しきちんと調べましょう。ただ、その片仮名表記については、スポーツ分野の外国語表記は死ぬほどめちゃくちゃなので、ルクサンドラ・ドラゴミルの表記もすぐには信用できません。ルーマニア語の発音とその日本語表記に詳しそうな人に聞いてみる必要がありそうです(後日探してみます)。
- そういうことならウクライナ語名にしましょう(日本語文献での表記、私も知りません)。ただ、すみません、最初に出てきたのがポーランド語名のほうだったので、深く考えずに全部ポーランド語風に直してしまったかもしれません。
- 私が「マクデブルク法」などという専門用語を知っているということは、多分どこかの日本語文献に書いてあったんだと思います。ただ、自信がないのでとりあえずは「ドイツ法」で行きましょう。マクデブルク法も赤リンクですし。調べてみて「マクデブルク法」の用例が確認できれば、そのときに変更してもよいでしょう。「ドイツ法」ではあまりに指す対象が広すぎる気もするので(現代のドイツの法律も「ドイツ法」ですし)。
- 諒解です。よくあることです。パソコンは間違っていても「それらしく」変換してしまうので危ないですね。--PRUSAKiN 2009年3月17日 (火) 14:37 (UTC)
- 「ルクサンドラ」に関してはルクサンドラ・ドノーセを見つけました。--
 Alex K 2009年3月18日 (水) 04:51 (UTC)
Alex K 2009年3月18日 (水) 04:51 (UTC)
- ルーマニア語のわかる方に聞いてきました。その方がルーマニア人の友人に尋ねてくださったようで、「ルクサンドラ・ルプ」で間違いないようです。むしろ、「ヴァシレ・ルプ」なのか「ヴァシーレ・ルプ」なのかの方が問題のようでした。日本語文献で探してみたいところですが、一帯この辺りの歴史って、どの本に載ってるんでしょうね?--PRUSAKiN 2009年3月24日 (火) 10:51 (UTC)
調べていただいてありがとうございます。日本語文献に関しては以下のよう本がありますが、モロドヴァ史についての記述は詳しいかどうかわかりません。
- ルーマニア史 / コンスタンチィン・チェ・ジュレスク. 恒文社, 1972.
- ルーマニア史 / アンドレイ・オツェテァ. 恒文社, 1977.
- ルーマニア史 / ジョルジュ・カステラン. 白水社, 1993.
しかし、私はその本を読んだことがありませんが・・・--Alex K 2009年3月24日 (火) 12:53 (UTC)
- ありがとうございます。時間があったら調べてみたいと思います。多分、モルドバについても載っているでしょう。ヴァシレ・ルプはその道ではそれほどマイナーじゃないと思うので。--PRUSAKiN 2009年3月24日 (火) 13:26 (UTC)
- ところで、フメリヌィーツィクィイの乱の記事を作成してもいいでしょうか? それとも、まだ早過ぎるでしょうか? 私は見た限りでPRUSAKiNさんのおかげで当記事案はすでに完全に修正されております。いかがいたしましょう?--Alex K 2009年3月24日 (火) 14:26 (UTC)
もう少しあります。
- uk:Януш Тишкевичの名はウクライナ語名がよいですか、ポーランド語名がよいですか?
- Weinryb, Bernrd D. The Hebrew Chronicles on Bohdan Khmel’nyts’kyi and the Cossack-Polish War // Harvard Ukrainina Studies. Vol. 1 Number 2 June 1977.のリンクが切れています。確認お願いします。--PRUSAKiN 2009年3月24日 (火) 15:15 (UTC)
- pl:Tyszkiewiczowieはヴォルィーニ地方出身のルーシ系の貴族であるので[12]、ウクライナ語名にしましょう。「ヤヌシュ・ティシュケーヴィチ」でいいでしょうか?
- 確かに切れています。リンクなしで書いておきます。--Alex K 2009年3月24日 (火) 15:42 (UTC)
- 私はヤーヌシュのほうがいいと思うんですが、同じページ内にヤヌシュ・ラジヴィウがあるんでヤヌシュに合わせておいたほうがよいかもしれません。違っててかまわなければ、ヤーヌシュにしましょう。ほかのウクライナ人の名前は長音符ありが多いので。
- 了解です。あとは今は特に問題点が思いつきません。ページをアップしてもよいと思います。--PRUSAKiN 2009年3月24日 (火) 16:02 (UTC)
- わかりました。今回「ヤーヌシュ」にしましょう。今後とも問題がありましたら、いつでも議論と移動ができますし。
- ご苦労をかけいたしました。ほんとうに有難うございました。お礼の言葉もございません。m(_ _)m
- では、早速、記事を作成させていただきたいと思います。--Alex K 2009年3月24日 (火) 16:10 (UTC)
素敵な勲章ありがとうございました!私は武功もなくこのような勲章はもらったことがありません(日本は戦争してないので仕方ありませんが)。感謝感激です!
何かの時には今後ともよろしくお願い致します。ページの作成お疲れ様でした。素晴らしいページができましたね!--PRUSAKiN 2009年3月24日 (火) 17:28 (UTC)
こちらこそ有難うございました!PRUSAKiNさんの御協力がなければ、あのページが出来上がらなかったはずです。重ね々々御礼を申しあげます。これから、私の方からもお役に立つことができれば、嬉しく思います。今後とも時間と希望が許す限り、頑張りましょう!よろしく御願いいたします。--Alex K 2009年3月24日 (火) 17:37 (UTC)
キエフ府主教
[編集]一連のキエフ府主教関連のカテゴリ整理、お疲れ様です。記事執筆者の意図を測りかねて整理を躊躇っていたところでした。個別の記事については異論がこれからあるかもしれませんが、取り敢えず、上位カテゴリの肥大化を避ける事には賛成です。ありがとうございました。--Kliment A.K. 2009年3月26日 (木) 04:01 (UTC)
- コメント有難うございました。今後とも東欧関係の記事を修正して行きましょう。よろしく御願いします。--Alex K 2009年3月26日 (木) 04:14 (UTC)
ウラジーミル1世の家庭生活と子どもたち
[編集]ウラジーミル1世の家庭生活と子どもたちについてですが、ノート:ウラジーミル1世の家庭生活と子どもたちに編集意図を説明の上で、一部修正させて頂きました。ノートを御覧頂ければ幸甚です。--Kliment A.K. 2009年3月26日 (木) 04:25 (UTC)
- ありがとうございました。すでにコメントを書いておきました。--Alex K 2009年3月26日 (木) 04:35 (UTC)
202.71.90.139
[編集]こんにちは、いつも精力的な活動お疲れ様です。利用者‐会話:202.71.90.139で注意をしている利用者がいるようですが、利用者:Alex K/工房2を編集している202.71.90.139はAlex Kさんですよね。私は、このIPアドレスがAlex Kさんならば、IPで利用者:Alex K/工房2を編集することが問題のある行動だとはおもいませんが、【誤解を受ける恐れ】があるので、利用者:Alex K/工房2を編集しているIPがAlex Kさんでいらっしゃることだけ、確認させていただけますでしょうか。IPの会話ページでの注意には、「余計なおせっかいだ」と不愉快に感じておられるかもしれませんが、誤解による余計な衝突は避けるようにお互い努めていただければ何よりです。--Peccafly 2009年3月27日 (金) 12:46 (UTC)
- コメント有難うございました。ご察しの通り、202.71.90.139のIPは私のIPです。--Alex K 2009年3月28日 (土) 00:01 (UTC)
- お返事ありがとうございました。「注意」を行っていたOh Hさんの会話ページにも私のほうからお伝えしておきましたが、「誤解による余計な衝突」は誰にとっても不幸なことなので、先の件については不快に感じられたかもしれませんが、誤解を受けないように先手を打っておくことも有効かも知れないと思っています。これからもよろしくお願いいたします。ps.ホパークとても面白く拝読いたしました。これからも期待しております。--Peccafly 2009年4月7日 (火) 11:01 (UTC)
- こちらこそ有難うございました。今後とも宜しく御願いします。--Alex K 2009年4月7日 (火) 11:29 (UTC)
- あ、あと翻訳のときは(部分訳でもですが)[13]のように翻訳元の日時も書いておくほうが無難です。Wikipedia:著作権#ウィキペディアにおける翻訳を見ると、一応アウトではないとは思いますが、日時の明記が推奨されているようです。--Peccafly 2009年4月7日 (火) 12:19 (UTC)
- 了解いたしました。丁寧なご説明ありまとうございました。参考にいたします。--Alex K 2009年4月7日 (火) 13:47 (UTC)
質問です
[編集]こんにちは。お久しぶりです。またですが、若干の質問をさせてください。
- ひとつは、File:UPAPrzemysl.jpgで見える青と黄色の旗についてです。これはFile:Flag of Ukrainian People's Republic.svgの旗に似ていると思うのですが、この旗は海軍の旗だったという解説を読んだことがあります。UPAの人はUNRの海軍旗を持っているのでしょうか。それともこの旗は本当は海軍旗ではないのでしょうか。あるいは、一見似ているようだがふたつの旗は別物なのでしょうか。
- もうひとつ、ウクライナ国ヘーチマンの称号についてです。http://flagspot.net/flags/ua_htman.html のページでは「Hetman of Ukraine, Don Host and Kuban Host」というような表現が見えます。スコロパツキーが「全ウクライナのヘーチマン(Гетьман всієї України)」という称号を使っているのは見たことがあるのですが(1918年4月29日の声明の署名。偽物でなければですが)、「ウクライナ、ドン軍、クバーニ軍のヘーチマン」という称号も用いていたのでしょうか。
毎度すみませんが、ご意見いただけると幸いです。--PRUSAKiN 2009年5月11日 (月) 10:59 (UTC)
いつもお世話になっております。質問ありがとうございました。
- チェルニーヒウ州立公文書館によりますと、UNRの海軍旗に描かれているトルィースブの裏側は白色です。File:Flag of Ukrainian People's Republic.svgの場合は、トルィースブの裏側は青色です。つまり、UPAの軍人は海軍旗ではなく、独特な旗を持っているだけです。ただ、チェルニーヒウ州立公文書館のページに載っている情報はどこまで信じていいのかわかりません。たとえば、20世紀前半の軍旗・軍服を研究テーマにしている私の旧同級生は、この論文においてUNRの海軍旗はトルィースブのない単なる青黄の二色旗であったと主張しています。
- スコロパードシクィイ閣下の称号、大公に相当する称号で、「Гетьман всієї України」(全ウクライナのヘーチマン)、「Його Світлість Ясновельможний Пан Гетьман всієї України, Верховний Воєвода Української Армії і Фльоти」となっているそうです。[14]、[15](pdfの場合は称号を当時の文書で確認できます)。「ドン軍、クバーニ軍」の追加は誰かの悪戯だと思います。閣下は、ウクライナ国とクバーニ人民共和国と連合する計画を立てていたが、「クバーニ軍のヘーチマン」という称号を持っていなかったと思います。
あまり答えになっておりませんが、どうかご容赦ください。--Alex K 2009年5月11日 (月) 16:53 (UTC)
ありがとうございます。
- 私もコモンズの画像は少し間違っているんじゃないかと思っているのですが、svgファイルを修正する技術を持っていないためそのまま放置しています(残念)。さらに言うと、現代のウクライナ海軍の旗の方もすこしデザインと色が間違っていると思います。File:Naval Ensign of Ukraine (dress).svgです。ウクライナ国の海軍旗もちょっと違うと思います。File:Naval Ensign of Ukraine (dress, 1918).PNGです。ただ、いずれもものすごく間違っているというわけじゃないし、そのまま気にせず使用してしまっています……。
では、UPAの人の持っているのは独自の旗であり、あまり関係はないのですね(もしかして、UPAの何かの部隊の旗?)。
1917年以降の黒海艦隊ではウクライナの旗が掲げられたという記述は読んだことがあるのですが、これまで一度も実際にその旗が掲げられている写真を見たことがありません(尤も、ロシア人の言うようなドイツの旗が掲げられているのも見たことありませんが)。写真や公式文書があまり残っておらず、そのため研究者の間でも意見が割れているという状況なのかなあと想像しています。 - スコロパードシクィイ閣下の称号についてとおもしろいサイトを教えていただき、感謝致します。大きなpdfファイルについては、ちょくちょく見て行きたいと思います。「Його Світлість Ясновельможний Пан Гетьман всієї України, Верховний Воєвода Української Армії і Фльоти」はなんと日本語訳したら美しいと思いますか?(「Фльот」というのがフルシェーウシクィイ風ですね。現代ウクライナ語でもこの綴りを用いることはありますか?)
- ところで、この頃のヘーチマンといえばen:Green Ukraineには「Hetman G. Semyonov」と書かれているのですが、私はセミョーノフがヘーチマンであったという記述を読んだことがありません。これは事実でしょうか、誤り(アタマンか何かの間違え)でしょうか。
続けざまにすみません……。--PRUSAKiN 2009年5月13日 (水) 11:23 (UTC)
こちらこそありがとうございます。
- 詳しくわかりませんが、UPAの人が持ってっている旗は特定の軍旗ではないと思っています。ただの国章付きの国旗だと思います。
- Його Світлість Ясновельможний Пан Гетьман всієї України, Верховний Воєвода Української Армії і Фльотиの訳に関しては自身がありません。母国語から外国語に訳することが難しいからです。「全ウクライナのヘチマン閣下、ウクライナ陸軍・海軍の最高将官」でいいでしょうかな?
- セミョーノフのヘーチマン称号は誤りだと思います。彼はウクライナ・コサックの伝統を引くコサック軍に属していませんし、ウクライナ人でもありません。それに「ヘーチマン」という称号は西洋風な称号であったため、当時のロシアの軍人の間ではあまり好まれていなかったと思います。--Alex K 2009年5月16日 (土) 09:10 (UTC)
ご回答ありがとうございます。
- 旗はそのように解釈したほうがよさそうですね。
- 日本には戦前はたくさんの尊称語が存在していましたが、戦後そうした言葉の使用は廃止されてしまったため、戦後生まれの私たちはその種の言葉がさっぱりわかりません(ほぼ外国語状態)。正直、「Пан」にあたる日本語表現すらよくわからない(馴染みがない)状況です。戦前の日本人ならきっとこういう称号をうまく訳したのでしょうが……。大意は「全ウクライナのヘチマン閣下、ウクライナ陸軍・海軍の最高将官」なのだと思いますが、あれ随分短くなったなあ、などと思ったりします……(Його Світлість Ясновельможний Панが「閣下」の一語に……)。私にもこの日本語訳はよくわからないんです。
- わかりました。多分英語版が何か間違えたのでしょう。--PRUSAKiN 2009年5月16日 (土) 14:53 (UTC)
すみません、別件ですが、ちょっとツァーリを査読していただけませんか?ロマン・ムスティスラーヴィチやダヌィーロ・ロマーノヴィチのこととかが出てきているようなのですが、よくわからないので見ていただければと思います。具体的には、2009年3月25日 (水) 02:12の版でIPによって加筆された部分です。西ウクライナを含めると「ロシアのツァーリ」という節名は「ルーシの」に変えねばならないと思いますが……。--PRUSAKiN 2009年5月16日 (土) 15:36 (UTC)
急いで返答させていただきます。
- 「Ясновельможний Пан」は中世の東欧風な称号であり、「卿」として訳するのが可能だと思います。15-17世紀には、平の貴族は「Пан」(殿)、中ぐらいの貴族は「вельможний Пан」(尊殿)、最高の貴族は「Ясновельможний Пан」(光尊殿)と呼ばれていました。
- 「Його Світлість」は近世のラテン語風な称号であり、日本語では「閣下」として訳するのが一般的となっております。
- 時間が許せば、「ツァーリ」を見てみます。ロマン公とダヌィーロ公はルーシの「самодерджец」(君主、sovereign)と呼ばれたことがありますが、「ツァーリ」の称号を有していなかったと思います。--Alex K 2009年5月22日 (金) 08:47 (UTC)
お忙しいところありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。202.71.90.139さんはAlex Kさんでしょうか?だとしたら、ツァーリの項への対処、御礼申し上げます。--PRUSAKiN 2009年5月24日 (日) 14:57 (UTC)
こちらこそありがとうございます。時間と筆記能力が足りなくて、本当に申し訳なく思っております。
202.71.90.139は私です。「ツァーリ」は聖職者の「専門用語」です。年代記には「ロマン公」あるいは「ダニーラ王」という「名前+称号」というパターンがしばしば見られますが、「ロマン・ツァーリ」あるいは「ダニーラ・ツァーリ」というパターンが見られません。また、年代記には「ツァーリ」は聖書に登場するユダヤの君主や東洋の賢人に対して称号として用いることがあります(ダビデ・ツァーリ、ソロモン・ツァーリ, 三人のツァーリ(東方の三博士))。ルーシの諸君に対し、年代記の編纂者が用いていた「ツァーリ」は、正式的な「称号」より、聖書的な「譬え言葉」だったといえます。
そういえば、ヤロスラヴ賢公は「ツァーリ」だけでなく、「カハン」とよばれたことがありますが、「カハン」は彼の称号であったことは、いささか考えがたいです。--Alex K 2009年6月1日 (月) 02:26 (UTC)
コメントありがとうございます。お返事が遅くなってすみません。
なるほど、当時の人々は「偉い人」を讃えるために知っている限りの称号を用いたという具合に見えますね。それは一種の「比喩」ですね。ベタな意訳をすれば、「聖書に出てくる賢人(ツァーリ)のように偉大な我が君」程度な感じで使われていたのかと想像します。
さすがにキエフ・ルーシの君主が正式に「カハン」なる称号を持っていたとは考えにくいですし、「ツァーリ」についてもそれと同じような用法だと考えれば理解しやすいですね。--PRUSAKiN 2009年6月15日 (月) 14:50 (UTC)
こちらこそありがとうございます。「ツアーリ」のことを詳しく説明していくと、論文になりますので、Wikipediaより東欧研究雑誌に載せた方が言いと思います (^V^)。--Alex K 2009年6月21日 (日) 11:59 (UTC)
ベレザーニ
[編集]はじめまして、Penn Stationと申します。Alex Kさんの投稿されたベレザーニ(市)ですが、Wikipedia:記事名の付け方のガイドラインに明らかに沿っていなかったため、Wikipedia:ページの改名#改名前にすべきことに基づきベレザーニ (キエフ州)へ即時移動させていただきました。具体的には以下の2点です。
- 「ただし、曖昧さ回避のために記事名に括弧を用いる場合には、パイプの裏技が使えるように、記事名の後に半角のスペースを入れ、半角括弧 () で分類名を囲んで、「記事名 (分類名)」とする。」(WP:NC#全角と半角の使い分け)
- 「地名、島等の名前同士で同一名称がある場合には、それぞれの記事名について国名で曖昧さ回避を行なう。同一国内で複数の同一地名がある場合には、州名などにより区別する。 」(WP:NC#地名)
同様の理由によりベレザーニのリンクも修正しました。以上、ご確認お願いします。--Penn Station 2009年8月28日 (金) 10:24 (UTC)
黒ルーシ
[編集]Alex Kさん、こんにちは。黒ルーシの投稿ありがとうございます。さて、本記事ですが、私の行った編集内容をAlex Kさんが差し戻されました[16][17][18]。以下に改めて指摘および質問させていただきますので、ご見解をお聞かせください。
- 日本語の修正について:何箇所か日本語としておかしな箇所がありましたので修正したのですが、Alex Kさんによって差し戻されてしまいました。具体的には、「初めて「黒ルーシ」という地名は、ルーシ側の史料ではなく、14世紀以降ばの西欧側の記録などで見られる。」(初めて「黒ルーシ」という地名は)および「I.カルピーンスキによる「黒ルーシ」のは18世紀以後の歴史学・地理学に定着して今に至っている。 」(「黒ルーシ」のは)の部分です。Alex Kさんは日本語ネイティブではないとのことで、利用者ページにも「私が書いた記事では日本語の間違いは多くあると思います。御修正いただければ、有難いです。」とあったので修正させていただきましたが、これらの文に関する私の修正に何か問題があったのでしょうか?差し戻しの意図についてご説明お願いします。
- typo修正について:「歴史知名辞典」は「歴史地名辞典」の誤りかと思いますが、同様に差し戻されてしまいました。ご確認お願いします。
- リダイレクト回避について:リダイレクトを回避するために[[西欧]]、[[英国]]を[[西ヨーロッパ|西欧]]、[[イギリス|英国]]に修正したのですが、これも差し戻されてしまいました。将来西欧や英国が単独記事として作成される見込みはなく、敢えてリダイレクトにリンクする必要性は全くないと思いますが、いかがでしょうか。
- Otherusesについて:{{Otheruses}}ですが、テンプレートの説明には「項目名にその他の用法や曖昧さ回避ページがある場合、パラメータの指定方法によって柔軟な使い方のできるテンプレートです。」とあります。「その他のルーシ」として「ルーシ」への誘導を行っていますが、「黒ルーシ」にその他の用法や曖昧さ回避ページがある訳ではありませんので、この利用方法は不適切であり、ルーシは関連項目として紹介するのが良いと思いますが、いかがでしょうか。
- カテゴリについて:Category:ベラルーシの地名を指定されていますが、同カテゴリが存在しておらず、また、他国の場合でも(すべて調べて訳ではありませんが)「〜の地名」というカテゴリはなく代わりに「〜の地理」「〜の都市」などのカテゴリがあるため、Category:ベラルーシの地理に変更したのですが、これも差し戻されてしまいました。Category:ベラルーシの地名を指定されている意図を教えてください。
- 言語間リンクについて:英語版以外への言語間リンクおよびDEFAULTSORTも削除されましたが、何故でしょうか?(言語間リンクはその後ロボットにより追加されたようです)
以上6点、長くなりましたが、よろしくお願いいたします(もしこれらのコメント・質問で意味が分からない点があれば、遠慮なくご質問ください)。--Penn Station 2009年10月22日 (木) 03:01 (UTC)
- はじめまして、Alex Kです。御修正ありがとうございました。Penn Stationさんの修正を削除しまったこと、申し訳なく存じます。そもそも、Penn Stationさんの編集は差し戻すつもりはありませんでした。Penn Stationさんが削除した「ラテン語:Ruthenia Nigra」[19]を追加したかっただけですが、なぜか、私の編集でPenn Stationさんの修正が削除されました。本当に失礼しました。--Alex K 2009年10月22日 (木) 05:47 (UTC)
- ご回答および復帰作業ありがとうございました。もしかしたら編集ミスかなとも思ったのですが、編集が複数回あったため、意図的なものかと思った次第です。事情は了解いたしました。また、私の編集で意図せずラテン語表記が削除されてしまっていたようで、こちらは大変申し訳ありませんでした。とりあえず現状で問題ないと思います。それでは今後ともよろしくお願いいたします。--Penn Station 2009年10月22日 (木) 09:26 (UTC)
ノート:救世主変容教会
[編集]いつも記事作成お疲れ様です。ノート:救世主変容教会で、ページの存続そのものの是非が議論されています。作成者として意見をお聞かせ下さい。私個人はこのページは無くとも良いと思いましたが、作成者であるAlexKさんの意向・意図を全く無視してリダイレクト化される行為には納得がいかず、差し戻した次第です。--Kinno Angel 2009年11月16日 (月) 02:53 (UTC)
- お知らせ有難うございます。今のところ、リダイレクトでも曖昧さ回避でも構いません。救世主変容教会(ヴェルィーキ・ソローチンツィ)の記事名問題が解決したら、考ええてもいいと思います。--Alex K 2009年11月17日 (火) 02:04 (UTC)
ご挨拶
[編集]ご自分が正しいと思われても差戻しを繰返せばWikipedia:Three-revert ruleuk:Вікіпедія:Правило трьох відкотівに掛かります。johncapistrano 2009年11月30日 (月) 07:13 (UTC)
- ありがとうござみます。そのルールなら知っております。今のところ3つの差戻し以上はやっておりませんので、「挨拶」は無用です。ご安心ください。--Alex K 2009年11月30日 (月) 10:40 (UTC)
ご挨拶
[編集]Вітаю Вас з наступаючим Новим Роком!
- Бажаю добра і щастя! --PRUSAKiN 2009年12月30日 (水) 16:01 (UTC)
コメント依頼ご報告
[編集]Wikipedia:コメント依頼/AlexKを出しました。ここに報告いたします。--Kinno Angel 2009年12月31日 (木) 04:12 (UTC)
御祝
[編集]
|
御目出とう御座ます。 |
Христос народився! -
Славімо Його! クリスマスおめでとうごさいます! |
-Alex K 2010年1月7日 (木) 08:21 (UTC)
- おめでとうございます。東方典礼では今日でしたね。すっかり忘れてました。^^;johncapistrano 2010年1月7日 (木) 08:32 (UTC)
- Alex Kさん、大変なものをありがとうございます。クリスマスおめでとうございます。Alex Kさんの一年が、素晴らしきものとなることをお祈り申し上げます。--Libertas 2010年1月7日 (木) 10:13 (UTC)
- ありがとうございます。今年も宜しく御願いいたします。m(_ _)m--Alex K 2010年1月7日 (木) 23:58 (UTC)
- 遅れ馳せながら、クリスマスおめでとうございます。当方のページにお祝いを寄せていただき有難うございました。昨日は時間の関係でパソコンに触れることができなかったので、今日になってのお返事お許し下さい。今年もあなたにとって良い年でありますことをお祈りしております。--港町奉行 2010年1月8日 (金) 02:38 (UTC)
ご挨拶
[編集]この文書Wikipedia:多重アカウント、日本語が分かり辛ければ分かり易い言語版で結構なんでご確認下さい。johncapistrano 2010年1月20日 (水) 06:46 (UTC)
- 有難う御座います。拝読いたしました。ウクライナ語版では多重アカウントを持つ利用者が沢山いますが、問題などを起こしたりはしません。利用者は互いに知り合っているからです。また、ウクライナ語版ではチェックユーザーという制度がありませんので、Wikipedia:多重アカウントを拝読して勉強になりました。日本語版の規則はウクライナ語版と異なっているようです(- -;)--Alex K 2010年1月20日 (水) 09:30 (UTC)
リファールについて質問
[編集]セルジュ・リファールについて加筆ありがとうございました。ところでウクライナ語における綴りですが、"Лифар" でよろしいのでしょうか? ウクライナの文献にそうある以上一見自明のようですが、疑問点として、1)本人の署名では "р" のあとに "ь" らしきものを入れている形跡がある(冒頭の切手)。2)ウクライナのTV局のウェブサイトで、"Сергій Михайлович Лифарь" と表記している。3) セルジュの弟とその配偶者はロシア語では "Лифарь" 表記(1)。4)本人の墓にはロシア語で "Лифарь" 表記(File:Сергей Лифарь.jpg)。5)本人のロシア語の著書があるが、名前は "Лифарь" 表記(2)。6)キエフの新聞報道によると、本名は "Лифаренко" とある。とすると、ウクライナには今も昔も本来 "Лифар" なる名前は存在せず、西欧で有名になったから現代のウクライナ人が "Lifar" をキリル文字に転記しただけではないのか?・・・この弱音記号が入るか否かでずっと分からなかったので、改名提案したまま放置していたのですが…。もしかしたら、リファール本人はウクライナ語など知らないか、ほとんど忘れてしまった可能性もあるのではないかと推測しています。ウクライナが御専門のようですので、"Лифар" なる人名が本名としてウクライナで実際に存在するのかどうか、この機会に御教示頂ければ幸いです。--トトト 2010年1月27日 (水) 12:10 (UTC)
- 現代のウクライナに "Лифар" という姓の人は沢山いるようですね…。大騒ぎして失礼しました。--トトト 2010年1月30日 (土) 00:39 (UTC)
- はじめまして、Alex Kです。ウクライナ語でЛифарь(リファーリ)とЛифар(ルィファール)とも見られます。冒頭の切手をご覧いただければ、分かると思います。私はウクライナ語版の綴り通りに編集しただけです。--Alex K 2010年2月2日 (火) 05:06 (UTC)
- あのですね、本人は「ロシア人」と述べている発言があるのですよ。切手にある筆記体はどう見てもロシア語でしょう(йの前は、i ではなく、ѣ ですね)。バレエの基本文献3点で、1)International Dictioanry of Ballet, vol.2, ISBN 1-155862-157-X p.860 "LIFAR, Serge: Russian/French dancer,...", 2) International Encyclopedia of Dance, Vol.4, ISBN 0-19-517588-3, "Lifar, Serge: ...Russian dancer...", 3) The Concise Oxford Dictionary of Ballet, ISBN 0-19-311330-9, p.255, "Lifar, Serge:...Russ.-Fr. dancer..." で、いずれも「ロシア人」となっています。ウクライナは自国に英雄がほしいものだから、やたらとリファールを自国人と強調する傾向があるようですが、本人のアイデンティティは「ロシア人」でした。こうした基本情報を踏まえた上で先の御尋ねをしたわけですが、どうもリファールについて私が提示した情報以上の知識はお持ちでないようですので、本日Alex Kさんがなされました編集については一部差戻しをさせて頂きます。近く大幅に加筆する予定ですので、御理解下さい。
- 私が伺いたかったのは、なぜロシア語表記の "Лифарь" が、現代のウクライナで "Лифар" と表記されることが多いのか、ということでした。--トトト 2010年2月2日 (火) 06:17 (UTC)
- 「ウクライナは自国に英雄がほしいものだから」などは関係してないと思います。私の曾祖父も死ぬまでに古い正書法にしたがって署名したが、常に「自分はウクライナ人、コサックだ」と主張したので、署名や国籍によって東欧人の民族所属を判断することができないと思います。さらに、バレエの基本文献にRussian/French dancerとは「ロシア人」を意味しているではなく、「ロシアの」(ロシア出身)を意味しているのではないかと思います。現在、マイペディア百科事典を含む文献の一部にもウクライナのことを「南ロシア」、ウクライナ人のことを「ロシア系・ロシア人」という書き方が見られることを考慮すれば、バレエの基本文献に書いてあることに驚けません。リファールは民族的にウクライナ人だったが、当時の多くウクライナ人(Вернадский, Скоропадский, Махно)と同様にロシア文化を愛し、その文化の担い手であると確信していたと思います。ですから、リファールは「ロシア帝国出身の人物」・「ロシアのバレエ文化の担い手」であるが、民族的に「ウクライナ人」であることが矛盾していません。--Alex K 2010年2月2日 (火) 06:49 (UTC)
- お返事、御教示ありがとうございます。御先祖がコサックであられたのですか…。確かに仰ることは御尤もで、民族的に「ウクライナ人」であることとは矛盾しないかもしれません。--トトト 2010年2月2日 (火) 07:24 (UTC)
- 「ウクライナは自国に英雄がほしいものだから」などは関係してないと思います。私の曾祖父も死ぬまでに古い正書法にしたがって署名したが、常に「自分はウクライナ人、コサックだ」と主張したので、署名や国籍によって東欧人の民族所属を判断することができないと思います。さらに、バレエの基本文献にRussian/French dancerとは「ロシア人」を意味しているではなく、「ロシアの」(ロシア出身)を意味しているのではないかと思います。現在、マイペディア百科事典を含む文献の一部にもウクライナのことを「南ロシア」、ウクライナ人のことを「ロシア系・ロシア人」という書き方が見られることを考慮すれば、バレエの基本文献に書いてあることに驚けません。リファールは民族的にウクライナ人だったが、当時の多くウクライナ人(Вернадский, Скоропадский, Махно)と同様にロシア文化を愛し、その文化の担い手であると確信していたと思います。ですから、リファールは「ロシア帝国出身の人物」・「ロシアのバレエ文化の担い手」であるが、民族的に「ウクライナ人」であることが矛盾していません。--Alex K 2010年2月2日 (火) 06:49 (UTC)
- あのですね、本人は「ロシア人」と述べている発言があるのですよ。切手にある筆記体はどう見てもロシア語でしょう(йの前は、i ではなく、ѣ ですね)。バレエの基本文献3点で、1)International Dictioanry of Ballet, vol.2, ISBN 1-155862-157-X p.860 "LIFAR, Serge: Russian/French dancer,...", 2) International Encyclopedia of Dance, Vol.4, ISBN 0-19-517588-3, "Lifar, Serge: ...Russian dancer...", 3) The Concise Oxford Dictionary of Ballet, ISBN 0-19-311330-9, p.255, "Lifar, Serge:...Russ.-Fr. dancer..." で、いずれも「ロシア人」となっています。ウクライナは自国に英雄がほしいものだから、やたらとリファールを自国人と強調する傾向があるようですが、本人のアイデンティティは「ロシア人」でした。こうした基本情報を踏まえた上で先の御尋ねをしたわけですが、どうもリファールについて私が提示した情報以上の知識はお持ちでないようですので、本日Alex Kさんがなされました編集については一部差戻しをさせて頂きます。近く大幅に加筆する予定ですので、御理解下さい。
- はじめまして、Alex Kです。ウクライナ語でЛифарь(リファーリ)とЛифар(ルィファール)とも見られます。冒頭の切手をご覧いただければ、分かると思います。私はウクライナ語版の綴り通りに編集しただけです。--Alex K 2010年2月2日 (火) 05:06 (UTC)
記事の差し戻しについて
[編集]またしても三位一体大門教会の移動を差し戻しましたね。私は改名の議論には参加していませんでしたが、第三者視点から議論の経過を見る限り、2010年1月21日の時点で合意は成立しているものと見られます。その後のノート:三位一体大門教会でのKinno Angelさんの抗議や、Koon16000さんの指摘も完全に無視し、何ら議論も起こさず、2度に渡って差し戻しを行うのは、さすがに呆れます。Wikipediaで禁止されている、対話拒否・編集の強行と見られても仕方の無い行為です。自分が気に入らなくても、一度成立した合意に反対するならば、再度自ら提案し、新たな合意を取るべきです。
一応申し上げておきますが、私の立場としては、改名には賛成でも反対でもありません。あなたの、議論や合意を無視した独善的な行為に憤りを覚えているだけです。二度とこのようなことはお止め下さい。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 05:26 (UTC)
- 説明は当ページに書きました。--Alex K 2010年2月2日 (火) 05:28 (UTC)
- だから、今頃書くのは順番が違うのです。よくお読み下さい。先に差し戻してから説明をするのではなく、まず説明をして、合意を得てから改名しなければなりません。1ヶ月以上も放置しておいて、自分の期待している回答が無いから合意ではない、などということは、全く道理が通りません。あなたの無断差し戻しを、合意が得られている至聖三者大門教会に差し戻した上で、あらためてあなたが三位一体大門教会への改名提案をし、議論の合意を得るべきです。以上。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 05:34 (UTC)
- 1ヶ月以上に私の質問を「放置」したのは「賛成」側です。合意がなかったにも関わらず、改名することが違反です。以上。--Alex K 2010年2月2日 (火) 05:37 (UTC)
- どう見ても議論を放棄したのは、あなたの方です。あなたは、2010年1月1日 (金) 06:15 (UTC)以降、何も意見を述べられていません。Kinno Angelさんの、2010年1月5日 (火) 04:58 (UTC) 及び2010年1月16日 (土) 03:00 (UTC)の告知に対しても、あなたは何も返事をしていません。あなた一人が「放棄ではない」と思っていても、あなた以外の誰が見ても議論放棄であり、合意の成立が有効であると見て取れます。合意成立後に、文句を言うのは、議論無視であり、そのような行為はWikipediaのルール上、許されるものではありません。即刻、あなたの無断移動差し戻しを取り消し、あらたに再改名提案をして合意を得ること。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 05:48 (UTC)
- Kinno Angelさんは私を2ヶ月間にハラスメトし続けている利用者です。彼と会話することを控えています。「賛成」側の方は私の質問に答えを出せなかったので、いちいち同じような質問をくりかえすことが必要はありません。私は「議論無視」したではなく、「賛成」側は私の質問と根拠を無視したのです。そして合意が成立していなかったにもかかわらず、Wikipediaのルールに反して改名を行ったのです。--Alex K 2010年2月2日 (火) 05:57 (UTC)
- ですから、あなたとKinno Angelさんとの間の個人的な感情や問題を理由にして、あなたがKinno Angelさんとの議論をしないのは自由ですが、だからと言って合意の無効を主張することは理屈が通りません。先ほども言いましたように、2010年1月5日 (火) 04:58 (UTC) 及び2010年1月16日 (土) 03:00 (UTC)の間に、反対者無しで、合意は成立しています。それに改名提案に意見を述べているのは、あなたとKinno Angelさんだけではありません。他のユーザーの方はいずれも賛成票を投じており、反対票を投じているのはあなた一人のように見えます。唯一反対意見を主張されているあなたが、いかなる理由があろうと反対意見を長期間述べていないのですから、合意は成立していると見るのが妥当です。気持ちとしては納得できない所はあるかもしれませんが、自分が気に食わないからといって、コミュニティの合意や、それまでの議論の経緯を無視することはできません。反対意見を述べなかったあなたの側に落ち度があるのです。いくら納得できなくても、無断で差し戻すことは絶対にいけません。一旦、合意が得られているページ名に戻して、あらためて改名提案をして下さい。それから、Kinno Angelさんとの個人的な諍いは、コメント依頼なりブロック依頼なり、しかるべき場所でやって下さい。改名提案の場にそのような争いを持ち込まないようにして下さい。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 06:14 (UTC)
- 改名提案は2009年12月31日に出されました。2010年1月5日の時点ではありません。反対者がいたので、合意は成立していません。合意は多数決ではありません。--Alex K 2010年2月2日 (火) 06:21 (UTC)
- 2010年1月5日に成立したなどとは言っておりません。「2010年1月5日 (火) 04:58 (UTC) 及び2010年1月16日 (土) 03:00 (UTC)の間に、反対者無しで」成立したと言っているのです。もちろん合意形成は多数決ではありません。しかし、唯一反対を主張していたあなたが、反対を主張されませんでしたので、明らかに合意は有効です。個人的な理由で勝手に議論から身を引いておいて、合意成立後しばらくたってから、ひっくり返すのは、道理が通りません。あなたのような行為がまかり通るのなら、Wikipediaでの全ての合意は成立しなくなります。最初に反対意見を述べておいて、合意成立後に、自分は同意していない、などと主張して議論を白紙に戻すようなことが許されるわけがありません。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 06:31 (UTC)
- &繰り返します。(1)改名提案は2009年12月31日に出されました。2010年1月5日の時点ではありません。反対者の有無を確認するなら、2010年1月5日からではなく、2009年12月31日から御願いします。(2)私は「議論から身を引いた」ではなく、「賛成」側は私の質問と根拠を無視して「議論から身を引いた」のです。(3)合意は多数決ではありませんので、2009年12月31日以後に改名提案に対し「反対」一票があったので、合意が無かったと考えられます。(4)合意がなかったので、「賛成」側がおこなった改名は無効です。よって私による差し戻しは道理に適っています。--Alex K 2010年2月2日 (火) 06:58 (UTC)
- (1)改名提案が12/31に出されたことは存じていますし、そのようなことを問題にはしていません。1月5日04:58にKinno Angelさんが「これ以上議論を無視し続けられるようであれば、議論に参加している方々からは合意が得られたものとして、改名を実行するしかないと考えております。1週間以内に回答が無ければ改名を実行します」と宣言しています。1月16日03:00にも「これ以上議論を無視し続けられるようであれば、議論に参加している方々からは合意が得られたものとして、JST月曜日(2010年1月18日)には改名を実行します」と宣言しています。あなたはこれにも反論しませんでした。したがって、合意は成立したとみなされます。(2)前述のように、再三の呼び掛けにあなたは応じませんでした。あなたが心の中で「賛成側が身を引いた」と考えていたとしても、あなた以外の人は誰一人としてそうは思っていません。(3)前述のように唯一の反対者が反論に応じなかった時点で、合意となります。(4)いずれにしても、合意は成立しており、「合意が成立していない」というあなたの主張には、何の客観的な根拠もなく、あなたの内面的な思いによるものだけです。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 11:32 (UTC)
- Kinno Angelさんは宣言や「最後通牒」などを出すのを自由です。彼は私の反論や質問に対して具体的な答え(出典)を出せんでした。一方、私は自分の反論を繰り返すつもりはなかったです。私の沈黙は反論の根拠の力を弱めたわけではありません。想像はごじゆうですが、どうみても、Wikipedia:合意形成で書かれている「合意」は成立しなかったです。単なる多数決です…--Alex K 2010年2月2日 (火) 12:34 (UTC)
- 「彼は私の反論や質問に対して具体的な答え(出典)を出せんでした」というのは、あなたの勝手な印象でしょう。それを、あなたはどこで表明しましたか? 心の中で反論しても、それは議論にはなりませんよ。あなたの反論や質問に対して、Kinno Angelさんは返答していますよ。その回答内容を、あなたは気に食わなかったとしても、それを表明しなければ相手には伝わりませんよ。それを行わず、一方的に自分の心の中だけで「反論」しても、実際の議論の場で表明しなければ、「議論放棄」とみなされます。誰もあなたの心中までは想像してはくれません。
- それからWikipedia:合意形成#合意形成には、「合理的な期間〔通常は168時間程度(約7日間)が妥当でしょう〕内に異論がなければ、提案がそのまま決定事項となります」と、はっきりと明記されています。あなたは1月1日以降、何も反論していませんでした。「Kinno Angelさんは宣言や「最後通牒」などを出すのを自由です」ではなく、Kinno AngelさんはWikipediaのルールに則って然るべき期間以上に十分な猶予をとった上で反論が無いことを確認しています。多数決ではありません。Wikipedia:合意形成で書かれている「合意」は成立しています。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 12:47 (UTC)
- 「Kinno Angelさんは返答していますよ」→ 返答には出典・論文やなかったんです。「議論放棄」はあななの勝手な想像にすぎません。
- それからWikipedia:合意形成#合意形成には、「合理的な期間〔通常は168時間程度(約7日間)が妥当でしょう〕内に異論がなければ、提案がそのまま決定事項となります」と、はっきりと明記されています。しかし、以前の反論にはまともな答えが出されていなかったので、「合意」が成立したとは思えません。--Alex K 2010年2月2日 (火) 12:54 (UTC)
- では、あなたが「以前の反論にはまともな答えが出されていなかった」ことを、いつどこで表明しましたか? あなたが「「合意」が成立したとは思えません」と考えるのは自由です。事実として、Kinno Angelさんの返答に対して、あなたは反論をしませんでした。まともな答えではない、とも何も表明しませんでした。これは事実ですね?--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 12:58 (UTC)
- &繰り返します。(1)改名提案は2009年12月31日に出されました。2010年1月5日の時点ではありません。反対者の有無を確認するなら、2010年1月5日からではなく、2009年12月31日から御願いします。(2)私は「議論から身を引いた」ではなく、「賛成」側は私の質問と根拠を無視して「議論から身を引いた」のです。(3)合意は多数決ではありませんので、2009年12月31日以後に改名提案に対し「反対」一票があったので、合意が無かったと考えられます。(4)合意がなかったので、「賛成」側がおこなった改名は無効です。よって私による差し戻しは道理に適っています。--Alex K 2010年2月2日 (火) 06:58 (UTC)
- 2010年1月5日に成立したなどとは言っておりません。「2010年1月5日 (火) 04:58 (UTC) 及び2010年1月16日 (土) 03:00 (UTC)の間に、反対者無しで」成立したと言っているのです。もちろん合意形成は多数決ではありません。しかし、唯一反対を主張していたあなたが、反対を主張されませんでしたので、明らかに合意は有効です。個人的な理由で勝手に議論から身を引いておいて、合意成立後しばらくたってから、ひっくり返すのは、道理が通りません。あなたのような行為がまかり通るのなら、Wikipediaでの全ての合意は成立しなくなります。最初に反対意見を述べておいて、合意成立後に、自分は同意していない、などと主張して議論を白紙に戻すようなことが許されるわけがありません。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 06:31 (UTC)
- 改名提案は2009年12月31日に出されました。2010年1月5日の時点ではありません。反対者がいたので、合意は成立していません。合意は多数決ではありません。--Alex K 2010年2月2日 (火) 06:21 (UTC)
- ですから、あなたとKinno Angelさんとの間の個人的な感情や問題を理由にして、あなたがKinno Angelさんとの議論をしないのは自由ですが、だからと言って合意の無効を主張することは理屈が通りません。先ほども言いましたように、2010年1月5日 (火) 04:58 (UTC) 及び2010年1月16日 (土) 03:00 (UTC)の間に、反対者無しで、合意は成立しています。それに改名提案に意見を述べているのは、あなたとKinno Angelさんだけではありません。他のユーザーの方はいずれも賛成票を投じており、反対票を投じているのはあなた一人のように見えます。唯一反対意見を主張されているあなたが、いかなる理由があろうと反対意見を長期間述べていないのですから、合意は成立していると見るのが妥当です。気持ちとしては納得できない所はあるかもしれませんが、自分が気に食わないからといって、コミュニティの合意や、それまでの議論の経緯を無視することはできません。反対意見を述べなかったあなたの側に落ち度があるのです。いくら納得できなくても、無断で差し戻すことは絶対にいけません。一旦、合意が得られているページ名に戻して、あらためて改名提案をして下さい。それから、Kinno Angelさんとの個人的な諍いは、コメント依頼なりブロック依頼なり、しかるべき場所でやって下さい。改名提案の場にそのような争いを持ち込まないようにして下さい。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 06:14 (UTC)
- Kinno Angelさんは私を2ヶ月間にハラスメトし続けている利用者です。彼と会話することを控えています。「賛成」側の方は私の質問に答えを出せなかったので、いちいち同じような質問をくりかえすことが必要はありません。私は「議論無視」したではなく、「賛成」側は私の質問と根拠を無視したのです。そして合意が成立していなかったにもかかわらず、Wikipediaのルールに反して改名を行ったのです。--Alex K 2010年2月2日 (火) 05:57 (UTC)
- どう見ても議論を放棄したのは、あなたの方です。あなたは、2010年1月1日 (金) 06:15 (UTC)以降、何も意見を述べられていません。Kinno Angelさんの、2010年1月5日 (火) 04:58 (UTC) 及び2010年1月16日 (土) 03:00 (UTC)の告知に対しても、あなたは何も返事をしていません。あなた一人が「放棄ではない」と思っていても、あなた以外の誰が見ても議論放棄であり、合意の成立が有効であると見て取れます。合意成立後に、文句を言うのは、議論無視であり、そのような行為はWikipediaのルール上、許されるものではありません。即刻、あなたの無断移動差し戻しを取り消し、あらたに再改名提案をして合意を得ること。--Dr.Jimmy 2010年2月2日 (火) 05:48 (UTC)
- 1ヶ月以上に私の質問を「放置」したのは「賛成」側です。合意がなかったにも関わらず、改名することが違反です。以上。--Alex K 2010年2月2日 (火) 05:37 (UTC)
ノート:救世主変容教会 (ヴェルィーキ・ソローチンツィ)でも全く同様の問題が起きています。このまま二つのページの問題が膠着する場合、まずこの問題に特化したコメント依頼などの方策も考えております。--Kinno Angel 2010年2月2日 (火) 07:20 (UTC)
